【講演会HowTo:その4】講演会の「当日」にすべきことと注意点!講師への接し方や会場設営のポイントを具体的に解説

着実に準備がすすみ、ついに講演会当日です!
当日もしっかり気を配り、もしもに備えることが大切です。満足感の高い講演会を目指しましょうね。
長年の講師派遣の実績をもとに、講演サーチが講演会の企画から実施、終了後までのHow Toをご案内します。
はじめて講演会を担当することになった方も、講演会がマンネリ化してきた方も
講演会の企画・運営に携わる皆様に参考にしていただけますよ。
その4「当日」編では、講演会を失敗させない当日の備えを詳しくご紹介しています。
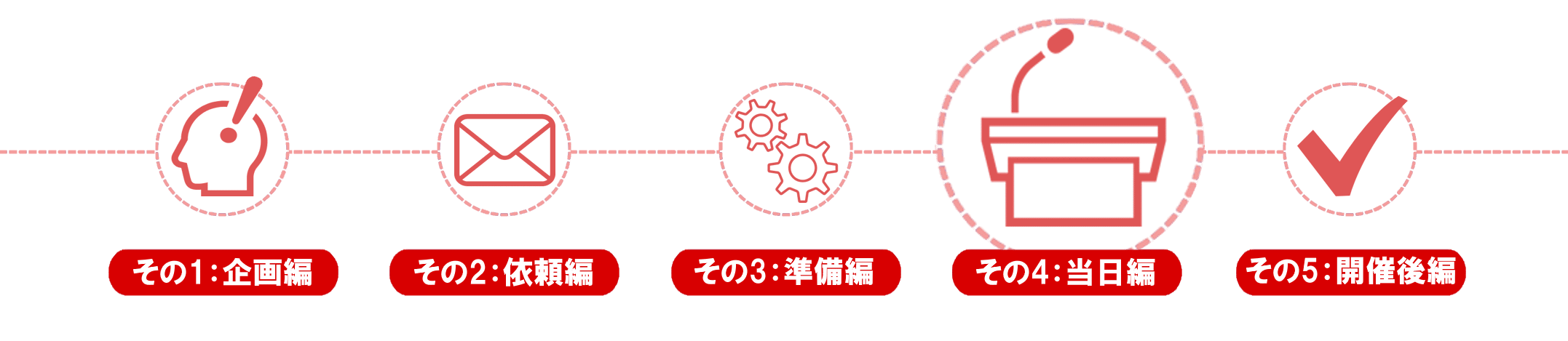
講演サーチは、講演会に欠かせないにも関わらず見逃しポイントの多い準備段階でも丁寧にサポート。
お気軽に無料相談をご利用ください。
当日も講演会担当者は大忙し?
と進めてきました。
いよいよ本番当日。
「うまくいくかな」「トラブルが起きたらどうしよう」などの不安が大きくなるかもしれません。
当日は、これまでしてきた準備を信じて、どんと構えておきましょう。
何かあったら準備していた通りに対処すると、スピーディに問題解決できるはずです。
トラブル対応などに加えて大切なのが、講師への対応です。
今回は講師への対応をメインに、講演会当日に注意したいことをお伝えします。
開催前のチェックポイント

いよいよ当日となると、講師でなくてもソワソワしますよね。初めて担当した講演会であればなおさらです。
開催前に準備はしっかりしていても、最終確認は欠かせません。
ここでは、当日開催直前までに確認しておきたい4つのチェックポイントを紹介します。
講演スケジュールのすり合わせ
講演前日もしくは前々日までに最終確認をしておきましょう。
講演会当日に講師の許可が取れれば、講師と最終確認をしておくのもおすすめです。
当日は1人で集中したい講師も多いです。
当日いきなり打ち合わせを頼むのではなく、事前に許可を取っておきましょう。
できれば、講師との最終打ち合わせは前日までに終えておくと安心ですね。
確認事項は、
・スケジュール
・進行台本
・講師のアテンド
・資料の内容と数
などです。
急な変更がないか、不備がないか、最新の注意をはらって確認しておきましょう。
講師のお出迎え
オンラインではなく会場で講演会を開催するなら、講師を出迎えに行く担当者が必要です。
迎えに行くことで、講師が迷ったりして時間に遅れるリスクを減らすこともできます。
お出迎えは約束した時間の10~15分前には待ち合わせ場所で待機しておくと失礼になりません。できるだけ講師をお待たせしないように、時間に余裕を持って待機しましょう。
講師が著名人の場合、人目を避けることをおすすめします。人の目につかない場所を選ぶと、周囲の混乱を避けてスムーズに合流できるはずですよ。
自家用車及びタクシー移動の場合、講演会に遅れることがないようタイムスケジュールを組むことが欠かせません。車移動の際は渋滞情報のチェックをしておくと良いでしょう。
ときには送迎担当者よりも講師が早く待ち合わせ場所に到着するかもしれません。
その場合に講師を不安にさせないように、担当者の携帯番号を事前に講師へ伝えておきましょう。
控え室も入り時間の1時間ほど前からは使用できるようにしておくのが理想です。
交通機関の乱れや不慮の事故等で予定時間に遅れてしまいそうなとき、とても焦ってしまいますよね。
講演サーチなら、もしもの状況でも経験豊富なスタッフが交通情報をチェックして適切な対応をご案内します。
.
講師が前日入りした場合の対応
講師と懇親会をするために、「もしかして宴会場を押さえておいた方が良いのかな?」と思うかもしれません。
講師に確認してみて参加されるようなら、懇親会の開催を検討してもよいでしょう。ただし、過剰な接待にならないような配慮が必要です。
・遠方まで来てくれたから
・人脈をつくっておきたいから
そんな思いで接待の場を設けようと考えるときがあるでしょう。しかし、講師によっては時間を制限される接待は歓迎されない可能性があります。特に、講演会前日は注意が必要です。講師は前日に講演内容の最終確認をしたり、資料の準備をしたりするケースが多くあります。
機材のセッティング
当日に使う機材の準備は万全にしておきましょう。前日までにチェックしておき、当日は最終チェックとすることが大切です。
チェックする内容は、
・パソコンとプロジェクターの接続
・マイクの接続
・マイク音量
・会場の講師用の台
・画面遠隔操作用のリモコン
・画面共有の設定(オンライン開催の場合)
・開催URLの確認(オンライン開催の場合)
などです。
開催形式などによってチェックすべき内容は変わります。ヌケモレがないようにチェックリストなどを用意しておくと安心です。
講師への接し方

講演会のメインスピーカーである講師は、講演会を成功させるために全力を尽くしてくれるはず。主催者側は集中しやすい環境づくりや声掛けを心がけ、できる限りのサポートをしましょう。
ここでは、講師への接し方で悩みがちなポイントを4つ紹介します。
開催直前は自由に使える時間にしよう
講師によって、講演会当日の過ごし方はさまざま。1人でいたい講師や打ち合わせで集中力を高めたい講師もいます。
過ごす場所も、控室や実際の会場、会場の外など、人それぞれでしょう。講師一人ひとりの希望に合わせて、集中しやすい環境を整えることが重要です。
挨拶のタイミングは?
講演会場に講師が到着したら、真っ先に「あいさつしなきゃ!」と思いますよね。
しかし、挨拶するタイミングは慎重に見極める必要があります。
講演前は1人静かに集中したい講師がいるため、集中を途切れさせないようなタイミングをはかりましょう。おすすめは、講師が会場に到着し、控え室にご案内したタイミングです。
主催の担当者や社長、管理者などがそのタイミングで挨拶できない場合は、講演終了時には必ず挨拶しておくようにしましょう。あるいは講演前の挨拶が難しいと事前に講師へ伝え、挨拶に伺っても良い時間を把握しておくとお互いに不満が生まれにくいですよ。
お礼のタイミングは?
講師へのお礼は、できるだけスムーズに行い、講師の足を引き留めすぎないように心がけましょう。講師によっては講演会終了後すぐに帰路につく場合があります。交通機関の兼ね合いもあるため長々と話すことは遠慮して、丁寧にお礼を伝えられると良いですね。
お礼を伝えるのは、講師が会場から退場したタイミングが適切です。お礼を伝えながら、そのまま会場のエントランスまでアテンドするとスムーズです。
スケジュールの都合で終了後にお礼ができない場合は、あらかじめその旨を伝え、ことわりを入れておきましょう。
記念撮影やサイン依頼は事前に
記念撮影やサインを講師に依頼するのなら、当日いきなりお願いするのではなく事前に了承を得ておく方が好印象です。
講師によっては、講演会終了後すぐに会場をあとにすることもあるため、先に時間を作ってもらっておくと講師としてはスケジュールが立てやすくなるでしょう。
また、当日に依頼するのは不躾な印象を与えかねません。事前に依頼することで、当日お願いするよりも快く引き受けてもらえる可能性が高まります。
依頼時は写真やサインの活用目的を必ず伝えましょう。個人的な記念であれば問題ありませんが、SNSや企業のサイト、ブログなどへ掲載する可能性がある場合は、講師本人の掲載許可と公開前の原稿確認が必要です。
スマートフォンなどの携帯電話での撮影は「失礼だ」と感じる講師がいるかもしれません。事前に撮影依頼をするなら特に、準備不足と思われないようにカメラ機材を用意しておきましょう。
きれいな写真が撮れれば、広報資料への活用の幅も広がります。
サインの枚数は常識の範囲内(10~15枚程度)に留めましょう。対応できる枚数は講師によって異なるため、しっかり確認した上で色紙を用意する必要があります。
また、講師によって使用する文具も異なります。マジックペンや毛筆など、講師の好みを確認しておいたり、講師が自由に選べるように複数種類の文房具を用意したりするのもおすすめです。
講師のために「支払調書」を準備しておこう
講演会で登壇してくれた講演料を講師に支払うにあたっては、「支払調書」を作成して渡すと親切です。
講演料は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」に該当するものです。これは、所得税法や相続税法などの法律によって、事業者が税務署への提出を義務づけられている「法定調書」の一種です。講師は毎年税務署に提出しなければならず、提出されないと罰則の対象となりかねません。講師や自社のためにも、必ず支払調書を作成して渡すようにしましょう。
講演サーチは、誰もが簡単に支払調書を作成できるように、テンプレートをご用意しました。
支払調書の例は以下のボタンより無料でダウンロードいただけます。講演サーチでは、支払調書の作成サポートも承っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
【重要】講演会当日のルール

もしこのように思っていたら危険です。講演内容の録音・録画は控え、必要なら必ず許可を得てください。
利用できる範囲も限られるので、勝手に使ってはいけません。
講演内容は講師の著作物
1つひとつの講演は、講師が時間をかけてつくりあげた作品であり商品です。決してその著作物を侵害しないようにマナーを守りましょう。
講演内容の著作権は講師が所有しています。無断で講演内容の詳細をブログやSNSに掲載するのはNGです。
そもそも、講演会はその場の参加者の雰囲気に合わせて展開されます。その時々に合わせたものだからこそ、録画や録音をせずに楽しく学びたいですよね。
万が一参加者に録音・録画をした人がいると判明した場合、講師本人だけでなく主催側の団体や企業に迷惑がかかります。録音や録画が禁止されていることは、参加者にもしっかり周知しておきましょう。
当日は最終チェックがメイン、あとは講演を楽しもう!
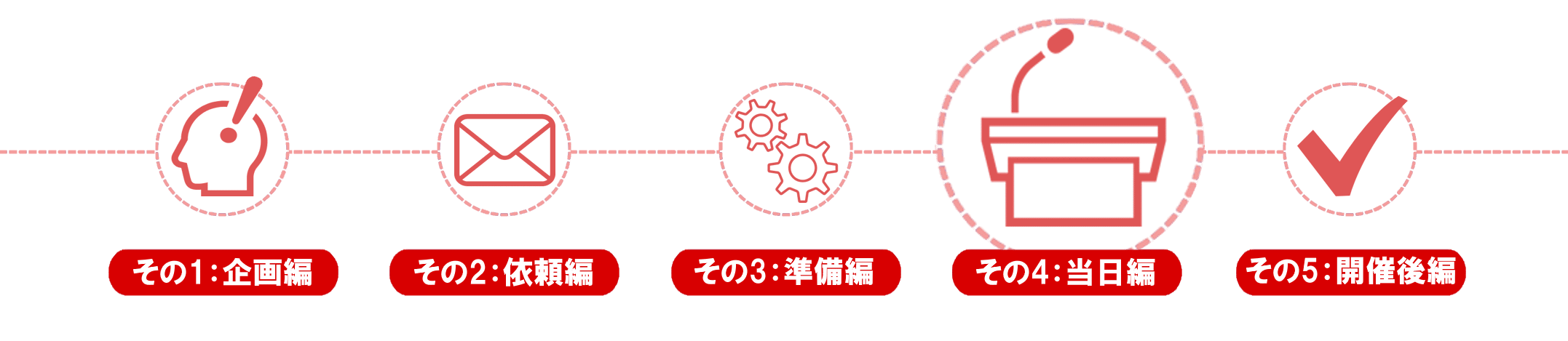
講演会担当としての集大成があらわれる開催当日。失敗しないように最後まで気を引き締めて最終確認を行いましょう。
機材トラブルへの備えはもちろん重要ですが、講師への対応も要注意。
失礼がないように配慮し、最高の講演会を目指してくださいね。
講演サーチなら、より具体的な注意点や開催当日の急なトラブルへのサポートにも対応しています。
ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。






