【三上康一講師特別コラム】中小企業が人材不足を克服するために「貢献意欲」が必要な理由
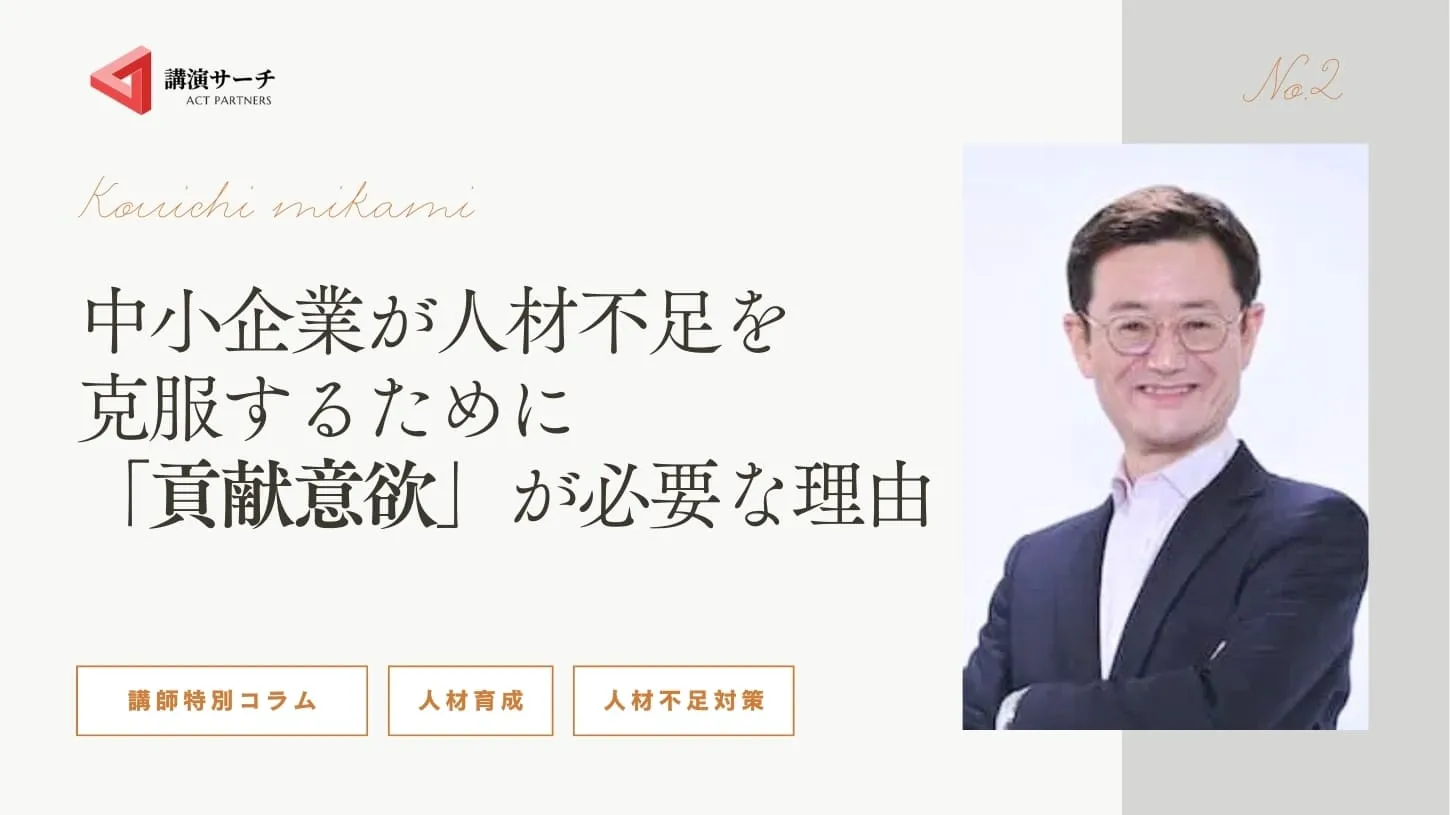

執筆講師
三上康一(みかみ こういち)
株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
【三上康一講師特別コラム】中小企業が人材不足を克服するために「貢献意欲」が必要な理由
組織の成立要件
前回の記事では、アメリカの経営学者バーナードが提唱した「共通目的」「貢献意欲」「コミュニケーション」という組織の成立要件についてご紹介しました。これらが揃ってこそ、単なる人材の集まりは初めて組織として機能するとされています。もし目的もやる気も意思疎通も欠けている場合は、人材は定着せず、人手不足の解決は困難になってしまうでしょう。
そのうえで「共通目的」について詳しく見てきましたが、今回の記事では「貢献意欲」に焦点を当て、これを高める方法について、モチベーション理論を参考に解説します。前回の記事と併せてぜひご覧ください。
私が人材不足の解決をテーマにする理由
私は、現在中小企業診断士として、経営コンサルティングを生業としていますが、人手不足対策に関するご相談も数多くいただきます。
私は、かつてガソリンスタンドを運営する企業に21年間在籍し、うち13年間は店長を担いました。店長経験が浅い頃は、人材がなかなか定着せず、新規に雇用しても退職者が相次ぎました。多い時には、年間70人以上のスタッフが私のもとを去り、深刻な人材不足に陥っていました。
そのような中、私は店長職を担いながら中小企業診断士の受験勉強を開始しました。組織論も学びましたが、今回ご紹介するモチベーション理論はとくに現場で非常に役立ちました。これにより人材の定着率が劇的に改善され、最終的にはこれから就職活動をするべき大学生のアルバイトスタッフが当社への就職を希望するようになりました。
当時の経験のほかに、コンサルタントとして学んださまざまな知見も踏まえて、人材不足対策を述べます。
人材不足という問題は、新規採用が不足しているというよりも、既存人材の離職が過多であるという構造的な問題だと考えられます。したがって、人材不足対策の第一歩は、離職率の抑制、すなわち既存人材の定着率向上に焦点を当てるべきです。これは、バケツに水を溜めようとする場合、まずはバケツの底に開いた穴をふさぐ必要があることと同じです。
人材の流出を止めるには、前述した「組織の成立要件」を満たすことが必要ですが、今回はその中の「貢献意欲」について見ていきます。
「動機づけ=衛生理論」とは
貢献意欲とは、共有する目的を達成するために、従業員が貢献したいと思う意欲の強さを指します。これが強い人材は、積極性が高く、自分が所属する組織に対して大きな満足感を持つものです。このようなモチベーションはどのようにして高まっていくのかについて、アメリカの臨床心理学者ハーズバーグが提唱した「動機付け=衛生理論」を解説します。
「動機づけ=衛生理論」によると、人材のモチベーションは、最初は中立的な状態、つまり「プラスマイナスゼロ」からスタートします。この状態の人材が仕事を通じて満足感を得ると、モチベーションは向上し、積極的な姿勢を見せるようになります。一方で、仕事をして不満を感じると、モチベーションは低下し、消極的な態度に変わるとされています。
仕事をすることで満足感を得た場合は「動機付け要因」が満たされた状態であり、その要因の具体例としては、承認、責任、達成感、仕事そのもの、昇進などが挙げられます。これに対して、仕事をすることで不満足感を得た場合は「衛生要因」が満たされていない状態であり、その要因の具体例としては、会社の方針、上司の監督、給与、人間関係、労働条件などが挙げられます。
つまり、「動機づけ要因」は満足感を左右し、「衛生要因」は不満足感を左右する要因であると言えます。よって、「動機づけ要因」を充足させれば満足度が上がりモチベーションが向上しますが、充足させなければ満足度が下がりモチベーションが減退します。ただし、その減退幅はプラスマイナスゼロ止まりであり、マイナスの領域には及ばないとされます。
これに対して、「衛生要因」を充足させなければ不満足度が大きくなり、最終的には退職してしまいますが、充足させれば不満足度が小さくなり、モチベーションは向上します。ただし、それによるモチベーションの向上はプラスマイナスゼロ止まりであり、プラスの領域には及ばないとされます。これはなぜなのでしょうか。
「衛生要因」に限界のある理由
ハーズバーグによると「衛生要因」としては以下が挙げられています。
| 会社の方針:会社が進むべき明確な方向性 上司の監督:上司の部下に対する明確な指示やサポート 給与:労働に見合った報酬 人間関係:上司・同僚・部下との良好な関係 労働条件:安全・安心な職場環境 |
例えば、一般的に人材は高い給与を期待するとされています。とはいえ、自身の能力、会社の状況、業界動向などを踏まえ、ある程度の「相場」を意識しているため、とにかく闇雲に昇給をさせたとしてもモチベーションは一定範囲に留まります。相場を無視した極端な昇給が不安を呼び起こすことは想像に難くありません。
同様に、人間関係を改善したとしても、その人間関係に一定の満足度を感じるので、それ以上の改善は期待しないという「天井感」が働くものです。そのため、人間関係の改善は一時的なモチベーション向上にはつながりますが、長期的かつ大きなモチベーション向上にはつながりにくいと言えます。
このような「相場」「天井感」のない動機づけ要因を充足させることが、モチベーション向上に効果的といえます。
ハーズバーグによると「動機づけ要因」としては以下が挙げられています。
| 承認:上司・同僚・部下など周囲から認められること 責任:重要な仕事や大きな仕事を任されること 達成感:目標を達成したり、課題を克服したりすること 仕事そのもの:やりがいのある仕事や、自身の適性を活かせる仕事に取組むこと 昇進:キャリアアップを実現したり、より上位の役職へ進んだりすること |
これらの要因は、「相場」「天井感」がなく、充足すればするほどモチベーションがどんどん大きくなっていくとされています。
多くの場合、人材のモチベーションを向上させようと「衛生要因」の充実に目が向くものです。しかし、その効果は限定的であり、改善したとしてもより「衛生要因」の良い事業者があればそちらに人材は流れてしまうものです。つまり「衛生要因」の充足に基づいて定着する人材の心理は「この職場にとりあえず不満はないから働き続ける」という消極的なものです。
これに対して「動機づけ要因」の充足に基づいて定着する人材の心理は「この職場は満足感が高いから働き続けたい」という積極的なものといえます。
まとめ
人材の「貢献意欲」を高めるためには、給料や労働条件といった衛生要因だけでなく、承認や達成感といった動機づけ要因を充足させることが必要です。多くの場合、衛生要因の充足に重きを置きがちですが、その充足には限界があります。特に経営資源の質・量が不利になっている中小企業は衛生要因の充足が人材定着の決め手にはなりにくいといえます。
ある程度衛生要因を充足させたら、動機づけ要因の充足に取り組んだ方が効果は高いといえます。貴社においては動機づけ要因の充足のために、どのような取り組みを行うことができるでしょうか。
次回の記事では人材不足対策として、組織の成立要件の中の「コミュニケーション」を解説します。

執筆講師
三上康一(みかみ こういち)
株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役








