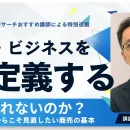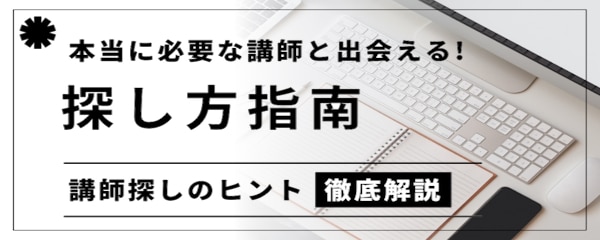理想の顧客を引き寄せる「引力」【櫻木隆志講師特別コラム】
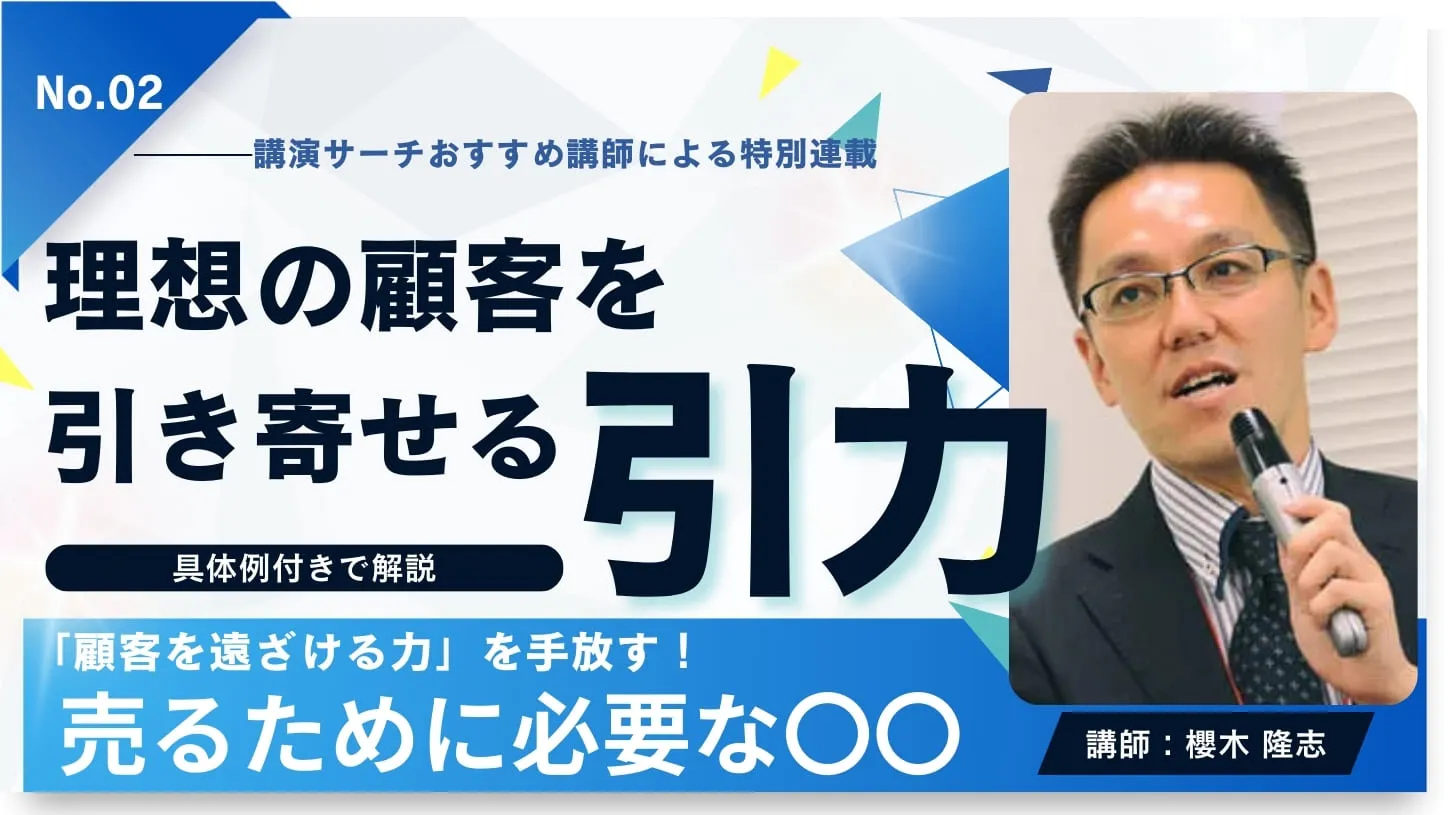

櫻木隆志(さくらぎ たかし)
(株)南九州デジタル 取締役笑倍繁盛事業部長
「笑倍繁盛 絆の会」主宰
理想の顧客を引き寄せる「引力」【櫻木隆志講師特別コラム】
目次
顧客を遠ざける力
あなたのビジネスには、顧客を遠ざける力が働いています。
あなたのビジネスに限りません。基本的にほとんどのビジネスには、顧客を遠ざける力が働いています。
それは、あなたのビジネスがビジネスだと思われていることです。
???
禅問答のようですが重要な真実です。これは前回の記事で書いた、ビジネスの定義の問題です。
現在の世の中では「ビジネス=利益目的で行われる活動」とされています。辞書にそう書かれています。つまり「ビジネス=利益目的」というのが常識であり、人々の共通認識。
つまりあなたのビジネスに限らずどんなビジネスも、ビジネスである限り、それは利益目的で行われているものだと思われています。
そして私たちは誰もが、利益目的の人には会いたくありません。売り込まれるのは嫌だし、いい人そうに見えてもビジネス(利益目的)なんでしょう…と勘ぐり、近寄りません。
たとえばアパレルショップで服を見ている時に店員さんが近づいて来たら、その場を離れたりしませんか。あれが、顧客を遠ざける力です。磁石の同じ極同士のように、近づこうとすると離れる力が働くのです。
ビジネスだと思われる=利益目的だと思われる=顧客を遠ざける力が働くということです。
あなたはこの「顧客を遠ざける力」を認識していますか?その力にどのように対処していますか?
顧客を引き寄せる力
この「顧客を遠ざける力」を無効化して、逆に「顧客を引き寄せる力」に変える方法があります。
それは、あなたのビジネスを再定義することです。
再定義と言っても、商品を変えたり、ターゲット顧客を変えたり、ビジネスモデルをつくり直したり、、、そんなことをする必要はありません。
売っている商品も変えず、ターゲット市場や顧客も変えず、自社の強みや特徴もビジネスモデルも変えなくていいです。
問題は、あらゆるビジネスに作用している「顧客を遠ざける力」です。これを無効化したいのです。逆に「顧客を引き寄せる力」に変えたいわけです。
そのために再定義しなくてはならないのは、WHAT(商品やサービス)ではありません。HOW(売り方や特徴など)でもありません。「WHY」です。なぜ、何のためにそのビジネスをやっているのか、なぜその商品を売るのか、あなたがそのビジネスをやっている理由、その商品やサービスを売っている理由です。
顧客を遠ざける力が働くのは、常識どおりの利益目的のビジネスだと、無意識的に思われるからです。だから利益目的ではない(常識どおりではない)ビジネスだと思われたら、顧客を遠ざける力を無効化できます。
ではどうすれば、「利益目的ではない」と思われるのでしょうか?「我が社は利益目的ではありません」などとメッセージを発信したところで、誰も信じてくれません。わざわざそんな発信をすると、逆に怪しい会社と思われます。
「利益目的ではない」と発信するのではなく、利益ではないあなたのビジネスの目的を発信するのです。
利益以外の何かのためにそのビジネスをやっているということが伝わり、その目的に納得してもらえたら、顧客を遠ざける力が無効化されます。さらにその目的に共感されたら、逆に「顧客を引き寄せる力」が働き始めます。
WHAT(商品・サービス)もHOW(強みや特徴)も、WHYを実現するための手段。顧客を遠ざけるのも、引き寄せるのも、WHYの力なのです。
顧客を引き寄せるWHYの具体例
それでは、顧客を引き寄せる「WHY」の具体例を見ていきましょう。
Apple(アップル)
HOW: 使いやすく、美しいデザインと直感的なUIを提供
WHAT: iPhone、Mac、iPadなどの製品
→ Appleは、単にコンピュータを作る企業ではなく、「人々の創造力を解放し、世界を変えるツールを提供する」ことをブランドの核としています。この理念が、Appleの熱狂的なファンを生み出し続けています。
Patagonia(パタゴニア)
HOW: 環境負荷を最小限に抑えた製品づくり、リペアサービスの提供
WHAT: アウトドアウェア、ギア
→ パタゴニアは「単に服を売る会社」ではなく、「環境保護を使命とする企業」としてブランドを確立しています。例えば、「Don’t Buy This Jacket(このジャケットを買わないで)」という広告キャンペーンでは、消費主義を抑え、環境への配慮を訴えました。この一貫したメッセージが共感を呼び、ファンを増やしています。
参考:Patagonia Stories「「Don’t Buy This Jacket(このジャケットを買わないで)」:ブラックフライデーとニューヨーク・タイムス紙」
スターバックス
HOW: 高品質のコーヒーと、居心地の良い空間の提供
WHAT: コーヒー、フード、グッズ
→ スターバックスは単なる「コーヒーチェーン」ではなく、「第三の居場所(サードプレイス)」としての価値を提供するブランドです。この理念が、単なるコーヒーの味だけでなく、体験としてのブランド価値を高めています。
IKEA(イケア)
HOW: 手頃な価格でデザイン性の高い家具を提供
WHAT: 家具、インテリア用品
→ IKEAは「家具を売る会社」ではなく、「誰もが手軽におしゃれで快適な暮らしを実現できるようにする」ことをミッションに掲げています。シンプルな組み立て式の家具や、スウェーデンのデザインを取り入れた製品が、世界中で支持されています。
誰もが知っている有名な企業のWHYの事例を並べてみました。当然ながら、WHYの力は大企業だけに働くわけではありません。中小零細企業や個人事業にも同じように働きます。むしろ、経営者の想いが直接的に顧客に伝わる中小企業や個人事業の方が、WHYの力が働きやすいとも言えます。
街の電器屋さんでも証明されたWHYの力
私はこのWHYの力のブランディングを、全国各地の街の電器屋さんと一緒に実践してきました。
街の電器屋さんが売っている商品(WHAT)は、家電製品です。最近は電気、ガス、水回り、家のリフォームなどもやっているお店が多いです。
街の電器屋さんのHOW(強みや特徴)は、親切な接客、丁寧な工事、何かあったらすぐ駆けつける迅速さ、顧客の暮らしを理解し最善の提案ができること…等、顧客との関係性やサービス、そして店主や社員の人間性です。
では、街の電器屋さんのWHYは何か?
これは、当然ながら一概には言えません。WHYとは、人それぞれの価値観、信念、ビジョン等によるので、経営者ひとりひとりにそれぞれのWHYがあります。さらに言えば、働いているスタッフひとりひとりにもそれぞれのWHYがあります。
以下はその一例です。
・すべてはみんなの笑顔のために
・お客様と家族のような絆でつながり一緒に笑顔になる
・安心して笑顔で暮らせる街づくり
・この街の母屋のような存在でありたい
・
・
どのお店も、売っているのはエアコンとか冷蔵庫といった家電製品や、家の困りごと解決やリフォームなどですが、それらを売ることが電器屋さんの目的ではありません。
困ったをありがとうに変えることだったり、みんなを笑顔にすることだったり、街の母屋のような存在であることだったり、それらが電器屋さんをやっている理由でり目的です。
それぞれのお店にそれぞれのWHYがあり、家電製品を売るのも、家のリフォームをするのも、すべてそのための手段なのです。
電器屋さんがリフォーム事業もやっていることも、WHYの発信がなければ、「最近は家電だけじゃ厳しいからリフォームもやってるんだね」と思われてしまいます。しかしWHYがあれば、「困ったをありがとうに変えるためにリフォームもやってるんだね」と納得してもらえます。
そういうブランディングを行うと、そのWHYに共感した人が自然と顧客になり、売ろうとしなくても自然に売れるようになります。さらにそうした顧客はただモノを買うだけではなく、その店を応援してくれるようになります。それはWHYに共感しているから。共感したWHYを実現することに協力してくれたり応援してくれたりするのです。まさに理想的な顧客、理想的な関係性になるのです。
こうして、顧客を遠ざける力が、顧客を引き寄せる力に変わるのです。
まとめ
今回は、顧客を遠ざける力と、顧客を引き寄せる力についてお伝えしました。
WHYを発信しなければ、利益目的のビジネスだと思われて、顧客を遠ざける力が働きます。
WHYを発信して、それに共感されたら、顧客を引き寄せる力が働き、売ろうとしなくても自然に売れるようになります。さらには顧客から応援されるようになります。
ぜひ、あなたも自分のビジネスのWHYを明確にして、発信してみてください。