人手不足解消の鍵はここにある!経営理念が組織にもたらす力と、3社の事例から学ぶ成功の秘訣【三上康一講師特別コラム】
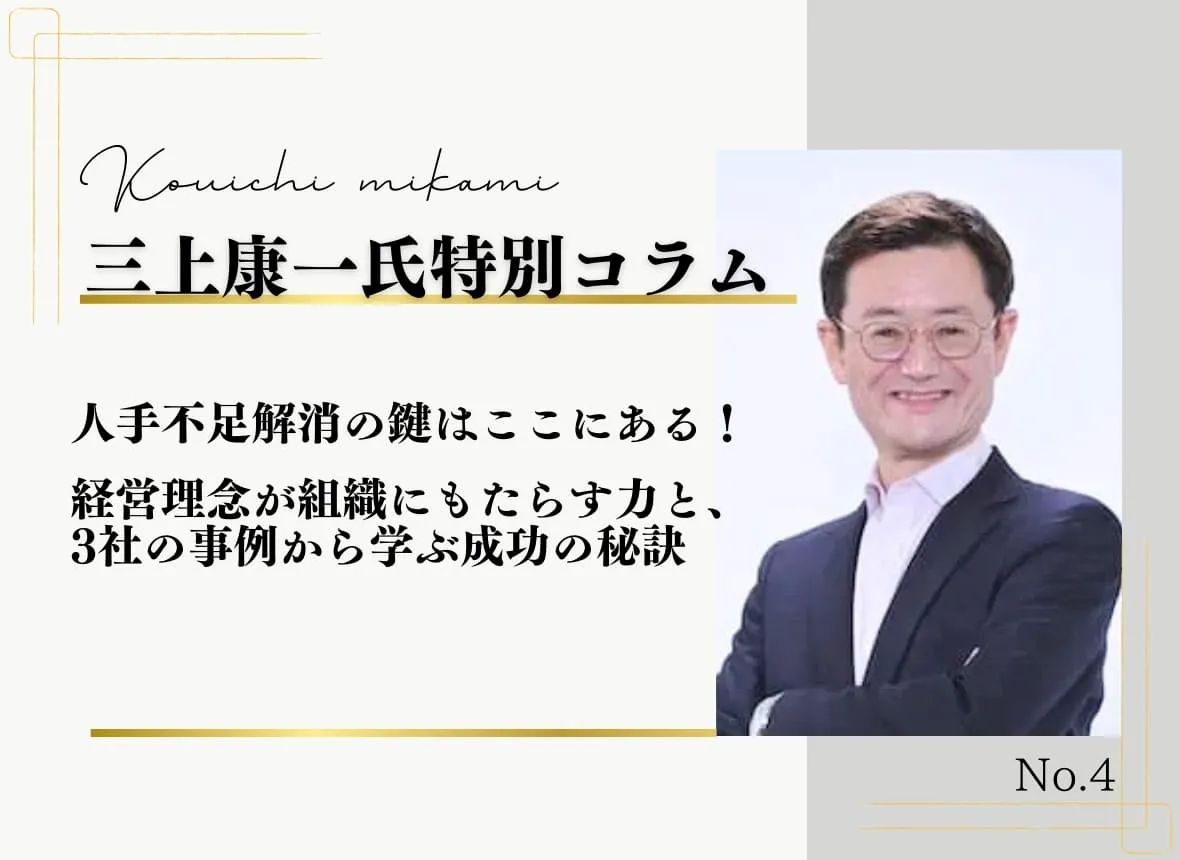

執筆講師
三上康一(みかみ こういち)
株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
人手不足解消の鍵はここにある!経営理念が組織にもたらす力と、3社の事例から学ぶ成功の秘訣【三上康一講師特別コラム】
目次

■はじめに
人手不足が深刻化する中、以下の記事では、中小企業が人材不足を克服するために「共通目的」を持つことの重要性を解説し、具体的な事例として私がガソリンスタンドで店長を担っていた頃の経験をご紹介しました。
経営理念とは、企業が「なぜ存在するのか」という根本的な問いに対する答えであり、企業活動の指針となるものです。これは単なるスローガンではなく、企業が目指すべき方向性を明確に示し、その方向に従業員が一丸となって進むための「共通目的」を形作るものです。
上記のリンク記事で述べたように、中小企業が人材不足を克服するために重要なポイントとして、「共通目的」を持つことが挙げられます。これがあることで、単なる人材の集合は組織として機能することとなります。経営理念は、まさにその「共通目的」を示し、企業の行動原理を作り上げる核となります。
この記事では、3つの企業の取組みを深掘りし、「共通目的」として経営理念が組織にもたらす影響について考察します。
■株式会社でん六の経営理念「豆を究め、喜びを創る」がもたらす効果
山形県山形市に本社を置く菓子メーカー、株式会社でん六は、1924(大正13)年に鈴木傳六(すずきでんろく)氏が創業しました。現在(※記事執筆時点)は創業者の孫にあたる鈴木隆一氏が3代目の経営者となっています。鈴木現社長は先代から経営を引き継いだ際に、「でん六は何のために存在しているのか」という点を考え直してみました。
その中で生まれたのが、「豆を究め、喜びを創る」という経営理念でした。この経営理念の特徴は「喜」という字には「豆」が含まれていることを意識した点です。これは、単に商品を作ることにとどまらず、企業の根底にある「豆」に対する深いこだわりと、それを通じて人々に「喜び」を提供するという高い志を表現しています。
「豆を究める」とは、でん六が豆という素材に対してどこまでもこだわり、品質を追求し続けるという姿勢を示しています。豆の栽培方法から加工、味のバリエーションまで、全てにおいて妥協しないことを約束しています。このこだわりが消費者の信頼を得る土台となり、他の菓子メーカーと差別化する大きな要素となっています。
そして、経営理念のもう一つの要素である「喜びを創る」には、でん六が提供する商品を通じて、消費者や取引先、さらには社員全員に「喜び」を届けるという強い意志が込められています。
この経営理念が社員に与える影響は大きく、組織全体が一丸となって「豆を究め、喜びを創る」ことに向かって日々の業務に取り組むことが、でん六を現在の成功へと導いています。
参考:株式会社でん六
■ホームセンター「ダイシン気仙沼店」の震災対応と経営理念
宮城県仙台市に本社を置き、生活用品の企画・製造・販売を行うアイリスオーヤマ株式会社は、経営理念として「ユーザーイン」—顧客目線で顧客のニーズを満たすこと—を掲げ、グループ全体でその実現に向けて取り組んでいます。
このアイリスオーヤマには、多数の子会社がありますが、そのひとつに宮城県を中心にホームセンター「ダイシン」を展開する株式会社アイリスプラザダイシンカンパニーがあります。ここでは、グループ企業内で共有された経営理念が有事の際に活用された事例をご紹介します。
2011年3月11日、東日本大震災は未曾有の被害をもたらし、無数の命と暮らしが奪われました。その中でも宮城県気仙沼市に立地する「ダイシン気仙沼店」は、経営理念に基づく誠実な対応で地域の人々を支えました。
震災当日、店内は一面水浸しとなり、停電も発生するなど、営業どころではない状況に見舞われました。しかし、震災後に生活必需品を求めて殺到した被災者を助けるべく、店長は、財布を持たない被災者に対し、名前と連絡先、商品代金をノートに記入してもらい、後日支払いをお願いするという形で商品を提供しました。驚くべきことに、後日ノートに記された全ての人が全額を支払いに訪れました。
さらに、同店は寒さに震える被災者1名1名に灯油10リットルを無料で配布しました。この行動を目の当たりにしたテレビ局の取材に対して、店長は「クビになるかもしれません。それでもいいんです。」と言いました。
親会社であるアイリスオーヤマの大山健太郎社長は、店長の行動を非常に高く評価し、「誇りに思う」と語りました。震災直後の厳しい状況下でも、経営理念に基づき、誠実に行動した店長の姿勢は、今もなお多くの人々の心に刻まれています。
現在、ダイシン気仙沼店は地域内で最も売上が高い店舗となっています。これは、震災時に助けてもらったことを決して忘れない地域住民が、「どうせ買うなら助けてくれた店で買いたい」と思うからに他なりません。このように、震災を通じて築かれた信頼は、単なる経済的な取引を超えた深い絆となり、地域社会における不動の信頼を勝ち取る結果となったのです。
ダイシン気仙沼店の店長は、企業グループ内で共有された経営理念である「ユーザーイン」を深く理解し、実践することで、顧客からの信頼を獲得し、従業員がやりがいを感じ、誇りを持てる職場を作り上げました。このように従業員が自分の仕事に価値を見出し、組織に貢献していると感じられるような環境づくりが、人手不足対策に繋がるといえます。
参考:住まいと暮らしのDIYセンターダイシン
参考:アイリスオーヤマ株式会社
ここまで経営理念の効果について事例をご紹介してきましたが、以下では、経営理念の策定プロセスについて事例をご紹介します。
■ぴあ株式会社の経営理念策定プロセス
東京都渋谷区に本社を置き、チケット事業・出版事業を展開する「ぴあ株式会社」は、1990年代後半にさまざまな事業に手を広げました。部署や社員が増える中で、経営者は、企業全体の方向性が曖昧になりつつあることに気づきます。
この時、社員が経営者に対して「企業の方向性が見えなくなってきた」と直接意見を言う場面がありました。この指摘は、経営理念が明確でないことが原因であると気づかせてくれました。
経営者は、自身の創業からの経験をもとに「社会があって自分たちがある」「社会に役立って初めて自分たちの存在意義がある」という思いを持っていました。しかし、その思いは社員には十分に伝わっていなかったのです。この気づきは、経営理念を再構築する必要性を強く感じさせるものでした。
経営者は、経営理念を作り上げるために社員との対話を重要視します。最初のステップとして、社員たちに自身の考えを伝えることから始めました。経営者のインタビュー記事や過去の経験を社員と共有し、企業の方向性や価値観について語りかけました。
社員は、経営者の思いを理解し、自分たちの会社がどのように社会と向き合っていくべきかを考えました。このプロセスを通じて、経営理念の骨子が見えてきましたが、理念が完全にまとまるまでには、約2年もの時間を要しました。
最終的に同社の経営理念は「ぴあアイデンティティ」という形でまとめられました。この理念は、利益の追求と社会貢献を車の両輪として進むことを目指したものです。具体的には、「ぴあアイデンティティ」には、社会に価値を提供し、顧客の生活を豊かにすることを目指し、社員一人ひとりが生き生きと仕事をし続けることが求められました。このように、企業の使命と社会的貢献を掲げた理念が、ぴあの方向性を示す指針となったのです。
参考:ぴあ株式会社
■まとめ
経営理念は、企業の羅針盤であり、社員一人ひとりの行動指針となるものです。経営理念を策定し、社員に浸透させることで、企業は組織となり、人手不足に対応できるでしょう。
経営理念を作る上では、社員の意見を聞き、具体的な行動指針を示し、トップが率先して実践することが重要です。また、社員に浸透させるためには、継続的にコミュニケーションをとることが大切です。
経営理念は、企業の文化を醸成し、社員のモチベーションを高め、ひいては企業の成長に繋がります。ぜひ、経営理念を策定し、組織全体の活性化につなげてください。

執筆講師
三上康一(みかみ こういち)
株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役









