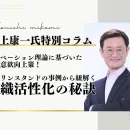部下のモチベーションを低下させる「パフォーマンス・キラー」から脱却して組織を活性化させる方法【三上康一講師特別コラム】
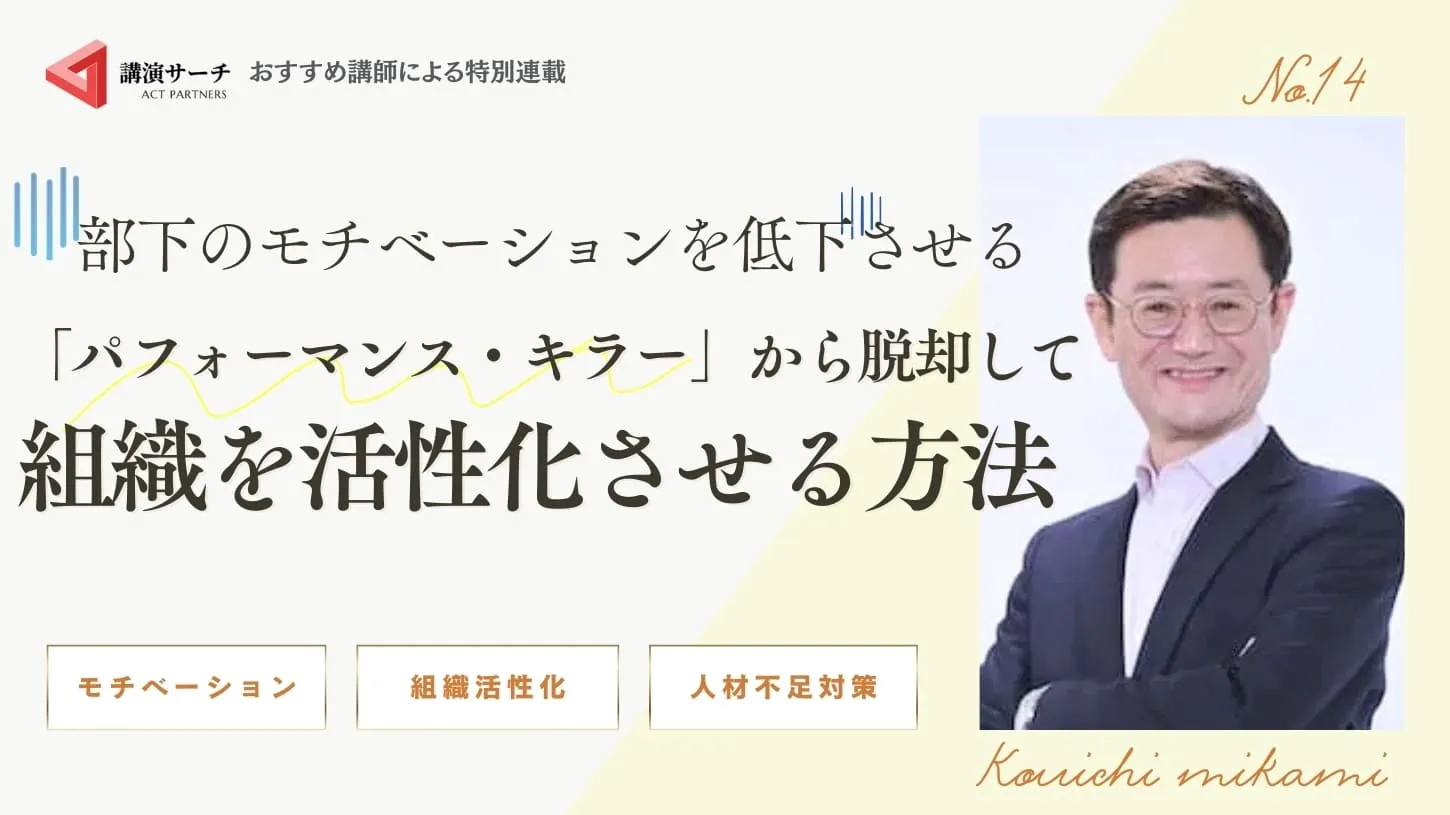

部下のモチベーションを低下させる「パフォーマンス・キラー」から脱却して組織を活性化させる方法【三上康一講師特別コラム】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
■はじめに:人材不足とモチベーション低下の悪循環
「人が辞めていく…」「常に人手不足…」もし、あなたの職場がこのような状況であれば、それは深刻な悪循環に陥っているサインかもしれません。
従業員が企業を去る理由の多くは「モチベーションの低下」です。その企業で働く意欲を失ってしまった人材は当然流出し、人員が不足します。それを補うために新たな人材を求めても、根本的な原因であるモチベーション管理が改善されなければ、同じく流出が繰り返されます。結果として、慢性的な人材不足、過重労働によるさらなる離職、そして最悪の場合、組織の崩壊へとつながってしまうのです。
では、どのようにすればこの悪循環を断ち切ることができるのでしょうか?
その答えは、「部下のモチベーションを高く保つこと」に他なりません。そして、モチベーション管理において最も重要なことは、「モチベーションを高める前に、モチベーションを下げないこと」です。
■「パフォーマンス・キラー」とは?:部下のやる気を奪う言動
部下のやる気を著しく低下させる言動、それが「パフォーマンス・キラー」です。どれほど素晴らしい施策を講じても、上司自身が「パフォーマンス・キラー」である限り、その効果は期待できません。
私はガソリンスタンドの運営会社に21年間勤務し、そのうち13年間は店長として現場を担当していました。店長としての経験が浅かった頃、私もこの「パフォーマンス・キラー」の言動を繰り返し、結果的に深刻な人材不足を招いていました。しかし、自分の言動を見直し、「パフォーマンス・キラー」から脱却したことで、職場のモチベーションが改善され、業績も向上しました。
現在は中小企業診断士として経営支援を行っており、過去の経験を活かして多くのリーダーに「パフォーマンス・キラー」から脱却する方法をアドバイスしています。これを実践することで、部下のモチベーションを高め、組織の活性化につなげることができると確信しています。
以下では、「パフォーマンス・キラー」の具体的な類型を紹介し、効果的な改善策を提案していきます。
■具体的な「パフォーマンス・キラー」9つのパターン
(1)批評:否定的な言葉で部下を傷つけてしまう
部下に対して、上司が自分の価値観に基づき、一方的に評価や判断をすることです。例えば、営業部長が部下に対して「経理しかやったことのない奴はこれだから使えないんだよ」と発言することは、部下にしてみると自分の言動が全否定されたと感じ、モチベーションは低くなってしまうでしょう。
(2)レッテル貼り:部下を一括りにして扱ってしまう
部下を一人ひとりの個性としてではなく、部下全員を一括りにしてしまうことです。例えば、「うちで働く連中はみんなそういうことを言うんだよね」といった言葉は、部下にしてみると自分の個性や意見が無視されていると感じ、モチベーションは低くなってしまうでしょう。
(3)表面的な賞賛:心のこもらない言葉で部下を傷つけてしまう
部下の言動やそれに基づく成果に対して、事実に基づくフィードバックをせず、表面的な褒め言葉を投げかけることです。例えば、「よく頑張っているね」と言いつつも、具体的に上司が何を評価しているのかを伝えない場合、部下は自分の言動や成果が本当に認められているのか疑問に思い、モチベーションは低くなってしまうでしょう。
(4)相手を無視したアドバイス:現状を確認しないまま指導してしまう
部下が置かれている状況や、本人が抱えている課題をしっかり理解せずに、一方的なアドバイスをしてしまうことです。例えば、時間を守ることができなかった部下に対して「仕事に対する意識を高く持ちなさい」と一般論を述べても、部下としては上司から親身なサポートを受けていないと感じがちであり、モチベーションは低くなってしまうでしょう。
(5)押し付け:一方的に決定し強制してしまう
上位の役職であるという立場を利用して、部下の言動や意見を無視し、とにかく物事を推し進めようとしてしまうことです。例えば、なかなか行動を起こすことができない部下に対して「グズグズ考えてないでとっととやれ!」と怒鳴っても、部下の自主性が奪われ、自分では何も決められないと感じ、部下のモチベーションは低くなってしまうでしょう。
(6)脅迫:恐怖心を利用してコントロールしようとしてしまう
部下が自主的に決定したように見えるものの、あらかじめ上司が決めておいた結論にしないとその部下に不利になるように条件を提示し、誘導することです。例えば、残業を依頼し、それを渋る部下に対して、降格や減給を匂わし、残業することに従わせたとしても、その部下の行動は恐怖心に基づくものですから、本来の実力を発揮できなくなりますし、上司に不信感を抱き、モチベーションは低くなってしまうでしょう。
(7)転嫁:責任を押し付け、問題の本質から逃避してしまう
上司が問題の本質から目を逸らしてしまい、別の話題にすり替えてしまうことです。例えば、成果が出ない部下がその原因として「人材が不足しているんです」と述べた際に「じゃあ人材を雇えばいいじゃないか」と的外れな発言をしてしまうと、部下としては、上司が自身の責任を回避したり、問題解決を先延ばしにしたりしていると感じ、モチベーションは低くなってしまうでしょう。
(8)理論武装:一方的な論理展開でコミュニケーションを遮断してしまう
上司が自分自身の意見について論理的に裏付け、部下に押し付けることです。例えば、部下から仕事上の新しいアイデアを提案された場合に、論理的な根拠に基づき「そのアイデアは非現実的じゃないのか」と取り合わないことは、一見、合理的かつ正しいように見えますが、部下としては、自身の置かれた状況や感情を考えていないように見え、モチベーションは低くなってしまうでしょう。
(9)元気づけ:空虚な励ましで問題を矮小化する
上司が部下に対して、具体的な解決策を示さずに、安易な言葉で励まそうとすることです。例えば、「仕事で悩んでいる」と部下から相談された際に、きちんと話を聞かないまま「君ならきっと大丈夫だよ」と安易に励ましてしまうと、部下が抱えている悩みを軽んじているように感じさせてしまい、部下のモチベーションは低くなってしまうでしょう。
■「パフォーマンス・キラー」の留意点
この記事では、部下のモチベーションを著しく低下させる「パフォーマンス・キラー」の具体的なパターンを9つご紹介しました。これらの言動は、一つひとつが独立しておらず、組み合わせて使われているケースが多々あり、ご自身のパターンを見極める必要があります。かつての私は(4)相手を無視したアドバイス、(5)押し付け、(6)脅迫を多用していましたが、これらを組み合わせることも多かったと思っています。
また、効果的なモチベーション管理は、まず「パフォーマンス・キラー」を排除することから始まることは前述のとおりですが、どんな状況でも「パフォーマンス・キラー」の9類型を排除するべきとは言えず、状況によっては却って効果を発揮できることも留意したい部分です。例えば、緊急時や危機的な状況下では、迅速な意思決定や指示が必要となる場合があり、ある程度の「押し付け」や「脅迫」が有効となる可能性があるでしょう。
■「パフォーマンス・キラー」から脱却するためのポイント
以上を踏まえ、部下のモチベーションを高めるためには、以下の点に留意しましょう。
| 傾聴と共感 | 部下の意見や感情に耳を傾け、共感する姿勢を示す。 |
| 個別対応 | 部下一人ひとりの個性や状況を理解し、適切な対応をする。 |
| 具体的なフィードバック | 成果や行動に対して、具体的かつ建設的なフィードバックを行う。 |
| 主体性の尊重 | 部下の自主性を尊重し、意思決定に関与させる。 |
| 信頼関係の構築 | 部下との信頼関係を築き、安心して意見交換できる環境を作る。 |
上司が「パフォーマンス・キラー」から脱却し、これらのポイントを実践することで、部下のモチベーションは確実に向上し、組織全体の活性化に繋がるでしょう。
リーダーの皆様が「パフォーマンス・キラー」から脱却し、部下のモチベーションを高め、組織の発展に貢献されることを心より願っています。部下のモチベーションを上げようとする前に、自身の行動が部下のモチベーションを下げていないかを検証し、柔軟で適切なリーダーシップを発揮することが、企業にとって最も重要な課題といえるでしょう。
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役