人材定着率向上の鍵は「傾聴」にあり!リーダーの反応準備バイアス克服法【三上康一講師特別コラム】
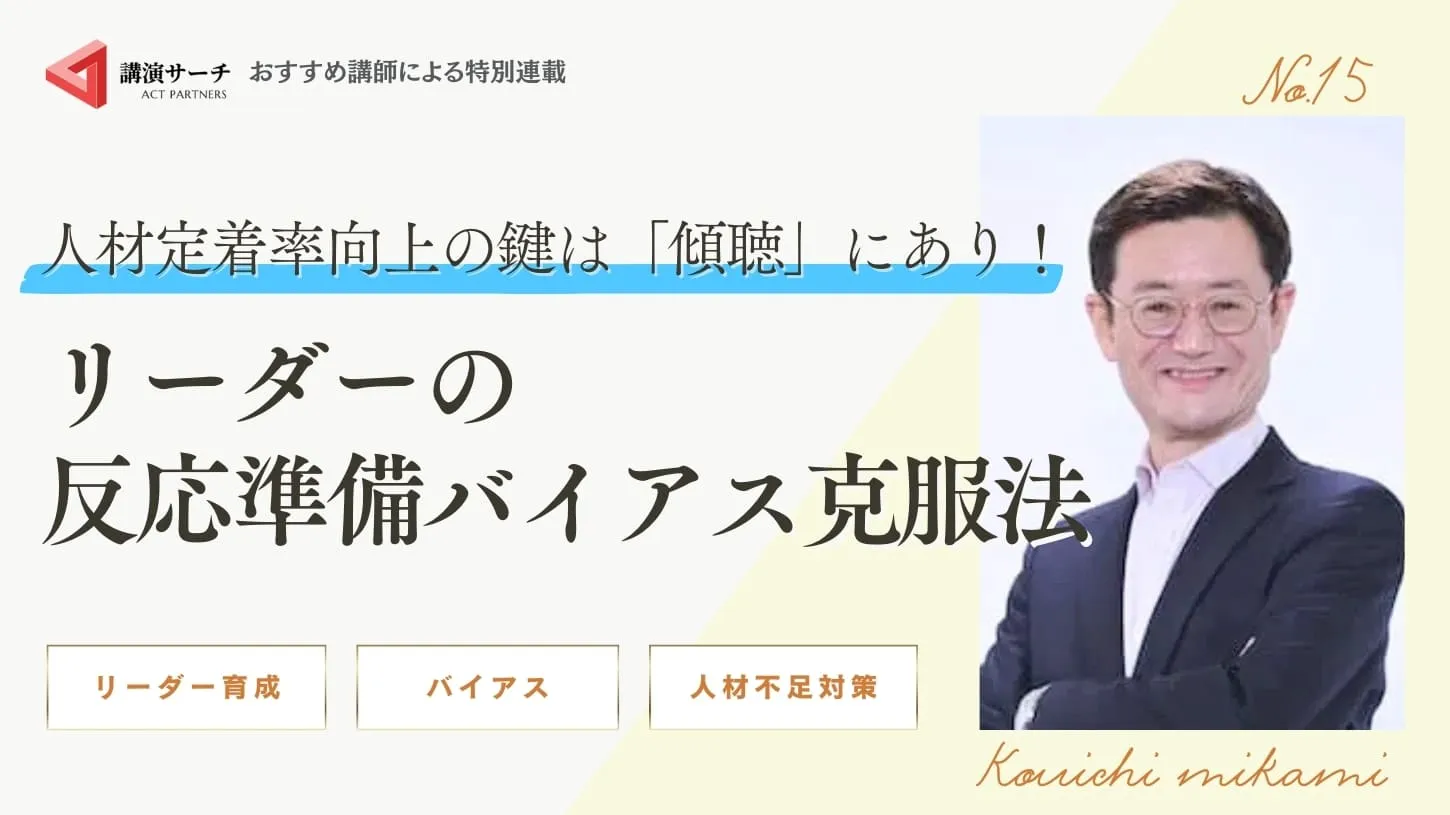

人材定着率向上の鍵は「傾聴」にあり!リーダーの反応準備バイアス克服法【三上康一講師特別コラム】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
■人材不足解消の鍵は「傾聴」にあり
職場の人材不足を招いた原因の多くは既存人材の退職ですから、人材不足解消のカギは、既存人材の定着率を向上させることといえます。そのための施策のひとつに、リーダーが部下の話を傾聴することが挙げられます。これにより信頼関係の構築、心理的安全性の確保などが期待できるためです。人間は自分の話に耳を傾けてくれる人を信頼しますし、何でも話せるリーダーが率いる職場は安心して働けるものです。
しかし、部下の話を傾聴できないリーダーは意外と多いものです。このようなリーダーは「聞く」ことよりも「話す」ことを重視しがちであり、これを改善するためには、「反応準備バイアス」を知ることがポイントとなります。
■傾聴を阻む「反応準備バイアス」とは?
「バイアス」とは、人間が意思決定をしたり、物事を判断したりする際の偏りや思い込みのことを指し、200種類以上のバイアスが存在する(※)とされています。その中のひとつ「反応準備バイアス」は、相手が話している途中で、自分は次に何を発言しようか、どのような反論をしようかと考える傾向を指します。このバイアスにより、人は集中力が削がれ、傾聴を阻む要因となります。
※参考:東京大学「令和4年度 産業経済研究委託事業 (ダイバーシティ経営推進に向けた アンコンシャス・バイアス研修のあり方と 効果測定指標等に関する調査) 事業実施報告書」
また、話している方も「聞かれた感」を抱くことができず、「本当に理解してもらえたのだろうか」という懸念を持ちます。これは、不信感を持ったままコミュニケーションが終了してしまったり、きちんとした「聞かれた感」を抱くために同じ話を繰り返して話が長くなってしまったりなどというリスクがあります。
実は、かつての私は非常に強い反応準備バイアスを持っていました。
■私の体験:反応準備バイアスと傾聴の重要性
私はガソリンスタンドの運営会社に21年間勤務し、13年間は店長として現場で働いていました。店長としての経験が浅かった頃は、強い反応準備バイアスを持っており、部下の話をしっかり傾聴できず、自分の指示を押し付け、命令ばかりしていました。これにより、部下の自立性は育たず、退職者が相次いでいました。
しかし、コーチングに出会い「傾聴」の重要性を知りました。傾聴をするために「反応準備バイアス」を手放すよう努め続けた結果、徐々に傾聴スキルが高まったのです。それによって部下自身が自分で物事を考えるようになり、仕事のやりがいに結び付いていきました。そして、定着率が向上し、退職者は激減するとともに、業績向上にも結び付いていきました。
現在、中小企業診断士として経営コンサルティングを行う際にも、この「傾聴」を大切にしています。実際にクライアント企業の経営者やスタッフの話を傾聴することで、有効な解決策を見出せることがあります。また、傾聴をテーマにした社員研修にも登壇しています。以下では、この研修で実施するワークについて述べていきます。
■傾聴力向上のためのワークショップ
私が傾聴の社員研修に登壇する際には、以下のワークをやっていただきます。
(1)1回目のワーク
まず、受講者が2人ひと組のペアになっていただき、話す側と聞く側を決めます。話す側は自分が自慢できることを3分間で話し、聞く側は頭の中を空にしてひたすら聞くというワークをします。3分経過したら終了し、話す側と聞く側を交代して同じワークをします。
このワークを終えて感想を聞くと、「次に自分が話す内容を考えながら聞いていた」「3分は意外と長い」「他のペアの声が耳に入ってきて集中できなかった」などの声が上がりがちです。そして、これを踏まえ以下の「話を理解しているサイン」について受講者に向けて解説していきます。
| 頷き・相槌 | 長さや大きさ、頻度を意図的に変えるようにします。 |
| 繰り返し | 相手の話の中で重要だと思うポイントをそのまま繰り返します。 |
| 言い換え | 相手の話の内容を自分の言葉で言い換えます。言い換えた結果、理解が不足していれば、さらに説明を求めます。 |
これらのサインは下にいくほどハードルが高くなりますが、その分コミュニケーションの効果も高まります。
(2)2回目のワーク
この「話を理解しているサイン」を理解していただき、2回目のワークを行います。1回目と同じペアで、話す側と聞く側を決め、話す側は自分が最近嬉しかったことを話します。聞く側は「話を理解しているサイン」を使いながら聴きますが、終了のコールがあったら、話す側と聞く側を交代します。
この2回目のワークをやるとわかるのは、終了のコールを出してもなかなか話が終わらないことです。また、1回目よりも時間が短く感じます。これは、1回目よりも2回目の方が相手の話に没頭して聞くことができた結果といえます。また、1回目は頭の中を空にしようと意識していただきますが、2回目は話を理解しているサインを出すことを意識していただきます。結果として2回目の方が頭の中が空になりやすいことがわかります。
つまり、反応準備バイアスを手放そうと頑張るのではなく、話を理解しているサインを積極的に出す聞き方が傾聴に結び付きやすいということがいえます。とはいえ、これまで傾聴をして来なかった方が急に聞き方を変えることは違和感を抱くものです。そこで以下の提案をしています。
■反応準備バイアスに気づき、コントロールする
反応準備バイアスの対策として、反応を準備しておかないと本当に効果的なコミュニケーションができないのかを考える必要があります。
実際に、反応を準備しないで相手の話をひたすら聞くという体験をしてみると、コミュニケーションは成立するだけでなく、より効果的になることが理解できるはずです。とはいえ、長年反応準備バイアスを持ちながら生きてきたわけですから、違和感があるのは当然です。
そこで、相手の話を聞く場合に、毎回反応を準備しないのではなく、3回に1回とか2回に1回といった形で、反応を準備しないコミュニケーションを意識します。そして徐々にその頻度を多くしていきます。このように、反応を準備しないコミュニケーションを段階的に導入することによって、徐々に反応準備バイアスを手放していけるようになります。
そして、反応を準備しながら聞くよりも、準備しないで聞いた方が有効なコミュニケーションが成立することを認識できれば、反応準備バイアスは手放しやすくなります。結果として、その聞き方がご自身の通常の聴き方になっていくでしょう。これが、傾聴スキルが身についた状態といえます。
■まとめ:傾聴で組織を活性化し、人材定着率を向上させる
人材不足の解消には、既存の人材が定着し、モチベーション高く働ける環境をつくることが不可欠です。そのためには、リーダーが部下の話に耳を傾け、信頼関係を築くことが重要です。しかし、反応準備バイアスに囚われているリーダーが多く、そのバイアスを乗り越えるためには、まず「聴く」ことに意識することが必要です。
反応準備バイアスを手放すためには、反応を準備しないコミュニケーションを実践し、段階的にその頻度を増やしていくことが効果的です。また、「話を理解しているサイン」を意識し、反応の準備をしないようにすることで、コミュニケーションは深まり、最終的に定着率向上や業績向上につながります。
リーダーとして傾聴力を高めることで、部下の自立性を育み、強固な信頼関係を築くことができるといえるでしょう。日々のコミュニケーションにおいて、ぜひ今日から実践してみてください。反応準備バイアスを意識し、意図的に傾聴を行うことで、組織全体がより良い方向に進んでいくことを確信しています。
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役






