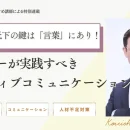【最新調査と対策】カスハラから従業員を守り抜け!人手不足時代の定着率向上と企業成長の鍵【三上康一講師特別コラム】
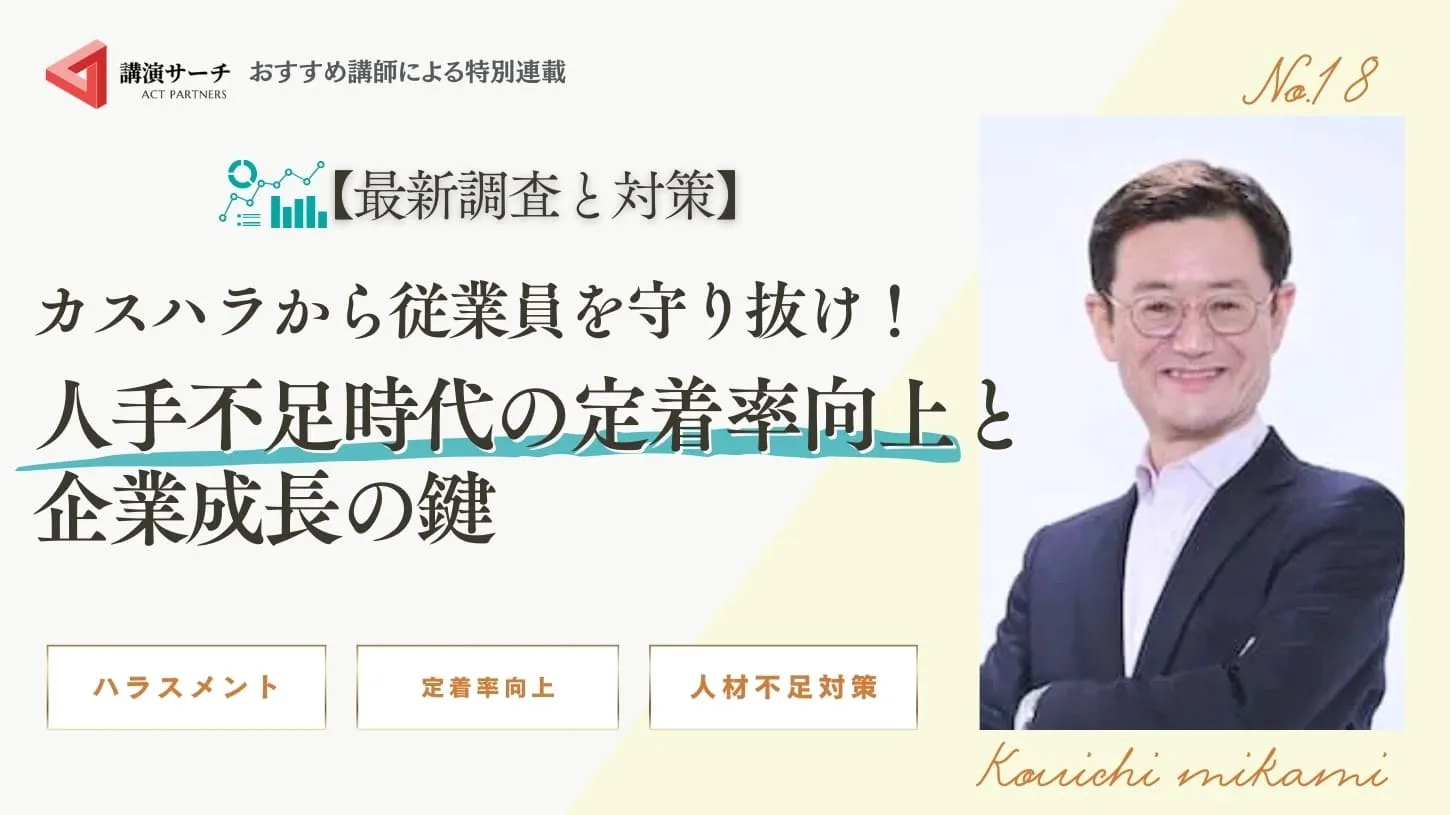

【最新調査と対策】カスハラから従業員を守り抜け!人手不足時代の定着率向上と企業成長の鍵【三上康一講師特別コラム】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
■人手不足とカスハラの深刻化
人手不足が深刻化するなか、企業にとって従業員が「働き続けたい」と思える職場環境づくりは、競争力を維持するための最重要課題となっています。そのカギを握るのが、今や社会問題化している「カスタマー・ハラスメント(カスハラ)」の対策です。
理不尽な要求や暴言にさらされ、職場や上司から十分なサポートを得られない環境では、従業員は安心して働き続けることができません。特に小規模事業者では、「顧客を失いたくない」「対応に手間をかけるほど人材がいない」といった理由から、対応が後手に回るケースも多く、結果的に人材の流出を招いています。
今回の記事では、カスハラ対策が従業員の定着率向上に直結し、長期的には企業の安定と成長を支える重要な施策であることを、最新の調査データとともに紐解いていきます。
■カスハラとは?顧客からの不当な要求・ハラスメントの実態
カスハラは、顧客や取引先などが、事業者や従業員に対して行う不当・理不尽な言動や要求を指します。本来、企業は顧客に対して誠実な対応を行うべき立場にありますが、その立場を利用して、以下のような行為を繰り返すケースであり、カスハラは社会問題化しています。
【具体例】
・不当な値引きや返金の強要
・暴言・恫喝・脅迫
・長時間にわたるクレーム対応の強要
・セクシャルハラスメント(セクハラ)
・土下座などの過剰な謝罪要求
・SNSなどでの公開処刑的な投稿をほのめかす
このカスハラについての調査結果が公表されました。
■【最新調査】サービス業の半数が被害経験:UAゼンセンの警告
日本最大の産業別労働組合であるUAゼンセンが、2024年6月5日に発表したサービス業の組合員3万人を対象としたカスハラ調査結果は、その深刻な被害状況を浮き彫りにしています。そのポイントは以下となります。
・過去2年以内に、46.8%もの組合員がカスハラ被害を経験。
・カスハラ行為者の年代別割合では、60代が29.4%と最も多く、その主な要求内容は謝罪や商品交換に集中する傾向。
・スーパーやドラッグストアといった小売業においては、60代の男性客によるポイント制度に関連したトラブルが、女性従業員に対して頻発。
・パチンコ業界や医療・介護・福祉分野においては、60代から70代の顧客による女性従業員へのセクハラ被害が比較的多い。
参照:UAゼンセン「”職場におけるカスタマーハラスメントの実態把握へ” 第3弾調査実施」
このような状況の中、対策に乗り出すケースも目立ってきました。
■動き出したカスハラ対策:従業員を守るための具体的取り組み
(1)自治体の動き:全国初のカスハラ防止条例
東京都は、2025年4月1日施行の「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」を制定しました。これは、顧客から従業者への理不尽な要求や暴言などの行為を防止し、就業環境の改善を図ることを目的としています。
条例では、カスハラは就業者の人格や尊厳を侵害し、事業の継続に悪影響を及ぼすものであるとの認識の下、社会全体でその防止が図られなければならないとしています。また、顧客等と就業者が対等の立場で相互に尊重することが防止の基本であると定めています。
具体的には、「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない」とし、カスハラを一律に禁止しています。ただし、顧客の正当な主張やクレームは顧客の権利であるため、その権利を不当に侵害しないよう留意することも求められており、東京都、顧客等、就業者、事業者のそれぞれに責務を課しています。
参照:東京都「「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」を策定しました」
(2)JR東日本グループの取組み
JR東日本グループは、2024年4月26日に「JR東日本グループカスタマー・ハラスメントに対する方針」を策定し、グループ全体に周知しました。この方針は、顧客からの貴重な意見や要望に真摯に対応する姿勢を堅持しつつ、公共空間で発生する悪質なカスハラ行為に対して、毅然とした対応を取ることを明確にしています。
近年、公共交通の現場では、顧客からの暴言や威圧的な言動、土下座の要求、さらには従業員の個人情報がSNSに投稿されるなど、深刻なハラスメント行為が報告されています。これらの行為は、従業員の尊厳を傷つけ、働きやすい環境を損なうものです。
JR東日本グループは、これらの行為に対しては、お客様への対応を中止するのみならず、悪質と判断される場合には警察や弁護士などの関係機関と連携し、法的措置を含む厳正な対応を行う方針としました。このアプローチは、公共交通機関としての信頼性を守り、従業員が安心して職務に従事できる環境づくりに貢献しています。
参照:JR東日本「カスタマーハラスメントに対する方針」
参照:日本経済新聞「JR東日本グループ、カスタマーハラスメントに対する方針を策定」
(3)個人店の自衛策:顧客を選ぶという選択
大企業だけでなく、顧客との距離が近い個人店においても、カスハラに対する意識は高まっています。SNS上では、横柄な態度を取る顧客には販売を拒否したり、タメ口での注文に対して料金を上乗せしたりするなど、独自の対策を講じる店舗の張り紙が散見されるようになりました。これは、小規模事業者であっても、従業員を守ることの重要性を認識し、売上至上主義から脱却する動きと言えるでしょう。
■なぜ今、カスハラ対策が加速しているのか:放置が招く負の連鎖
これまでも存在していたカスハラに対し、なぜ現在になって対策が本格化しているのでしょうか。その背景には、以下の要因が考えられます。
| 深刻な労働力不足 | 人口減少が進む日本において、人材の確保は企業の最重要課題です。カスハラが原因で従業員が離職することは、企業にとって大きな損失であり、採用コストや教育コストの増大を招きます。 |
| 従業員の意識変化 | カスハラに対する社会全体の意識が高まる中、従業員も不当な扱いに対して声を上げやすくなってきています。企業が従業員の訴えを無視することは、企業イメージの低下や訴訟リスクに繋がる可能性があります。 |
| SNSの普及 | カスハラの実態がSNSを通じて可視化されやすくなり、企業イメージへの影響が大きくなっています。企業は、炎上リスクを回避するためにも、カスハラ対策に積極的に取り組む必要に迫られています。 |
| 法規制の動き | 東京都をはじめとする自治体の条例制定の動きは、カスハラ対策を企業にとって無視できない義務へと近づけています。 |
これらの要因が複合的に作用し、企業は従業員が安心して働き続けられる環境づくり、すなわちカスハラ対策を、経営戦略の重要な柱として捉え始めているのです。
■【警鐘】カスハラ放置が招いた悲劇:あるガソリンスタンドの事例
過去には、カスハラを放置した企業も少なくありません。例えば、私が長年身を置いていたガソリンスタンド業界の事例では、顧客からの理不尽な要求や暴力を受けた従業員を守ろうとせず、ただただ耐え忍ぶことを強制してきたというものがあります。そのような企業からは従業員の流出が相次ぎ、深刻な人材不足となり、業績に悪影響を及ぼしました。それでも業績を上げようと、経営陣が従業員に無理をさせた結果、自殺者まで発生するという悲劇が起こってしまいました。
■結論:従業員を守る経営こそが、企業の持続的な成長を導く
人手不足が深刻化する現代において、従業員の定着率向上は企業の生命線です。その阻害要因となるカスハラに対し、今、社会全体が対策へと動き出しています。東京都のカスハラ防止条例の制定、JR東日本グループをはじめとする企業の毅然とした対応、そして個人店の自衛策の広がりは、従業員を大切にするという価値観が社会全体に浸透しつつある証拠と言えるでしょう。
カスハラを放置することは、従業員の心身を疲弊させ、離職を招き、企業の競争力を著しく低下させます。目先の顧客を失うことを恐れるあまり、従業員を守ることを怠れば、結果としてより多くの貴重な人材を失い、長期的な衰退を招くことになるでしょう。
今回ご紹介したように、企業がカスハラ対策に積極的に取り組むことは、従業員エンゲージメントを高め、定着率向上に繋がり、ひいてはサービス品質の向上、企業イメージの向上、そして収益の安定化という好循環を生み出します。従業員が安心して働き続けられる環境こそが、激しい競争を勝ち抜き、持続的な成長を実現するための不可欠な条件となるのです。
今こそ、企業は「お客様は神様」という言葉の真意を改めて理解し、従業員一人ひとりを尊重し、守る経営へと舵を切るべき時です。カスハラのない、誰もが安心して働ける社会の実現に向けて、企業、従業員、そして社会全体が連携し、意識改革を進めていくことが求められます。
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役