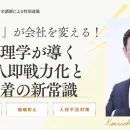人手不足時代の切り札?「思い込みの力」で従業員が輝くプラセボマネジメントのススメ【三上康一講師コラム】
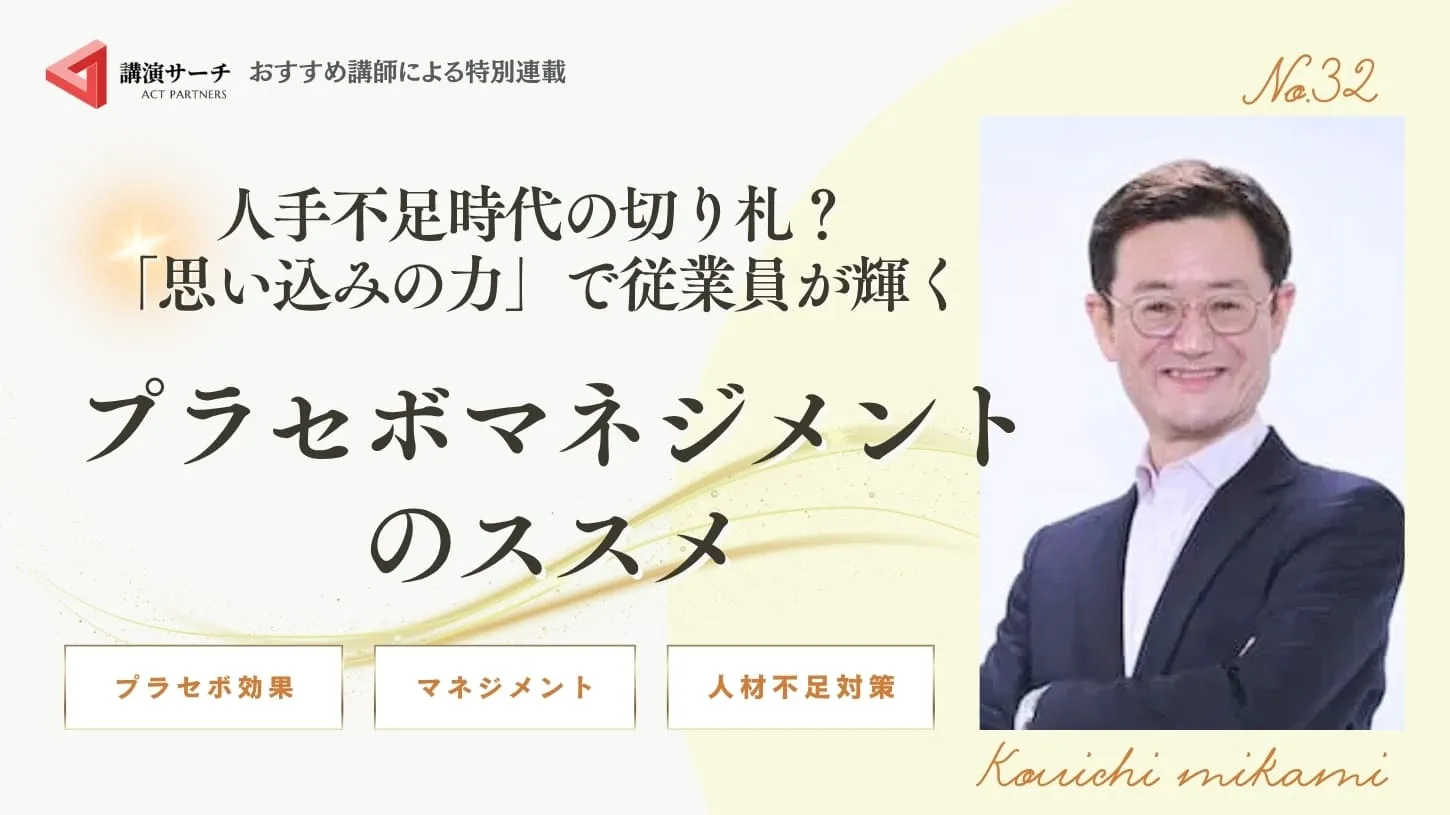

人手不足時代の切り札?「思い込みの力」で従業員が輝くプラセボマネジメントのススメ【三上康一講師コラム】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
最近、リカバリーウェアが話題となっています。これは、着用することで体の疲労回復や筋肉のコリの軽減などを目的とした特殊な衣類であり、一般的なパジャマやルームウェアとは異なり、科学的な根拠に基づいた技術や素材が用いられています。
先日私が入店した書店でも売っており、価格もさほど高くなかったので買ってみました。自宅で着てみたところ、体がじんわりポカポカしてくるのがわかります。まさに血行が良くなった感じがしたのですが、これはもしかしたら「プラセボ効果」も大いに働いているのかもしれないな、と思います。
プラセボ効果とは「効果のないものでも『効く』と信じることで実際に体や心に良い変化が現れる現象」のことを指します。心理的な期待感やポジティブな思考が、健康や行動にプラスに働くことを示しています。
「プラセボ(placebo)」という言葉は、ラテン語の「placebo(プラケボ)」に由来しており、「私は喜ばせるだろう」「私は満足させるだろう」という意味を持っています。
そしてこのプラセボ効果は、昨今深刻化する人手不足対策にも応用できる可能性があります。
人手不足の根本原因のひとつは、既存従業員の退職にあります。特に中小企業は、大手企業のような高待遇や充実した福利厚生制度を提示するのは難しいケースが多く、だからこそ「人の心」に働きかけるマネジメントが求められています。
私がリカバリーウェアで感じた「体がポカポカする」という感覚が、もし純粋な科学的効果だけでなく、「特殊な繊維が血行を良くする」という事前情報による期待感から生まれたものであれば、それはまさにプラセボ効果のなせる業です。
ここで誤解してはならないのは、これは「小手先のテクニックで部下をだましましょう」という話ではないということです。
むしろ、組織の中でポジティブなメッセージや環境づくりを通じて、従業員一人ひとりが「自分はここで成長できる」「この会社は自分を大切にしてくれている」と信じられる状態を生み出すことが、本質的なマネジメントなのです。
つまり、「信じることで得られる力」を引き出す環境設計こそが、今の時代に必要とされるマネジメント手法――すなわち「プラセボマネジメント」なのではないでしょうか。

■「承認」と「賞賛」の使い分けの重要性
この「プラセボマネジメント」を実践する上で鍵となるのが、従業員への声かけ、つまり「承認」と「賞賛」の適切な使い分けです。似たように見える両者ですが、その意味や効果は大きく異なり、混同するとかえって従業員のモチベーションを損なうリスクもあります。
同志社大学の太田肇教授の研究では、上司からの事実に基づいた「承認」によって、従業員の自己効力感や内発的モチベーションが高まり、結果的に業績向上にもつながることが実証されています。
だからこそ、リーダーには「承認」と「賞賛」の違いを正しく理解し、状況に応じて使い分ける力が求められるのです。
(1) 承認とは
「承認」とは、従業員の行動や成果といった「事実」をしっかりと認め、言葉で伝えることを指します。たとえば「◯件対応してくれましたね」「◯◯が売れましたね」など、具体的な事実を伝えることで、従業員は「自分の働きがきちんと見られている」「ここに自分の居場所がある」と感じるようになります。
こうした実感は、従業員の「自分はもっとできる」という自己効力感を高めていきます。自己効力感が育まれると、従業員はやりがいや意欲を持って、指示されなくても自発的に動くようになります。これは「内発的動機づけ」と呼ばれ、長期的な成長や貢献を引き出す大きな力となります。
(2) 賞賛とは
一方、「賞賛」は、従業員の行動や能力に対して、感謝や尊敬の気持ちを伝えることを意味します。たとえば「頑張っていますね」「君のセンスは素晴らしい」といった言葉がそれに当たります。賞賛を受けた従業員は、自分の仕事が認められているという喜びや誇りを感じるでしょう。
しかし、賞賛は外からの評価や報酬に動機づけられる「外発的動機づけ」によるものです。そのため、賞賛に頼りすぎると、褒められないと動かない、つまり「ニンジンをぶら下げなければ働かない」状態になってしまうリスクもあります。
また、言葉の選び方や関係性によっては、賞賛が逆効果になることもあります。たとえば、上司からの賞賛が「ご機嫌取り」や「操作のための言葉」と受け取られてしまうと、信頼を損なう可能性があるのです。心にもないような褒め言葉は、かえって不信感を招きかねません。

■「承認」と「賞賛」の実例から見る違い
では、承認と賞賛をどのように使い分ければ良いのでしょうか。以下に、具体的な事例を通じて、その効果の違いを紹介します。
(1) 承認が機能した成功例
セルフサービスのガソリンスタンドに勤務するAさんは、給油中のお客様に「タイヤの空気圧を無料で点検しますよ」と積極的に声をかけ、実際に多くの車両を点検していました。その結果、パンクや摩耗したタイヤを見つけることができ、販売につながるケースが増えていきました。
店長は、こうしたAさんの取り組みに対し、「今日の午前中だけで32台のお客様に声掛けしましたね」と具体的な数値を挙げてフィードバックしました。Aさんは自分の努力が正しく見られていると実感し、「もっとお客様の役に立ちたい」という想いが強くなっていきました。
結果として、Aさんはさらに自発的に声掛けや点検を行うようになり、店長からの承認がなくとも成果を出し続けるようになったのです。
(2)賞賛が裏目に出た失敗例
一方、別のフルサービスのガソリンスタンドで働いていたBさんは、以前から店長にあまり良い印象を持っていませんでした。
そんな中、ある日突然、店長から「君の販売力は素晴らしい。これからも頼むよ」と声をかけられました。しかし、Bさんはその言葉を「どうせ本心じゃないだろう」と受け止め、むしろ不信感を抱く結果に。やる気を失い、最終的には退職してしまいました。
このように、賞賛は「評価」を含むため、受け取り方に個人差が出やすく、関係性や言葉の裏にある意図によってはマイナスに働いてしまうことがあります。店長の言葉が本心だったとしても、Bさんにとっては信頼関係が築かれていなかったため、逆効果となってしまったのです。
■適切な使い分けが信頼を育む
このようなリスクを避けるためには、「承認」と「賞賛」を混同せず、それぞれの意味と効果を理解し、状況や相手との関係性に応じて使い分けることが大切です。
特に、信頼関係が十分でないうちは、評価よりも「事実に基づいた承認」を丁寧に積み重ねていくことが、従業員の信頼と内発的なやる気を引き出す近道となります。
■まとめ:真の「プラセボマネジメント」で従業員の潜在力を引き出す
人手不足の時代を乗り切るためには、従業員一人ひとりの「信じる力」と「内なるモチベーション」を引き出す「プラセボマネジメント」が不可欠です。それは、単に「褒める」ことではなく、具体的な事実に基づき、従業員の努力と存在そのものを「承認」することによって、彼らの自己効力感を育み、自律的な成長を促すことです。
もちろん、感謝の気持ちを伝える「賞賛」も大切ですが、その前に、まずは従業員の行動や成果という「事実」をしっかりと見つめ、それを彼らに伝え、承認することから始めましょう。そうすることで、従業員は安心して働き、自分にはもっとできると信じ、会社への貢献意欲を自然と高めていくでしょう。
リカバリーウェアが「効くかもしれない」と思ったことで体が軽く感じられたように、上司からの真摯な承認も、従業員の心に前向きな変化をもたらします。信じる気持ちが力になる――それが「プラセボマネジメント」の本質なのです。
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役