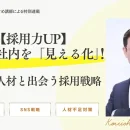無知と無能は違う~人手不足の時代に求められる人材育成の視点~【三上康一講師コラム】


無知と無能は違う~人手不足の時代に求められる人材育成の視点~【三上康一講師コラム】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
人手不足が社会全体で深刻化している今日、私たちは「即戦力になる人材」を求めがちです。特に事業規模が小さくなるほど、その傾向がより顕著です。しかし、そこで見過ごしがちなのが、育成の視点です。果たして、「使えない人材」とは本当に無能なのでしょうか?それとも、単に「知らない」だけではないでしょうか?
「できない」と「知らない」、この2つは本質的に異なります。その違いを見過ごしてしまうと、せっかくの将来有望な人材を、無駄に失うことになりかねません。人手不足の根本的な原因は、単なる人材の不足ではなく、むしろ「育てる文化の欠如」にあるのではないでしょうか。
本稿では、無知と無能の違いを理解し、育てる文化が組織を強化する重要性を考えます。
■現場での一コマ:吉川くんの領収書
17年前まで、私はガソリンスタンドの運営会社に20年以上雇用されていました。そのうち13年間は店長として現場に身を置いていましたが、店長経験が浅かった頃の話です。ある日、アルバイトで働く高校生・吉川(仮名)くんに頼んで、近くのコンビニでゴミ袋を買ってきてもらいました。領収書も忘れずにお願いし、彼はゴミ袋・釣銭・領収書を持って、戻りました。しかし、彼から受け取った領収書の宛名欄には「吉川様」と書かれていたのです。
理由を聞くと、彼は「レジで『お名前は?』と聞かれたので、自分の名前を言いました」と無邪気に答えました。彼は、正直に、そして忠実に指示を実行しただけでした。しかし、結果は少しズレていました。これは、「無能」ではなく「無知」だったのです。
■無知と無能
吉川くんは決して無能ではありませんでした。彼は与えられた指示を忠実に実行し、仕事への責任感を持っていました。ただ、ビジネスマナーや商習慣、つまり「領収書の宛名は会社名であるべき」という基本的な知識を持っていなかっただけでした。このような「無知」と「無能」を混同してしまうと、人材を見誤り、大切な成長のチャンスを無駄にしてしまいます。
「無知」とは「知らないこと」であり、「無能」とは「できないこと」です。無知は教えれば解決できますが、無能は訓練や経験がなければ克服できません。この違いを正しく認識し、適切に対応することが、現場での人材マネジメントにおいて非常に重要です。

■無知は教えれば解消できる
吉川くんにとって必要なのは、領収書の扱い方を教えることでした。私は彼に、「領収書は誰が払ったかではなく、誰の経費として計上するかで宛名が決まる」と説明しました。その後、彼はすぐに理解し、宛名の間違いはなくなりました。この一件を通して、無知は教育によって解決できることを実感しました。
無知な人材を早々に切り捨てるのではなく、正しい知識を伝える土壌を作ることが、組織を強くします。育成のプロセスを大切にし、「無知」を改善する文化が、企業にとってどれほど大きな力になるかを理解するべきです。
■育てる文化の重要性
一方で、私が当時悩んでいたのは、いくら教えてもアルバイトで働く若者たちが学校卒業や就職を機に辞めていくことでした。「どうせ辞めるのに、教えても無駄だ」と感じることもありました。しかし、ある経営コンサルタントの言葉で私は考えを改めました。
「君がやるべきは、一人ひとりを育てることではない。新人が入ってきたときに、誰もが自然と手を差し伸べられるような『育成の仕組みと空気』を作ることなんだ。」
この言葉は私にとって、非常に大きな転機でした。育成を属人的なスキルや経験に頼るのではなく、育てる文化を組織全体に根付かせることが、持続的な成長には不可欠だと気づいたのです。とはいうものの、目先の人材不足を早くどうにかしたいという思いがあることも理解できます。この点について考察していきます。

■「即戦力依存」の問題
・なぜ企業は即戦力を求めるのか
現在、多くの中小企業が「即戦力」を求める背景には、ひとえに「育成の時間を惜しむ」という現実的な問題があるといえます。経営者やリーダーたちは、目の前の業務や成果を最優先に考え、すぐに結果を出せる人材を欲しがります。それは理解できることですが、問題は「即戦力」を求めるその背後にある、育成に対する無理解や、時間とリソースをかけることへの抵抗です。
即戦力を求める理由はシンプルです。企業が求めているのは「今すぐ業務に役立つ人材」であり、新たに採用した人材がすぐに戦力として活躍してくれれば、経営の負担を軽減でき、業績向上にもつながります。短期的な視点で見れば、即戦力を採用することは効率的で合理的に見えます。しかし、これは実は企業にとって大きなリスクを抱えた選択でもあります。
・即戦力採用が抱えるリスク
即戦力となる人材は、すでにスキルや経験が豊富なため、市場においても限られた存在です。また、採用するためには高い給与を提示しなければならない場合が多く、その分、企業側の負担が増します。それに加えて、自身の業務に対するこだわりが強く、企業文化との不一致を感じて退職してしまうことが少なくありません。このような採用コストや高リスクが、企業にとっては負担となり、結局は「即戦力」に頼り続けることが、持続的な成長を妨げる原因となります。
一方、育成に時間とリソースをかけるアプローチは、長期的に成長できる人材を育て上げることを目指します。このアプローチは、最初は時間や労力が必要となるものの、長い目で見れば、企業にとって大きなメリットをもたらします。育成の時間を惜しまず、社員一人ひとりをしっかりとサポートできれば、その社員は企業文化に適応し、自ら成長し、最終的には企業の重要な戦力として活躍することができます。
・育てる文化が未来の競争力を生む
また、育成を重視する企業は、自然と「育てる文化」を根付かせることができます。これは、単に一人の社員を育てるのではなく、組織全体で新しい人材を支え合い、成長を促す仕組みを作ることを意味します。この「育てる文化」が確立されることで、新たに入ってきた人材も、自分が成長できる環境に身を置いていると感じることができ、長期的に企業に貢献し続ける可能性が高くなります。
したがって、「即戦力を求める」というアプローチは、確かに現場の忙しさや短期的な成果を求める気持ちから来ているものですが、その先に待っているのは高コストで不安定な人材採用のリスクです。むしろ、育成に力を入れ、長期的に成長できる人材を作り上げることこそが、企業の持続的な成長を支える鍵となるのです。今こそ、企業は「即戦力依存」を見直し、育成を重視する文化を作り上げていくべき時なのです。
目先の課題に追われることが多い経営者やリーダーにとって、「人を育てる時間」を持つことは難しいと感じるかもしれません。しかし、その時間こそが企業の未来に対する最も確実な投資です。育成にかける時間を持つからこそ、社員は成長し、組織全体が強くなります。リーダーは、即効性のある「目の前の問題」に対応するだけでなく、長期的に見た現場力を向上させるために、育てる文化を根付かせなければなりません。
■育てる文化が企業を魅力的にする理由
企業の成長を支えるのは、「成長できる場」であるという実感を社員に与えることです。成長できる環境こそが、社員のモチベーションを高め、企業にとっても競争力を持つ要素となります。教育や育成をおろそかにすると、社員は「自分は何も学んでいない」と感じ、退職のリスクが高まります。
また、企業が持つ育てる文化は、求人活動にも大きな影響を与えます。求職者にとって、「学びながら成長できる環境」は非常に魅力的です。社員が育成のプロセスに自然と関わることができる組織は、「働きがいのある職場」として評価され、結果として人材採用の優位性を高めます。

■終わりに
あの「吉川様」の領収書の出来事から学んだのは、無知は教えれば解消できるというシンプルなことです。しかし、無知な人を無能だと切り捨てるのではなく、育てる文化を育て、育成の重要性を認識することが、組織にとって最大の価値を生み出すのです。
中小企業の経営者の皆さん、そして現場でリーダーシップを発揮している皆さんに問いたいのは、次のことです。
その社員、本当に無能ですか?それとも、ただ「知らない」だけではありませんか?
無知と無能の違いを見極め、育てる文化を根付かせること。それが、人手不足の時代における、もっとも効果的で、人間的な解決策だと信じています。
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役