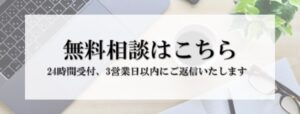オンライン講演とは?メリットとデメリット、他の開催方法との違いを解説【初めての開催におすすめ】

オンライン講演とはZOOMなどのオンライン配信ツールを用いて行われる講演会のことです。主催者側にも 参加する聴講者側にもメリットがあるため、実施する企業や組織が増えており、近年注目されています。
本記事では オンライン講演のメリットとデメリット、よく似た言葉との違いや初めてのオンライン講演におすすめの情報をご紹介します。
オンライン講演は、主催者にも聴講者にもメリットがある開催方法です。デメリットに注意しながら、目的に合わせて講演会の開催スタイルを選びましょう!
講演依頼・講師派遣のプロである講演サーチなら、初めてのオンライン講演でも【失敗しない】サポートをいたします。
アクト・パートナーズが運営する講演サーチは、長年の経験をもとに企業や組合といった組織の課題解決に役立つ講師派遣・講演依頼を承っています。
オンライン講演開催のご相談はもちろんリアル開催の講演依頼でも、ぜひ無料相談をご活用ください。
オンライン講演とは?メリットとデメリット、他の開催方法との違いを解説【初めての開催におすすめ】
目次
オンライン講演とは?

オンライン講演とは、インターネット上で配信する講演会や研修のことです。
ZOOMなどのオンライン配信ツールを用いて行われ、主催者側も聴講者側も別々の場所で配信または聴講が可能です。
配信を行うためのパソコンやカメラなどの機器は必要になり、聴講者側は他の聴講者との交流の機会がないのが難点といえます。
講演会の規模や内容によっては、対面で行う講演会がより適している可能性もあるため、オンライン講演にするかどうかは慎重に決めたいですね。
メリットやデメリットをしっかりと把握して、必要に合わせてオンラインの選択もできるようにしていくと講演会の幅も広がります。
ウェビナーやwebセミナーとの違い
近年「ウェビナー」や「Webセミナー」という単語を聞く機会が増えた方もいるのではないでしょうか?
ウェビナーとは「Web(ウェブ)」と「Seminar(セミナー)」を掛け合わせた造語であり、Webセミナーのことを指します。
ウェビナーWebセミナーの2つは、呼び方に違いがあるだけで意味に違いはありません。
また、オンライン講演とWebセミナーも明確な違いはなく、どちらも講演会や研修などをインターネットを介して行うことを指しています。
ウェビナーやWebセミナーは、企業の集客を目的とした講演会を意味することもありますが、多くの場合はオンライン講演と区別されずに使われています。
言葉が違うと意味も違うのでは、と思いやすいですが、ウェビナーやWebセミナーと聞いたらオンライン講演(オンライン研修)と捉えて問題はありません。

【主催者側】オンライン講演の6つのメリット

オンライン講演には、主催者側にとって以下のメリットがあります。
・場所の制限なしに集客できる
・新型コロナウイルス感染症対策に有効
・会場費や交通費などのコスト削減が可能
・移動の手間と時間を有効活用できる
・録画を編集でき、社内共有しやすい
・チャットやアンケート機能でリアルタイムで反応を集められる
6つのメリットをそれぞれ詳しくご紹介します。
場所の制限なしに集客できる
オンライン講演は場所の制限なしに集客ができます。対面で講演会を行う場合、聴講者は会場近隣の方や勤務している方に限られます。
聴講者にとって会場が遠い場合、交通事情や金銭事情などにより参加できない可能性があるからです。
例えば、銀行などが顧客向けに「誰でも参加OK」の講演会を開いても、移動コストを考えると会場近くの方しか積極的に参加することは少ないでしょう。
せっかくなら多くの人を集客して、新規顧客獲得につなげたいですよね。
オンライン講演であれば、自宅やコワーキングスペースなど、個人の好きな場所から講演会に参加でき、会場から遠い場所に住む方でも簡単に参加可能です。
オンライン講演は集客率アップを狙えるため、主催者側にとっては大きなメリットとなります。
新型コロナウイルス感染症対策に有効
オンライン講演は新型コロナウイルス感染症対策に有効です。
新型コロナウイルスが蔓延してから人が集まる行事やイベントはほぼ中止や自粛になりました。
感染を避けるためにできるだけ外出を控えている方やマスクの着用といった感染対策を続けている方も多くいるのではないでしょうか。
「参加したい」と思っていても、人が集まる場に対して不安を感じている方は参加を断念せざるを得ません。
オンライン講演であれば、人と対面しないため新型コロナウイルス感染症対策ができています。
感染症対策ができていることで、不特定多数と接触することへの不安を払拭し、集客率アップを図ることができるでしょう。
会場費や交通費などのコスト削減が可能
オンライン講演はコストの削減につながります。
対面で行う講演会は会場を借りたり、自社で所有している会場を使ったりするため、多くの講演会では移動の必要性が発生します。
つまり主催者も聴講者も、時間とコストをかけて会場まで移動しなければなりません。
外部講師に講演依頼している場合は、講師にも会場まで来てもらう必要があります。
そのため、主催者は参加する従業員や講師の移動費用というコストがかかるのがネックだといえるでしょう。
オンライン講演なら会場を借りる必要がありません
オンライン講演を配信するために貸し会議室や自社の個室などを用意する必要はありますが、移動コストは少なく済みます。
オンライン講演の聴講者は、自社や自宅などから参加でき、会場までの交通費がかかりません。
少しでもコスト削減できれば、主催者側としては嬉しいですよね。
移動の手間と時間を有効活用できる
オンライン講演なら移動の手間と時間を有効活用できます。
対面の講演会で会場までの移動に手間と時間がかかった経験はありませんか?
近くの会場ならば良いですが、距離のある会場だと移動手段の手配や移動などで多くの手間と時間がとられます。
オンライン講演であれば、自宅や自社から参加できるため移動の必要なく効率よく参加できるでしょう。
結果として集客率が上がるなど、主催者側にも聴講者側にもメリットがあります。
録画を編集でき、社内共有しやすい
オンライン講演は、録画と編集をして社内共有しやすいメリットもあります。
オンライン講演を録画して社内共有する許可が取れている場合は、オンライン講演の録画動画を編集できます。
編集例としては、
・司会進行役のあいさつをカットする
・機材トラブル等で進行ストップしたタイミングをカットする
・ワークの画像と講師の表情を並べてより理解しやすい動画にする
などができます。
講話の内容やワーク、メソッドなどは講師に著作権があるため、勝手に録画や配布するのは禁じられています。
社内で共有したいと考えているなら、講師への依頼時に先に伝えておくと親切です。
また、対面の講演会では講演会の内容を把握できるのはその場にいた聴講者のみです。
オンライン講演なら録画して編集することで、伝えたい情報を伝えたい人全員に配信できます。
効率よく講師の話を聞けるため無駄がなく、聴講者の聞く意識が高いまま情報伝達が可能となるでしょう。
チャットやアンケート機能でリアルタイムで反応を集められる
オンライン講演に使用する配信ツールには、チャット機能やアンケート機能がついており、リアルタイムで反応を集めることができます。
対面の講演会の場合も、聴講者の表情をみたり、ときには挙手してもらったりしてリアルタイムの反応を集められますが、質問や感想を受け取ることはできません。
オンライン講演ならチャット機能を使用して、聴講者が自由なタイミングで質問や意見を投稿できます。
ZOOMなどにあるアンケート機能を使えば、発言するのは気が引ける聴講者でも気軽にリアクションができるのは嬉しいポイントです。
オンライン講演でリアルタイムで反応を集められると、講師と聴講者のコミュニケーションが活発化するでしょう。
お互いに反応を確認できるため、講演会の満足度アップも期待できます。

【主催側】オンライン講演の4つのデメリット

オンライン講演のメリットは多くありますが、残念ながら主催者側には以下の4つのデメリットがあります。
・配信トラブルが生じるおそれがある
・聴講者のリアクションが伝わりにくい
・聴講者同士の親睦を深めづらい
・配信側の管理や環境づくりが手間
デメリットがあると聞くと身構えてしまいそうですが、デメリットを把握したうえで適切な対処ができれば問題ありません。
メリットとデメリットを比べて、オンライン講演の開催を検討してみてくださいね。
配信トラブルが生じるおそれがある
オンライン講演では、インターネットを介したオンライン配信ツールで講演の様子を配信します。
インターネットの接続状況が悪かったり、配信ツールで何かしらの不具合が起きたりして配信トラブルが生じるおそれがあるため注意が必要です。
トラブルが起きると、
・聴講者の集中力低下
・聴講者の理解度の低下
・聴講者の満足度の低下
を招きかねません。
そのため、事前に配信ツールの使用方法や通信環境の見直しなどをしっかりと行う必要があります。
事前に確認をしていてもトラブルが起きる可能性はゼロではありません。配信トラブルが生じた際に対応できるスタッフを待機させておくのがおすすめです。
聴講者の表情が伝わりにくい
オンライン講演では、聴講者の表情が主催者や講師に伝わりにくい点がデメリットとなり得ます。
対面の講演では聴講者の顔が見えるため、表情や仕草などから理解度や反応を感じ取ることができますね。
しかし、オンライン講演では聴講者の顔は配信者側に見えないことも多いため、生のリアクションが伝わりにくいです。
配信者側が一方的に話すだけになってしまい、聴講者が置いてけぼりになってしまうことも少なくありません。
オンライン講演では、リアクションを確認するためにチャット機能を使って反応を示してもらうとよいでしょう。
配信者側にもリアクションが伝わり、聴講者も置いてけぼりにならずに済みます。
ただし、聴講者のなかには自主的に反応するのが苦手な方もいるため、こちらから反応してもらえるよう働きかけていくと反応しやすくなりますね。
聴講者同士の親睦を深めづらい
対面の講演会は聴講者同士が会場に集まるため、親睦を深めることが可能です。
特に、共通の業種など聴講者同士に何かしらの共通点がある場合は、横のつながりも増え聴講者にとってもメリットがあります。
また、聴講者同士が同じ会場にいることで、一体感を感じてもらい講演会に対する意識の向上を図れるでしょう。
しかし、オンライン講演では聴講者同士が顔を合わせることはありません。
少人数で行われるミーティングなどとは異なり、不特定多数がいるケースが多いため、聴講者のカメラはオフのまま行われることがほとんどです。
聴講者は「自分以外に誰が参加しているのか」が曖昧な状態で講演会に参加することになります。
もし親睦を深めてもらいたいと望むのならば、講演会とは別に場を設けてみてはいかがでしょうか。
聴講者限定のSNSグループを作ったり、オンラインでつながれる場をつくると親睦を深めることができます。
このとき、聴講者に参加を強制しないような配慮が大切です。
配信側の管理や環境づくりが手間
オンライン講演の場合、配信側の管理や環境づくりに手間がかかります。
もちろん対面の講演会でも準備には手間がかかりますね。
会場の準備には、音響の確認や照明の当たり具合、また主催者側の身だしなみや話し方にも注意が必要です。
オンライン講演の場合はプラスで、配信のための準備が必要となるので手間が増えたと感じるかもしれません。
プラスで準備するのは、
・配信用のパソコン
・講師撮影用のカメラ
・パワーポイントなど資料を投影する機材各種と接続するパソコン
・配信ツールの使用方法案内
・配信ツールの設定
・配信ツールの参加リンク送信等の事務
・快適なインターネット環境
・配信トラブル対応用の待機スタッフ
・聴講者側のトラブル対応にあたるカスタマーサポートスタッフ
などです。
オンライン講演では、聴講者が集中して聞ける環境づくりがとても大切です。
初めてオンライン講演を開催する場合は特に、細かな点まで事前に準備や確認するのは難しいかもしれません。
不安があるときや外部に任せたい場合は、講演サーチのような講演会をサポートしてくれるサービスの利用がおすすめです。
満足度の高い講演会が開催できるよう、プロの力を借りながら準備を進めていくと楽になりますよ。

【聴講者側】オンライン講演に参加する4つのメリット

オンライン講演は聴講者側にも多くのメリットがあり、うまく活用すれば参加率や満足度のアップが期待できます。
ここでは以下の4つのメリットをご紹介します。
・好きなタイミングで聴講できる
・会場に行く時間と交通費をかけずに済む
・対面よりも気軽にチャットや挙手で質問できる
・講師の表情までみえるので親近感がわきやすい
どのようなメリットがあるのかしっかりと把握して、満足度アップにつなげましょう。
好きなタイミングで聴講できる
オンライン講演なら好きなタイミングで聴講できるメリットがあります。
対面の講演会は当日会場に行き聴講しなくてはならないため、スケジュール調整をする必要があります。
主催者としては必要な人に情報を届けることができない場合も考えられます。
しかしオンライン講演なら、自宅や休憩中など、聴講者のタイミングで聴講できます。
好きなタイミングで聴講できることでストレスがなく、多くの人の聴講が期待できます。
会場に行く時間と交通費をかけずに済む
オンライン講演なら会場に行く時間と交通費がかかりません。
会場までの距離が遠い場合は、多くの時間と交通費がかかってしまいますね。
交通事情や金銭事情により、参加できない方もいるかもしれません。
しかしオンライン講演なら自宅からの聴講も可能なため、時間と交通費がかかりません。
遠方の方も参加でき、今まで参加を断念してきた方にとっては大きなメリットではないでしょうか。
また、スマホやパソコンで聴講できる環境さえ整っていれば、他に準備することもないため時間を有効活用できますね。
手軽にお金をかけずに参加できるため、主催者は聴講者を増やす効果が期待できます。
対面よりも気軽にチャットや挙手で質問できる
オンライン講演なら、気楽に質問ができるメリットもあります。
対面の講演会では、会場の空気感や周りの目などを気にして「質問(挙手)しづらい」と感じる聴講者がいるでしょう。
特に人前で話すことが苦手な方からすると、会場での質問はなかなか勇気が要るものであり、精神的な負担も大きいです。
オンライン講演なら、配信ツールにあるチャット機能や挙手機能を使うことで周りの目を気にすることなく気軽に質問ができるため、精神的負担が少なく済みますね。
質問をすることは聴講者の意識向上や理解力向上につながります。
意識向上や理解力向上につなげるためにも、主催者側は質問のしやすい雰囲気づくりを心がけましょう。
講師の表情までみえるので親近感がわきやすい
オンライン講演は講師の表情がみえるため、講師に対して親近感がわきやすいメリットがあります。
対面の講演会は会場の座席からステージまでが遠く講師の表情までは見えないことも多く、講師の顔をしっかり認識できず親近感がわきにくい傾向があります。
オンライン講演は画面を通して講師の顔を目の前で見ることができ、表情などもはっきりとわかるのは大きなメリットです。
例えば、
・講師が笑っている
・真剣な表情をしている
・(カメラを通して)目が合っている
といったことをリアルに感じられるでしょう。
表情や仕草から講師の人となりがよく伝わり、聴講者は講師に対して好意的な感情を抱きやすくなります。
その結果「もっとしっかり聴こう」「この講師の話をよく聴きたい」という学習意欲アップにつながるのです。
さらに、聴講者はリラックスした状態で聴講でき、質問しやすくなるといった効果も期待できます。
講演中は資料などを表示することもありますが、なるべく講師の表情が見えるように画面を構成するのがおすすめです。
【聴講者側】オンライン講演に参加する4つのデメリット

オンライン講演は聴講者側に以下のような4つのデメリットをもたらす可能性があります。
・インターネット環境を整える必要がある
・集中力を保ちにくい
・参加者同士でコミュニケーションが取りづらい
・オンライン配信ツールや機器の操作を学ぶ必要がある
これらのデメリットは、場合によって途中退出の理由となり得るため、事前案内や講演会の内容、サポート体制といった細部まで気を配ることが必要です。
主催者側で対応できることは対応するように努めることで、聴講者にとって良い講演会と感じてもらえますよ。
インターネット環境を整える必要がある
オンライン講演は聴講者側もインターネット環境を整える必要があります。
通信環境が悪いと配信に遅れが生じる可能性や、音声が途切れる可能性があります。
聴講者自身で環境を整えられる場合は良いですが、通信機器などに疎い場合は各自で対応するのは難しいかもしれません。
スムーズに配信が見られないと、聴講者がストレスを感じてしまいます。結果的に、講演に集中できず途中退出してしまう可能性があるため注意が必要です。
しかし、主催者側が聴講者に代わってWi-Fi設備の整備やツールの設定といった環境を整えることはできませんよね。
主催者としては、できる限りスムーズにオンライン講演に参加できるようなサポート体制を整えておきましょう。
例えば、
・配信ツールの使用方法をメールで送付
・トラブルシューティングを事前に案内する
・トラブル発生時の問い合わせ先を知らせる
・必要な環境や機器を事前に知らせる
・講演中のトラブル対応要員を待機させておく
などが有効です。
丁寧なサポートができると、聴講者に親切な印象を与えることができます。
集中力を保ちにくい
オンライン講演は聴講者側の集中力を保ちにくいデメリットがあります。
対面の講演会では会場の雰囲気や他の聴講者との一体感などにより集中力を保つことができますが、オンライン講演は自宅などから一人で聴講するケースが多いため、集中力が保ちにくいです。
また、オンライン講演では、講師は聴講者の姿勢や理解度を把握するのがなかなか難しいため、聴講者の自主性に任せてしまいやすくなります。
集中力低下や理解度の低さは満足度の低下につながる可能性があるので、主催者側があらかじめ対策しておくと安心ですね。
例えば、
・クイズをはさむ
・リアクションボタンを押してもらう
・気軽な質問や感想を随所で受け付ける
・参加者名簿から指名して発言してもらう機会をつくる
・ワークを取り入れる
といった工夫は飽きさせません。
外部講師にオンライン講演を依頼する場合は、講師に相談してみましょう。
講師によっては、より楽しく集中できる工夫を凝らして講話してくれる場合があります。
参加者同士でコミュニケーションが取りづらい
オンライン講演では参加者同士でコミュニケーションを取ることは難しいです。
対面の講演会では参加者同士も顔を合わせるために会話をする機会も増えますよね。
内容によってはグループワークをはさむなどして、参加者同士に会話を促すこともできます。
オンライン講演ではどのような人が参加しているのかすら分からない場合もあり、ただ講師の話を聞いて終わりになってしまうケースが多いのが難点です。
参加者同士のコミュニケーションが「ほとんどない」ケースは珍しくないため、聴講者は孤独感を抱きやすいでしょう。
参加者同士のコミュニケーションを望むなら、参加者限定で入れるSNSグループをつくるなどもおすすめです。コミュニティをつくることで、参加者同士の意識や理解の向上を図りやすくなります。
さらに、ワークを取り入れて参加者同士がやり取りする機会を作ってもよいでしょう。
昨今のオンライン配信ツールには、参加者を少人数にわけられる機能をもつものがあります。グループワークで積極的なコミュニケーションを促せば、自然と参加意欲の向上が見込めます。
オンライン配信ツールや機器の操作を学ぶ必要がある
オンライン講演では使用する配信ツールや機器の操作が必要です。
配信ツールや機器を初めて使用する場合は、操作方法を事前に確認しておかなければなりません。
しかし、機器や配信ツールに疎い人などは事前に学んでおかなければ参加やリアクションが難しい可能性があるので注意が必要です。
学ぶこと自体に抵抗がある方にとっては、初めて扱うオンライン配信ツールや不慣れなパソコン操作などは「面倒だ」と感じられるでしょう。
この場合、自由参加の講演だと参加を諦めてしまうかもしれません。
主催者側から、事前に操作方法や注意事項を案内しておくと参加率を上げられます。
まとめ:オンライン講演を選ぶなら講演サーチが安心!
オンライン講演はITの発展や新型コロナウイルスの蔓延に伴い、実施する企業などは続々と増えてきました。
主催者側にも聴講者側にも多くのメリットがあるため、実施を検討する企業も年々増えています。しかし、対面の講演会同様に準備には多くの時間を要し手間がかかるうえ、オンラインだからこそ必要な準備もあります。
もしオンライン講演を検討されているなら講演依頼のプロ「講演サーチ」にご相談ください。適切な講師選びだけでなく、講演会の準備から当日までしっかりサポートし、不安なことや必要なことは、経験豊富なスタッフが寄り添い解決します。
「初めてのオンライン講演で不安」な方も「もっとよい講演会を開催したい」方も、講演サーチの無料相談をご利用ください。素晴らしい講演会になるよう、全力でサポートします。