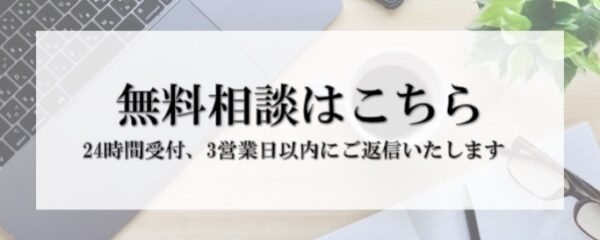全国安全週間には安全大会の開催がおすすめ!歴代のスローガンや取り組み例、安全大会の重要性をご紹介

全国安全週間は産業界に勤めている人なら知っている人も多いのではないでしょうか。
全国安全週間とは、厚生労働省と中央労働災害防止協会が主唱しているもので、労働災害を削減するために実施されています。
期間中には安全大会を開催する企業が多く、安全をより強く意識する期間です。
しかし、「安全大会の重要性は分からない」という人も少なくありません。
この記事では「全国安全週間とは何か」「何をすれば良いか」「安全大会は必要か」ご紹介しています。
日々の業務を安全に行うためにとても重要な役割を担う全国安全週間の、歴代スローガンや取り組み例なども含めてお伝えします。
安全週間に実施される機会の多い「安全大会」とは何かは、こちらの記事で解説しています。
全国安全週間とは
目次

全国安全週間は昭和3年から現在までで96回実施されています。
厚生労働省と中央労働災害防止協会が主唱しており、各労働災害防止協会などが協賛している取り組みです。
「人命尊重」を基本理念とし、“安全活動を行う・安全を意識する・安全活動を定着させる”を目的としています。
そのため、全国安全週間が行われる毎年7月1日から7月7日までの本週間は、各企業で安全に対してのさまざまな取り組みが行われます。
労働災害による死亡者数は令和4年は774人となっており、前年に比べ0.5%減少しました。全体の死亡者数は若干減少しましたが、休業4日以上の死傷者数は132,355人と1.4%増加傾向にあります。つまり、幸いにも死亡事故にはならなかったものの、怪我をして休業せざるを得ないほどの事故は増えているのです。
現場の人々は「高所での作業」や「機械や工具の使用」などの点から、日々危険と隣り合わせになっています。時にその危険は先に紹介したような死亡事故に繋がることもあるほど。働く一人ひとりの心身の健康を守ることが、結果的に地域や日本の健康維持につながるのですね。
製造業や建設業の人々が日々の業務を安全に遂行するためにも、全国安全週間の取り組みはとても重要です。
安全は日々意識して業務を行う必要がありますが、全国安全週間によってさらに強く意識し定着させていきましょう。
全国安全週間の準備期間とは
全国安全週間は毎年6月1日から6月30日までを準備期間としています。
準備期間、厚生労働省は
・広報資料の作成
・広報資料の配布
・安全意識の啓発
などの活動を行います。
各企業は安全活動の定着や安全水準の向上のために、安全に対する教育やマニュアルの作成といった、さまざまな災害に対する対策の実施が求められる期間となるでしょう。
“本週間”や“準備期間”と分けられてはいますが、全国安全週間は「安全活動の定着」も目的としているため、その期間だけ実施すれば良いわけではありません。
1年を通して、日々安全に業務が行えるように安全教育や対策を考え実行していくことが大切です。
全国安全週間中の取り組み例
全国安全週間中の取り組み例として以下のようなものが挙げられます。
・安全大会等により、関係者の意志の統一および安全意識の向上
・安全パトロールによる職場の点検
・危険チェックリストなどを用いた点検
・“見える化を図るため”に安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会などの開催
・文書配布や職場見学などを実施し、労働者家族へ協力を呼びかける
・災害や緊急時に対する訓練の実施
・安全に対する教育やマニュアルの作成・共有
・職場内での災害対策を図るミーティングの実施
全国安全週間中の取り組みは企業により実施すべきものが異なります。
今回挙げた以外にも企業で必要だと感じることを実施していきましょう。
特に現場の人々の安全に対する教育は、安全管理能力や意識を向上させるため、講演会や研修は多くの企業で実施されています。
全国安全週間の歴代スローガン

全国安全週間は昭和3年より実施されており、毎年スローガンが掲げられます。
このスローガンは毎年一般公募が行われるため、全国誰でも応募が可能です。安全災害に対する注意喚起などを目的としているため、周知の意味でも広くアイデアを募集しているのですね。
ここでは、平成元年から現在までの歴代スローガンをご紹介します。
| 第62回 | 平成元年度 | 決意新たに みんなで築こう災害ゼロの明るい職場を! |
| 第63回 | 平成2年度 | 災害ゼロはみんなのねがい あなたのために家族のために |
| 第64回 | 平成3年度 | みんなで決意 みんなで努力 前進させよう職場の安全 |
| 第65回 | 平成4年度 | 設備と作業の安全で 実現しよう 災害ゼロの明るい職場 |
| 第66回 | 平成5年度 | 災害ゼロの安全職場!トップの決意・現場の実行 |
| 第67回 | 平成6年度 | 職場の安全 家族の安心 災害ゼロはみんなの願い |
| 第68回 | 平成7年度 | つみとろう危険の芽 トップの決意 みんなの努力 |
| 第69回 | 平成8年度 | 『危なかった』は赤信号 つみとろう職場に潜む危険の芽 |
| 第70回 | 平成9年度 | 安全はトップの決意とあなたの努力 めざそう災害ゼロの明るい職場! |
| 第71回 | 平成10年度 | 今一度確認しよう「安全第一」 つみとろう職場にひそむ危険の芽 |
| 第72回 | 平成11年度 | 見逃すな危険の芽 さらに高めよう職場の安全 |
| 第73回 | 平成12年度 | 災害ゼロから危険ゼロへ みんなで築こう新しい安全文化 |
| 第74回 | 平成13年度 | 世紀をこえて「安全第一」 めざそう職場の危険ゼロ |
| 第75回 | 平成14年度 | めざすゴールは危険ゼロ 進めよう職場の安全管理 |
| 第76回 | 平成15年度 | 危険をみつけて進める改善 高めよう職場の安全管理 |
| 第77回 | 平成16年度 | 危険をみつけて取り組む改善 トップの決意とみんなの実行 |
| 第78回 | 平成17年度 | トップの決意とみんなの創意 リスクを減らして進める安全 |
| 第79回 | 平成18年度 | 全員参加でリスクの低減 確立しよう「安全文化」 |
| 第80回 | 平成19年度 | 組織で進めるリスクの低減 今一度確認しよう安全職場 |
| 第81回 | 平成20年度 | トップが率先 みんなが実行 つみ取ろう職場の危険 |
| 第82回 | 平成21年度 | 定着させよう「安全文化」 つみ取ろう職場の危険 |
| 第83回 | 平成22年度 | みんなで進めようリスクアセスメント めざそう職場の安全・安心 |
| 第84回 | 平成23年度 | 安全は 家族の願い 企業の礎 創ろう元気な日本! |
| 第85回 | 平成24年度 | ルールを守る安全職場 みんなで目指すゼロ災害 |
| 第86回 | 平成25年度 | 高めよう 一人ひとりの安全意識 みんなの力でゼロ災害 |
| 第87回 | 平成26年度 | みんなでつなぎ 高まる意識 達成しようゼロ災害 |
| 第88回 | 平成27年度 | 危険見つけてみんなで改善 意識高めて安全職場 |
| 第89回 | 平成28年度 | 見えますか?あなたのまわりの 見えない危険 みんなで見つける安全管理 |
| 第90回 | 平成29年度 | 組織で進める安全管理 みんなで取り組む安全活動 未来へつなげよう安全文化 |
| 第91回 | 平成30年度 | 新たな視点でみつめる職場 創意と工夫で安全管理 惜しまぬ努力で築くゼロ災 |
| 第92回 | 平成31年度 (令和元年) |
新たな時代に PDCAみんなで築こう ゼロ災職場 |
| 第93回 | 令和2年 | エイジフレンドリー職場へ! みんなで改善 リスクの低減 |
| 第94回 | 令和3年 | 接続可能な安全管理 未来へつなぐ安全職場 |
| 第95回 | 令和4年 | 安全は 急がず焦らず怠らず |
| 第96回 | 令和5年 | 高める意識と安全行動 築こうみんなのゼロ災職場 |
こうしてスローガンを見てみると、安全に対する意識は「企業だけ」や「現場だけ」が意識するだけではいけないことが分かります。
企業と現場のそれぞれの人、一人ひとりの意識によって安全は成り立っているのです。
また、安全のためには危険の予知や、早くに危険に対処することも重要です。危険の予知には、KY活動やヒヤリハット報告書などを活用すると良いですね。
全国安全週間には安全大会の開催がオススメ

安全大会は安全に対する知識や意識の向上や、安全な体制をつくるために行われる集会です。
安全大会とは何か、詳しくは関連記事「安全大会とは?建設業における安全大会の重要性と講師選びの相場とポイント」でご紹介しています。
日々の業務を安全に行うためには企業や企業で働く従業員だけでなく、関係者の人たちも安全に対して知識をつけ、理解していくことが大切です。
そのため、安全大会を行う際は自社の従業員のみならず、取引先などにも参加を要請し開催することが多くあります。
安全大会を開催することで、文書のみで発信するよりも参加者の中で共通の知識や意識を持つことができ、安全な体制をつくることができるでしょう。
全国安全週間にはぜひ安全大会を開催して、専門家の知識や外部の経験談を知る機会を設けてみてはいかがでしょうか。
安全大会開催は義務?
安全大会開催は法律上決められているわけではないため、義務ではありません。
しかし、厚生労働省から通知されている全国安全週間の各企業の実施事項内に「安全大会の開催」が記載されています。
つまり、安全週間中の取り組み内容として「安全大会」の開催が効果的であり推奨できるといえるのです。
実施事項内でも触れているように、安全大会の開催は「安全に対する関係者の意思の統一や意識向上」が目的です。
文書のみだと読んでいない人がいたり、共通の認識を持ったりすることが難しく、安全な体制をつくることができません。
法律上、開催しないことで罰則などはありませんが、安全大会の開催は関係者の共通認識や意識向上に必要です。
オンラインでも安全大会の開催は可能?
安全大会はオンラインでも開催は可能です。
近年、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点などから、Zoomなどのオンラインミーティングツールを使用しての講演会開催も増えました。安全大会も実際にオンラインで開催する企業も少なくありません。
ただ、オンラインの場合は聞き流してしまうこともあり、各参加者と顔を合わすこともないため「モチベーションが上がりにくい」という欠点もあります。
一方、オンラインでの開催であれば、移動の手間や交通費などがかからないため「経費削減」や「参加者の負担軽減」などの利点もあります。
また、安全大会の内容を後日配信でき、スマホを使えば自宅でも視聴することが可能です。
オンラインで開催する利点も多くあるため、参加人数や関係各所の事情に合わせてオンラインでの安全大会開催を選択肢に入れても良いかもしれませんね。
全国安全週間の安全大会は講演サーチにお任せください

自社で安全大会を開催するとなると、会場や講師の選定や申し込み、参加者の取りまとめなど事前準備に多くの時間と労力を要します。通常業務もある中でさまざまな準備をこなすのが難しいと感じる人も少なくありません。
安全大会を開催し成功させるために、ぜひ講師派遣・講演依頼のプロである講演サーチをご利用ください。
実績豊富な講師と経験を積んだ講演サーチスタッフが、安全大会を成功へ導くお手伝いをいたします。安全大会に適任の講師の派遣や、チラシ作成などもお任せください。
初めての安全大会はもちろんのこと、今まで開催したことがある企業の「マンネリ打破」にも講演サーチは多くの喜びの声をいただいています。
数多くの講演会を見てきたプロだからこそできる提案で、安全大会を成功へと導きます。
ぜひ、全国安全週間中の安全大会のご用命は講演サーチの無料相談よりお寄せください。
まとめ
今回は全国安全週間についてご紹介してきました。
全国安全週間は昭和3年から厚生労働省などが主唱して行われてきました。
“安全活動を行う・安全を意識する・安全活動を定着させる”を目的としており、産業界の労働災害防止に役立っています。
産業界では高所作業や機械や工具の使用などにより、毎年多くの労働災害が発生しており、時に死亡事故に繋がる労働災害もあるのが実情です。
日々安全を意識して業務に取り組むことが求められますが、さらに意識を強く持たせ安全活動を定着させるのが“全国安全週間”です。
全国安全週間では安全大会の開催が推奨されており、それにより皆で共通の意識を持ち安全な体制をつくることができます。
安全大会は対面でもオンラインでも開催できますが、どちらも事前準備などに多くの時間と労力がかかります。
安全大会を開催するのであれば、プロの力を借りるのがおすすめです。安全大会に適任の講師がいる講演サーチに、ぜひ一度ご相談ください。