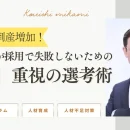新規雇用者の早期離職を防ぐ!効果的な1on1の実践方法とポイント【三上康一講師特別コラム】

新規雇用者の早期離職を防ぐ!効果的な1on1の実践方法とポイント【三上康一講師特別コラム】
目次

執筆講師
三上康一(みかみ こういち)
株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
■新規雇用者の早期離職がもたらす影響
新規に人材を雇用したものの、早期離職をされてしまうことは、募集告知・採用面接・入社手続きといった時間的・金銭的コストが水の泡となるだけでなく、人手不足の中、身を粉にして働いてきた既存人材が抱く「やっと人手不足から逃れられる」という期待を打ち砕き、彼らの人材流出のリスクも高まってしまいます。
これを防止する方策として、新規に雇用した人材に対する1on1が挙げられます。ここでいう1on1とは、上司と部下が相対し、定期的に1対1で行う面談を指しています。このコラムでは、1on1がなぜ早期離職を防ぐことができるのかという理由と、効果的な1on1を実施するためのコツについて述べていきます。
■1on1が早期離職を防ぐ理由
「認知的不協和」という心理現象があります。これは、人が自身の内部で矛盾する認知(考え、信念、価値観など)を同時に抱えたときに生じる不快感や心理的ストレスのことです。例えば、店舗で試着をした上で購入した洋服を家で着てみるとどうも似合わない感じがしたという経験はないでしょうか。この時、人は「買い物で失敗してしまった」という思いと、それを認めたくない思いの間で葛藤し、不快感を覚えます。
そこで、その洋服についてインターネットで検索し、肯定的なレビューや紹介記事などを読み、その買い物が失敗ではなかったという思いを強めようとします。これができないと、買い物の失敗を認めざるを得ず、悔しい思いをすることになります。
新規に雇用された人材も、いざ働いてみると入社前に持っていた職場への期待と、実際の業務内容や職場の雰囲気などといった現実との間にギャップを感じるものです。つまり、「良い職場に入社したはず」という思いと「今回の入社は失敗だったのではないか」という思いの間で認知的不協和が発生します。そして、この不快感を解消できないままでいると離職に繋がってしまいます。
そこで、「1on1」を実施します。これにより、入社後に抱いた不安や疑問を、直接上司に相談できるため、新規の人材は認知的不協和を解消することができます。
次に、新規人材の早期離職を防ぐための1on1のポイントを見ていきます。
■効果的な1on1を実施するためのタイミング
1on1を実施するタイミングは、職場の環境に合わせて、柔軟に調整することが重要です。特に、人材が入社した後の最初の1on1は、早期の不安解消や相互理解を深めるために、入社後2週間を目安に実施することが効果的です。このタイミングで、入社後の感想や疑問点を共有することで、よりスムーズなスタートを支援できます。ただし、これはあくまで目安であり、状況に応じて最適なタイミングを個別に検討することが望ましいと言えます。
また、1on1は1回限りではなく、その後も定期的に行うことが望ましいと言えます。例えば、1ヶ月後、3ヶ月後、半年後など、一定の期間を設けて実施することで、その後の状況を確認するとともに、今後取り組むべき課題の設定や成長の度合いを評価できます。
1on1の継続を怠ると、人材としては「最初は話を聞いてくれていたのに、最近は放ったらかしにされている」と感じ、不安定な心理になりがちです。このことは、モチベーション低下や、ひいては離職のリスクを発生させることになります。
■1on1で大切な「傾聴」のポイント
1on1の場は、上司にとっては部下にアドバイスをしやすい環境と言えます。ですが、まずは部下の話にしっかりと耳を傾けることが必要です。人は自分の話をしっかり聞いてくれる人に信頼を寄せ、そういう方からのアドバイスを素直に受け取るものです。傾聴をするために、以下を意識しましょう。
頷き・相槌
部下の話を聞きながら適切なタイミングで頷きや相槌を示しましょう。頷き・相槌はその大きさや長さなどバリエーションを持たせると、話す側もきちんと聞いてくれているという認識を持ちやすく、より多く深い話をしたくなるものです。
繰り返し
部下が話した内容でポイントだと思う部分を繰り返し、相手に確認することで、自分の話を理解してもらえているという意識が醸成されやすくなります。
言い換え
部下の話を上司自身の言葉で言い換えることで、話の理解度が明確になり、理解できていない部分は再度説明してもらえます。また、深い理解度に基づく言い換えは、部下が理解してもらえているという認識を強め、信頼関係を築くことが可能になります。
■承認と賞賛の使い分け
新規に入社した人材は、まだ職務経験が浅いため、業務に自信を持てない場合がほとんどです。そのため、1on1では、人材の自己肯定感を高める働きかけを行い、仕事へのモチベーションを向上させましょう。この際に、賞賛と承認を区分し、承認を行うことがポイントです。
「承認」は、部下の行動や成果など事実を認めます。これにより、従業員は安心感や満足感を得て、「自分はもっとできる」と自己効力感を持つようになります。
自己効力感が高い人材は、モチベーションが高まり、自発的に行動するようになります。これは、内発的動機づけとされ、外部からもたらされる報酬に関わらずやりがいを感じて行動する状態とされます。
これに対して「賞賛」は、「よくやっているね」「頑張りましたね」など、部下の行動や能力に対して感謝や尊敬の意を示すことを指します。これにより、人材は自分が評価されているという喜びや誇りを持つことができます。これは、外発的動機づけと呼ばれ、外部からの評価や報酬によって行動する状態とされます。
この外発的動機付けは、賞賛をし続けないと人材は行動を起こせなくなるリスクが発生します。また、人材が上司から投げかけられた賞賛を、自分をコントロールするための手段だと解釈すると、モチベーションの低下に繋がります。
以下では、承認と賞賛の事例をご紹介します。
■承認の成功事例
あるガソリンスタンドに勤務するX氏は、来店客にタイヤの空気圧を無料で点検していることを訴求し、積極的に点検をしていました。これにより、劣化したタイヤを見つけ出し、販売に結び付けていました。
これを踏まえ、X氏の上司は「今日は〇台のお客様に空気圧点検のアプローチをしていましたね」とX氏の行動を事実として承認するようにしていました。これにより、X氏の内発的動機が高まり、タイヤの空気圧点検台数は増加し、それに比例してタイヤの販売本数も増加していきました。そして最終的には、承認がなくとも成果が上がるようになりました。
■賞賛の失敗事例
別のガソリンスタンドに勤務するY氏は、上司に良いイメージを持っていませんでした。そんな上司がある日突然「Y君の販売力は素晴らしい。これからも頼むよ」と言いました。
これに対して、Y氏は「うちの上司は、そんなこと思ってもいないくせによく言うよ」と解釈し、却ってモチベーションを低下させてしまいました。Y氏の上司は本当にY氏の販売力を評価していたのかもしれませんが、賞賛は評価を伝えますので、部下の解釈が影響します。よって、ネガティブに捉えられると逆効果になります。
これに対して、承認は事実を認めますので、解釈が入り込む余地がありません。よって、上司は承認と賞賛を混同せず、適切に使い分ける必要があります。
■まとめ:1on1を通じた定着率の向上
新規に雇用した人材の早期離職を防ぐためには、効果的な1on1が重要です。入社後の最初の1on1を適切なタイミングで実施することで、認知的不協和を解消し、不安や疑問に対応することが可能になります。定期的な1on1を通じて、部下の信頼を築き、自己肯定感やモチベーションを高めることが、長期的なパフォーマンス向上にも繋がります。
また、1on1の際には、部下の話をしっかりと傾聴し、適切に承認を行うことが大切です。賞賛と承認を使い分け、部下が自信を持って働ける環境を整えることで、定着率の向上や組織全体の成長を支えることができます。
これらの取り組みを通じて、早期離職のリスクを減らし、組織の活力を保つことができるでしょう。

執筆講師
三上康一(みかみ こういち)
株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役