人材不足解消の鍵は「パワハラ防止」!リーダーが意識すべき3つの類型と対策【三上康一講師特別コラム】
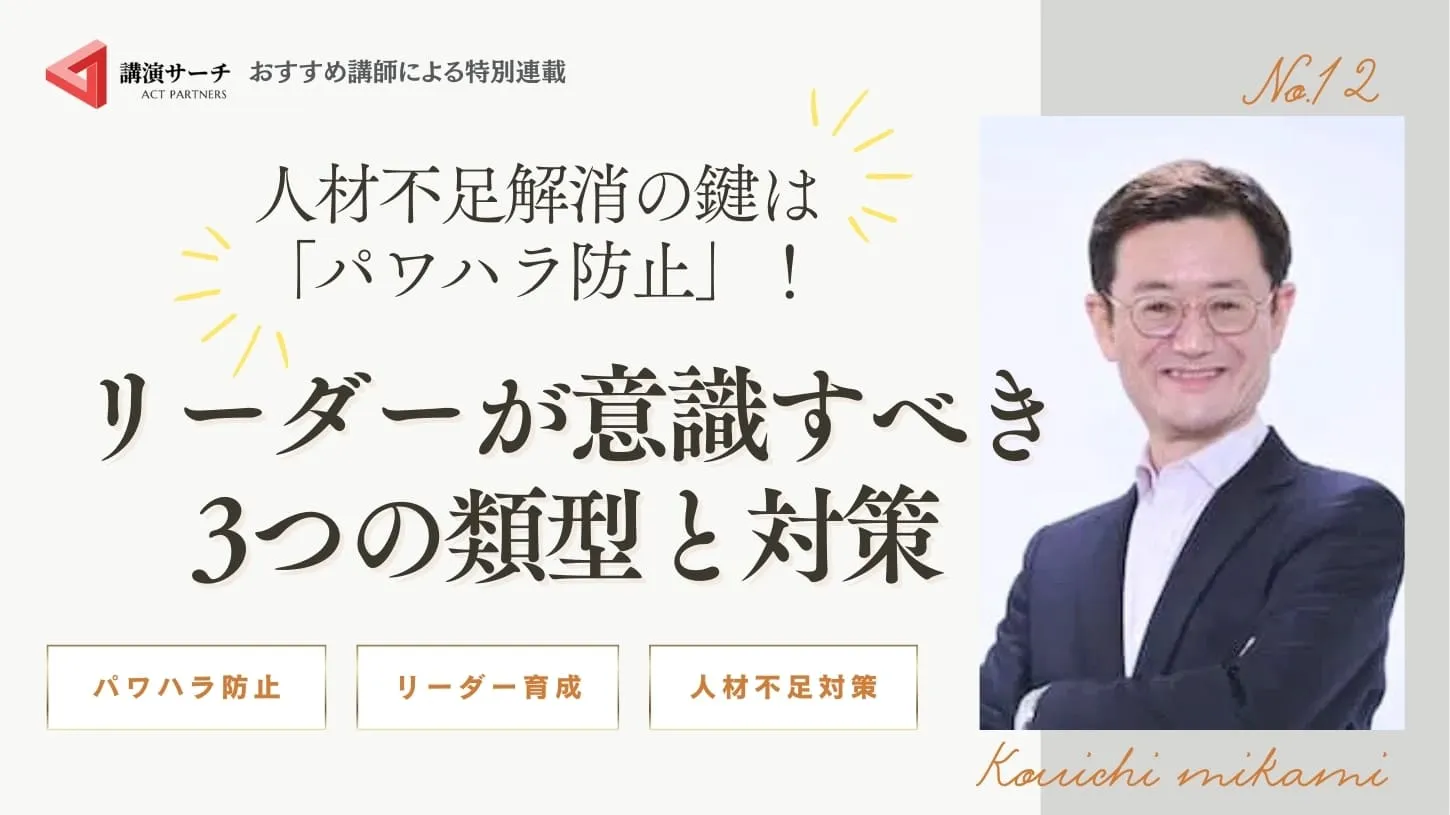

人材不足解消の鍵は「パワハラ防止」!リーダーが意識すべき3つの類型と対策【三上康一講師特別コラム】
目次
執筆講師
三上康一(みかみ こういち)
株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役

■人材不足を乗り越えるために:定着率向上の重要性
人材不足の企業は、募集をかけても人材の応募が少ないと嘆くケースが多い印象があります。しかし、募集をかける理由は既存の人材が退職したためである場合がほとんどですから、応募が少ないと嘆く前に、既存人材の定着率を高める方策を検討する必要があります。
既存人材の流出が激しい職場では、リーダーが大なり小なりパワーハラスメントを働いていないか一度振り返ってみる必要があります。今回の記事では、パワハラの類型をご紹介し、今の時代だからこそ陥りがちなパワハラのパターンを見ていきます。
■パワハラとされる3つの要素
パワハラとは、職場における優越的な関係を利用した言動で、業務で求められる範囲を超え、労働者の就業環境が害されるものを指します。以下の3つの要素を満たしてしまうとパワハラとされています。
優越的な関係を利用した言動
例えば、上司が部下に対して「来週の休日にオレの用事を手伝え」と指示するなど業務に関係のない私的な用事を強要することが挙げられます。また、上司から部下への言動だけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司への言動も含まれます。
業務で求められる範囲を超えた言動
例えば、能力や経験に見合わない達成困難な目標やノルマを課すなど、業務を遂行する上で必要とされる指示命令や指導であっても、その方法・程度が社会通念上相当と認め難いケースにおいてはパワハラとされる可能性があります。
労働者の職場環境が害される言動
例えば、部下を意図的に無視したり、コミュニケーションを遮断したりすることによって孤立させるなど、精神的・身体的な苦痛を与えるだけでなく、労働者自身が持つ能力を発揮できる環境を阻害する行為も含まれます。
これらをふまえて、パワハラを起こす上司の類型を見ていきます。
■パワハラ上司3つの類型
神奈川県立保健福祉大学のヘルスイノベーション研究科に所属する津野香奈美氏は、パワハラやリーダーシップの専門家です。同氏の著書「パワハラ上司を科学する(ちくま新書)」では、パワハラを発生させてしまうリーダーの類型を「脱線型」「専制型」「放任型」に分類しています。以下では、これらの類型を解説していきます。
(1)脱線型
このタイプは、かつては適切なリーダーシップを発揮していたものの、新しい職位に就いた結果、不適切なリーダーシップになってしまうタイプです。具体的には以下の特徴があるとされます。
提案を取り入れない
かつては柔軟な思考を持ち、周囲からのアイデアを受け入れようとしていたものの、新しい職位に就いてからというもの、自分の意見を押しつけることが増えます。
部下と競争したがる
かつては職場のメンバーと協力して業務を進める姿勢が強かったにもかかわらず、新しい職位に就いてからというもの、部下など職場のメンバーを競争相手として見るようになります。
このようなリーダーは「メタ認知」を知っておくことが効果的です。「メタ認知」とは、「認知を認知すること」と言われ、自分の認知活動(考えていることや感じていること)を客観的に捉え、それをコントロールする能力を指します。つまり、「もう一人の自分が自分自身を見ている」ような状態を指します。具体的には、以下のような能力が含まれます。
自己評価: 自分の能力や知識、思考パターンなどを評価する能力
自己制御: 自分の思考や行動を意識的にコントロールする能力
このような能力を意識して自身のリーダーシップを第三者の視点から見てみることを意識しましょう。
(2)専制型
このタイプは、権力を盾にして、暴君のように振る舞います。部下の発言に過剰に反応し、怒鳴ってしまったり、「こんなこともできないのか」と部下を小馬鹿にしてしまったりする場面が目につきます。このようなリーダーの多くは「~すべき」といった譲れない価値観を持っており、それに相反する言動に出くわした際に怒りが生じます。この「~すべき」という譲れない価値観を「コアビリーフ」と呼びます。
例えば、「部下は率先して上司に挨拶するべき」というコアビリーフを持っている上司は、部下から先に挨拶がないと「何でこの部下は先に挨拶しないのか」と怒りを持つことがあります。ですが、部下はたまたま挨拶のタイミングを逃したのかもしれませんし、どちらが先に挨拶するべきかという点に何のこだわりも持っていないのかもしれません。
つまり、怒りは、「誰か」や「何か」に怒らされた結果というよりも、自身が怒ることを選択した結果であるということです。よって、怒りを感じた場合は、自分がどのようなコアビリーフを持っているのかに気づく良い機会といえるでしょう。
(3)放任型
パワハラタイプで着目するべきはこの放任型です。このタイプは、自分自身による意思決定を避ける傾向があり、部下に対するフィードバックも積極的ではありません。ですが、このような一見無害に見えるリーダーシップが、実際にはパワハラにつながりやすいことに注意が必要です。
放任型タイプのリーダーが率いる職場では、部下が「リーダーに毛嫌いされているのではないか」「後で責められるのではないか」と不安を抱えがちになります。また、リーダーから適切な指示がないため、失敗した責任を部下同士がなすりつけ合うなど、衝突が発生しやすくなります。よって、ハラスメントを避けるためにリーダーが部下との関わりを避けようとしているのであれば、それは間違いであるという認識が必要です。
■パワハラ防止のための「個別配慮型リーダーシップ」
前述の津野香奈美氏は、パワハラの防止策として、部下を集団の1人としてではなく、個人として接する「個別配慮型リーダーシップ」を提唱しています。これは、リーダーが部下に誠実な関心を向けるとともに、個人が抱えるニーズや興味に寄り添う接し方といえます。
このような接し方の例として、部下とのコミュニケーションをとる場合に、以下の5W3Hを明らかにしていくという手法があります。
Why(なぜ) 理由や動機
Who(誰が) 対象
When(いつ) 時期や時間帯
Where(どこで) 場所
How(どのように) 手段や方法
How many(どのくらい) 規模
How much(いくらで) 価格
これらを明らかにしていく質問を、誠実な関心を持って投げかけることによって、コミュニケーションの内容が具体化され、情報が共有されやすくなっていきます。ただし、質問攻めにならないように、部下の状況やペースに合わせて質問することや、部下が答えにくい質問・プライベートに関わる質問は避けることに留意する必要があります。
■まとめ:リーダーの意識が組織全体のパフォーマンスを向上させる
既存人材の定着率向上のために、リーダーが意識すべきパワハラ防止策について解説しました。
リーダーは、自身の言動がパワハラに該当しないか常に振り返り、自己認識を深めることが重要です。特に、「脱線型」「専制型」「放任型」といったパワハラの類型を理解し、自身の行動パターンを客観的に見直すことで、パワハラを未然に防ぐことができます。
また、部下とのコミュニケーションにおいては、「個別配慮型リーダーシップ」を意識し、5W3Hを明確にするための質問を通じて、部下の状況やニーズを深く理解することが大切です。これにより、部下は尊重されていると感じ、心理的安全性が高まります。
リーダーがこれらのポイントを意識することで、パワハラを防止し、人材の定着率を高め、組織全体のパフォーマンス向上に繋げることができるでしょう。
執筆講師
三上康一(みかみ こういち)
株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
21年間ガソリンスタンドの運営会社に勤務し、17か所の現場を経験。店長としての13年間で、赤字店舗の4年ぶり黒字転換、2店舗においてガソリン販売量新記録達成(自店比)などの実績を挙げる。
2008年(平成20年)に中小企業診断士取得。翌2009年(平成21年)に創業。









