離職率低下の鍵は「言葉」にあり!リーダーが実践すべきポジティブコミュニケーション【三上康一講師特別コラム】
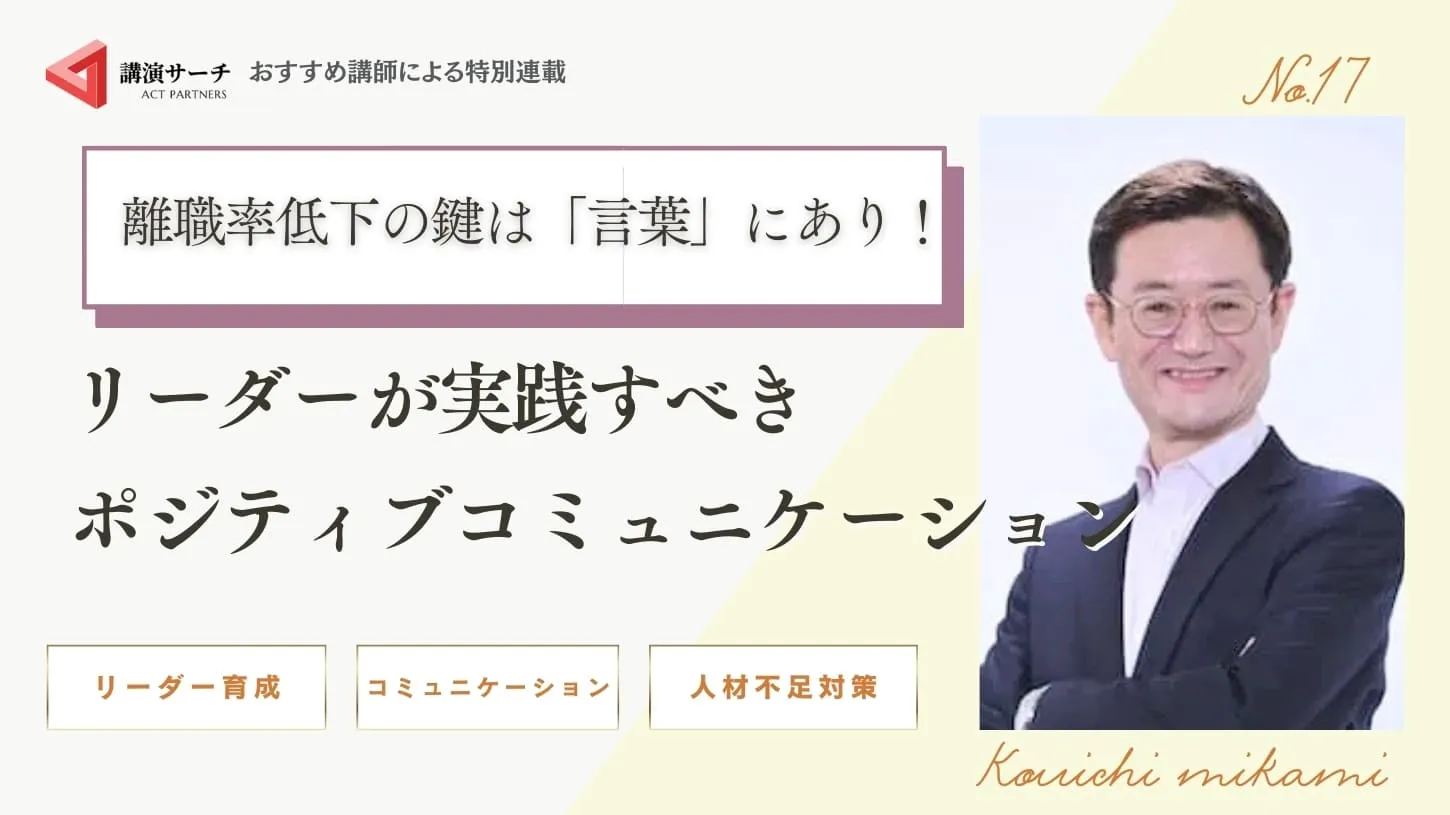

離職率低下の鍵は「言葉」にあり!リーダーが実践すべきポジティブコミュニケーション【三上康一講師特別コラム】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
現代の企業経営において、人材の定着率は重要な経営課題のひとつです。従業員が職場に留まり、高いモチベーションで働き続けることが、人材不足を防止し、企業の持続的な成長に繋がるからです。しかし、現実には多くの企業で従業員の離職率が高く、特に中小企業や小規模事業者にとって深刻な問題となっています。これを解決するために、「職場のリーダーがポジティブな言葉」を積極的に使うことが、効果的である理由を述べていきます。
■言葉の力が人材定着に与える影響
言葉の力は、私たちの思考や行動に強い影響を与え、職場で使われる言葉が従業員の行動やモチベーション、さらには定着率に直結するといえます。ポジティブ心理学という分野では、ポジティブな言葉や思考がどのように人々の心に影響を与え、行動を変化させるかが研究されています。この考え方をビジネスの現場に活用することで、従業員の定着率を高めることが可能になります。
■プライミング効果とポジティブな言葉
ポジティブな言葉が従業員の行動にどのように影響を与えるのかを理解するためには、プライミング効果という心理学的現象を知ることが重要です。
プライミング効果とは、特定の言葉や刺激が、その後の行動や思考に無意識的に影響を与える現象のことを指します。特定の言葉がどのように私たちの行動を変化させるのかという点について、ニューヨーク大学で行われた実証実験をご紹介します。
この実験では、被験者(実験に参加する対象となる人々)をいくつかのグループに分け、それぞれに異なる単語が書かれた単語カードを複数枚配布しました。被験者はそのカードに書かれた単語を使った文章を作成します。そして、あるグループに配布したカードには「杖」や「介護」など、高齢者を連想させる単語が書かれていました。
各グループは配布されたカードに書かれた単語を使って文章を作りました。次に、被験者に対して、キャンパス内を歩いて別の教室に移動するよう指示を出しました。
その結果、高齢者を連想させる単語を使用したグループの被験者は、他のグループの被験者よりも歩く速度が明らかに遅かったことがわかりました。この実験の結果は、接する言葉が人々の行動に実際に影響を与えることを示しています。
このプライミング効果は、企業においても同様に働きます。職場で使用する言葉が従業員の行動や感情に無意識のうちに影響を与えるため、ポジティブな言葉を使うことで、従業員の態度や行動が前向きに変わることが期待できます。これにより、職場の雰囲気が改善され、定着率が向上するということです。
■ポジティブな言葉を使った具体的な事例
職場で、言葉をどのように活用すれば良いのかを理解するために、具体的な事例を挙げてみましょう。私がかつて店長を務めていたガソリンスタンドは、従業員の離職率が高く、慢性的な人材不足に苦しんでいました。そこで、従業員が感じる「職場の負担感」や「仕事のネガティブな側面」を少しでも改善するため、私はポジティブな言葉を使うことに決めました。
例えば、次のような言い換えを行いました。
「売上が伸び悩んでいる」→「顧客ニーズを深掘りし、新たな価値提供に繋げる好機だ。」
「人材が足りない」→「チームの能力を最大限に引き出し、効率的な組織作りを目指す絶好の機会だ。」
「店舗が暇だ」→「この時間を有効に使って、スタッフ同士のコミュニケーションを深めよう。」
これらのポジティブな言い換えは、職場の雰囲気をポジティブなものへと変え、結果としてスタッフのモチベーションが高まり、定着率の向上につながりました。
■「経営の神様」のポジティブ思考とは
パナソニック株式会社の創業者であり、「経営の神様」と称された松下幸之助氏は、新入社員の採用面接において、ある質問を欠かさず行っていたといいます。
それは――
「あなたは、自分のことを運が良いと思いますか?」という問いかけです。
この質問に「運が悪い」と答えた応募者は、どれほど優れた学歴や実績を持っていても、松下氏は採用しなかったと伝えられています。
実は松下氏自身、裕福とは程遠い家庭に育ち、健康にも恵まれず、学校も小学校4年で中退するという苦労を重ねた人物でした。しかし、彼はその境遇を悲観するどころか、「裕福でなかったからこそ無理な挑戦をせず、堅実に経営ができた」「健康ではなかったからこそ、部下に仕事を任せ、育成することができた」「学歴がなかったからこそ、多くの人の知恵を借りられた」と振り返り、自らの人生を「運が良かった」と語っていたのです。
松下氏が重視していたのは、「自分は運が良い」と信じられる前向きな姿勢でした。そうした人は、自分の力では変えられない状況を受け入れた上で、変えられる部分に目を向け、チャンスを見出す力を持っている――そう考えていたのです。
たとえば、新型コロナウイルスの流行に直面したときに、「客足が遠のいた」「来店客が減って困った」とネガティブに捉えるか、「オンライン販売へ切り替えるチャンスだ」と前向きに発想を転換できるかで、その後の成果は大きく変わってくるでしょう。
同じ出来事であっても、ポジティブに受け止められる人は、新たな可能性を見つけ出しやすく、ビジネスの世界で生き抜く力があると松下氏は信じていたのです。
■ポジティブな言葉を使うことで得られるメリット
ポジティブな言葉を使うことには、従業員の定着率を高めるだけでなく、その他にもさまざまなメリットがあります。
1. モチベーションの向上
ポジティブな言葉は、従業員が自身の業務に対して前向きな感情を抱く手助けをします。具体的な改善点や成長の機会を強調することで、従業員は自分の仕事に対する誇りややりがいを感じ、モチベーションが向上します。
2. ストレスの軽減
仕事で生じるストレスやプレッシャーを軽減するためには、ポジティブな言葉が効果的です。問題や困難を「チャレンジ」「成長の機会」と捉え直すことで、従業員はストレスを感じにくくなり、心身の健康を保ちながら業務に取り組むことができます。
3. チームワークの強化
職場で使われる言葉がポジティブであれば、従業員同士のコミュニケーションも良好になります。例えば、ネガティブな言葉で互いに責任を押し付け合うのではなく、ポジティブな言葉で互いにサポートし合うことができるため、チームとしての結束力が高まります。
4. 従業員のエンゲージメント向上
エンゲージメントとは、従業員が企業に対してどれだけの愛着や忠誠心を抱いているかを示す指標です。ポジティブな言葉はエンゲージメントを高める要素のひとつです。ポジティブな環境で働くことで、従業員は自分が企業に貢献していると感じ、仕事に対する情熱を持ち続けます。
■まとめ
この記事では、職場のリーダーがポジティブな言葉を積極的に使うことの重要性を、心理学的効果と具体的な事例を交えて解説しました。
言葉は、私たちの思考や行動に深く影響を与え、職場で使われる言葉は、従業員のモチベーションや定着率に直結します。ポジティブな言葉を使うことで、従業員の行動を前向きに変え、職場の雰囲気を改善し、最終的には人材の定着率向上につながります。
「プライミング効果」という心理学的現象からも、言葉が人の行動に与える影響は明らかです。職場でポジティブな言葉を使うことは、従業員の態度や行動に好影響を与え、チームワークの強化、ストレスの軽減、エンゲージメントの向上など、多岐にわたるメリットをもたらします。
パナソニック創業者の松下幸之助氏の例からもわかるように、逆境をチャンスに変えるポジティブな思考は、ビジネスにおける成功の鍵です。リーダーがポジティブな言葉を意識的に使うことで、従業員は困難な状況でも前向きな姿勢を保ち、新たな可能性を見出すことができます。
現代の企業経営において、人材の定着は重要な課題です。ポジティブな言葉を積極的に活用し、従業員が長期的に活躍できる職場環境を作り上げることが、企業の持続的な成長に繋がります。
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役






