成功するチーム作りの要素:心理的安全性と定着率向上の重要性【三上康一講師特別コラム】
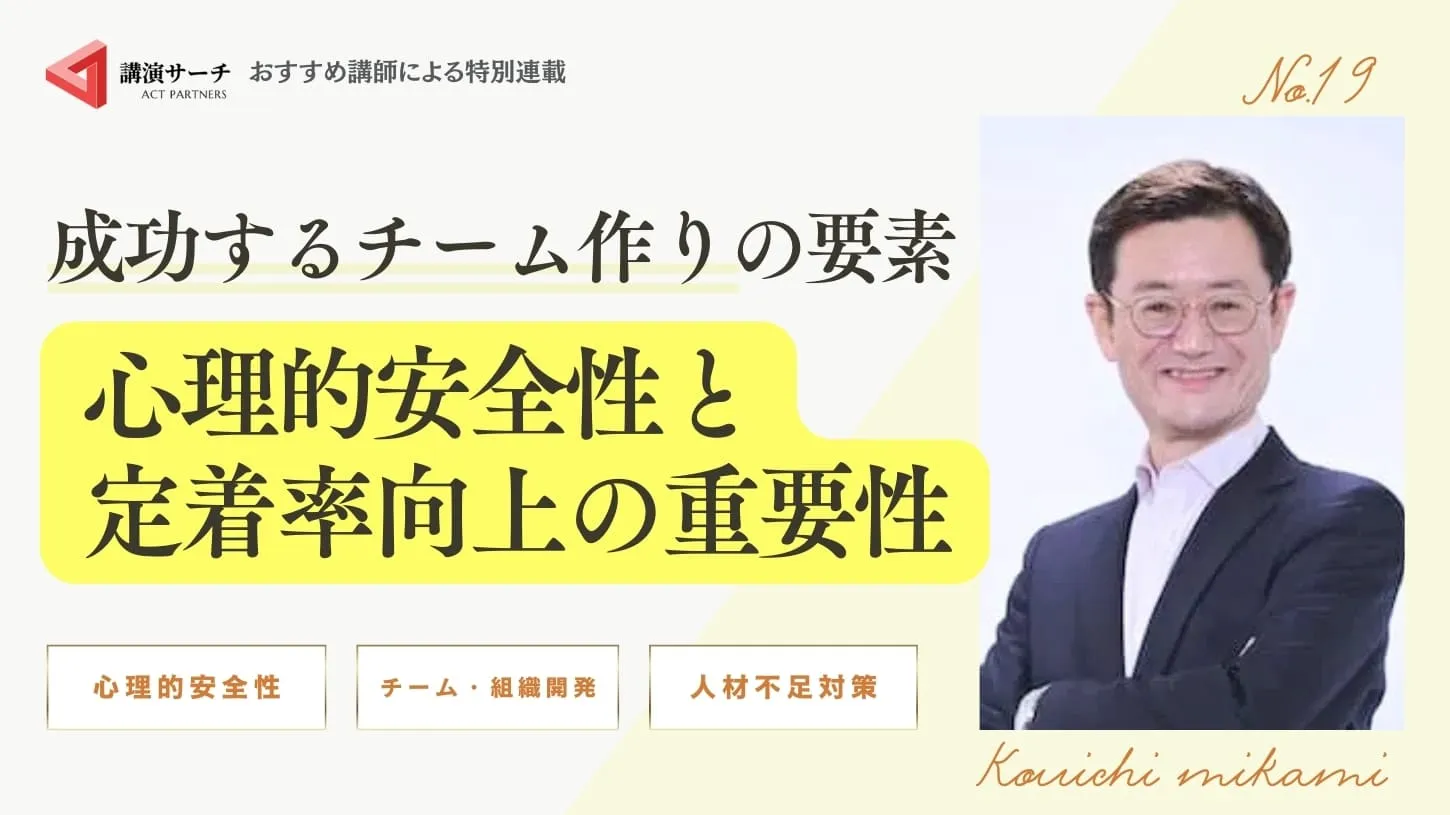

成功するチーム作りの要素:心理的安全性と定着率向上の重要性【三上康一講師特別コラム】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
■Google「プロジェクトアリストテレス」が示した成功するチームの要素
人手不足が深刻化の一途を辿る現代において、企業が持続的な成長を遂げるためには、現在働いている従業員の定着率を高めることが不可欠です。では、従業員が長く安心して働き続けられる組織とは、一体どのような特徴を備えているのでしょうか?
その問いに対する重要なヒントが、テクノロジー業界の巨人、Googleによる大規模な調査「プロジェクトアリストテレス」の中に隠されています。2012年から2年間にわたり、社内の180ものチームを徹底的に分析した当該プロジェクトからわかったことは、目覚ましい成果を上げるチームには、共通する5つの要素があるということです。
それは、「心理的安全性の高さ」「信頼できるチームメンバーの存在」「明確な目標とビジョン」「効率的な意思決定」「生産的なミーティング」です。中でも特筆すべきは、メンバーが安心して意見を交わし、失敗を恐れずに挑戦できる「心理的安全性」の重要性です。
心理的安全性の高いチームでは、活発な情報交換が促され、潜在的な問題が早期に発見・解決されるだけでなく、革新的なアイデアも生まれやすくなります。そして何より、従業員の離職率が低下し、組織全体のパフォーマンス向上に大きく貢献することが期待できます。本稿では、人材の定着率を高め、人手不足を解消するための具体的な戦略と実践的なアプローチを深く掘り下げていきます。
■心理的安全性への本能的な欲求:ハーロウの代理母実験からの示唆
心理的安全性の重要性を示す事例として、心理学者ハリー・ハーロウの代理母実験が挙げられます。
この実験では、生まれたばかりの子ザルが、針金で作られた代理母と、柔らかい布で作られた代理母のどちらを選ぶかが観察されました。なお、針金製の代理母にはミルクの入った哺乳瓶がついており、布製の代理母には哺乳瓶がついていませんが、その布はヒーターで温められています。
子ザルは、栄養を得るためだけに針金製の代理母に近づきましたが、ほとんどの時間を温かい布の代理母にしがみついて過ごしました。たとえ針金製の代理母がミルクを与えても、子ザルは温かさと安心感を提供する布製の代理母を強く求めたのです。
さらに興味深い観察結果があります。檻の中に針金製の代理母と子ザルだけの状況を作り、研究者らが蛇のおもちゃを檻の中に入れたところ、子ザルは激しく怯え、檻の隅にうずくまって動けなくなってしまいました。
しかし、針金製の代理母を温かい布製のものに交換し、再び蛇のおもちゃを檻に入れたところ、子ザルの行動は劇的に変化しました。最初は蛇のおもちゃを警戒して布製の代理母にしがみついていましたが、次第に好奇心が勝り始めたのです。温かい代理母から離れ、慎重に蛇のおもちゃに近づき、触ったり、探ったりする様子が見られました。
この実験は、心理的安全性が、単に精神的な安定をもたらすだけでなく、未知のものへの恐怖心や不安を克服し、探求心や冒険心を育む上で重要な役割を果たすことを示しています。安全な基盤があるからこそ、リスクを取り、新しいことに挑戦する意欲を持つことができるのです。
Googleのプロジェクトアリストテレスが示した「心理的安全性の高さ」は、職場の人間関係におけるこの「布製の代理母」に相当すると言えるでしょう。安心して自分の思考や感情をオープンにできる環境があってこそ、従業員は精神的に安定し、自分の能力を最大限に発揮し、組織への帰属意識を高めることができるのです。
参考:jstage「愛―霊長類学からのアプローチー」
■海部町の事例に見る「安心して頼れる文化」
心理的安全性の重要性は、日本の地域社会においても、異なる形で現れています。その好例が、自殺率が低いことで知られる徳島県海部町(現在の海陽町)の事例です。過去30年間の全国3,318市区町村の自殺統計を基に、人口規模や年齢分布を調整した結果、極端に人口の少ない自治体を除外した上で明らかになったのは、最も自殺率が低い町が同町であるということです。
その背景には、住民同士の強い信頼関係と、「困ったときは遠慮せずに相談する」という文化があります。例えば同町では、近隣住民の様子がおかしいと感じた際、周囲が気軽にうつ病の受診を勧めることが一般的です。これに対し、他の地域では精神的な問題に対する偏見やタブーが強く、うつ病の受診を拒む人が多いのが現実です。
海部町には「病(やまい)は市(いち)に出せ」ということわざが伝わっています。悩みや問題を周囲にオープンにすることで、早期に支援を受け、深刻化を防ぐという文化が根付いているのです。このような環境では、助けを求めることが自然に受け入れられ、精神的な健康が守られやすくなります。
実際、海部町ではうつ病の受診率が高く、精神的な不調を早期に発見して支援を受ける人が多いとされています。このように、住民が自らの健康に敏感であり、必要な支援を早期に受け入れることができる環境が整っています。一方で、他の地域では精神的な問題を隠そうとする風潮が強く、問題が深刻化してしまうことがあります。
このような地域文化は、企業の組織づくりにも大きなヒントを与えてくれます。
■組織における「心理的安全性」の重要性
海部町のような「相談をためらわない文化」を職場に持ち込むには、まず経営者やマネージャーが率先して心理的安全性を確保する姿勢を示す必要があります。従業員が本音を語れるようになるには、「話しても大丈夫」という確信が不可欠です。
たとえば、定期的な1on1面談の実施や、匿名で意見を寄せられる仕組みの導入、上司が自らの弱さや失敗も共有する姿勢などが、心理的なハードルを下げる効果があります。さらに、「誰かの発言に対して批判や嘲笑をしない」「感情の共有を歓迎する」といったチームの行動規範を明文化することも、安心できる空気づくりに貢献します。
■「自己効力感」の向上が従業員の定着率を高める
海部町では、「自己効力感」の高い住民が多いことでも知られています。自己効力感とは、「自分の言動が周囲や社会に対して何らかの影響を与えることができる」という感覚を指します。簡単に言えば、「自分にも何かできる」という実感です。
この町では、子どもたちが小さい頃から「あなたにもできることがある」と励まされ、自分なりの方法で社会に貢献することの大切さを教えられて育ちます。人それぞれの能力の違いを前提に、決して画一的な成功を押しつけるのではなく、各自が「自分らしい貢献」をできる環境が整っているのです。
町の意思決定の場である議会でも、この考え方は徹底されています。新人議員であっても、古参議員と対等に扱われ、初日から積極的に発言することが求められます。発言権を得るために長い下積みを経るのが一般的な多くの自治体とは対照的に、海部町では「誰もが声を持っている」という前提が当たり前のように共有されているのです。
この文化の力は、数値にも現れています。住民を対象としたある調査では、「自分のような存在に政府を動かす力はない」と答えた人の割合が、海部町では26.3%にとどまったのに対し、自殺率の高いある町では51.2%にも上っていました。つまり、自分には何もできないと感じる人が多い地域では、無力感や孤立感が広がりやすく、それが深刻な結果につながる可能性があるのです。
この海部町の事例は、職場における従業員の自己効力感にも通じます。従業員が「自分の意見が尊重されている」「役に立っている」と感じられる環境では、やる気も定着率も自然と高まっていくのです。
■定着率向上が人手不足解消の最も効果的な手段
人手不足が深刻化する中で、「採用」にばかり目を向けていては、根本的な解決にはなりません。むしろ、すでにいる人材が辞めない環境づくり――すなわち、定着率の向上こそが最大の人手不足対策であり、その鍵を握るのが心理的安全性です。
Googleが明らかにした「成果を出すチーム」の要件も、海部町のような地域社会の実践も、本質的には「人と人が安心してつながれる環境づくり」の大切さを物語っています。
一人ひとりが自分の意見を出し、支え合い、挑戦できる職場こそが、社員に選ばれ、結果的に企業の成長を支えていく――その確信を持って、今こそ組織の在り方を見直すときではないでしょうか。
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役






