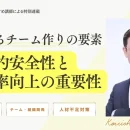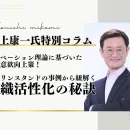怒りが職場を壊す前に!人手不足の根本原因を解決する「アンガーマネジメント」入門【三上康一講師特別コラム】
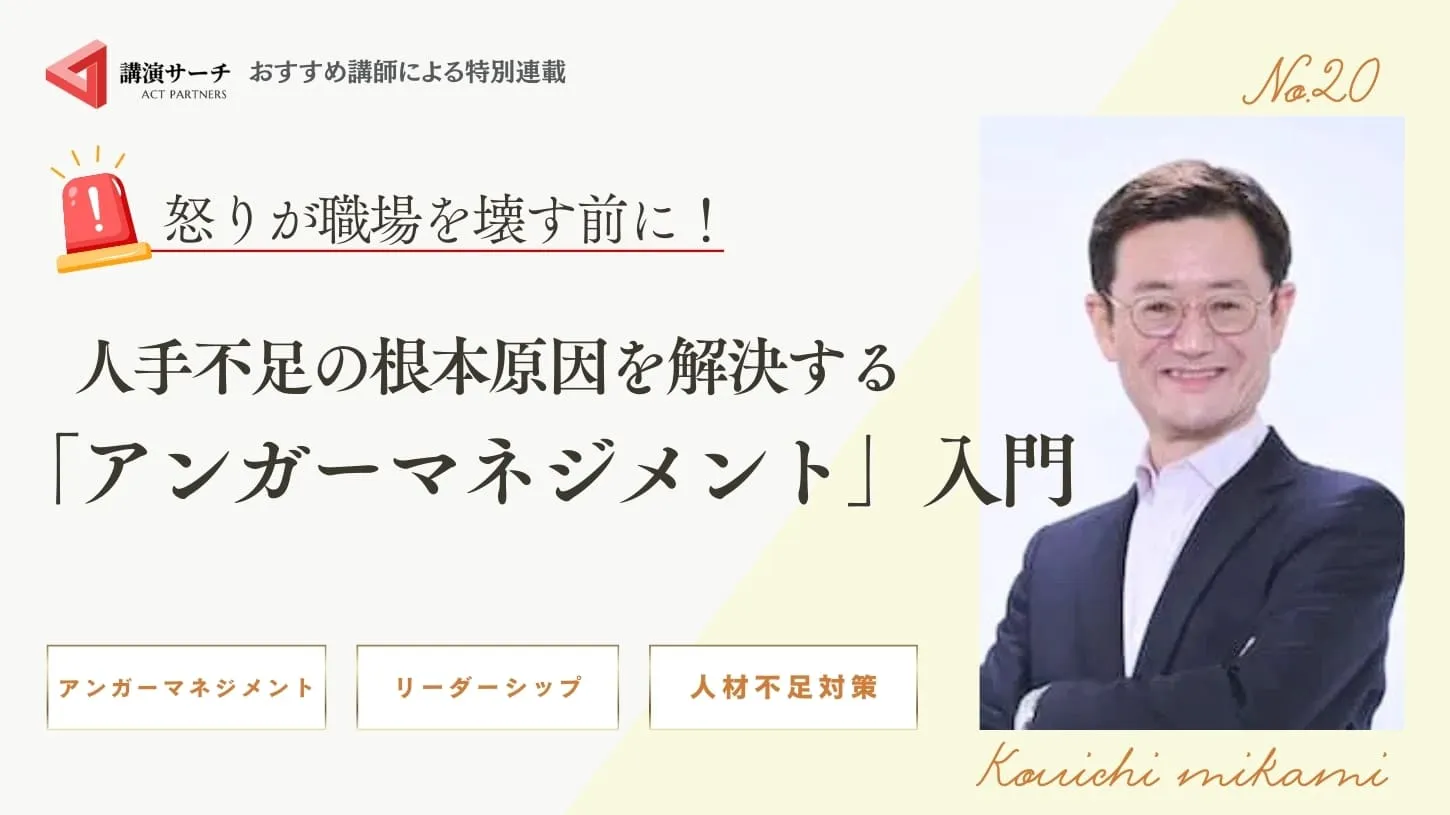

怒りが職場を壊す前に!人手不足の根本原因を解決する「アンガーマネジメント」入門【三上康一講師特別コラム】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
■人手不足の真相:リーダーの怒りが引き起こす負の連鎖
人手不足が深刻化する一因に、職場リーダーの抑えきれない怒りが挙げられます。感情的な叱責、高圧的な態度、理不尽な要求。リーダーの怒りは、職場の空気を淀ませ、従業員のモチベーションを著しく低下させます。そして、彼らは静かに、しかし確実に、そんなリーダーの元から去っていくのです。
多くの場合、人手不足は既存の従業員が退職することによって引き起こされます。これを防止する方策を検討しないまま、新規の従業員を採用しても、早期に退職されてしまい、結果として人手不足は解消されません。
本記事では、リーダーの怒りがもたらす負の連鎖を断ち切り、従業員が安心して長く働ける職場を築くためのアンガーマネジメントについて解説します。リーダーが、怒りの感情に振り回されるのではなく、それを理解し、コントロールすることで、人手不足の根本的な解決へと導くことができるでしょう。
■アンガーマネジメントとは?怒りの管理手法
アンガーマネジメントとは、誰もが抱く自然な感情である「怒り」を、適切に理解し、コントロールするための技術や方法です。
その代表的な手法のひとつが「6秒ルール」。怒りがこみ上げた瞬間に、たった6秒間だけ反応を抑えることで、感情の爆発を防ぎ、冷静さを取り戻しやすくなると言われています。
しかし、実際には6秒も待てないと感じる人も少なくありません。そうした現実に対し、名古屋大学の研究グループは、より実行しやすく効果的なアプローチを開発し、実証実験を通じてその有効性を検証しています。
参照:名古屋大学研究成果発信サイト「紙とともに去りぬ ~怒りを「書いて捨てる」と気持ちが鎮まることを実証~」
■【名古屋大学の研究】「書いて捨てる」怒りの鎮静効果
この実験では、参加者(被験者)はまず、穏やかな状態で自身が抱えている怒りのレベルを数値化した「怒りスコア」を記録しました。続いて、一般的な社会問題に関する短い文章(エッセー)を作成しました。
その後、このエッセーは意図的に厳しい評価を受けます。実際の内容に関わらず、低い評価が付けられ、「とても教養のある大学生が書いたとは思えない」といった、尊厳を傷つけるような辛辣なコメントが添えられました。
被験者は、この評価とコメントによって湧き上がった感情を怒りスコアとして記録するとともに、その怒りスコアになった理由を詳細に紙に書き出しました。その後、彼らは以下の2つのグループに分けられました。
| 廃棄グループ | 書き出した紙を丸めて捨てる、またはシュレッダーにかけるよう指示されました。 |
| 保存グループ | 書き出した紙を机の上のファイルに保管するよう指示されました。 |
その上で、再度怒りスコアを記録しました。この実験の結果、以下の点が明らかになりました。
・屈辱的で手厳しいコメントによって、被験者の「怒りスコア」は顕著に上昇しました。
・しかし、そのコメントに対する自身の感情とその理由を紙に書き出すことで、「怒りスコア」は速やかに低下しました。
・特に、書き出した紙を物理的に処分した「廃棄グループ」では、怒りの感情がほぼ完全に消失しました。
・一方、「保存グループ」でも怒りの感情はいくらか収まったものの、「廃棄グループ」と比較すると依然として高いままでした。
この結果から、名古屋大学の研究グループは、「怒りの感情を紙に書き出し、物理的に処分するという行為は、ビジネスの現場においても応用できる可能性がある」と結論付けています。今後は、メールなどのデジタルな媒体においても同様の効果が得られるかどうかの検証が予定されています。
■6秒ルールが難しいあなたへ:「書いて捨てる」が有効な理由
なお、前述の6秒ルールは、怒りの「瞬間」に使う「衝動対策」です。一方、紙に書く行為は、怒りの「余韻」や「蓄積された怒り」に対して使う「内省と解放のプロセス」です。
つまり、衝動的に怒ってしまった人が、その場で紙に感情を整理するのは難しいと言えますが、「怒ったあとに後悔している人」や「同じことで何度もイライラしてしまう人」にとっては、冷静になったタイミングで紙に書くことは可能ですし、むしろ有効です。
名古屋大学の実験も、「怒りを感じた瞬間に紙に書け」という話ではありません。実験では、怒りを引き起こす刺激(屈辱的コメント)を与えた後、その怒りをある程度「意識化」できるようになってから紙に書かせています。これは、「怒りのピークを過ぎた後に、どう処理するか」という話であり、
・衝動的な怒り→即行動を防ぐ「6秒ルール」
・感情が落ち着いた後→怒りを内省・放出する「書いて捨てる方法」
というように、時間軸の異なる2つのアプローチとして位置づけられます。
よって、6秒ルールが守れない人でも、「怒った後」に気持ちを整理したいと思うことは多く、その段階で紙に書く方法は十分に実行可能かつ効果的です。
この行為を繰り返す中で、「自分がどのような出来事に、なぜ怒りを感じるのか」といった感情の傾向を客観的に把握できるようになります。それにより、怒りの感情が湧き上がった瞬間にも「これは以前にも感じたパターンだ」と気づきやすくなり、感情の爆発を抑える6秒ルール的な自制心が自然と鍛えられていきます。
つまり、「書いて捨てる」ことを通して怒りの蓄積を防ぐだけでなく、その後の場面で怒りに気づくスピードや、冷静さを保つ力が高まり、結果的に怒りを未然に抑える力(=アンガーマネジメント能力)そのものが強化されていくという、前向きな循環が生まれるのです。
■怒りの根源を探る:あなたの「コアビリーフ」は?
アンガーマネジメントをより深く理解し、効果を高めるためには、自身の怒りの根本原因を探ることが不可欠です。私たちが怒りを感じる時、その奥には「~であるべきだ」という、個人的な譲れない価値観が存在していることが多いのです。
この核となる信念、いわゆる「コアビリーフ」こそが、怒りの引き金となっている場合が少なくありません。
例えば、ある職場のリーダーが「部下は上司に対して逐一報告をするべきだ」という強いコアビリーフを持っていたとします。ですが、もし部下が進行中の業務について逐一報告せず、自分の判断で対応していた場合、そのリーダーは「なぜ勝手に判断したんだ!」と強い苛立ちを感じるかもしれません。
しかし、その部下には、もしかしたら「忙しいリーダーに細かい報告をして負担をかけたくない」という配慮があったのかもしれません。あるいは、「任された仕事は、自分で責任を持つべきだ」という価値観を持っていた可能性もあります。
ここで重要なのは、リーダーのコアビリーフによってリーダーの感情が変わるということです。リーダーが「部下は上司に対して逐一報告をするべきだ」という強い信念を持っているからこそ、部下の報告がないという行動に対して「なぜ勝手に判断したんだ!」という怒りの感情が生まれるのです。
怒りの根本原因は、部下の行動そのものではなく、リーダー自身の内にある「~すべき」というコアビリーフと、現実の状況との間に生じたギャップにある、という認識を持つことが大切です。最終的に、そのギャップに対して「怒り」という感情を選択しているのは、他でもない自分自身なのです。
自身のコアビリーフを理解し、それが絶対的なものではないと認識すること。そして、他者との価値観の違いを受け入れる寛容さを持つこと。これこそが、怒りを適切にコントロールし、より穏やかなリーダーシップを発揮するための重要な第一歩となるでしょう。
■怒りをコントロールし、魅力的なリーダーになるために
本記事では、人手不足の深刻な要因となり得る、職場リーダーの怒りの感情とそのマネジメントについて掘り下げてきました。怒りは誰にでも起こりうる自然な感情ですが、その制御を誤れば、大切な人材を失い、組織の活力を奪いかねません。
アンガーマネジメントの基本である「6秒ルール」に加え、名古屋大学の研究が示す「書いて捨てる」という手法は、衝動的な怒りだけでなく、蓄積された不満や後悔の念を解放する有効な手段となり得ます。自身の怒りの根源にある「コアビリーフ」を理解し、それが絶対的なものではないと認識すること、そして他者との価値観の違いを受け入れる寛容さを持つことこそが、怒りを適切にコントロールし、信頼されるリーダーシップを発揮するための鍵です。
今、リーダーに求められているのは、感情に振り回されるのではなく、自身の感情と向き合い、コントロールする力です。アンガーマネジメントを学び、実践することで、リーダー自身がより穏やかになり、従業員との信頼関係を深めることができるでしょう。その結果、従業員のエンゲージメントが高まり、定着率の向上、ひいては人手不足の解消へと繋がるでしょう。怒りをマネジメントすることは、単なる感情の抑制ではなく、組織の土台を固め、持続的な成長を築くための重要な投資なのです。
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役