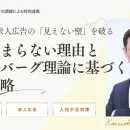「教える」が会社を変える!心理学が導く、新人即戦力化と定着の新常識【三上康一講師特別コラム】
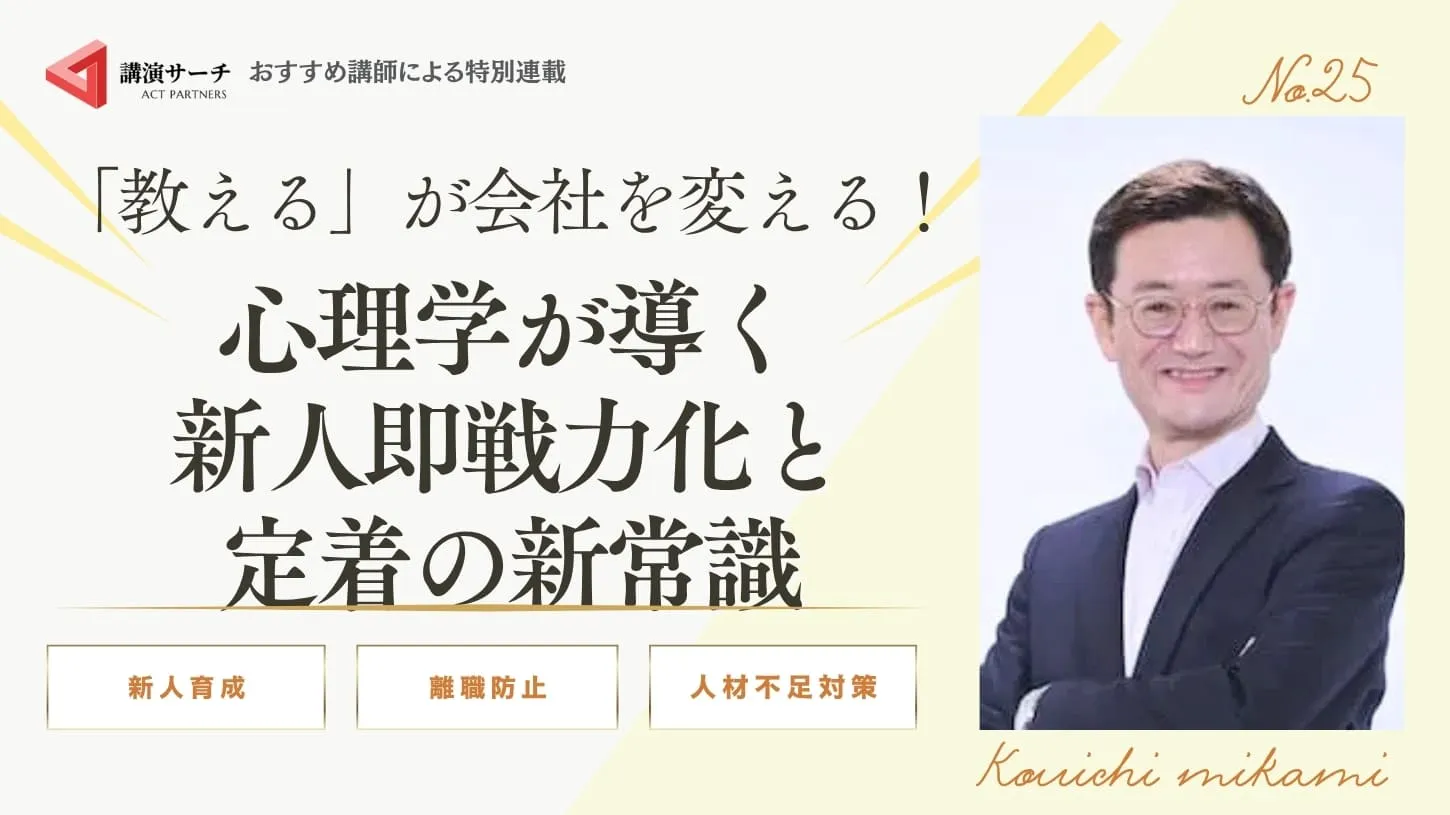

「教える」が会社を変える!心理学が導く、新人即戦力化と定着の新常識【三上康一講師特別コラム】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
近年、多くの企業で慢性的な人手不足が深刻化する中、新人をいかに早期に戦力化し、定着させるかが大きな課題となっています。そのための手段として広く導入されているのが「OJT(On-the-Job Training)」ですが、現場ではしばしば「教える余裕がない」「任せたまま放置してしまう」といった問題が発生し、本来の効果が得られないばかりか、新人の早期離職を招いてしまうケースが少なくありません。
実は、こうした問題の背景には「教える側のモチベーション不足」が潜んでいます。ところが、心理学の研究によれば、他者に教えること自体が、教える側の意欲や成長を促す強力な手段であることがわかっています。
本記事では、実際にOJTの在り方を見直し、「教えること」を仕組みとして職場に取り入れたことで、人材の早期離職を防ぎ、内側から人手不足を解消していった現場の取り組みを紹介します。新人も既存社員も育つ、“教えるOJT”の仕掛けとは何か。その鍵は、意外にも「心理的効果」にありました。
■深刻化する人手不足の現実とOJTの「落とし穴」
新人育成の手段として多くの企業が導入しているOJTは、実務を通じてスキルや知識を身につける効果的な教育方法です。しかし実際の現場では、「教える余裕がない」「任せたまま放置してしまう」といった問題から、「OJTという名のほったらかし」や「OJTという名のぶっつけ本番」が発生し、新人スタッフが退職してしまうケースも少なくありません。
新人は職場に入って間もない時期、常に「ここでやっていけるだろうか」「自分は受け入れられているのだろうか」といった不安を抱えています。そのような心理状態の中で、OJT中にトレーナーが他の業務で忙しいことを理由に新人を放置してしまうと、「自分には関心を持ってもらえていない」「どうでもいい存在なんじゃないか」「ここは安心して質問できる環境じゃない」と感じ、心理的安全性が著しく損なわれ、退職につながります。
また、新人が業務に十分な準備や練習をしないまま、いきなり現場に立たされると、高確率でミスを起こします。これによって「ちゃんと教わっていないのに、できない自分が悪いのか?」「向いてないのかもしれない」「ここで続ける自信がない」と感じ、結果として、自己効力感(自分はやれるという信念)が失われ、早期離職の引き金になります。
こうした問題の根底には、トレーナーの負担過多や育成に対する動機づけの弱さがあります。そこで私がガソリンスタンドの運営会社に勤務し、現場で店長を担っていた頃に実施したのは、「教えること」を通してトレーナー自身のモチベーションを引き出す仕組みづくりでした。
■「教えること」がモチベーションを高める科学的根拠
この方針の背景にあるのが、シカゴ大学のアイエレット・フィッシュバック博士らが行った研究成果です。彼女の研究は、目標達成のメカニズムや、人がどのようにしてモチベーションを維持し、障害を乗り越えるのかを明らかにすることに焦点を当てています。
彼女が行った実験の一つで、特に注目すべきは「他者へのアドバイスが自身のモチベーションを高める効果」に関するものです。この実験では、以下のような内容が報告されています。
【実験内容】
318人の学生を2つのグループに分けました。一方のグループのメンバーは、後輩に対して勉強のモチベーションを高めるためのアドバイスを手紙に書くように指示されました。
もう一方のグループのメンバーは、教師から勉強のモチベーションを高めるアドバイスが書かれた手紙を受け取りました。両グループとも週1回ペースで3週間にわたって同じ作業を行い、各グループメンバーの勉強に対するモチベーションが調査されました。
【実験結果】
後輩にアドバイスを与えたグループは、教師からアドバイスをもらったグループよりも、勉強時間が38%も多くなっていました。同様の実験がダイエット、貯金、職探しといった他のテーマでも行われましたが、結果はすべて、他者にアドバイスを与えたグループの方がポジティブな結果を示しました。
【示唆されること】
この実験は、他者へのアドバイスを考える過程で、具体的な行動(いつ、どこで、誰と、どのように)を具体的にイメージすることが、自身のモチベーションを高め、行動を促す効果があることを示唆しています。つまり、自分が目標を達成するために必要な行動を、他者に教えることで、自分自身の行動に対するコミットメントも高まるということです。
■【実例】「教えるOJT」で変わったガソリンスタンドの現場
・「教えることのやりがい」がもたらした人材定着の好循環
私が店長を担っていたガソリンスタンドでは、この心理的メカニズムを活かすため、それまで正社員が担っていたOJTのトレーナーを比較的経験のある大学生のアルバイトスタッフに任せました。すると、新人を教える過程でスタッフ自身の知識が強化され、自信が育ち、仕事に対する意欲が高まっていく姿が見られました。
さらに、この「教えることのやりがい」が動機づけとなり、彼は卒業後に正社員としての入社を希望しました。彼が正社員になった段階で、新たに別の大学生アルバイトスタッフにOJTのトレーナーを担っていただいたところ、やはり同様に、育成の喜びをモチベーションとして当社への就職を決めました。こうして、「教えることで人が育ち、人手不足を内側から解消するサイクル」が生まれていきました。
この取り組みは、単に新人教育の質を高めるだけでなく、アルバイトスタッフの成長意欲や職場への愛着を育む副次的効果も生みました。教えることによって自分の価値を実感し、「もっと学びたい」「もっと貢献したい」と感じるようになる――まさに、フィッシュバック博士の研究が示す“他者へのアドバイスが自己のモチベーションを高める”効果が、現場レベルで立証された形です。
・「ほったらかし」「ぶっつけ本番」の解消とOJTの質向上
この仕組みを導入したことで、従来発生していた「OJTという名のほったらかし」や「OJTという名のぶっつけ本番」も自然と解消されていきました。その理由は、「常時現場にいる」アルバイトスタッフによる手厚いフォローが実現したためです。これまでは多忙な正社員がOJTトレーナーを兼任していたため、急な顧客対応や別の業務で、どうしても新人のそばを離れざるを得ない状況が頻繁に発生していました。しかし、トレーナーを常に現場にいるアルバイトスタッフに任せたことで、この状況は一変しました。
さらに注目すべきは、この取組みがもたらした人材定着の相乗効果です。トレーナーを任された大学生のアルバイトスタッフは、自らの成長と共に、職場における自分の役割や影響力を実感します。結果として、学校を卒業した後にアルバイトから正社員へと移行する意欲が高まり、離職率の低下、さらには人手不足の根本的な解消へとつながっていったのです。
■他業種にも応用可能な仕組み
この事例はガソリンスタンドという現場に限らず、飲食、介護、小売、物流など、多くの業種でも応用可能です。
重要なのは、以下の工夫を取り入れることです。
・トレーナー役に明確な責任と役割を与え、上司がフォローをする。
・トレーナー用のマニュアルを共有し、指導内容を明確化する。
こうした工夫により、新人も既存スタッフも安心して働ける職場環境が整い、結果として職場全体の活性化にもつながります。
■まとめ:OJTを「育てる仕組み」に変え、持続可能な組織へ
これまでのOJTは「新人を教える手段」として捉えられがちでしたが、これからは、「既存のスタッフを伸ばす手段」としても機能させる必要があります。
教える側にとっての成長機会としてOJTを再設計し、心理学的な知見を取り入れることで、「教える人も育ち、教えられる人も育つ」仕組みが生まれます。それこそが、人材不足という構造的な課題に対する、組織内部からの持続可能な解決策であり、未来を担う人材が育ち続ける組織文化づくりの第一歩なのです。
貴社の新人育成は、新人の心理的安全性や既存社員のモチベーションを考慮した設計になっているでしょうか?
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役