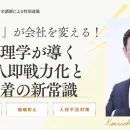「底辺の仕事」というレッテル貼りの危険性:職業への偏見が人手不足を加速させる負の連鎖を断ち切るには【三上康一講師】
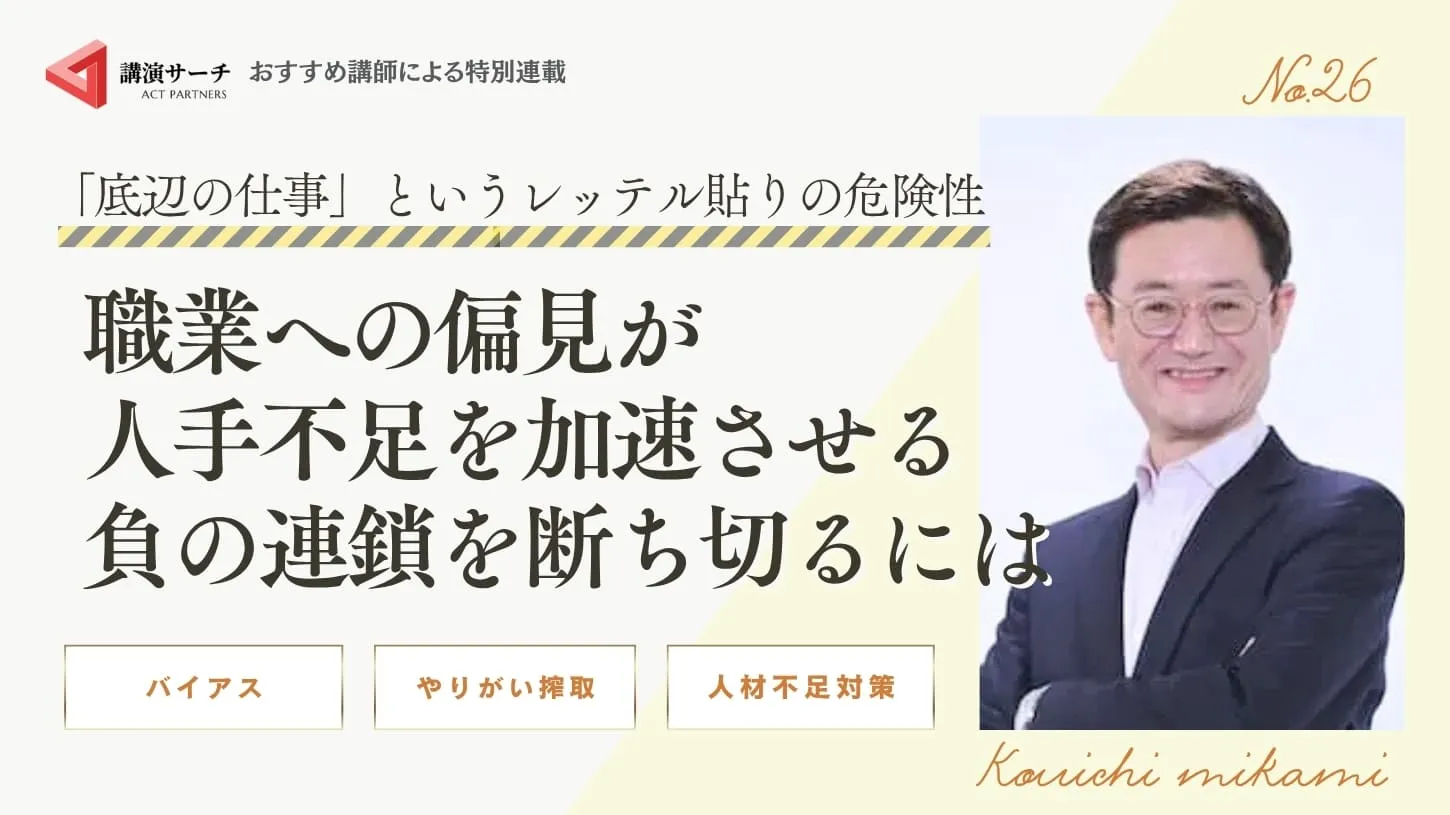

「底辺の仕事」というレッテル貼りの危険性:職業への偏見が人手不足を加速させる負の連鎖を断ち切るには【三上康一講師】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
数年前、インターネット上で「底辺の仕事ランキング」と称する記事が拡散され、SNSでの炎上を巻き起こしました。
参考:東洋経済オンライン「「底辺の仕事ランキング」批判集めた6つの問題点 “誰でもできる”の罪深さ、差別で片づけられず」
この記事は、特定の職業を公然と蔑み、多くの批判を集めました。なぜこのような記事が生まれ、そしてなぜ私たちは、こうした職業に対する偏見に流されがちなのでしょうか。現代社会が直面する深刻な人手不足の背景には、この根強い職業への偏見が深く関わっているのです。
問題の核心は、「底辺」という言葉が持つ差別的な響きだけではありません。記事が示唆する「誰でもできる仕事は底辺だ」という考え方は、あらゆる仕事に存在する専門性やスキルを軽視する、根本的な誤解に基づいています。例えば、一見単純に見える清掃作業でも、効率的な動線計画、汚れの種類に応じた洗剤の選定、感染症対策など、プロフェッショナルな知識と技術が求められます。しかし、そうした見えない努力や専門性はしばしば無視されがちです。
さらに、こうした記事が、単にアクセス数やアフィリエイト収益を目的に、意図的に過激な表現で人々の感情を扇動している現実も見過ごせません。大衆の潜在的な偏見を刺激し、炎上マーケティングの材料にすることで、誤った情報が社会に広まってしまうのです。
このような職業観が広がることで、「この仕事には価値がない」「自分は社会の底辺にいる」と思い込む人が現れ、仕事への誇りを失い、結果として職場から離れていく人も増えていきます。これは、ただの社会的問題にとどまらず、労働人口が減少する中で、すでに慢性化している人手不足をさらに深刻化させるという、企業経営にも直結する喫緊の課題となっています。
本記事では、「底辺の仕事」というレッテル貼りの危険性と、それが職場や従業員の意識に与える影響、さらに上司が自らの仕事に誇りを持つことが、部下のモチベーション向上と人材の定着につながる鍵であることを掘り下げていきます。
■上司のネガティブな「解釈」が引き起こす負の連鎖
かつて私がガソリンスタンドの運営会社に勤務し、現場で働いていた頃に、当時の上司が「ガソリンスタンドの仕事は厄介だ。肉体労働のくせに接客もしなければならず、愛想を良くしなければならないからだ」と言ったことがあります。また、別のガソリンスタンド運営会社の上司は「ガソリンスタンドで働く奴は頭が悪くて体が強ければそれでいいんだよ」と、部下の人格すら否定するような発言をしたこともありました。
もしあなたの職場で、上司がこのように自分の仕事や業界についてネガティブな発言をしていたらどうでしょうか?
部下は上司の背中を見て育ちます。上司が自身の仕事に誇りを持てないでいると、その感情は部下にも伝播し、負の連鎖を引き起こしかねません。上司のネガティブな姿勢は、部下から仕事の「意義」や「やりがい」を奪い、単なる作業として業務を遂行させるだけの結果につながりかねません。仕事の意義を見出せない、世間から評価されていないと感じる部下は、より良い機会や、自身の価値を認めてくれる職場を求めて他社へ転職する可能性が高まります。
■認知バイアスの罠:なぜ「解釈」が仕事の価値を決めるのか
「認知バイアス」とは、人間が情報を処理する際に、客観的な事実から逸脱し、解釈に基づいて主観的な見解や判断を形成する傾向を指します。私たちは無意識のうちに、情報の収集、解釈、記憶のあらゆる段階でバイアスがかかり、それが特定の職業に対する「偏見」や「思い込み」となって現れます。
例えば、「自分の仕事は底辺だ」「こんな仕事には価値がない」という認識は、客観的な事実に基づいていません。それは、個人の偏見に基づいた「解釈」に過ぎないのです。そして、この「解釈」こそが、その人自身の仕事の価値、ひいては自己肯定感をも左右します。
上司が自らの仕事に誇りを持てないのも、過去の経験や社会の評価、あるいは自身の認知バイアスによって、その仕事に対するネガティブな「解釈」を形成してしまっているからかもしれません。認知バイアスには様々な種類があり、仕事に対する歪んだ認識を生み出しやすいものとして、以下のような例が挙げられます。
| 確証バイアス | 自分の考えが正しいと思い込み、それを裏付ける情報ばかりを集めてしまう傾向です。「やっぱりこの仕事はダメだ」というネガティブな考えを持つと、その考えを肯定する情報ばかりに目が向き、反対の意見や良い点が見えなくなってしまいます。 |
| 同調バイアス | 周りの意見や世間の評価に強く流されやすく、「みんながそう言っているから、この仕事は価値がないんだ」と安易に決めつけてしまうことです。たとえ自分の中に違う感情があったとしても、集団の意見に合わせようとしてしまいます。 |
| 利用可能性ヒューリスティック | 思い出しやすい情報や、印象に残っている情報だけで判断を下してしまう傾向です。テレビやネットで目にしたネガティブな情報だけを鵜呑みにして、特定の職業全体を悪いものだと決めつけてしまうなどがこれにあたります。 |
これらの認知バイアスが、本来は価値ある仕事に対しても、ネガティブな「レッテル」を貼ってしまう原因になっていると言えます。
■自分の解釈こそが、仕事の価値と自己肯定感を決める
「自分は大学を出ていない、ろくでもない人間だ」と考えている人がいるとしましょう。この場合、「大学を卒業していない」というのは客観的な事実ですが、「ろくでもない」というのはその人の解釈です。つまり、事実が人の価値を決めるのではなく、自分の解釈が自分の価値を決めるのです。
実際に、大学を出ていなくても、自身の価値を高く評価し、社会で活躍している人はたくさんいます。例えば、独学でプログラミングスキルを身につけ、IT企業で活躍する人や、専門学校で技術を磨き、世界で認められる職人になった人もいるでしょう。
仕事についても同じです。社会的な評価や偏見によって、特定の仕事を「底辺」と呼ぶ人がいるかもしれません。しかし、どんな仕事にも必ず価値があり、社会に貢献する役割があります。先述したガソリンスタンドの仕事も、清掃員、介護士、建設作業員、トラックドライバーなど、社会の基盤を支えるあらゆる仕事がそうです。これらの仕事は、たとえ地味に見えても、私たちの生活や経済活動にとって不可欠な「エッセンシャルワーク」です。
仕事の価値を他人の評価に依存する必要はありません。自分の仕事の価値は自分で決める、という強い意志を持つことが必要なのです。
■満足できない人は、どこにいても満足できない
外部の声に振り回されているうちは、どんな仕事に就いても、その仕事を「底辺」だと解釈してしまうのではないでしょうか。かつて、ある心理カウンセラーが、この「解釈」について次のように話してくれました。
> 中卒の人は高卒という学歴を羨みます。
> ですが、高卒の人は大卒という学歴を羨みます。
> その大卒の人は東大卒を羨みます。
> 東大卒の人は東大医学部卒を羨みます。
> 東大医学部卒の人は同学部の首席を羨みます。
これは、どれほど高い地点に到達しても、「満足できない人は、結局のところ、何があっても満足できない」ということを示唆しています。周囲の喧騒や社会の無責任な評価に惑わされず、「自分はこれでいい」「今の仕事に価値がある」と自分で決めることが肝心なのです。
もちろん、周囲の声に耳を傾け、客観的な視点を取り入れることは大切です。しかし、最終的に自分自身をどのように評価し、どのような人生を歩むかは、自分自身の判断に委ねられています。他人の言葉に惑わされず、自分自身の価値観を信じ、自分らしい人生を歩むことが、真の自己肯定感につながるのです。
■まとめ:負の連鎖を断ち切り、誇りある職場と持続可能な社会へ
部下が仕事に誇りを持てずに辞めていく背景には、上司自身の仕事への認識が深く関わっていることがあります。上司が自身の仕事に心から誇りを持てない限り、部下に「この仕事は素晴らしい」と力強く伝えることはできません。そして、その偏見が、人手不足という社会課題をさらに悪化させる要因となっていることを私たちは認識すべきです。
認知バイアスという「解釈の罠」から抜け出し、自身の仕事の真の価値を再発見すること。そして、その誇りを部下と共有し、共に成長できる環境を築くこと。これが、優秀な人材の定着、ひいては組織全体の持続的な発展を可能にする鍵となります。
すべての仕事には価値があり、社会を支える不可欠な役割を担っています。私たちは、個人の意識と組織の努力を通じて、あらゆる仕事が尊重され、誰もが自身の仕事に誇りを持てる社会を築いていくべきです。
あなたの職場では、上司も部下も、自身の仕事に心から誇りを持っていますか?そして、その誇りを未来へとつなぐために、今、何ができるでしょうか?
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役