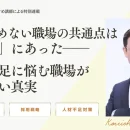社員が辞めたくなる本当の理由──“心理的リアクタンス”が離職率を高めるメカニズム【三上康一講師コラム】
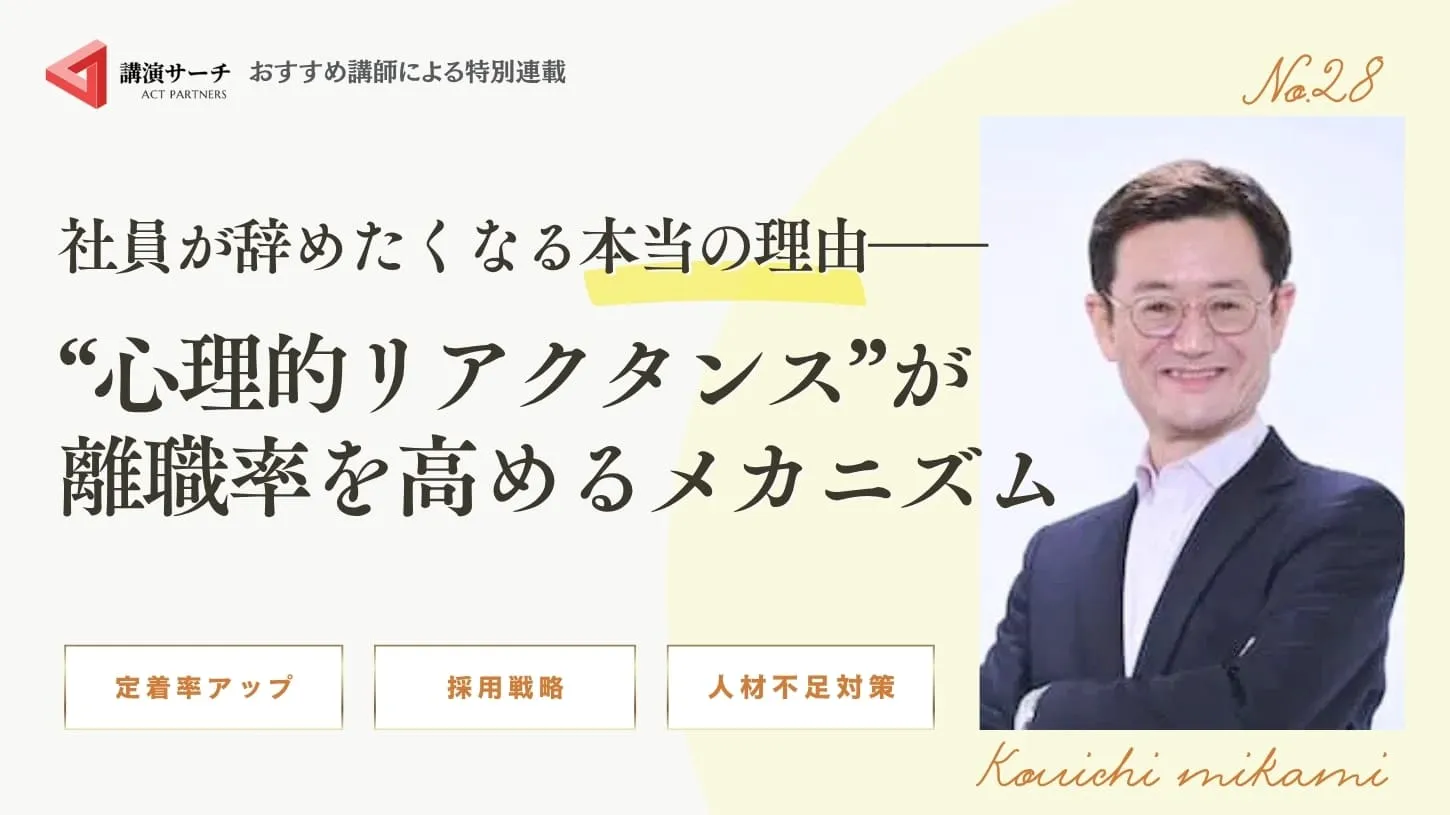

社員が辞めたくなる本当の理由──“心理的リアクタンス”が離職率を高めるメカニズム【三上康一講師コラム】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
■なぜ社員は辞めたくなるのか?
「なぜ、あの優秀な社員が突然辞めたのか分からない」
「辞める理由を聞いても、“なんとなく居づらくて…”と曖昧な答えしか返ってこない」
多くの経営者やマネージャーが一度は経験する“離職の謎”。数字で語られる退職理由(給与・労働時間・人間関係)だけでは、組織の“空気の変化”や、個人がひそかに抱いている“心理的な違和感”を捉えることはできません。
その違和感の正体の一つが、「心理的リアクタンス」です。
心理的リアクタンスとは、人が自分の意思や自由を制限されたときに感じる反発感情のことで、強制や管理が強くなるほど、「やりたくない」「離れたい」と感じる力が強くなります。これは一見小さなきっかけでも、時間をかけてじわじわと蓄積され、やがて「ここにはもういたくない」という結論を導いてしまう厄介な心理メカニズムです。
本記事では、「社員が辞めたくなる理由」を、数字や制度ではなく“心の働き”から読み解く視点を提供します。そして、心理的リアクタンスがどのように日常のマネジメントの中で生まれ、どのように“静かな退職”を引き起こしてしまうのかを解説したうえで、解決策としての「承認マネジメント」について、研究者・太田肇教授の知見を交えながら紹介します。
■心理的リアクタンスとは何か?
心理的リアクタンスは誰にでも起こる自然な反応であり、例えば以下のようなケースが典型例です。
Aくんは放課後、友達と外で遊ぶのが大好きな小学生です。ある日、家に帰るとお母さんからこう言われました。
「早く宿題やりなさい!遊ぶのはそれから!」
Aくんは「わかってるよ!」と返事をするものの、すぐには勉強に取りかかろうとしません。 むしろテレビをつけて、鉛筆も持たずにゴロゴロしています。お母さんが怒って「まだやってないの?!」と叱ると、Aくんはムスッとした顔で「もうやらない!」とふてくされてしまいました。
このときAくんは、「自分がいつ宿題をやるか」を自分で決める自由を奪われたと感じています。 お母さんから強制されたことで、「自由に選べない」「やらされている」と感じ、反発心が生まれ、「やりたくない」という気持ちが強化されるのです。
では、職場ではどのようなケースが考えられるのでしょうか。
■職場でリアクタンスが起きる瞬間とは?
リアクタンスは、例えば以下のような場面で起こりやすいです。
・「この日、絶対に出勤して」と一方的にシフトを押し付けられる
・会議での発言が毎回否定され、「黙って従え」と言われる
・「やる気が足りない」と叱責されるが、自由に提案する機会はない
これらはすべて、個人の裁量権が奪われる体験です。その結果として、「この職場では自分らしく働けない」と感じ、離職という選択を取りやすくなります。

■リアクタンスが離職を招くメカニズム
リアクタンスは、時間とともに蓄積されます。一度きりの制限ではなく、「いつも縛られている」と感じる状態が続くことで、人は次第にストレスをためていきます。そのストレスがある量を超えたとき、「辞める」という行動がもっとも明快で、確実な“自由の回復”手段として浮かび上がります。
実際、離職理由として「裁量がない」「決定権がない」「自由に発言できない」などの声がよく聞かれます。これこそ、リアクタンスの心理が最終的に引き起こす“出口”の一つです。
■離職を防ぐカギは「承認」にある
リアクタンスを抑えるために効果的なのが、強制ではなく“承認”を軸にしたマネジメントです。
同志社大学の太田肇教授は、「承認とは、単に褒めることではなく、相手の存在や能力、貢献、成長の事実を本人に伝え、自覚させることだ」と定義しています。これは、相手の価値や努力を、誠実に伝える行為です。そして、この「承認」という行為の中に、実は「選択肢を与え、その自律性を尊重する」という要素も深く含まれているのです
例えば「この2つの提案、どちらを進めたい?」「この仕事のやり方はあなたに任せるね」といった声かけは、一見ただの“配慮”のようですが、実は深い意味があります。
それは、
・あなたには選ぶ力がある
・あなたの判断を信頼している
・あなたに任せたいと思っている
という、非言語的な承認のメッセージに他なりません。
つまり、「選ばせること」は、相手の自律性や能力を信頼し、尊重していることの表れであり、それ自体が承認なのです。
このように、選択肢を与えることは、心理的リアクタンスを防ぐだけでなく、相手に対して存在意義や影響力を実感させる“ダブルの効果”を発揮します。結果として、内発的なモチベーションが高まり、主体性を持った働き方が促されるのです。
また、同氏の研究では、承認が以下の4つの側面に良い影響を与えるとされています。
1.自己効力感の向上
「自分にはできる」という自信、すなわち自己効力感が高まります。これにより、困難な課題に対しても積極的に挑戦し、困難を乗り越えられるという感覚を持つようになります。
2.内発的モチベーションの向上
「会社から評価されるから」「報酬がもらえるから」といった外的な理由だけでなく、「仕事そのものが面白い」「自分の成長が楽しい」といった、内側から湧き出る意欲(内発的モチベーション)が高まります。これにより、仕事への取り組み方がより主体的で積極的になります。
3.影響力の知覚(貢献感)の向上
自分が周囲や組織に貢献できているという感覚が芽生えます。自分の存在や仕事が意味を持つと感じることで、責任感が強まり、リーダーシップを発揮しようとする意識も高まります。
4.業績の向上
上記の自己効力感、内発的モチベーション、貢献感が高まる結果として、目標達成に向けてより積極的に行動するようになり、高い成果を生み出すことにつながります。

■承認を効果的に行う3つのポイント
承認を効果的に行うためには、いくつかの重要なポイントがあります。
1.具体的な行動や成果を褒める
「よく頑張ったね」という漠然とした褒め言葉よりも、「〇〇の資料、とても分かりやすくまとまっていたよ」「先日のクライアントへの提案、具体例が豊富で素晴らしかった」のように、具体的な行動や達成した成果に焦点を当てて伝えることが重要です。これにより、相手は何を評価されたのかを明確に理解し、再現性のある行動につながります。
2.客観的な情報に基づいて伝える
「すごい!」といった主観的な感情だけでなく、「今月の売上目標、〇〇さんが中心になって〇%達成できたね」「チーム全体の残業時間が先月比で〇時間減ったのは、〇〇さんの業務改善提案のおかげだ」のように、客観的な事実やデータに基づいて伝えることで、承認に信頼性が生まれ、相手は「本当に認められている」と感じやすくなります。
3.タイミングを逃さない
承認は、行動や成果が出てから時間が経つと効果が薄れてしまいます。プロジェクトが成功した直後、顧客から感謝の声が届いたとき、あるいは困難な業務を乗り越えた直後など、できるだけ素早く、適切なタイミングで伝えることで、その承認は最も効果的に従業員のモチベーションを高めます。
■まとめ──「人は管理ではなく、尊重によって動く」
社員が辞める理由のすべてが待遇や制度にあるわけではありません。
その陰には、「この組織では自分の声が届かない」「自由に動けない」「自分がいてもいなくても同じだ」という、心理的な孤立感や抑圧感が潜んでいることがあります。
「心理的リアクタンス」は、人間が本能的に持つ「自由でありたい」という欲求の裏返しです。これを無視したマネジメントは、知らず知らずのうちに従業員の心を離れさせ、離職率を高めてしまいます。
ではどうすればいいのか? 答えは、「自由を与えること」ではなく、「存在を認めること」です。太田肇教授が提唱するような“承認”のマネジメントは、社員の存在や努力を事実に基づいて認めることで、彼らの内発的モチベーションと貢献意識を高め、リアクタンスの発生を抑える有効な方法です。
これからのマネジメントに求められるのは、管理による制御ではなく、承認による共感と信頼の構築です。人が「辞めたい」と思う前に、「ここにいてもいい」と思える職場を、日々のコミュニケーションで築いていきましょう。

執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役