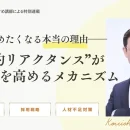「隣の芝生は青く見える」心理から考える人手不足時代の従業員定着術【三上康一講師コラム】
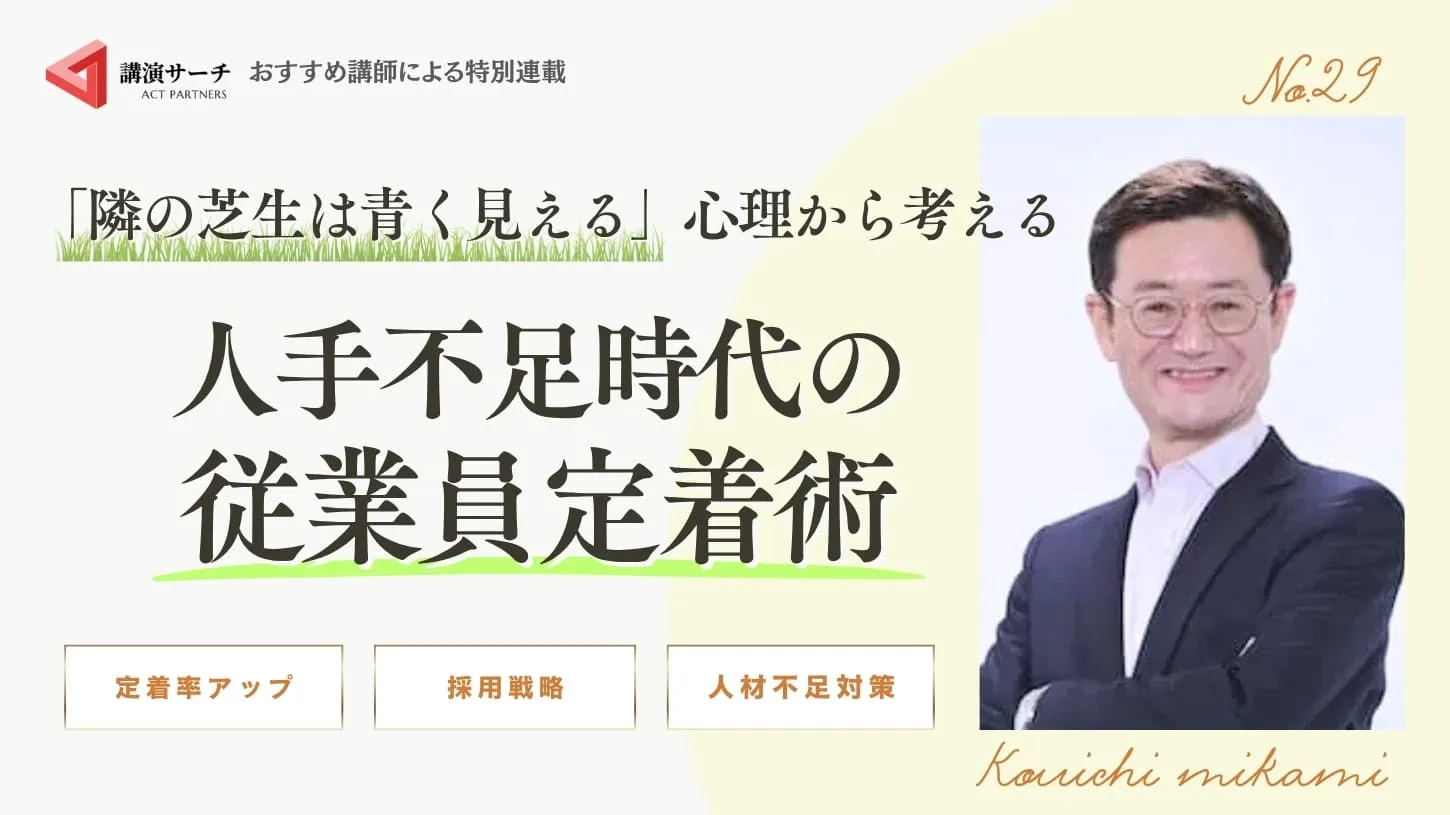

「隣の芝生は青く見える」心理から考える人手不足時代の従業員定着術【三上康一講師コラム】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
■新幹線で気づいた「隣の芝生」現象
先日、人手不足対策セミナーに登壇するため、東海道新幹線の「S WorkPシート」を利用して現地へ向かいました。S WorkPシートは3列シートの真ん中のシートにパーテーションが設置され、1人で1.5席分を使える設計で、追加料金が必要となっています。このシートに座って移動中、ふと周囲を見ると通路を挟んだ隣の2列シートの通路側席が空席ばかりなのに気づきました。よって、隣の2列シートの窓側に座っている方は、追加料金なしで2席をまるごと使え、どちらかと言えば快適そうに見えます。
もちろん、2列シートに誰かが乗り込んでくれば1席しか使えないリスクもあり、S WorkPシートにはそのリスクがありません。にもかかわらず、空いている2列シートが快適そうに見えるのは、まさに「隣の芝生は青く見える」現象です。
この心理は、従業員が現在の職場よりも他社の条件を魅力的に感じ、退職につながってしまう心理によく似ています。今回はこの心理を踏まえながら、人手不足の時代に求められる従業員の定着策について考えてみたいと思います。
■ハーズバーグの動機づけ=衛生理論とは
多くの企業は人出不足対策として、給与や労働環境の改善などに力を入れていますが、それだけでは離職を完全に防げません。従業員の中には、現在の職場の環境や条件に満足していても、「隣の芝生が青く見える」心理から、他社のより良い条件に魅力を感じ、転職を決意してしまうケースが後を絶ちません。
こうした現状は、従業員定着において従来の衛生要因だけでなく、従業員の心理や認知の側面にも目を向けた新たな視点の必要性を示しています。
1959年にフレデリック・ハーズバーグは、職場における従業員の満足と不満足は同じ軸上で反転するものではなく、別々の要因によって生じると提唱しました。
| 衛生要因 | 職場環境、給与、労働条件、人間関係など。これらは不満を「取り除く」役割を果たすが、充足しても満足感を生み出すとは限らない。 |
| 動機づけ要因 | 仕事の内容そのものから得られる達成感、承認、責任感、自己成長、そして昇進の機会。これらが充実すると、内発的な満足感ややる気を引き出し、従業員のモチベーション向上につながる。 |
動機づけ要因は、マズローの欲求段階説の「自己実現欲求」や、デシとライアンの「自己決定理論」にも通じる概念です。
| 自己実現欲求 | 人は成長し、能力を発揮し、意味ある仕事を通じて自己実現を追求したいという欲求を持つ。 |
| 自己決定理論 | 人は自律性・有能感・関係性が満たされるときに、最も高い内発的動機づけを経験する。 |
動機づけ要因は、まさにこれらの心理的ニーズを満たす要素であり、単に外的報酬を超えた「働く意味」や「価値の実感」を従業員に提供します。

■衛生要因とは「不満をなくす土台」にすぎない
ハーズバーグの動機づけ=衛生理論における衛生要因が不十分だと不満が高まり、いずれ退職してしまいます。しかし、これらは「不満を取り除く」ための土台であり、モチベーションを際限なく高めるものではない、という点を理解することが重要です。
例えば、給与は典型的な衛生要因です。従業員は自身の貢献に見合った適正な給与を求めますが、大幅な昇給が必ずしもモチベーションの持続的な向上につながるとは限りません。なぜなら、従業員は自身のスキルや業界動向から「給与の相場感」を持っており、それを大きく超えるとむしろ「なぜ?」と不信感を抱くことがあるためです。給与が低い場合、適正水準に達すれば不満は解消されますが、それ以上はモチベーションが比例して上がり続けるわけではありません。
同様に、人間関係も重要な衛生要因です。これが悪ければストレスや不満が高まり、改善されれば一時的に意欲は回復します。しかし、ある程度良好になった後は「職場の人間関係はこんなもの」と感じ、さらなる改善を期待しなくなります。これは、衛生要因には一定以上で効果が頭打ちになる「天井感」があることを示しています。
■衛生要因だけに頼った施策の限界と「隣の芝生」現象
衛生要因が整っている職場の従業員は、現状に大きな不満はないため、表面上は定着しているように見えます。しかし、彼らのモチベーションは「不満がないから働いている」という状態に過ぎません。この状況では、他社がより高い給与や良い環境を提示した途端、「隣の芝生」が青く見え、簡単に転職してしまうリスクが残ります。
この現象は、先ほどの新幹線の座席エピソードと似ています。追加料金を払って快適なS WorkPシートに座っていても、隣の無料で使える2列シートの方が、より広い空間を提供し、心理的に「得」に感じてしまうことがあります。この「隣の芝生は青く見える」心理が働くことで、本来の価値が見えにくくなり、他社の魅力的な条件が目に入ると、現在の職場に対する満足感が薄れてしまうのです。
■今すぐ取り組める「動機づけ要因」を充足させる施策
ハーズバーグ理論でいう「動機づけ要因」は、仕事そのものに内在するやりがいや達成感、自身の成長といった、内発的モチベーションに深く関わる要素です。そのため従業員は「この会社で働き続けたい」と心から思うため、他社の条件が多少良くても簡単に転職しません。彼らは、単なる給与や福利厚生といった外的な報酬だけでなく、仕事そのものから得られる充実感や自己実現を重視しているため、企業への帰属意識が非常に高くなります。
具体的な動機づけ施策としては、以下のような取り組みが考えられます。
・承認 (導入ハードル:低~中)
上司や同僚からのフィードバックや感謝の言葉によって、自分の仕事が正しく評価されていると実感できることは、大きなモチベーションにつながります。特に、成果や努力に対してタイムリーかつ具体的な言葉で認められることは、自己肯定感を高め、「もっと頑張ろう」という前向きな意欲を引き出します。
・責任 (導入ハードル:中)
単なる作業の担当ではなく、意思決定や成果に責任を持つ役割を任されることは、信頼されているという実感を与えます。責任のある仕事を通じて、自分の裁量や判断が業務に反映される経験が、仕事への主体性や成長意欲を高めます。また、業務設計において「任せる」姿勢を持つことが、責任感とやりがいの醸成に直結します。
・達成感 (導入ハードル:低~中)
設定した目標に向かって努力し、それを達成したときに得られる充実感や喜びは、仕事へのモチベーションを大きく引き上げます。特に、難易度の高い課題を乗り越えた経験は、自己効力感を育み、次のチャレンジへの原動力になります。目標設定は、「少し頑張れば届く」レベルで段階的に設計することが効果的です。
・仕事そのもの (導入ハードル:中~高)
自身の興味や関心、あるいは専門性を活かせる仕事に取り組めることは、働くうえでの喜びや意味を感じる重要な要因です。自分が価値を発揮できているという実感は、長期的なエンゲージメントにもつながります。職務設計の柔軟性や、個々の強み・希望を踏まえた業務アサインが求められます。
・昇進 (導入ハードル:中~高)
職位の上昇だけでなく、キャリアステップが明確に提示され、自身の成長が実感できる環境は、将来への展望を持たせ、継続的なモチベーションを支えます。評価基準やキャリアパスの透明性を高めることで、従業員は目指すべき方向を持ちやすくなり、自律的な成長に向かいやすくなります。
■「満足して働ける職場」が、人手不足を突破する力になる
「隣の芝生は青く見える」という心理は、多くの人にとって共感できる感覚です。しかし、本当に大切なのは、目の前にある芝生をどう育てていくかです。従業員が「ここで働いてよかった」と心から思える環境とは、給与などの衛生要因が整っているだけでなく、自身の仕事に意味ややりがいを感じられる場です。
企業が動機づけ要因を意識し、仕事のやりがいや成長の機会、貢献実感を与え続けることで、従業員は「隣の芝生」を気にすることなく、自分の足元の芝生を大切に育てようと思えるようになります。
つまり、「隣の芝生が青く見える」状態から、「自分の芝生をもっと青くしていきたい」と感じられる職場こそが、人手不足の時代を生き抜く企業の競争力なのです。

執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役