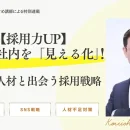感謝の力で人手不足を乗り切る! 従業員定着率向上と組織力アップの秘訣【三上康一講師コラム】


感謝の力で人手不足を乗り切る! 従業員定着率向上と組織力アップの秘訣【三上康一講師コラム】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
■なぜ今、人手不足対策に「感謝の力」が必要なのか
2025年1~7月に判明した「従業員退職型」の倒産件数は前年同期比で約6割増、過去最多を大幅に更新する勢いで、年間100件超えも確実視されています。
参考:Yahoo!ニュース「従業員「退職」で倒産、 前年比1.6倍に急増 過去最多を大幅更新へ 初めて年間100件台に到達の可能性(帝国データバンク)」
「従業員退職型」の倒産とは、会社の従業員や経営幹部などの退職が原因となって、事業の継続が困難になり倒産に至るケースを指し、具体的には、以下のような状況が該当します。
・主要な技術者や資格保持者、営業幹部が退職し、業務遂行が困難になる
・人材流出により必要な労働力が不足し、受注や生産が滞る
・退職による業務負荷増大やコスト増加で経営悪化が加速する
・従業員退職が連鎖的に発生し、組織としての機能が維持できなくなる
この厳しい状況を回避するためには、「既存人材の定着」に取り組むべきであることは言うまでもありません。そこで多くの企業が「賃上げ」を最優先に考えますし、上記の記事でも賃上げに触れています。ですが、給与にこだわりすぎることは必ずしも安全策とはいえません。
なぜなら、社員が感じる「満足」や「安心」は、単にお金の額面だけで決まるものではないからです。心理学の研究では、感謝の気持ちが高い人ほど困難に耐える力が強く、離職率を下げる効果があることが明らかにされています。さらに著名な実話からも、感謝の言葉がもたらす驚異的な効果が確認されています。これらのメカニズムを以下で詳しくご紹介します。

■賃上げしても辞めてしまう社員の心理と、感謝が持つ給与を超える力
社員が賃金だけでなく職場に求めるものは「働きがい」や「自分の存在価値の実感」、そして「職場で認められている」という感情です。たとえ給与が高くても、感謝されず、評価や信頼を感じられなければ、「自分は大切にされていない」という心理が生まれ、職場への愛着や忍耐力が育ちにくくなります。結果として、より良い条件の職場を求めて転職してしまうのです。
一方で、「感謝の言葉」や「感謝の気持ち」が持つ力は、こうした心理の穴を埋める役割を果たします。感謝は社員の心に「認められた」「必要とされている」という実感を与え、職場への帰属意識ややる気を強めます。これは心理学的にも、給与を超える強い動機づけ要因として機能することが証明されています。このように、給与は重要な要素の一つですが、それだけに頼ることは経営リスクを伴いかねません。
以下では、心理学の研究データから『感謝の力』が社員の忍耐力やモチベーションを高め、離職を防ぐメカニズムをご紹介します。
■感謝の気持ちは社員の「忍耐力」を高める
ノースイースタン大学心理学部のリア・ディケンズ博士らが行った研究では、感謝の気持ちと忍耐力の関係が明らかにされました。105人の大学生を対象に、感謝の気持ちが強いグループと弱いグループに分けた上で、1年後にもらえる100ドルを現在の価値に換算してどれくらいの価値と感じるかを評価してもらいました。
今すぐもらえる50ドルを年利5%で銀行に預けた場合、1年後には約52.5ドルになります。これは、将来の金額を現在の価値に換算する考え方の一例です。この調査では、年利を示さずに、1年後に得られる100ドルを参加者が主観的に現在の価値としてどの程度評価するかを測定しました。
その結果、感謝の気持ちが強い人は、1年後にもらえる100ドルを現在の約33ドル分と評価し、感謝の気持ちが弱い人は同じ100ドルを約21ドル分と評価しました。つまり、感謝の気持ちが強い人は将来の報酬を高く評価し、忍耐強く待つことができる傾向があるのです。
この研究は、日常的に感謝の気持ちを持つ人ほど忍耐力が高く、困難な状況でも感情をコントロールしやすいことを示しています。よって、そのような人材は簡単には退職しないため、定着率が向上するでしょう。
では、どうすれば社員が感謝の気持ちを持てるようになるのでしょうか。
■リーダーの感謝が社員を育てる――感謝の連鎖と忍耐力の向上
組織の文化や風土は、トップやリーダーの言動が大きく影響します。リーダーが率先して社員一人ひとりに感謝の気持ちを示すことで、社員は「感謝されることの価値」と「感謝を伝える習慣」を学びます。
この感謝の連鎖が職場全体に広がると、社員はただ給料を得るだけでなく、職場の人間関係や業務の中に「意味」や「やりがい」を見出すようになります。その結果、困難な状況でも「ここで頑張ろう」「この仲間のために続けたい」と感じる忍耐力が育まれ、結果として社員の定着率が向上します。
また、感謝の文化は社員同士の信頼関係を強化し、チームワークの向上やコミュニケーションの円滑化にも寄与します。こうした環境は、生産性の向上や離職率の低下という経営成果につながるのです。
以下では、感謝の言葉がもたらす力を示す実話をご紹介します。

■「ありがとう」の力は奇跡を生む
・感謝の言葉がもたらす奇跡の実話
著作家であり心学研究家の小林正観氏は、その温かい人柄と深い洞察で多くの人々に感謝の心の大切さを伝えてきました。彼が講演で紹介したある実話は、感謝の力が持つ驚異的な効果を象徴しています。
小林氏が登壇したある講演会で、彼の許可を得た末期がんと診断された患者が壇上に上がりました。そして、「私はもっと生きたい。どうか私に『ありがとう』の言葉をかけてほしい」と聴衆に呼びかけました。集まった約200人の聴衆は、一斉に1分間に100回、合計2万回もの「ありがとう」を患者に向けて声をかけました。その瞬間、会場は暖かく静謐な空気に包まれ、患者の目には涙があふれました。
驚くべきことに、その患者は数日後の精密検査で、がん細胞が完全に消失していたことが確認されたのです。医師も説明できない奇跡の回復は、多くの人々に感謝の言葉がもたらす力の大きさを示す出来事となりました。
・言葉が持つエネルギーを可視化した実験
また、小林氏は感謝の言葉の影響を科学的に示すために、ユニークな実験を行いました。彼は2つのペットボトルに水を入れ、一方には「ありがとう」、もう一方には「ばかやろう」という言葉を書きました。そして、それぞれのボトルの水を凍らせ、その結晶を顕微鏡で観察しました。
その結果、「ありがとう」と書かれた水はまるで宝石のような美しく整った結晶を形成したのに対し、「ばかやろう」と書かれた水は乱れた形で変形し、美しい結晶は見られませんでした。この現象は、水が言葉や感情のエネルギーを受け取り、その形状に影響を受けることを示唆しています。
■感謝の言葉が組織と社員を支える力に
これらの話から分かるように、「ありがとう」という感謝の言葉は単なる挨拶以上の意味を持ちます。組織内で感謝が行き交う環境は、社員同士の信頼や結束を強め、心の安定ややる気の向上につながります。逆に、否定的な言葉や感情は職場の雰囲気を悪化させ、生産性や定着率の低下を招きかねません。
経営者やリーダーは、日頃から「ありがとう」の言葉を積極的に使い、社員一人ひとりの貢献を認めることで、組織の雰囲気を温かくし、社員の心を支える強力な武器を手に入れることができるのです。
■感謝の力を活かしつつ、総合的な人手不足対策を
これらを踏まえ、企業が今すぐできる対策としては以下が挙げられます。
・毎日の朝礼や終礼で、個々の社員の努力に感謝の言葉を必ず伝える
・社内チャットやSNSで「ありがとう」や「助かったよ」の声を共有し合う
・1on1面談で、業務だけでなく日頃のねぎらいの言葉をかける
・感謝の気持ちを形にして、感謝カードやメッセージを書き合う習慣をつくる
感謝だけではなく、適正な給与・待遇改善や働き方改革も不可欠です。 しかし、感謝の気持ちが組織文化として根付けば、社員の定着率は格段に向上し、新規採用の負担も軽減されます。
経営者・管理者は「感謝の力」を最強の武器として活用し、社員が安心して働き続けられる環境をつくりましょう。

■まとめ
人手不足が企業存続の危機となる今、「従業員退職型倒産」という現実は、多くの経営者や管理職にとって無視できない脅威です。しかし、賃上げ競争に頼るだけでは、経営リスクを伴いかねません。だからこそ、私たちは給与だけでは満たされない、社員の「働きがい」と「心の安定」に目を向ける必要があります。
感謝の力は、そのための最も強力な武器です。日常的に感謝を伝える文化を築くことで、社員の心は満たされ、困難な状況でも粘り強く業務に取り組む忍耐力が育まれます。また、温かい言葉は組織全体の雰囲気を変え、社員一人ひとりのモチベーションと定着率を格段に向上させます。
私たちは、感謝の力を最強の武器として活用し、社員が安心して長く働き続けられる、強い組織を築くことが求められています。今こそ、リーダーが率先して「ありがとう」を伝え、社員と共に成長する未来を創造しましょう。
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役