なぜ「正論」で人は辞めるのか? 現場リーダーのための退職防止策【三上康一講師コラム】
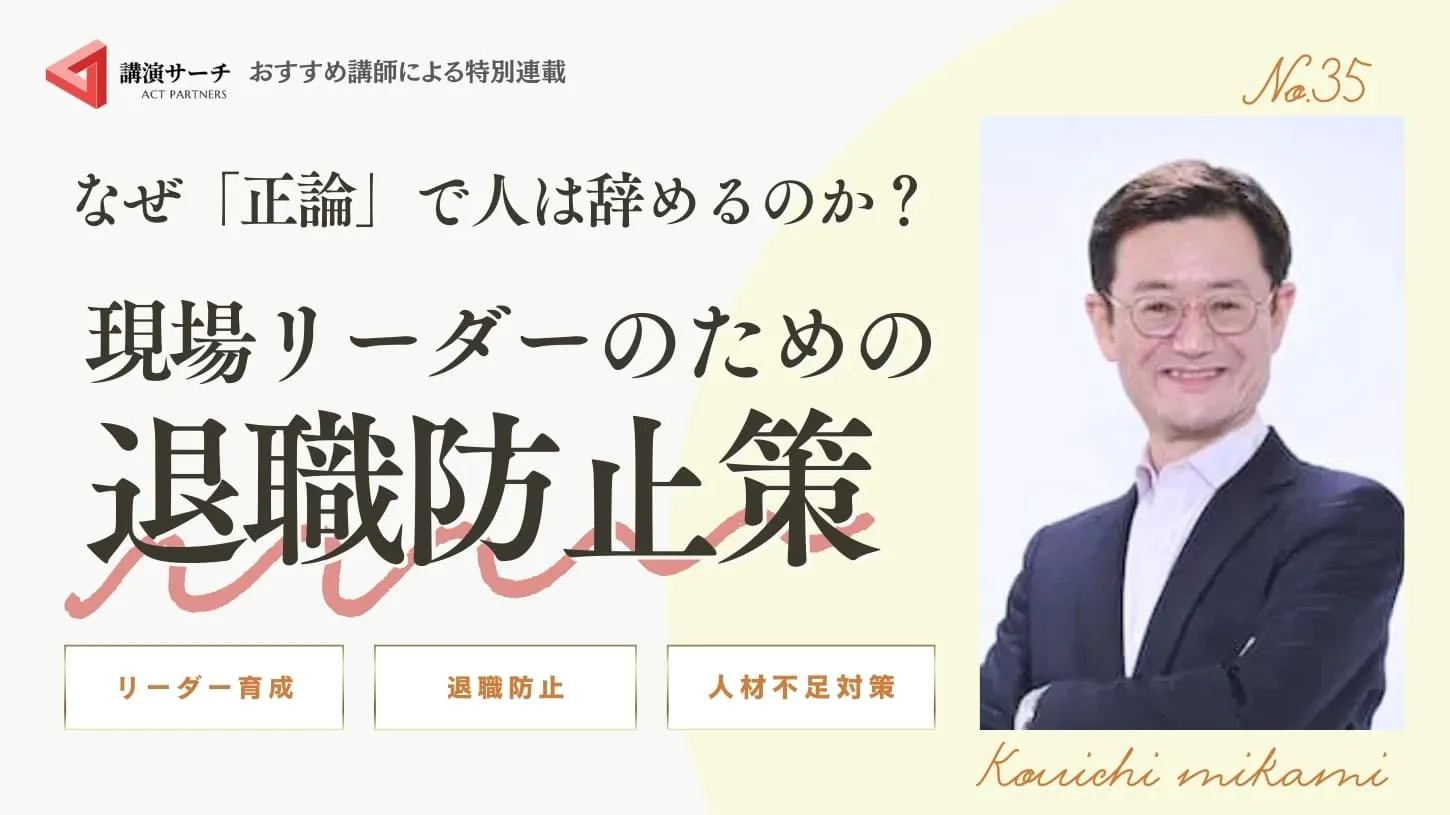

なぜ「正論」で人は辞めるのか? 現場リーダーのための退職防止策【三上康一講師コラム】
目次
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役
長年通い続けた歯科医院が、閉院することになりました。顔なじみのスタッフの方々とのお別れは寂しかったですが、これも新たな出会いのチャンスだと捉え、新しいかかりつけ医を探すことにしました。
いくつかの歯科医院を訪ねては、その治療方針や雰囲気を確かめる日々。どの先生も丁寧に対応してくださり、私の歯の現状と治療法について説明してくれました。しかし、どことなく心が決まらないままでした。
そんな中、ある医院で出会った先生の言葉が、私の心に深く響きました。
診察を終え、私の歯の治療法について説明してくれた先生は、「これは正論にすぎません」と前置きをした上で、こう続けたのです。
「我々が提示する治療法は、患者さんが心から納得していなければ意味がありません。もし納得度が低い場合は、別の治療法を提示する必要があります。患者さんにとって、心から納得できる治療法こそ、最善の治療法だと考えています。」
この言葉を聞いた瞬間、私は迷いが吹っ切れ、この先生にお願いしようと即座に決めました。
なぜなら、この先生の言葉は、私自身が中小企業診断士として大切にしている信念と、全く同じだったからです。経営者に「正論」だけを伝えても、それが彼らの心に響き、行動を変えることは難しい。本当に必要なのは、経営者自身が「自分ごと」として納得できる支援であり、時には「正論」から外れてでも、対話を通じて共に最適な道を探すことが必要だと常々感じていました。
医療の現場でも、経営の現場でも、そしてあらゆる組織の現場でも、本当に必要なのは「正しさ」だけではありません。「納得感」と「対話」があってこそ、人は前に進み、最善の結果が生まれるのだと改めて確信しました。

■なぜ、あなたの「正論」は部下に響かないのか?
人手不足が深刻化する現代において、多くの職場で「なぜうちの会社はこんなに人が辞めていくんだ…」という悩みが聞かれます。
「もっと効率的に仕事を進めてほしい」「モチベーションを上げてほしい」「会社の方針を理解してほしい」…こうした思いから、部下や後輩に「正論」を伝えても、残念ながら響かないことが多いのではないでしょうか。
なぜなら、人は「正しい」と感じても、「納得」しなければ動かないからです。
歯科医師の言葉にあったように、たとえ正解とされる治療法でも、患者自身が納得できなければ意味がありません。これは、職場においても同じです。会社が掲げる目標や、上司が示す指示がどんなに「正しい」ものであっても、そこで働くスタッフが「自分ごと」として納得できなければ、その思いは届かないのです。それは結果としてスタッフの退職へとつながっていきます。この正論について以下の事例があります。
あるガソリンスタンド運営会社の本社と現場の店長とのやり取りを見てみましょう。
本社:「なぜ販売予算が未達で、人件費がオーバーしてしまったのですか?」
店長:「実は、私が現場に出られない日がありまして、アルバイトスタッフを多めにシフトに入れたんです。」
本社:「予算は予算ですよ。これを守らなければ、困ります。」
店長:「確かに予算通りに進めたかったのですが、その日はどうしても多くのスタッフが必要だったんです。」
本社:「だからこそ、予算が重要なんです。販売予算が未達で、しかも人件費がオーバーしているなら、利益が出るはずがないでしょう!」
本社の言っていることは、理論的には正しいのですが、目の前にいる店長の個別の事情にはほとんど触れていません。予算を守ることが重要だという点は理解できますが、現実的な事情や店長の努力を認めることなく「正論」を押し付ける形になっています。これでは、店長のモチベーションが下がるのは避けられません。
とはいうものの、正論を述べたがるリーダーが多いのはなぜなのでしょうか。
■善意が裏目に? リーダーが「正論」を言ってしまう心理
リーダーが正論を述べたくなる背景には、いくつかの心理的な要因が絡んでいます。
・自分の経験や知識に自信がある
リーダーは、これまでの経験や専門知識に自信を持っています。そのため、「自分が知っている方法や考え方が最も効果的だ」と思いがちです。自分が正しいと思うことを部下にも理解させようとするのは、リーダーとして当然の行動です。
・問題解決のためにすぐにアクションを起こしたい
問題に直面したとき、リーダーは迅速に解決策を提示したくなります。「これが正解だ」と確信を持ち、部下にもその通りに動いてもらおうとするのは、問題を早急に解決したいという焦りから来る心理です。
・責任感からくる指導の欲求
リーダーは部下を正しい方向に導かなければならないという強い責任感を抱いています。そのため、「正論」を述べることで、部下が間違った方向に進まないように注意を促し、正しい道へ導こうとするのです。

■「正論」が部下の心を閉ざす3つの理由
正論を強調し過ぎることがなぜ逆効果になるのでしょうか?その理由を理解することが重要です。
・相手の心に響かない「一方通行のコミュニケーション」
正論を強調しすぎると、部下は「自分の意見はどうでもいいんだ」と感じ、反発したり、次第に聞く耳を持たなくなったりすることがあります。特に、自分の意見や立場が尊重されていないと感じたことが、退職を決意する理由となることもあります。
・自律性を奪う「思考停止の強要」
正論ばかりが強調される職場では、部下が自分の考えを主張できず、自己表現を抑えるようになります。このような環境では、部下が次第に自分の価値を見いだせなくなり、「この職場で働く意味があるのか?」と疑問を抱くようになることがあります。
・変化に対応できない「硬直した組織文化」
正論に固執するあまり、柔軟な対応ができなくなることがあります。状況に応じた対応ができず、部下の状況や心情を無視した指導が続くと、スタッフは次第にストレスを感じ、退職に至ります。
■「正論」を「納得感」に変える4つの対話術
では、リーダーとして「正論」を伝えつつ、スタッフに納得してもらうためにはどのようにアプローチすべきでしょうか?
・耳を傾ける姿勢を持つ
正論を述べる前に、まず部下の意見や考えを十分に聞く姿勢を持ちましょう。スタッフが抱えている悩みや不満に耳を傾け、それを理解することで、より納得感のあるコミュニケーションが可能になります。
・背後にある「なぜ?」を共有する
自分が伝えたい「正論」をそのまま押し付けるのではなく、その背後にある理由や意図をスタッフに説明しましょう。例えば、「なぜこれが最善だと考えたのか?」を伝えることで、スタッフは自分が納得できる理由を理解しやすくなります。
・「共感」を示す
スタッフが悩んでいるときや反発しているときには、その気持ちに共感を示しましょう。共感することができるリーダーには、スタッフは信頼を寄せますし、納得感を得やすくなります。「正論」だけではなく、その人の立場や感情にも寄り添うことが重要です。
・「一緒に考える」姿勢を持つ
スタッフに指示やアドバイスをするだけではなく、問題の解決方法を一緒に考える姿勢を見せましょう。問題を共有し、一緒に解決策を見つけることで、スタッフは自分がチームの一員であると感じ、納得感が深まります。

■まとめ
リーダーとしての責任感や自信から、私たちはつい「正論」を口にしてしまいがちです。しかし、「正しさ」だけでは人の心は動きません。
歯科医院の先生は、「正論にすぎない」と前置きし、患者の「納得」こそが重要だと語りました。同様に、ガソリンスタンドの事例では、本社が「予算」という正論を振りかざした結果、現場の店長のモチベーションを下げてしまいました。
人は「正しい」と感じても、「納得」しなければ行動しません。そして、その納得感は、一方的な「正論」ではなく、相手の状況や感情に寄り添う「対話」から生まれます。
深刻な人手不足時代を乗り越えるためには、リーダーが「正論」を押し付けるのではなく、スタッフ一人ひとりの心に耳を傾け、共に解決策を探すことが不可欠です。
今日から、まずは一人ひとりのスタッフと向き合い、対話を通じて「納得感」を育むことを始めてみませんか?それが、退職を防ぎ、チームを強くする第一歩となるはずです。
執筆講師

株式会社ロードサイド経営研究所代表取締役







