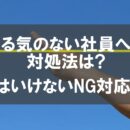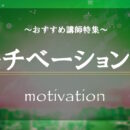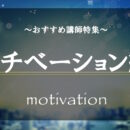モチベーショングラフとは?書き方や社会人が作成するメリットをわかりやすく紹介
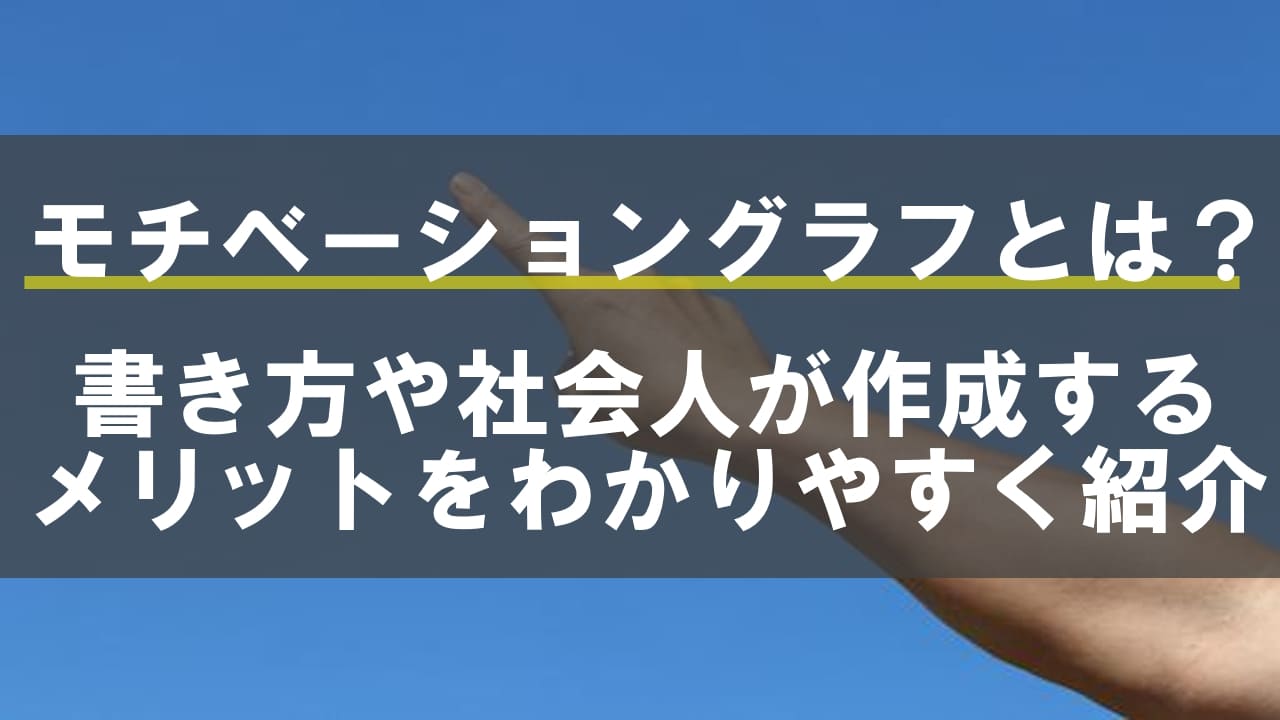
人材育成の場では従業員のモチベーション管理に悩む機会は多いものです。モチベーションを下げないようにするには、一人ひとりのモチベーションの上がり方を知ることが大切ですよね。
そこで役立つのが「モチベーショングラフ」です。
本記事では、モチベーショングラフとは何かの解説や書き方、社会人が作成するメリットをわかりやすく紹介します。
誰しもいつでも元気でやる気MAX!とはいきませんよね。士気が下がっても上手に立て直す方法を使って、モチベーションコントロールできると良いでしょう。
モチベーショングラフの概要や書き方ついて、初めて取り扱う社会人の方でもわかりやすく解説しました。社員が本来のパフォーマンスを発揮して、社会人としてさらなる活躍へ導けるようになるので、ぜひ最後までご覧ください!
モチベーションを下げてしまいかねないNGアクションを知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。
モチベーショングラフとは
目次

モチベーショングラフとはどのようなツールを指すのかについてみていきましょう。
簡単にいうとモチベーショングラフとは、過去の出来事と気持ちの浮き沈みを可視化した自分史です。
モチベーショングラフは主に、
・やる気の度合い測定
・就職活動などの自己分析
の際に役立ちます。
詳しくみていきましょう。
やる気の度合いを測定する
モチベーショングラフとは、自分のモチベーションが上下した過去の出来事を振り返り、時系列で並べた「自分史」のグラフです。
ビジネスでは「やる気」などと同様の意味で使われるモチベーションですが、モチベーショングラフを描くことでどのようなときにやる気が上下するのか把握が可能になります。
完成させたグラフをじっくりと分析し、やる気の高低ややる気が上下するタイミングの傾向や特徴を洗い出してみましょう。
判明した特性を自分のなかで適切に活用すれば、効率良く目標や自己実現を達成できるようになりますよ。
就職活動などの自己分析に効果的
モチベーショングラフは、主に就職活動などで積極的に利用され、企業と学生をマッチさせる橋渡し役を果たしています。
就職活動にともなう自己分析の際に、モチベーショングラフを作成したという人は多いのではないでしょうか?
モチベーショングラフは個人の適性にあった業界や企業をみつける際の指標となるため、就活でよく取り入れられている印象が強いかもしれません。
しかし活用の場は就活だけではなく、企業や団体などに所属してからも有効です。
モチベーションが上下した出来事に焦点を当てて自己分析をすれば、力を発揮できるように適切な人員配置ができるようになるでしょう。
就職活動などで活用すれば入社後のミスマッチの解消につなげられます。
ひいては長きにわたっての活躍が可能になるのです。
モチベーショングラフを企業で活用するメリット
 就活でよく取り入れられるモチベーショングラフですが、企業が取り入れるとどのような効果を得られるのでしょうか?
就活でよく取り入れられるモチベーショングラフですが、企業が取り入れるとどのような効果を得られるのでしょうか?
従業員のやる気を可視化できるモチベーショングラフを、企業で活用するメリットをご紹介します。
具体的には、以下の3つのメリットがあるので、ぜひ導入を検討してみてくださいね。
・社員のパフォーマンス向上や問題改善が実現する
・社員の適性判断の材料になる
・人材教育の教材として取り入れられる
それぞれ解説します。
社員のパフォーマンス向上や問題改善が実現する
モチベーショングラフによってみえた、やる気が高まるときと同様の環境を用意すれば、業務の質もアップして結果を出せるようになります。
例えば、過去にリーダー役を務めて人から頼りにされたときに嬉しくなった(モチベーションが高まった)経験があれば、似たポジションを与えると適任者となるかもしれません。
持ち前のリーダーシップを発揮できれば、同僚の力も引き出し一丸となって結果を残し、社会人として大成につながるでしょう。
反対に、やる気が下がったときの特徴をつかめば、業務の課題明確化や解決策の提案にも一役買ってくれます。
過去に知識不足で失敗を招いた経験があり、ここぞの場面で消極的になってしまう社員がいるケースはどうでしょうか?
この場合は社員に対し、研修や通信教育で知識不足を補うと同時に、失敗を恐れないよう後押しする姿勢などが対策として挙げられます。
モチベーショングラフは、社会人の間でも組織を活性化する有益な手法として確立できるのがわかりますね。
社員の適性判断の材料になる
モチベーショングラフによって、社員本来の能力や個性が表面化することで、最適な職種や働き方がわかるようになります。
十人十色の力量により近い職場環境を整えられれば、まさに適材適所の人員配置が可能となるに違いありません。
一人ひとりの力をフル活用できれば、質の高い仕事が積み上がって高い目標にも届き、やがて組織全体が強化されます。
モチベーショングラフの分析データをもとに、社員と企業両者が明るい展望となるキャリアを構築していきましょう。
人材教育の教材として取り入れられる
社会人となってからもモチベーショングラフを作成することで、自己実現を促す良き教材となります。
過去の振り返りによって、改めて自身がどのような人間なのか思い起こされ、ぶれない自分軸を深化させられるでしょう。
企業側も、活躍を期待する社員の価値観や考え方を再確認できるので、一石二鳥の人材教育として重宝するはずです。
各世代の社員を対象にして、順を追って研修などに取り入れ、教育の充実化を図ってみてはいかがでしょうか。
研修の実施には「講演サーチ」のような講師派遣会社などを上手に活用するのがおすすめです。
モチベーションをテーマに学びを深めてきた、プロ講師の講話を通して、企業や従業員にはなかった新たな視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。
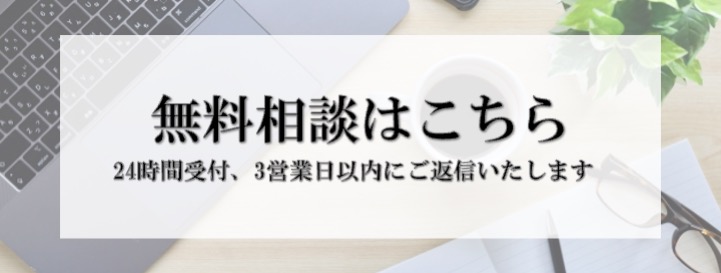
モチベーショングラフの書き方

モチベーショングラフの具体的な書き方を、順を追ってわかりやすく紹介します。
以下の手順でモチベーショングラフを作成しましょう。
①縦軸と横軸を作成する
②過去の出来事を記入する
③出来事からモチベーションを振り返る
縦軸と横軸を作成する
グラフの縦軸には、モチベーションの度合いを+ 100〜-100までの数値で示します。
横軸は時間の推移を示し、小学生時代〜現在までなどが一例です。
さらに細かく分析したい場合は、幼少期から始めるなど、記憶をたどれる範囲で広げましょう。
過去に遡って目立った出来事を記入する
自分のモチベーションに影響を及ぼした出来事を、過去から現在に至るまで洗い出して記入しましょう。
学生時代を例にあげてみます。
・体力測定の結果が良く、陸上大会代表に選ばれた→+70
・風邪をこじらせて肺炎にかかり、半月欠席して学習の進捗が遅れてしまった→−80
モチベーションがアップした出来事は+、ダウンした場合は−数値で評価付けをしましょう。
過去の主だった出来事を、年代ごとにできる限り多く掘り起こせば、より精密な自己分析につながりますよ。
数値で評価した点と点を結べば、グラフが完成します。
選定した出来事からモチベーションを深読みする
過去の出来事を選定できたら、そこからなぜモチベーションが上下するのかを考え、自分の傾向や特徴をつかみましょう。
「体力測定の結果が良く、陸上大会代表に選ばれた」のケース
成績や評価が良くなると、モチベーションも高まるなどと読み取れます。
業務の過程でも、社員のモチベーションが上がるときの状態を引き出す工夫を取り入れれば、パフォーマンスも上向くでしょう。
「風邪をこじらせて肺炎にかかり、半月欠席して学習の進捗が遅れてしまった」の場合
万全な体調ではなかったり、計画どおりに進まなかったりすると下がる……などと言い換えられますね。
社員の様子をみて、モチベーションが低下したときの状態とわかれば、業務体制の改善や見直しを行うなどの対策も講じられます。
長時間労働の常習化や、無駄なプロセスにより円滑な業務遂行が妨げられているなど、様々なケースが想定されます。
グラフが注意喚起をしてくれているとも捉えられますので、上手く拾い上げて対処していきましょう。
モチベーションを知るには講演の開催が有効
モチベーションは、人が働くうえで切っても切り離せない、内面から湧き起こり、行動を左右する重要なものです。
モチベーションの上下は仕事の成果に直結するので、モチベーションをうまくマネジメントするスキルは社会人の成功を握っているといっても過言ではありません。
モチベーションの上手なマネジメントを実現するために、スペシャリストによる講演会の活用も欠かせない戦略の1つです。モチベーションをメインテーマに掲げ、研究を続けてきた第一人者と時間を共にすれば、新たな知識を得られるでしょう。
「講演サーチ」では、モチベーションのアップや保ち方についても主要ジャンルに位置付けており、第一線で講演活動中の講師が多数在籍しています。
【JA向け】モチベーションアップをテーマにしたおすすめ講師特集
【労働組合/企業向け】モチベーションアップをテーマにしたおすすめ講師特集
社員の高いモチベーションを維持して、職場の雰囲気に力をみなぎらせたいとお考えの方は、講師派遣会社への講演依頼を視野に入れてみましょう。
まとめ
モチベーショングラフはグラフによってやる気を視覚化して、人が持つ本来の能力を発揮するための一助となる自己分析ツールです。対象者の深層部を読み取り、成果の向上や問題の解決策立案につながるので、社会人の間で取り入れるのも有効な手段となります。わかりやすく解説した書き方を参照し、従業員のモチベーションの可視化をしてみてください。
「講演サーチ」には、講演・研修でモチベーショングラフを取り入れている講師も在籍しています。
モチベーション向上の専門知識を持った講師から学びを得て、関連知識全般をさらに高めて組織強化を目指しませんか?
社員の成長を心より支えたい方は、公式サイトからふさわしい人材を選出し、講演会の主催をご検討ください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください!