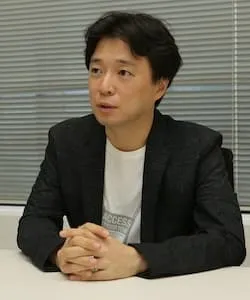飯田 剛弘 いいだ よしひろ プロフィール

飯田剛弘(いいだよしひろ)氏プロフィール
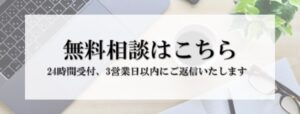
略歴
愛知県生まれ。南オレゴン大学卒。
ITベンチャーでマーケティング担当者として、データベース監査市場でシェア1位獲得に貢献 (ミック経済研究所調べ)。外資系製造企業では、日本、韓国、東南アジア、オセアニアのマーケティング責任者を務める。
現在は、マーケティング支援会社を経営するかたわら、AI活用の専門家として、全国の官公庁、団体等での研修、著書に関する講演など、人材教育にも力を入れている。著書は7冊。日刊工業新聞等で連載中。
中小企業基盤整備機構 経営アドバイザー|あいち産業振興機構 エキスパートあいち (DX担当)
講演テーマ
プロジェクトマネジメント入門 〜チームで目的達成を目指す方法〜
想定する受講者
・後輩や部下に仕事を任せるようになってきた方
・チームを引っ張っていく立場になってきた方
・プロジェクトの管理をすることになった方
・これから、プロジェクトの進行を任される予定の方
・プロジェクトマネジメントを学びたいけど、難しそうと思っている方
受講者へ伝えたいこと
プロジェクトマネジメントと聞くと「専門的で難しそう」「みんな苦労してそう」とイメージする人は多いです。学ぼうと思っても、専門用語に圧倒され、挫折した人もいるのではないでしょうか?
しかし、プロジェクトマネジメントの本質は、「チームで成果を出す技術」というとてもシンプルなものです。チームのメンバーには、それぞれ違った考え方や価値観があります。長所や短所も違います。そのようなメンバーと一緒に成果を出すことです。
本セミナーでは、専門知識や経験をベースにしたプロジェクトマネジメントから離れ、普段の仕事や生活目線での解説やワークを通じて、チームの仕事をスムーズに進められる基本を身につけていただきます。
・目標達成に向けた考え方ややり方を学べます
・チームと同じ方向を見て仕事できるようになります
・チームでの仕事の効率的な進め方や段取り力が身につきます
・さまざまな種類や規模の仕事やプロジェクトに対応しやすくなります
・上司の指示の背景にある意図を汲み取れるようになります
講演内容
・本当はやさしいプロジェクトマネジメント
・みんなが同じ方向を向ける「ゴール設定術」
やるべきことを洗い出す
・チームの仕事を成功に導く「段取り」
役割分担する
作業時間を見積もる
作業の流れを見る
スケジュールを作る
作業負荷をならす
・思いもよらないことに対応できる「リスク管理術」
・バラバラをまとめる「ワンチーム」
メンバーとうまくやる
ミーティングをする
進捗を加速させる
標準化する
・経験を成長につなげる「振り返り」
テレワークでも成果を出す「段取り」×「スケジュール」実践講座
想定する受講者
・仕事のムダを省き、さらに短い時間で成果を上げたいビジネスパーソン
・効率よく成果を出せないチームを何とかしたいと思っているビジネスパーソン
・テレワークで、うまく仕事を進めたいと思っているビジネスパーソン
受講者へ伝えたいこと
■メリット
・限られた時間内に成果を出す考え方が得られます
・効率的な仕事の進め方と時間の使い方が身につきます
・締め切りで焦ったり、慌てたりすることが減っていきます
・テレワークでも余裕をもって、仕事を進めることができます
・自分の使える時間が増えます
■本講座では、
(1)限られた時間内に成果を出す考え方
(2)効率的な仕事の進め方と時間の使い方を、実践練習を交えて習得します。
講演内容
1.どうしてギリギリになるのか?:段取りとスケジュールの必要性
2.逆算思考による「仕事の見える化」:ゴールから考える&成果物を考える
3.仕事の時間割を作る
4.スケジュールを組むための「作業仕分け」
5.テレワークでの「コラボレーション」:情報共有と協働
定時内に成果を出す“スケジュール管理”による業務効率化
想定する受講者
・一生懸命やっているのに、定時に終わらない
・仕事にいつも追われて、納期ギリギリになんとか終わらせている
・提出が1日、2日遅れてしまうことがある
・慌てたために、品質が悪くなってしまう
・やるべきことがわかっていても、なかなか手がつけられない
・Todoリストが「やりたいけど、やれていないリスト」になってしまう
・「手帳を活用して仕事の予定を管理しよう」と決意したが、挫折してしまう
受講者へ伝えたいこと
■メリット
・限られた時間内に成果を出す考え方が得られます
・効率的な仕事の進め方と時間の使い方が身につきます
・締め切りで焦ったり、慌てたりすることが減っていきます
・余裕をもって、仕事をすすめることができます
・自分の使える時間が増えます
講演内容
1.ギリギリになる原因と対策
・アタマの切り換えを減らす
・「探しもの」をする時間はムダ
・「仕事の時間割」を作れば集中力も高まる
2.スケジュールを組むための「作業仕分け」
①:何をすべきか?
②:いつはじめ、いつ終わるのか?
③:「タスク置き場」をどこにするか?
3.いつまでにを癖にする「デッドライン」
・優先順位をつける
・合格ラインを明確化させる
・見積もりのコツを身につける
・仕事の成果の価値とは?
4.探す時間を減らす「タスク置き場」
・「タスク置き場」の作り方
・整理するのではなく、検索からはじめる
・メールも「作業仕分け」で効率化
5.時間効率を上げるテクニック
・時間の意味づけを変える
・振り回されない「コントロール術」
・ムダを減らす積み重ね術
・ビジネスコミュニケーション
6.ミーティング時間を有効活用する
・ミーティングの生産性を落とす原因
・短い時間で成果を出すテクニック
・議事録を作るのに時間をかけない
7.やり直しの時間ロスを防ぐ「逆算思考術」
・チームの仕事の特徴
・やるべき作業のヌケやモレをなくすプランニング
・「待たせる」をなくす、スケジュール作り
8.時間を予算管理する
・価値を生み出す仕事で予定を埋める
・労力を減らすと時間当たりの価値が上がる
・「時間予算カレンダー」を活用する
うまい仕事の進め方(こじらせ仕事のトリセツ)
想定する受講者
・後輩や部下に仕事を任せるようになってきた方
・チームを引っ張っていく立場になってきた方
・プロジェクトの管理をすることになった方
・これから、プロジェクトの進行を任される予定の方
・プロジェクトマネジメントを学びたいけど、難しそうと思っている方
受講者へ伝えたいこと
■メリット
・チームでの仕事の効率的な進め方や段取り力が身につきます
・上司の指示の背景にある意図を汲み取れるようになります
・目標達成に向けた考え方ややり方を学べます
・さまざまな種類や規模の仕事やプロジェクトに対応しやすくなります
・チームと同じ方向を見て仕事できるようになります
講演内容
1.見える化しよう
落とし穴:ゴールが見えない
落とし穴:やることを決められない 落とし穴:思いもよらない失敗をする
2.計画を立てよう
落とし穴:進め方がわからない落とし穴:予定通り終わらない
落とし穴:誰が何をするかわからない
3.うまく進めよう
落とし穴:みんながバラバラになる落とし穴:ムダな打合せが多い
落とし穴:変更するとやることが増える落とし穴:ものごとを決められない
落とし穴:失敗を繰り返す
4.次に備えよう
落とし穴:経験が成長につながらない
はじめてのテレワーク
想定する受講者
■開催趣旨
これまでは「オフィスに出勤する」が当たり前の勤務形態でした。しかし、働き方改革や多様な働き方の推進、事業継続 性の確保のため、今、ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方「テレワーク」が注目されています。
本研修では、「テレワークとは何か?」という基本的なところから、テレワーク導入・運用における課題や対策、テレワークがうまくいくコツを紹介します。企業にとって効果のあるテレワーク活用方法の考え方を習得していただきます。
■参加対象
・テレワークの概要を把握したい方
・テレワークが、自社とどのように関係するか、イメージがわかない方
・テレワークを始めてみようと考えている方
・テレワークを始めたいが、どのように進めたらよいかわからない方
受講者へ伝えたいこと
■メリット
・テレワークが、会社や従業員にとって、どういうものかがわかります
・テレワークの働き方をイメージできるようになります
・テレワーク運用において、注意したい点を事前に把握できます
・テレワークで成果を出せるコツを学べます
講演内容
1.テレワークとは?
2.テレワーク導入を考える
3.テレワーク導入の基礎となる3つのポイント
・制度やルール
・ツールやシステム
・組織風土と仕事の進め方
4.テレワークに必要なスキルやノウハウ
・見える化(目標、成果など)
・コミュニケーション力
・セルフマネジメント力
・必要不可欠なもう一つスキル
5.まとめ ~アクションプランの策定
実践マーケティング短期集中講座
想定する受講者
■開催趣旨
マーケティングの難易度は大きく上がりました。多様化する顧客のニーズや行動に対応するために、マーケティングのサービスやツールが多様化・高度化したためです。その結果「結局、何から始めていいのか分からない」「どのサービスやツールを選べばいいかの分からない」といった悩みを抱える企業も増えました。
本講座では、IT業界や製造業のBtoBマーケティングで実践し、成果を出してきたノウハウやメソッドなど、マーケティング全般を学ぶことができます。戦略立案から施策の実施まで、成果を出すための知識を得ることができます。
■参加対象
・マーケティングの基礎を学びたい人
・マーケティングのノウハウが社内になく、やり方がわからない方
・マーケティングを踏まえ、営業や企画など戦略的に業務に取り組みたい方
・予算をどの施策に、どれくらい投下すればいいのかわからない方
受講者へ伝えたいこと
■メリット
・マーケティングに関する理解を深めます
・顧客への理解を深め、実務に活かすことができます
・マーケティングプランを作れ、実行できるようになります
・マーケティングチームの立ち上げを加速できます
・マーケティングチームのレベルを底上げできます
講演内容
第1部 マーケティング概要
・マーケティングって何ですか?
・なぜマーケティングを気にするのか?
・主なマーケティング手法
・データベースの必要性
・マーケティング組織と役割、業務
第2部 マーケティング戦術 実践編
・マーケティングの目的
・マーケティングプランと戦略
・マーケティングROI管理と目標/予算の考え方
・リサーチ&分析
・マーケティング・コミュニケーション&メッセージ
・クリエイティブ
・プロモーション
・キャンペーンの企画
・インターネットマーケティング
・イベント・セミナー
・その他(価格戦略、チャネル戦略など)
令和上司のすすめセミナー
想定する受講者
・現在、管理職の方
・部下や後輩の育成に関わる上司や中堅社員の方
・チームで仕事をするマネージャーやリーダー
・これから上司になる方
・HR(人材開発、育成・研修、人事)、教育関係者
受講者へ伝えたいこと
<メリット>
・令和の時代に求められる上司の姿をイメージできるようになります
・育てるサイクルを基にした、部下への仕事の任せ方やフィードバックなどの成長支援術を学べます
・育てるプロセスから自身が成長できる勘所をつかめます
・上司の悪い癖とその対策のコツも学べます
講演内容
第1章 多様なメンバーと仕事ができなきゃ上司じゃない
第2章 「私の方が優れている」が部下育成を妨げる
第3章 教えるべきことを整理する【教える力】
第4章 部下が活躍できるように授ける【任せる力】
第5章 ほったらかしせずにフォローする【確認する力】
第6章 自分が話すよりも相手の話に耳を傾ける【聞く力】
第7章 前向きになる率直なフィードバックをする【観察する力】
第8章 相手の能力を引き出せるように質問し、コーチングする【導く力】
第9章 部下のやる気を引き出し、成長を加速させる【応援する力】
第10章 自分も成長し、成果を出し続ける
※基本的には、本の構成を基に進めます。ただし、ご要望やセミナー時間などにより、特定の内容に絞ったり、一部省いたりしてカスタマイズいたします。
期限内にキッチリと成果を出す!「段取り」×「スケジュール」実践講座
想定する受講者
・一生懸命やっているのに、定時に終わらない
・仕事にいつも追われて、納期ギリギリになんとか終わらせている
・提出が1日、2日遅れてしまうことがある
・慌てたために、品質が悪くなってしまう
・やるべきことがわかっていても、なかなか手がつけられない
・Todoリストが「やりたいけど、やれていないリスト」になってしまう
・「手帳を活用して仕事の予定を管理しよう」と決意したが、挫折してしまう
受講者へ伝えたいこと
■メリット
・限られた時間内に成果を出す考え方が得られます
・効率的な仕事の進め方と時間の使い方が身につきます
・締め切りで焦ったり、慌てたりすることが減っていきます
・余裕をもって、仕事をすすめることができます
・自分の使える時間が増えます
講演内容
どんなにやる気があっても、予定通りに仕事が終わらない、あるいは仕事が進まないことがあります。なぜ、このようなことが起きるのでしょうか?それは、以前と比べてやることが増えているのに、仕事の進め方や時間の使い方を変えなかったためです。スケジュール成功の鍵は、努力や根性ではありません。やるべきことを合理的に、ムダなく管理してい くことが重要なのです。本講座では、(1)限られた時間内に成果を出す考え方 (2)効率的な仕事の進め方と時間の使い方を、実践練習を交えて習得します。
■講座内容
①なぜ、段取りとスケジュールだったのか?
②どうしてギリギリになるのか?
③仕事の時間割を作る
④スケジュールを組むための「作業仕分け」
⑤時間効率を上げる「ちりつも力」
⑥時間は金よりケチって使え!
Zoomウェビナー活用入門講座
想定する受講者
■開催概要
「新商品やサービスをプロモーションしたいのに、展示会が中止・延期になり、思うようにPRできない」
「(対面型の)自社セミナーやイベントが開催できない」
「オンラインでのプロモーションを強化したい」
このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?
いま抱えている悩みを解決する手段の一つが、ウェビナーです。つまりオンラインセミナーです。本講座では、「ウェビナーとは?」と基本的なところから、ウェビナーの企画・運営・フォローアップ、さらにZoomウェビナーのスケジュールの立て方などについてわかりやすく解説します。
■参加対象
・オンラインでの販促やプロモーションに力を入れたい方
・オンラインセミナーを活用していきたい方
受講者へ伝えたいこと
・今までアプローチできなかった層に訴求できる
・遠方の顧客でも集客ができる
・参加者との関係を築ける
・どこからでも配信ができる
・録画して二次利用できる
・手間やコストを削減できる
講演内容
1.ウェビナーの基礎
・オンライン営業・マーケティングで注目の「ウェビナー」とは?
・ウェビナーの目的
・ウェビナーのメリットとは ?
・ウェビナーの配信方式
・参加者にとってのメリットとデメリット
・ウェビナー マーケティング とは?
・ウェビナーを実施する主な流れ
2.Zoomウェビナーの開催方法
・Zoomウェビナーとは
・ZoomミーティングとZoomウェビナーの違い
・参加者の役割の違い
・主催者から見た、Zoomウェビナーの特徴
・Zoomウェビナーを開催する手順
・Zoomウェビナーに参加者を追加・招待する方法
・ウェビナー登録ページのカスタマイズ
・メールの設定について
・投票・アンケート・質疑応答機能の使い方
オンライン営業・マーケティング研修
想定する受講者
・マーケティング専任がいない営業や販促に関わる方
・オンラインからの問い合わせや商談を増やしたい方
・オンラインでの販促やプロモーションに力を入れたい方
・オンラインで新規開拓をしたい方
受講者へ伝えたいこと
次のようなことにお困りではないでしょうか?
・訪問営業が難しくなってきている
・ホームページが機能していない(=問い合わせがない)
・オンラインでの顧客開拓の仕組みがない
・なかなか商談化できない
・売上が落ち、問い合わせ数が減っている
・展示会が中止や延期になり、宣伝する場がない!
新型コロナウイルスにより、いろいろな行動変化が起きました。
「今までのやり方ではうまくいかない。オンラインでの販促の強化もしていかないといけない」
と考えられている方も多いのではないでしょうか。
また、お客様の行動変化は、以前から言われていたデジタル化などに伴う変化が加速したという考え方もできます。例えば、お客様の情報収集も展示会などだけではありません。
それらを踏まえ、本セミナーでは、小手先のテクニックやウェブツールの使い方の説明ではなく、オンラインでもしっかりPRして、まずは問い合わせを増やすために、どういうことを考え、どのようなことをするのか・できるかについてやさしくお伝えしていきます。
〈メリット〉
・従来の対面型だけではなく、オンラインでもPRできるようになる
・ウェブへの訪問者や問い合わせを増やす考え方やコツを学べる
・新規顧客開拓や販路開拓のアイデアや考え方を学べる
・お客様によりそったプロモーションができる
・営業やマーケティングのDXの改善につながる
講演内容
1.何が変わったのか?
・お客さまの情報・購買行動が変わった
・営業が接点を持つ前に勝負はついている
・時代遅れの販促の設計図を更新する必要がある
・お客様から問い合わせいただく仕組みを作っていく
・デジタル化により、パーソナライゼーションが可能
・自社をアピールできるよう言語化が必要
2.法人向け営業・マーケティングの特徴
・法人向け営業・マーケティングの主な役割
・お客さまが買い続ける仕組みをつくる
・なぜマーケティングを気にする必要があるのか?
・意思決定者について考えてみましょう
・顧客体験DXが加速している
3.プロセス&役割&体制づくり
・マーケティングから営業までをスムーズにつなげる
・測定できないものは管理できない
・マーケティングオートメーションのイメージ
・それぞれの段階から考える
4.販促の設計図を描く
・企業目線にならない顧客像
・バイヤーペルソナの作り方
・顧客が購入に至るプロセス
・カスタマージャーニーマップの作り方
5.対策案について考える
・オンライン営業・マーケティングの課題や挑戦
・6つの対策案
6.よくある課題と対策案
・12のよくある課題と対策案
※後半が実務上重要になってくるため、詳細の記載をしておりません。
これからはじめる、ウェビナーマーケティング
想定する受講者
■開催概要
「新商品やサービスをプロモーションしたいのに、思うようにPRできていない」
「オンラインでの販促を強化したい」
「これからはネットを使って、もっとプロモーションしていきたい」 このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?
いま抱えている悩みを解決する手段の一つが、ウェビナーマーケティングです。つまりオンラインセミナーによるマーケティング活動です。本講座では、「ウェビナーによるマーケティングとは?」と基本的なところから、ウェビナーの企画・運営・フォローアップ、さらに、Zoomウェビナーによる実際のデモンストレーションを交えながら、わかりやすく解説します。
■参加対象
・営業・販促・マーケティングに関わる担当者の方
・オンラインでの販促活動にも力を入れていきたい方
・オンラインセミナーを活用したいと考えている方
受講者へ伝えたいこと
・今までアプローチできなかった層に訴求できる
・遠方の顧客でも集客ができる
・相手に応じた情報提供ができる
・参加者との関係を築ける
・手間やコストを削減できる
・どこからでも配信ができる
・開催時間を柔軟に決定できる
・録画して二次利用できる
講演内容
1.ウェビナーマーケティングの基礎
・オンライン営業・マーケティングで注目の「ウェビナー」とは?
・ウェビナーマーケティングの目的
・ウェビナーのメリットとは ?
・ウェビナーの配信方式
・参加者にとってのメリットとデメリット
・ウェビナーマーケティング とは?
・ウェビナーマーケティングを実施する主な流れ
2.Zoomウェビナーによる実践デモンストレーション
・Zoomウェビナーとは
・ZoomミーティングとZoomウェビナーの違い
・参加者の役割の違い
・主催者から見た、Zoomウェビナーの特徴
・Zoomウェビナーを開催する手順
・Zoomウェビナーに参加者を追加・招待する方法
・ウェビナー登録ページのカスタマイズ
・メールの設定について
・投票・アンケート・質疑応答機能の使い方
インバウンド営業&マーケティングのすすめ
想定する受講者
●参加対象
・自部門にマーケティング担当がいない法人営業のリーダー
・オンラインからの問い合わせ、オンライン商談を増やしたいマーケティングのリーダー
・オンラインで新規開拓したい方
・これからの営業・マーケティングの役割や連携を体系的に学びたい方
・オンラインで販促するための思考方法とノウハウを把握したい方
●インバウンド手法とは、押し売りではなく、有益な情報を発信して、お客さまに見つけてもらいます。そして、適切なタイミングで適切な情報を提供していくことで、購買意欲を高めてもらい、関係を築きながら、最終的には自社製品やサービス販売へとつなげていく手法です。
働き方の変化、デジタル化等により、お客さまの情報・購買行動は大きく変わりました。多くのお客さまが課題を解決するために自らの手で欲しい情報を検索し、評価するようになりました。今までの販促のやり方ではうまくいかなくなったのです。この事実を踏まえ、見込み客にアプローチする方法やプロモーションなどを変えていく必要があります。
受講者へ伝えたいこと
本セミナーでは、インバウンド手法で問い合わせや商談を増やすために、どういうことを考えるのか、そして効果を上げていくために、何をするのかについてわかりやすくお伝えします。
講演内容
1.なぜ今インバウンド営業&マーケティングが必要なのか
・お客さまの情報・購買行動が変わった
・営業が接点を持つ前に勝負はついている
・お客様から問い合わせいただく仕組みを作るなど
2.社内のプロセスや体制をつくる
・マーケティングから営業までをスムーズにつなげる
・測定できないものは管理できない
・インサイドセールスなど
3.問い合わせや商談を増やすマーケティング施策
・お客さまに伝わるメッセージ&キャッチコピー作り
・お客さまの声と事例制作
・ウェビナー/オンラインセミナーなど
4.企業目線にならない顧客像を描く
・バイヤーペルソナとは
・バイヤーペルソナの作り方
5.顧客が購入に至るプロセス
・カスタマージャーニーとは
・カスタマージャーニーマップの作り方
6.オンライン営業・マーケティングでよくある課題や対策案
AI時代に生き残るためのプロジェクトマネジメント入門
想定する受講者
・プロジェクトをうまく進め、成果を出したいリーダー
・プロジェクト管理を任されたが、どのように進めたらいいのか分からない方
・チームを引っ張っていく立場になった方(今後プロジェクトマネージャーになる方)
・チームでやる仕事の進め方に不安があるリーダー
・プロジェクトマネジメントについて基本から体系的に学びたい方
受講者へ伝えたいこと
目まぐるしく変化し、先が予測できないDX時代において、プロジェクト型の仕事が増加しています。必ずしも決まった正解があるわけではなく、目の前の仕事に対し、自分たちで目的や目標を設定し、進めていくことが求められます。
プロジェクトマネジメントは、ゴールを定め、計画を立て、見える化し、進捗管理しながら、何とかうまくやり遂げるためのノウハウです。プロジェクトマネジメントのスキルはこの不確実な時代を生きるすべてのビジネスパーソンに必須のスキルだと言えるでしょう。
講演内容
1.プロジェクトとは?
・プロジェクトマネジメントとは●●のようなもの
2.みんなが同じ方向を向ける「ゴール設定術」
・やるべきことを洗い出す
3.チームの仕事を成功に導く「計画の立て方」
・役割分担5つのステップ
・作業の流れを確認する
・スケジュールを組む
4.予想外の状況に慌てない「プロジェクトの進め方」
・進捗管理とスケジュール短縮
・リスクマネジメントと変更管理
5.経験を成長につなげる「振り返り」
6.質疑応答
※上記は3時間の研修プログラムです。研修時間によってアレンジ致します。
デジタル人材育成の進め方
想定する受講者
・デジタル人材育成に関わる経営層や人事担当者
・デジタル人材を増やしたい経営層や人事担当者
・DX推進リーダーや管理職
受講者へ伝えたいこと
時代の変化により、デジタル技術を使ったビジネスが急速に普及しています。デジタルスキルを持った人材の育成は急務です。しかし、デジタル人材を育成するのは簡単ではありません。特に、経営層や管理職、人事関係者が理解していなければ、人材育成はなかなか成功しません。そこで、本研修では、デジタル技術の基礎から応用まで、幅広い知識を身につけることができます。また、人材育成に必要なマネジメントや組織改革についても学ぶことができます。デジタル人材育成に携わる方々には、ぜひご参加いただき、組織の競争力強化につなげましょう。
〈デジタル人材育成研修の開催主旨〉
「自社のDX化に必要な人材とはどんな人材であるか」「どんなスキルが必要か」そんな悩みを抱えている経営や人事担当者へ、まずDXの本質を紹介した上で、DX実現のためのデジタル人材の人材像やレベル、DX推進を担う人材の確保などを丁寧に解説していきます。現場を意識したワークを交え、デジタル人材育成の方針や計画など、進め方を具体化していきます。
〈本研修の効果〉
自社内においてDXを推進・導入するに当たり、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革する人材の育成方法を習得する。
講演内容
・1日研修がお勧めですが、講演形式での開催も可能ですので、ご相談ください。
・最新情報などにより、内容の一部が変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
【DXリテラシーと業務改革】
〇DXの基礎と事例紹介
・DXが必要な背景と社会的影響
・DXの本質とは?
・DXの事例紹介
〇デジタル人材とは
・デジタル人材の人材像とレベル
・DXリテラシー標準とは
・DXに求められる能力
〇業務改革プロジェクトの成功の鍵
・業務改革必要な3つの要素
・業務フロー図作成で業務を見える化
・【ワーク】業務改革プロジェクト
【DX推進を担う人材】
〇DXを推進する人材の役割
・DX推進スキル標準 – 人材類型の定義
・DX推進において担う責任
・推進体制例
〇DX導入フェーズにおけるDX人材
・DX推進人材に必要とされる能力
・【ワーク】自社に必要なDX推進人材を考える
・DX人材候補者の選定手法
【デジタル人材の育成方法】
〇DX人材のスキルと学習項目
・デジタルスキルマップについて
・【ワーク】必要なスキルや学習項目を洗い出す
・【ワーク】不足する人材の質と量を明確化する
〇リスキリング
・DX人材の育成方法や事例
・【ワーク】自社に必要なDX人材育成の方針と計画の作成
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進 ~デジタル化&データ経営の実現に向けて~
想定する受講者
DX化が必要とお考えの経営者、経営幹部の方々
DXを導入&推進しようとお考えの管理職の方々
DXの担当者になり、何から手をつけたらいいか、わからない方
DXの基礎や考え方、活用事例について知りたい方
受講者へ伝えたいこと
DXの話になると、導入する企業だけではなく、それを支援する企業も、多くの場合、トランスフォーメーション(変革)の意識が弱く、手段(IT化や作業の効率化)に目を奪われがちです。事実、日本企業は、アメリカの企業と比べ、新規ビジネスの創出においては成果が出ていない報告もされています。とりあえず現場に任せっぱなしということもよくあります。
そうならないように、経営者・役員、管理職の方向けに、手段にとらわれない、デジタル時代において、企業は何をはじめるべきか、どう企業がデジタルやデータとかかわるべきか、全体がわかる研修を行っていきます。生き抜くための変革! 何をどうして、どうすれば、何ができるのかをやさしく徹底解説します。
〈DXの推進研修のねらい〉
DX(デジタルトランスフォーメーション)による企業変革の有効性を理解し、自社のDX推進に向けたポイントを習得する。
〈DXの推進研修の開催主旨〉
・「DX」という言葉は耳にするが、そもそもDXって何かよくわからない
・DXを推進したいけど、どこから始めればいいのかわからない
・DXの全体像とはじめの一歩を知りたい
・DX人材がおらず、推進できずに困っている
・DX人材に育成する方法を知りたい
そんな悩みを抱えている方へ、まず、DXとは何かの前に、デジタル化の潮流についてご紹介します。そこで社会の現状を理解し、変化を捉えることで、DXとはそもそも何か、DXの全体像がどういうものかがイメージしやすくなります。それを踏まえた上で、DX戦略の導入について掘り下げていきます。
また、DX現場を意識した、対話による「わからない」から「わかる」へ、そして、DX実現のためのDX人材の確保や育成など、目指すべき方向性やどのようなことをするのかを具体化していきます。
講演内容
・1日研修がお勧めですが、講演形式での開催も可能ですので、ご相談ください。
・最新情報などにより、内容の一部が変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
【DX概論】
〇DXとは
・デジタル化の潮流とは
・DXの本質
・【ワーク】属人化における現状と課題
〇DXを進める際に立ちはだかる大きな壁
・なぜDXが必要か
・デジタルで何が変わるのか~IT化とDX化の違い~
・DX化における現状と課題
〇対話による「わからない」から「わかる」へ
・DXの目的が分からない
・【ワーク】なぜDXを推進するのか?
【DX導入事例】
〇DXの基礎知識&事例紹介
・デジタイゼーション/デジタライズゼーション/DX
・RPA、IoT、AIの概要(特徴、効果、活用例)
【DX戦略の導入】
〇DX導入から推進における流れと課題
・【ワーク】DXの設計図をつくる(DXの具体的な取組領域の決定)
・DX化がうまくいかないよくある間違い
・【ワーク】DX化で直面する課題とは
〇DX推進の体制づくりや進め方
・DXプロジェクトを柔軟に進める考え方
・二段階方式で進める
・DXに向けた体制例
〇DXを実現するための人材育成
・IT経営成熟度レベル
・DX人材の役割やスキル
・人的資源がコンピューティング資源に置き換わる
・【ワーク】自社に必要なDX人材とはを考える
DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入 ~DXの基礎知識~
想定する受講者
DXを導入&推進しようとお考えの管理職の方々
DXの担当者になり、何から手をつけたらいいか、わからない方
DXの基礎や考え方、活用事例について知りたい方
受講者へ伝えたいこと
何をどうして、どうすれば、何ができるのかをやさしく徹底解説。
DX導入には多くのメリットがありますが、具体的な手順や部署の連携が課題となる場合があります。
しかし、それを乗り越えることができれば、企業の競争力強化につながる可能性があります。
本研修では、DXの基礎知識から始め、各部署との連携や業務プロセスの最適化方法まで、具体的な解決策を提供します。現場で必要なスキルやノウハウを身につけ、ビジネスを変革しましょう!
〈DXの導入研修のねらい〉
自社の業務変革を目指して、業務のシステム化に向け、自社のニーズに合致したシステムを企画できる知識を習得する。
〈DXの導入研修の開催主旨〉
・「DX」という言葉は耳にするが、そもそもDXって何かよくわからない
・DXを推進したいけど、どこから始めればいいのかわからない
・DXの全体像とはじめの一歩を知りたい
・DX人材がおらず、推進できずに困っている
・DX人材に育成する方法を知りたい
そんな悩みを抱えている方へ、まず、DXとは何かの前に、デジタル化の潮流についてご紹介します。そこで社会の現状を理解し、変化を捉えることで、DXとはそもそも何か、DXの全体像がどういうものかがイメージしやすくなります。それを踏まえた上で、DX戦略の導入について掘り下げていきます。
また、DXにおける働き方として、アジャイルな考え方ややり方に焦点を当て、システム開発に有効なプロジェクトマネジメントを習得していただきます。また、PoCで注意しなければならないポイントも紹介します。
講演内容
・1日研修がお勧めですが、講演形式での開催も可能ですので、ご相談ください。
・最新情報などにより、内容の一部が変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
〈本研修の効果〉
・DXの本質を理解することができる
・DXを導入していくためには、何をしなければならないかを理解できる
・DX化を担当する社員に何が必要かを理解することができる
〈DX導入研修カリキュラム案〉
①DX導入手法とデジタル技術の活用
1.DX導入の3つの視点
・デジタル化の潮流とは
・DXの本質
・デジタイゼーション/デジタライズゼーション/DX
2 .DXを進める際に立ちはだかる大きな壁
・なぜDXが必要か
・デジタルで何が変わるのか
・DX導入における課題や現状
3.対話による「わからない」から「わかる」へ
・DXの目的が分からない
・どうすればDXになるのかが分からない
・DXの進め方が分からない
・【ワーク】デジタル化における現状と課題について考える
②DX導入手順
1.DX導入から推進のステップと基本知識
・STEP1:アナログのデジタル化
・【ワーク】アナログデータのデジタル化における現状と課題
・STEP2:デジタル化した情報をベースに業務改革
・【ワーク】RPAなどを活かせそうな業務の洗い出し
・STEP3:データ活用によるビジネスの変革
2.デジタル化がうまくいかないよくある間違い
・目的があいまいなまま進めてしまう
・IT業者にお任せになっている 等
・【ワーク】ITやDX導入を進める際の課題を考える
3.DX推進の体制づくりから進め方
・二段階方式で進める
・DXに向けた体制例
・DXの罠への処方箋
③DXプロジェクトの進め方
1.プロジェクトマネジメントの基礎を理解する
・プロジェクトマネジメントとは?
・なぜプロジェクトマネジメントが必要なのか?
・プロジェクトマネジメントの主な流れ
2.DXの鍵となるアジャイル開発とは?
・「とりあえず、アジャイルで」は注意!
・うまくいかないこと前提で進めていく
3.適切な開発アプローチを選ぶ
・今までのやり方とアジャイルの主な違い
・「正しくやる」だけではなく「正しいことをやる」
・【ワーク】プロジェクトの進め方を業務毎に考えてみる
④DX推進検証
1.PoCとは
・PoCの定義
・なぜPoCを実施するのか?
・プロトタイプの違い
2.PoCを使用した検証
・DXにおけるPoC
・PoCを実施するステップ
・PoCを失敗しないポイント
ビジネスにおけるChatGPT・AI活用
想定する受講者
・ChatGPTや生成AIについてよく聞くが、どのようなものか、何ができるのかを知りたい経営層・管理職
・自分のビジネスにAIを活用したいが、どこから始めればいいかがわからない経営層・管理職
受講者へ伝えたいこと
・ChatGPTと他のAIツールの基本的な機能と利用方法を理解
・スマホを使用してChatGPTを操作する体験
・自分のビジネスにおけるAIツールの活用方法を考えられます
講演内容
・最新情報などにより、内容の一部が変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
・内容はご希望に応じて変更できます。講演・研修内容例
1.AIとは何か?
・人工知能とは何か?
◼AIの主な分類(弱いAIと強いAI)
◼AIと機械学習、ディープラーニングの関係
◼便利なAIツールやサービスの紹介
2.ChatGPTとは何か?
・ChatGPTの概要と基本的な使い方
◼ChatGPTの可能性と制約
ChatGPT・生成AIでビジネスモデルを構築する! ~スタートアップのためのAI活用術~
想定する受講者
スタートアップの経営者や開発者、マーケティング担当者など、生成AI/ChatGPTに興味がある方
受講者へ伝えたいこと
①ChatGPT・生成AIの基本的な概要と機能を理解する。
②ChatGPT・生成AIを用いて、リーンキャンバスを作成する方法を習得する。
③ChatGPT・生成AIがどのようにビジネスモデルの構築に貢献するかを理解し、自社のビジネスに応用するアイデアを得る。
④ChatGPT・生成AIを始めるための基本的な手順と注意点を把握する。
講演内容
1.ChatGPTとは何か?
・生成AIやChatGPTの概要や歴史、技術的な仕組みを簡単に説明。
・ChatGPTができることやできないこと、利点や欠点を紹介
2.ChatGPTの活用事例
・ChatGPTを使って、リーンキャンバスやビジネスモデルキャンバスなどの事業計画書を作成した事例を紹介
・ChatGPTがどのようにビジネスモデルの構築に貢献したか、効果や課題を分析。
3.ChatGPTの始め方
・ChatGPTを使うために必要な条件や手順を説明。
・ChatGPTの料金体系や注意点を紹介。
・他のAIサービスとかも少し紹介する?
4.ワークショップ
【ケース:●●店を開業しよう】
・ChatGPTやその他生成AIを使い、どのような事業計画書づくりができるかやってみよう
・講師の活用方法の紹介
・生成AIが、どのようにビジネスモデルの構築に貢献したかをり返る
書籍
『やることを8割減らすダンドリ術』(大和書房 2023年)
『PMBOKはじめの一歩』(翔泳社 2022年)
『PMBOK対応 童話でわかるプロジェクトマネジメント 第2版』(秀和システム 2022年)
『まわるリモートチームのマネジメント術』(明日香出版社 2021年)
『令和上司のすすめ』(日刊工業新聞 2020年)
『こじらせ仕事のトリセツ』(技術評論社 2020年)
『仕事は「段取りとスケジュール」で9割決まる!』(明日香出版社 2018年)

| #飯田剛弘,#いいだよしひろ |