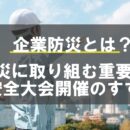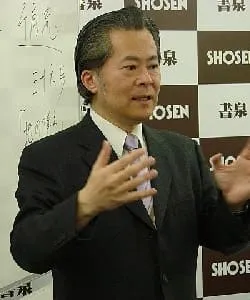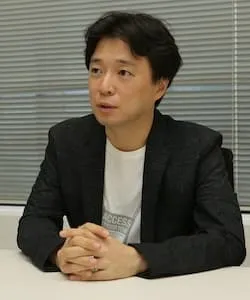ヒューマンエラーの12分類とは?分類ごとにみるエラーの原因と人的ミスを予防するために効果的な対策方法5選!

人的ミスとも呼ばれるヒューマンエラーは、誰しもが起こす可能性があり、時に大きな事故に繋がることもあるため対策が必要です。
ミスを完全になくすことは難しいかもしれませんが、原因や対策を知って安全性の高い業務や作業を行っていきましょう。
日々、業務や作業にあたっていると、ミスが起きてしまうことがありますよね。人的ミスとも呼ばれるヒューマンエラーは、誰しもが起こす可能性があり、時に大きな事故に繋がることもあるため対策が必要です。
そんなヒューマンエラーの原因や対策を知っていると、エラーの原因に合わせた対策によってエラーの発生率を下げることができます。
ミスを完全になくすことは難しいかもしれませんが、原因や対策を知って安全性の高い業務や作業を行っていきましょう。
今回は、ヒューマンエラーの原因とされる「ヒューマンエラーの12分類」について詳しく解説します。
分類ごとに異なる原因と対策方法をご紹介するので、現状と照らし合わせてエラー予防にお役立てください!
ヒューマンエラー以上に予防できないのが自然災害。企業が災害対策をする重要性と防止策はこちらでご紹介しています。
ヒューマンエラーがテーマのおすすめ講師特集はこちら
ヒューマンエラー12分類とは
目次
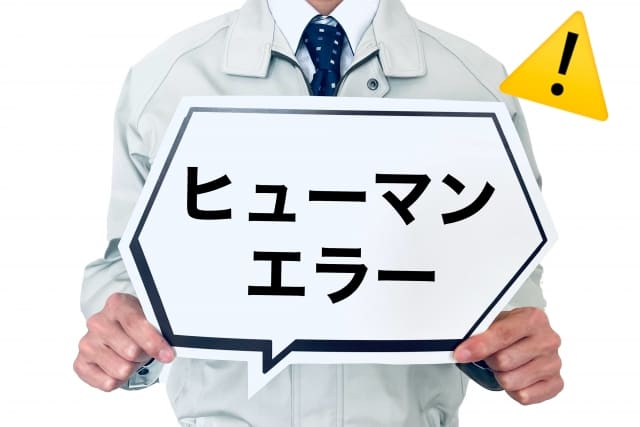
「ヒューマンエラー」という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか?
これは「人的ミス」とも呼ばれ、人の行動によって起きるミスのことを指します。
特に「ヒューマンエラー12分類」とは、ヒューマンエラーのよくある原因を以下の12種類に分類したものです。
危険軽視・慣れ
不注意
無知・未経験・不慣れ
近道・省略行動
高齢者の心身機能低下
錯覚
場面行動本能
パニック
連絡不足
疲労
単調作業による意識低下
集団欠陥
ヒューマンエラーは時に大きな事故に繋がる危険性があるため、原因を知って適切な対策をすることが欠かせません。
まずは原因を12に分けたヒューマンエラー12分類を見ていきましょう。
1:危険軽視・慣れ
危険軽視・慣れによるヒューマンエラーは、業務や作業に慣れてきたときに起こります。
業務や作業に慣れてくると「いつも大丈夫だから、これくらい良いだろう」と軽視してしまい、安全面への注意が疎かになりがちです。その結果、事故やミスに繋がってしまうことがあります。
「慣れてきたな」と感じるときこそ、安全面に注意を払って業務や作業にあたるようにしましょう。
2:不注意
不注意によるヒューマンエラーは、周りの状況に注意が払えないために起こります。
周りの状況に注意が払えないのは、過度の集中や注意散漫が原因と考えられます。周りが見えなくなることにより、自分だけでなく人に怪我やミスをさせてしまうなどの恐れがあるのです。
周りの人たちで、お互いに声を掛け合って注意が払える環境づくりが必要となります。
3:無知・未経験・不慣れ
無知・未経験・不慣れによるヒューマンエラーは、知識や経験の乏しさから起こります。
新人に多いミスではありますが、ベテランの人も初めての現場などは不慣れにより、ミスが起きてしまうことがあるため注意が必要です。
新人が現場にいるときは、一緒に作業にあたるなどしてヒューマンエラーが起こりにくいような対応が大切です。
4:近道・省略行動
近道・省略行動によるヒューマンエラーは、効率化などを図った結果に起こります。
業務や作業にあたっていると、効率化などを求められることもあると思います。しかし、効率性や生産性などを優先するあまり、必要な手順を省略してしまい、事故やミスに繋がってしまうことがあります。
特にベテランになると、ある程度の裁量権を持つがゆえに近道や省略行動によるヒューマンエラーが起きがちです。
効率性や生産性も大切ではありますが、安全面に考慮した手順などは絶対に省略などしないようにしましょう。
5:高齢者の心身機能低下
高齢者の心身機能低下によるヒューマンエラーは、ベテランと呼ばれる中高年や高齢者に多いです。
年齢が上がることで、記憶力や身体能力などは否応なしに衰えてしまいます。しかし、その衰えを自覚することができず過信した結果、事故やミスに繋がってしまうこともあります。
特に高齢者による事故などは、死亡事故に繋がってしまうケースも少なくありません。
衰えは、誰しも目をそらしたいと思うものですが、業務や作業にあたる以上過信することは危険です。周りの人も高齢者の尊厳を傷つけることのないよう配慮しつつ、お互いに助け合っていく姿勢が大切です。
6:錯覚
錯覚によるヒューマンエラーは、見間違いや聞き間違えなどにより起こります。また、慣れた作業によって「こうであろう」という思い込みも含まれます。
足場からの転落事故なども、足場があると思い込み起きてしまうことも少なくありません。
普段の生活でも見間違いや聞き間違え・思い込みは起きやすいものですが、業務や作業にあたる場合は何度も確認して安全面に配慮していきましょう。また周囲の人と声を掛け合っていくことも大切です。
7:場面行動本能
場面行動本能は聞きなれない言葉かと思いますが、1点に集中してしまうことで周りの人や状況が見えずに行動してしまう人間の本能のことです。
場面行動本能によるヒューマンエラーは、1点に集中しすぎることにより起こります。
例えば、重い木材などを運ぶ際に、落とさないよう集中するあまり周りが見えておらず、木材をぶつけてしまうなどが挙げられます。
現場での業務や作業をするにあたって、どのような場面行動本能が考えられるかを従業員同士で共有したり、お互いに声を掛け合いながら作業にあたることが大切です。
8:パニック
パニックによるヒューマンエラーは、慌てるような場面で起きやすくなります。
人は、慌てると脳が正常な判断をすることができず、安全面に注意することもできなくなります。その結果、重大な事故やミスが起きてしまうこともあるのです。
パニックは、想定外のことが起こることで引き起こされます。
業務や作業にあたる際は、どのような事が起こり得るか、さまざまな事態を想定して心や環境を整えておくことが大切です。
9:連絡不足
連絡不足によるヒューマンエラーは、コミュニケーション不足や正しい情報が伝わっていないことが原因です。
作業する人と管理する人の連携は、現場ではとても重要です。しっかりとコミュニケーションをとって、正しい情報を伝えることがヒューマンエラーを起こさないためには欠かせません。
従業員同士の連携も重要です。普段からコミュニケーションをしっかりと取っていくことが求められます。
特に安全面に関する情報は、全員がしっかりと理解しているかを把握していくことで、連絡不足によるヒューマンエラーを減らすことが期待できます。
10:疲労
疲労によるヒューマンエラーは、疲労によって引き起こされる注意力散漫や頭が働かなくなることが原因です。
疲労を感じると、人は脳の働きが悪くなり事故やミスを起こしやすくなります。
特に、長時間労働や夏の暑い時期などは頭がボーっとしてしまい、安全面への注意が難しくなります。
業務や作業が長時間にわたりそうなときや、暑い時期などはこまめに休憩を挟むなどして疲労を溜め込まないようにすることが大切です。さらに、管理者は従業員の体調に配慮し、常に目を配らせておきましょう。
11:単調作業による意識低下
単調作業による意識低下のヒューマンエラーは、交感神経が働かなくなることで起こります。
人間は、単調作業を繰り返すことで、緊張感を失い身体の活動が鈍くなります。
同じ作業をずっと繰り返すことで、眠くなってしまったことはありませんか?これが、単調作業による意識低下です。
人間は、ある程度緊張感があり身体を動かすことで交感神経が活発になります。これは、人間に備わっている本能のようなものなので仕方ありませんが、意識低下が起きると安全性も効率性も悪くなりがちです。その結果重大な事故やミスを引き起こすことも考えられます。
単調作業が続く場合は、こまめに休憩を入れたりするなどして意識低下が起きないようにしていきましょう。
12:集団欠陥
集団欠陥によるヒューマンエラーは、効率性や生産性を優先した結果に起こります。
集団欠陥とは、効率性や生産性を優先するあまり、作業する人全員が安全性に注意することができない状態を指します。
集団欠陥の恐ろしいところは、厳しい納期などを優先する現場の雰囲気から“全員”が安全性を二の次にしてしまうことです。しかし、安全性を二の次にしたことにより、重大な事故やミスを起こしてしまっては効率性や生産性を大幅にダウンさせてしまいます。
集団欠陥に陥る原因は、効率性や生産性ばかり求めるような会社や組織にもあります。ヒューマンエラーは、従業員のみならず会社や組織の意識改革も重要です。
ヒューマンエラーが多い人の特徴
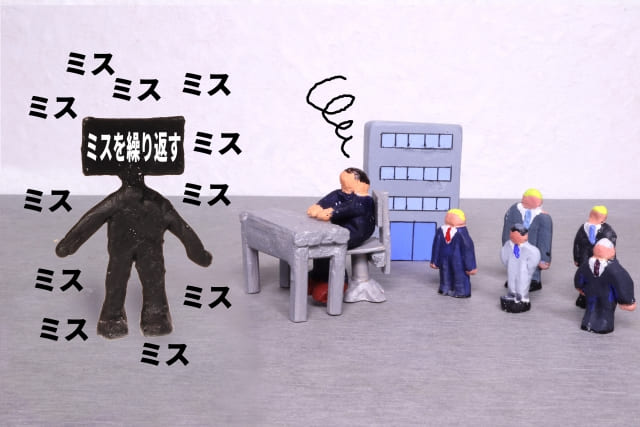
ヒューマンエラーの原因を見てみると、エラーの原因は決して特別なことではなく、誰でにでも起こり得ることだと分かります。
しかし、一緒に働いているとミスが少ない人と、多い人がいると感じる人は多いのではないでしょうか?
ヒューマンエラーが多い人には以下の4つの共通点があります。
・注意力が散漫
・ストレスへの対処が苦手
・作業に対する知識が不十分
・上司や同僚とのコミュニケーションが適切にとれていない
これらの特徴に当てはまる場合、ヒューマンエラーを起こしやすい環境ができているかもしれません。
周囲の環境を振り返ってみましょう。
注意力が散漫
周囲へ注意を払うことが苦手だと、ヒューマンエラーが多くなりがちです。
注意力散漫な人は、全てに対して注意力が散漫な場合もありますが、狭い範囲だけなど、範囲が限定される人もいます。
性格の大らかな人や適当な人も細かいところまで注意を払えないことがあります。
注意力散漫な傾向がある場合は、意識して周囲に気を配る心がけが重要です。一人では難しい場合は、周りの人に二重チェックをしてもらうなど、注意力をカバーする環境を整えると良いかもしれませんね。
ストレスへの対処が苦手
特徴2つ目は、ストレスへの対処が苦手なことです。ストレスを溜め込むと、疲労同様に脳の働きが悪くなります。ストレスに上手く対処できる人は多くありません。
ストレスを溜め込みんでしまうと、安全や周囲の状態まで気が回らずにヒューマンエラーが起きがちです。
ストレスへの対処が苦手な人は、同僚や友人に相談したり、自身でストレス発散したりできず、一人でストレスを抱え込んでしまっていることがあります。
企業としては、従業員のストレスチェックの実施や、相談ができる雰囲気づくり、部署間やチームメンバーの良好な関係構築に尽力する必要があるといえるでしょう。
作業に対する知識が不十分
特徴3つ目は、作業に対する知識が不十分なことが挙げられます。
新人などに多く見られる傾向ですが、業務や作業の手順などを正しく把握できておらず、曖昧なまま業務や作業にあたってしまうことが要因です。
少し慣れてきた従業員なども、正確に理解できていないまま中途半端な知識と経験に基づいた自己判断で、マニュアル外の業務や作業を進めてしまうことがあります。
知識不足を改善するには、正確な知識を学ぶ機会の提供や、従業員自らが進んで勉強する姿勢が大切です。会社や組織が研修などを行う機会を設けるのも有効です。
上司や同僚とのコミュニケーションが適切にとれていない
上司や同僚とのコミュニケーションが適切にとれていない特徴がみられる場合、会社や組織に問題があるケースがあります。
コミュニケーションが適切にとれていないことで、相談することができずに曖昧なまま業務や作業にあたることになりミスが起きるのです。
さらに、コミュニケーションが不十分なために連絡が行き届かず、ミスなどが引き起こされてしまいます。
その場合は、上司や同僚だけでなく、会社や組織が話しやすい環境を整え、働きかけていく必要があるでしょう。
ヒューマンエラーの防止方法5選

ヒューマンエラーは、誰でも起こしてしまう可能性があるため、完全になくすことは難しいかもしれません。
しかし、対処することで少なくすることは十分にできます。
ヒューマンエラーの防止方法を知って共有し、安全に業務や作業にあたりましょう。
KY活動
まず1つ目は、KY活動です。Kは“危険”、Yは“予知”を意味しており、危険と予知の頭文字をとってKY活動と呼ばれます。
危険を知り、安全に業務や作業にあたるようにするのが目的であり、建設現場などに潜む危険を見つけ、皆で話し合い対処方法を考えていきます。
KY活動をすることで、ミスを少なくして安全に業務や作業に取り組むことが可能です。
定期的にKY活動を行い、ブラッシュアップしていけると良いですね。
ヒヤリハットの報告
2つ目は、ヒヤリハットの報告です。ヒヤリハットは、業務中や作業中のミスや危険などにより「ヒヤリ」としたり「ハッ」としたりすることを言います。
ヒヤリハットは、ただ報告するだけで終わりにせず、しっかりと皆と共有することが大切です。
例えば、ヒヤリハット報告書をつくり、気付いたことがあった時には報告書を記入し、皆に共有し事故やミスがないよう改善していきます。
皆で共有することにより、注意点に気付き改善され、ヒューマンエラーを少なくすることができますよ。
指差呼称
3つ目は、指差呼称です。指差呼称とは、危険箇所や間違いがあると事故に繋がるような所で、体と声の両方で確認することを言います。
人間は、体と声の両方を使った方が意識レベルを上げることができます。
そのため、目視で確認するよりも指差呼称するほうが、確認の精度を上げることができるため、重大な事故やミスを防ぐために有効です。
KY活動で、危険箇所を共有した上で、必要な箇所に指差呼称を取り入れると良いですね。
マニュアルを作成する
4つ目は、マニュアルを作成することです。
現場などでは、人から人に言葉だけで教えていくこともあるため、マニュアルを作っていない会社や組織などもあります。
しかし、言葉だけで教えていく方法は、人によって知識や理解に差があるため、皆が同じ認識を持つことが難しいことも多いです。
マニュアルを作成することで、ルールや手順を明確にし、皆が同じ認識を持つことができるため、事故やミスを防ぐことができるでしょう。
特に、新人が入ったときなどでは、可視化された情報はとても役立ちます。
過去のヒューマンエラーをリスト化する
5つ目は、過去のヒューマンエラーをリスト化することです。
リスト化することで「どういった点に気をつければ良いか」が分かり、業務や作業をより安全に行うことができます。
リスト化する場合は小さなことでもしっかりと記載し、原因を特定・分析し、改善していくことが大切です。
一つひとつの出来事を軽視せずに分析し、再発防止に努めていきましょう。
ヒューマンエラーについて学ぶなら安全大会や講演の開催がおすすめ

ヒューマンエラ‐の原因は、主に12種類に分類できます。それぞれに対策方法があり、しっかりと準備をすることでヒューマンエラーの発生率は下げられるでしょう。
ヒューマンエラーがなぜ起こり得るのか、自社や組織ではどの分類のエラーが起こりやすい状況なのか、一度俯瞰して検証してみることが大切です。
第三者やプロの目線からヒューマンエラーについて知るには、講演会や安全大会を開催して安全への理解と意識を高めることをおすすめします。
講演サーチでは、安全への意識を変えるような経験・知識ともに豊富な講師が多数在籍しています。
難しい講師選びや面倒な事務手続きまでトータルサポートいたしますので、
安全大会・研修会・講演会の開催をお考えの方はぜひお気軽に無料相談をご利用ください。
おすすめ!講演サーチ厳選講師
清水 孝久 しみず たかひさ プロフィール
南 利幸 みなみ としゆき プロフィール
中山 隆嗣 なかやま たかつぐ プロフィール
小木曽 健 おぎそ けん プロフィール
清水 俊宏 しみず としひろ プロフィール
下江 美帆 しもえ みほ プロフィール
久留嶋 怜 くるしま れい プロフィール
野口 琢矢 のぐち たくや プロフィール
【こちらもおすすめ】
安全大会とは何かはこちらの記事で詳しく解説しています。