支部役員が「真の傾聴」を身につけることで、組合は変わる【梶浦正典講師特別コラム】
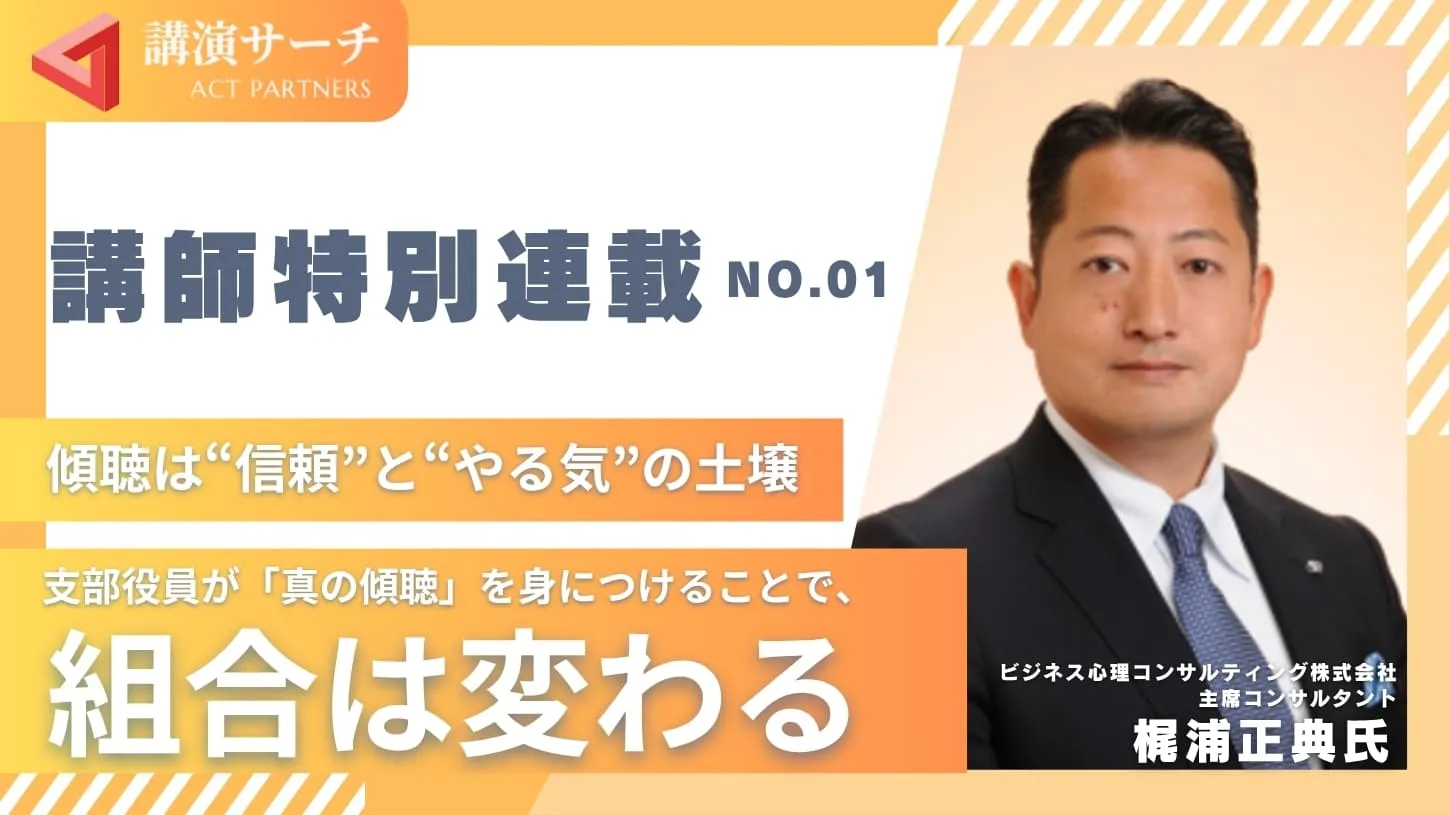

支部役員が「真の傾聴」を身につけることで、組合は変わる【梶浦正典講師特別コラム】
目次
執筆講師

ビジネス心理コンサルティング株式会社 主席コンサルタント
こんにちは。ビジネス心理コンサルティング株式会社の梶浦正典です。
私は長年、労働組合の現場で活動してきました。その経験と心理学の視点をもとに、いま組合に必要な“コミュニケーション力”の重要性を多くの講演や研修でお伝えしています。
今回は、「支部役員が“真の傾聴”を身につけることの意味と効果」について解説します。
結論から申し上げれば、支部役員の“聴き方”が変わるだけで、組合の雰囲気は見違えるように変わります。
なぜなら、傾聴は“信頼”と“やる気”の土壌だからです。
傾聴とは「相手を変える」のではなく、「わかろうとする」こと
一般的に、“聴く”という行為は当たり前のように思われがちです。
しかし、相手の話を「ちゃんと聴いている」つもりでも、無意識のうちに自分の考えや価値観で判断し、返答してしまっているケースが非常に多いのです。
例えば、組合員が「最近、仕事がつらくて自信がないんです」と打ち明けてきたとします。
このとき、私たちはついこう言いたくなるかもしれません。
・「まずは行動してみようよ」(命令や指示)
・「仕事の意味をもう一度考えてみない?」(説教・訓戒)
・「原因を整理してみたらどうかな?」(助言・提案)
・「誰にでもあることだよ。この壁を乗り越えて成長していくものだよ。」(講義・解釈)
一見すると励ましの言葉のようですが、これらはすべて「相手を変えようとする試み」です。
相手の心が開いていないうちにこうした反応を返してしまうと、相手は反発し、かえって距離ができかねません。
大切なのは、「変えようとする」のではなく、「わかろうとする」こと。
“傾聴”とは、相手の言葉の背景にある感情やニーズに注意を向け、「この人は今、何を感じているのだろうか?」と寄り添うことなのです。
支部役員が「真の傾聴」を身につけるとどうなるか
支部役員に求められる「真の傾聴」とは以下の4点に集約されると考えています。
1.組合員のココロに寄り添える
2.組合員の辛い気持ちや苦しい想いを引き出せる
3.組合員の承認欲求を満たし、信頼関係を築ける
4.組合員の気持ちが整理され、モチベーションが高まる
傾聴とは単なる会話のテクニックではなく、「相手の心を開き、前に進む力を引き出す関わり方」なのです。

支部役員こそ、“傾聴のプロ”であってほしい
なぜ支部役員に傾聴が求められるのか。
それは、組合員にとって最も身近な存在であり、最初に声をかけられる立場だからです。
支部役員は「イベントの案内」や「職場大会の呼びかけ」といった役割を担いますが、それだけではありません。組合員からの「ちょっと話を聞いてくれませんか?」という声にどれだけ丁寧に向き合えるかが、組合の信頼度を大きく左右します。
実際、ある支部で傾聴トレーニングを取り入れたところ、以前は敬遠されがちだった役員が、次第に「話しやすい人」「頼れる存在」として認識され、組合活動への参加率が改善した例がありました。
支部役員が“聴ける人”になることは、組合の求心力そのものを底上げするのです。
「誰かのモチベーションを引き出せる人」はどこでも重宝される
私がよく申し上げるのは、傾聴力を身につけた人は、組合だけでなく、職場全体でも信頼される存在になるということです。
上司からも部下からも「この人には話せる」と思われる存在。
チーム内で相談役として頼られ、自然と人が集まる人。
それが、「誰かのモチベーションを引き出せる人」であり、あらゆる組織で“超ひっぱりだこ”の人材となります。
もちろん最初からうまくできる必要はありません。
大切なのは、まず「聴くことの価値」を知ること、そして「相手を理解しようとする姿勢」を持ち続けることです。
傾聴は“組合を強くする力”になる
組合の目的は、待遇改善や制度交渉だけではありません。
仲間の声を受け止め、居場所と安心を提供し、「ここにいていいんだ」と思える場をつくることも、極めて重要な役割です。
聴くことは、誰にでもできる“最も人間らしい力”です。
そして、それこそが信頼とやる気を生む源なのです。
支部役員の皆さんには、ぜひ「真の傾聴」を通じて、組合活動の質を高めていただきたいと願っています。
執筆講師

ビジネス心理コンサルティング株式会社 主席コンサルタント







