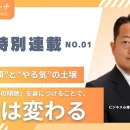組合員との信頼関係を築き、課題を解決に導く「聴き方」のステップ【梶浦正典講師特別コラム】
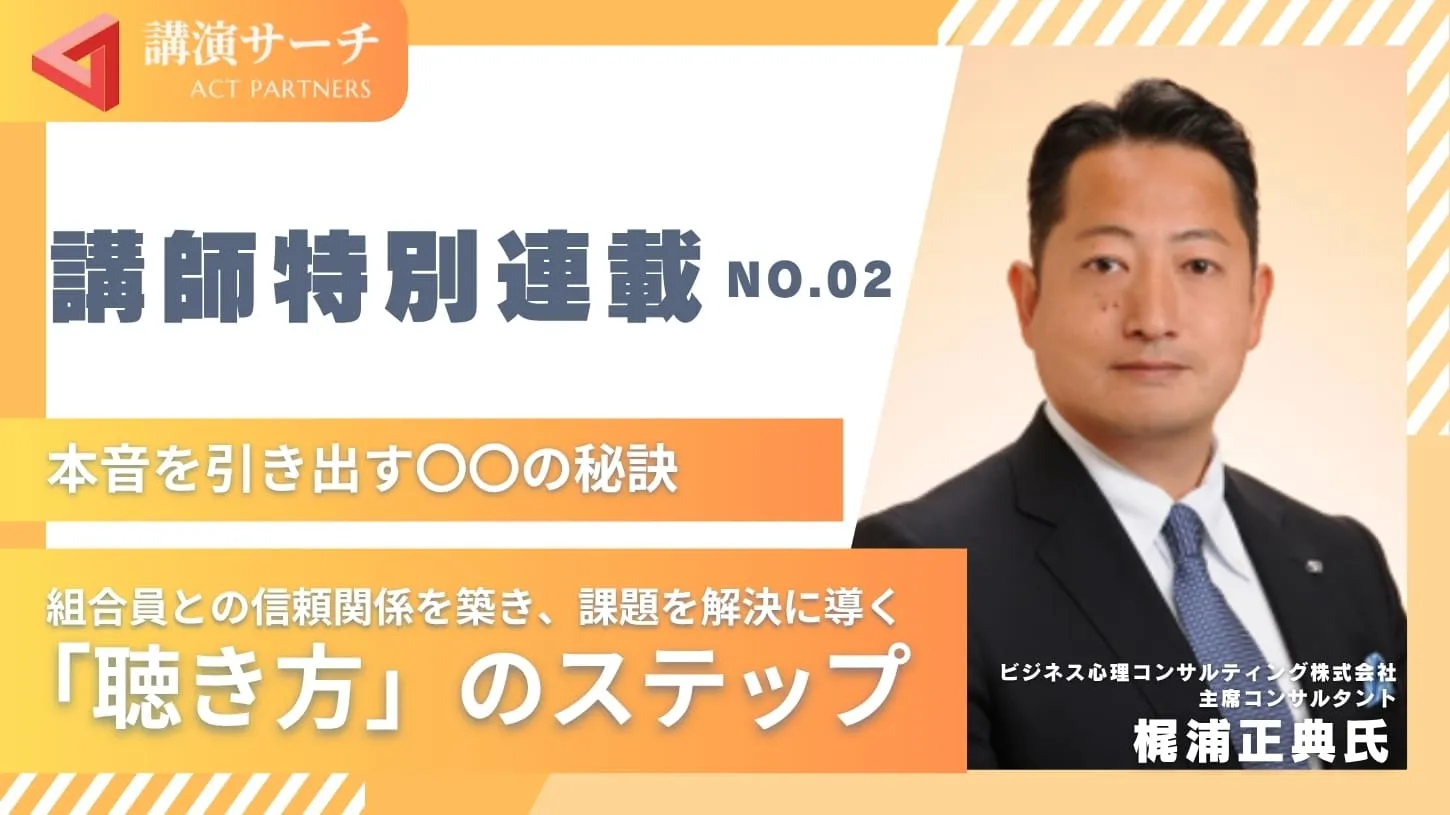

組合員との信頼関係を築き、課題を解決に導く「聴き方」のステップ【梶浦正典講師特別コラム】
目次
執筆講師

ビジネス心理コンサルティング株式会社 主席コンサルタント
こんにちは。ビジネス心理コンサルティング株式会社の梶浦正典です。
私が現場でご一緒する中で、もっとも多く聞く声のひとつが、「組合員が本音を話してくれない」「相談に乗っても、解決につながらない」というお悩みです。
その背景には、“聴き方”に対する誤解や思い込みがあることが少なくありません。
今回は、組合役員や支部幹部の皆さまにとって欠かせない「信頼関係を築くための“聴き方”」について、心理学的視点からお話ししたいと思います。
「話を聴いているつもり」が信頼を遠ざけてしまう
例えば、こんな場面を想像してみてください。
組合員が、「最近、仕事に自信が持てなくて……」と打ち明けてきたとき。
あなたは、どのように応えますか?
・「誰でもそういう時期はあるよ」(同意・理解)
・「まずは行動してみることが大事だ」(命令・指示)
・「原因を整理してみたらどう?」(助言・提案)
こうした言葉は、決して間違っているわけではありません。
むしろ、相手を思いやる善意の反応だと思います。
しかし、この段階では、組合員は「ただ気持ちを受け止めてほしかった」だけかもしれません。
つまり、こちらが「変えよう」「励まそう」として発した言葉が、結果的に相手の心を閉ざしてしまうことがあるのです。
聴くことの基本は「まず、わかろうとする」
信頼関係を築く上で最も重要なのは、「変えようとするな、わかろうとせよ」という姿勢です。
これは私が講演や研修でも繰り返しお伝えしている、大切なメッセージです。
“聴く”という行為は、単に耳を傾けることではなく、「あなたの話を、あなたの立場で理解しようとしています」という意思を持って関わること。
これを心理学では「共感的理解」と呼びます。
共感は同情とは違います。
相手の気持ちに巻き込まれずに、しかし誠実に理解しようとする努力――これが、信頼関係の土台になるのです。

課題解決に導く「聴き方」の3ステップ
私がおすすめしている“聴き方”の実践ステップは、以下の3つです。
①沈黙:話すための空間をつくる
意外に思われるかもしれませんが、聴くことの出発点は「沈黙」です。
何も言わず、ただ相手に時間と関心を差し出す――この姿勢が、安心感を生みます。
精神分析の世界では、「愛とは、相手本位に時間を提供すること」と表現されるほど。
沈黙に耐え、焦らずに聴くことで、「ここでは本音を話していいんだ」と相手は感じてくれます。
②チューニング:相手のペースに合わせる
声のトーン、スピード、表情、言葉の使い方などを、できるだけ相手に寄せていくことを“チューニング”と呼びます。
これを意識することで、心理的距離が縮まり、相手も自然と話しやすくなります。
また、適切なタイミングで「うんうん」「なるほど」とあいづちを打つことで、話が促されていきます。
③言い換え:気持ちを“受け取った”と伝える
「自分だけ成果が出ていないのが恥ずかしい」という相手の言葉に対して、「数字のことを気にして責任を感じているんだね」と返す。
このように、相手の言葉を受け止め、自分の言葉で繰り返して伝えることで、「わかってもらえた」「理解してもらえた」という実感が生まれます。
ポイントは、完璧な言葉選びや言葉の流暢さではなく、「あなたの話をちゃんと受け取っていますよ」という心です。
小手先の「技術」でなんとかするのではなく、相手をわかろうとする姿勢を見せること。
それだけで、相手は前向きな一歩を踏み出しやすくなります。
「理解されている」という感覚が、人を変える
私たちは、誰しも「見てもらいたい」「認めてもらいたい」という気持ちを持っています。
この“承認欲求”は、決して悪いものではありません。
むしろ、健全な人間関係を築く上で自然な感情です。
組合員が「この人には話せる」「ここにいても大丈夫」と思える瞬間が、信頼とエンゲージメントを育みます。
そしてその土壌が、課題を共有し、解決に向かって共に歩む力を生み出していくのです。
組合の“存在感”は、聴く力で決まる
制度や待遇だけでは、組合の存在意義は語りきれません。
人の気持ちに寄り添い、「心の安全基地」として機能することで、はじめて組合は“生きた組織”になります。
支部役員や幹部の皆さまにこそ、ぜひこの「聴く力」を意識していただきたいと願っています。
執筆講師

ビジネス心理コンサルティング株式会社 主席コンサルタント