安田 伸也 やすだ しんや プロフィール

安田伸也(やすだしんや)氏プロフィール
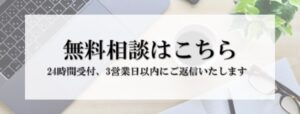
略歴
35年間、海上保安庁にて海上保安官として勤務。
職員の約2%しか就けないといわれる潜水士としても約8年間従事。
海難救助、領海警備、密入国や密輸船の取り締まりなど様々な任務に就く。
その間、延べ3000件以上の事件・事故調査にあたり、海難救助などの功績により海上保安庁長官表彰を3度受賞するなど、異色の経歴を持つ。
その一方で、自身もまたうつやパニック症などメンタル疾患を繰り返し発症する。
現場では生きることを許されなかった命がある一方、自ら命を絶つ者がいる現実に理不尽さを覚え、後輩潜水士の自死などを機に定年前に退職。
心理学とコーチングを学んだ後、うつ専門のメンタルコーチとして独立。
現在は「自死ゼロ・事故ゼロの世界」を目指し、コミュニケーションやメンタルヘルスからの事故防止 をテーマに企業研修や講演を行っている。
講演では、海難救助の実体験や失敗談を交え、コーチング手法を通じて気づきを引き出すスタイルが好評、多くの企業から支持を得ている。
資格
・米国NLP協会TMNLP マスタープラクティショナー
・日本プロフェッショナル講師協会TM認定講師
・一般社団法人 エフェクティブコーチング協会認定プロコーチ
・潜水士
・一級小型船舶操縦士
・4級海技士(航海)
講演テーマ
元海上保安庁潜水士が語る事故防止 〜ミスを前提で考える安全対策〜
提供する価値・受講者へ伝えたい事:
人はどんなに努力しても、ミスを完全に無くすことはできません。
逆に「人はミスをする生き物だ」という前提に立つことで、ミスを防ぎ、事故を未然に防ぐことが可能です。
この講演では、35年間の海上保安庁での経験と巡視艇船長としての事故原因究明の知識をもとに、組織ぐるみの危機管理とミスを前提とした安全対策をお伝えします。
現場においてどのようにミスに対処して、より安全な職場を全員で協力して作って行くかを具体的に学んでいただけます。
講演概要:
【レジュメ例】
1.人はミスをするという前提で考える事故防止
2.否定は肯定と同じ
・否定語で発生した事故事例紹介
・心理学の実験から見る正しい伝え方
3.そもそも情報は正しく伝わらない
・巡視艇船長時代の失敗
・言葉の落とし穴
・曖昧なコミュニケーション
4.事故防止に効果的なミーティング
・全員が参加したくなる最初のミーティング
・次に繋げる最後のミーティング
メンタルヘルスからの事故防止対策 〜心の健康が安全な職場を作る〜
提供する価値・受講者へ伝えたい事:
建設業や建築業の現場では、心の健康が事故防止に直結します。
この講演では、まず「うつとは何か」を理解し、うつのサインを見逃さず、適切な対応を取るためのポイントを解説します。
「頑張れ」と言ってはいけないという誤解や、正しいコミュニケーション方法もご紹介。
さらに、心と身体の健康が作業に与える影響や、現場での事故防止に向けたケアの具体的なアプローチを学び、リーダーとして現場の安全を守るための実践的な知識を提供します。
現場リーダー必見の内容です。
講演概要:
【レジュメ例】
1.うつとは何か?
2.うつのサインを見逃すな
・うつの人は相談しない
・メンタル異常のサイン
3.うつの人との接し方
・「頑張れ」と言ってはいけないは本当か?
・正しい関わり合い方
4.心と身体の健康からの事故防止
・心の健康が作業に与える影響
・事故防止のために大切な心と身体のケア
現場の安全は心のケアから 〜メンタルヘルスで離職を防ぐ新戦略〜
提供する価値・受講者へ伝えたい事:
現場での安全と効率を守るためには、心のケアが欠かせません。
過酷な労働環境や緊張感が続く現場では、ストレスやメンタル不調が原因で離職が増えることも。
海上保安庁で35年の経験を持つ講師が、メンタルヘルスの課題と解決策を現場視点で解説。
効果的なコミュニケーション術やコーチングを通じ、チームの絆を強化し、離職を防ぐ新戦略を伝授します。
リーダー層がすぐに実践できるテクニックも満載です。
講演概要:
【レジュメ例】
1.はじめに
・海上保安庁紹介
・現場でのメンタルヘルスの重要性
2.現場を守るのは心の健康!メンタルヘルスの課題と現状
・職場環境とストレス要因
・メンタルヘルスの影響
3.現場での効果的なコミュニケーション術
・現場におけるコミュニケーションの重要性
・積極的な傾聴とフィードバックの技術
4.心理学的視点から見るメンタルケアのアプローチ
・ストレスのサインを見逃さない
・心の健康を保つセルフケア方法
5.聴くことで始める離職防止策
・まずキチンと聴くことで創る信頼関係
・聴くことで働くモチベーションUP!
他人よりも先ず自分を満たせ!
〜みんなが幸福になる自分とのコミュニケーション〜
■想定する受講者
・サービス業(接客業、介護、医療従事者など)
・ビジネス・管理職(マネージャー、リーダー職)
・事務職・営業職
これらの職種は、対人業務が多く、他者の管理やサポートに追われる職種のため、自分のケアが疎かになりがちであるため。
■提供する価値・受講者へ伝えたいこと
・まず自分を満たすことが、他人との良好な関係の基盤になる
・「自分を大切にする」ことは利己的ではなく、むしろ周囲を支える力になる
・「ご機嫌な自分」を取り戻すことが、充実した人生を作る第一歩である
【解説】
他人に応えるばかりでなく、自分を優先して満たすことが、かえって共感や優しさを生み、円滑な人間関係の基盤となります。「自分を大切にする」ことは利己的ではなく、周囲を支える力にもなり、自分のご機嫌を整えることが心の安定や幸福感につながります。こうしたセルフケアが心の余裕を生み、職場や家庭での良好な関係づくりに役立ちます。
■テーマ内容
①メンタルヘルスとセルフケアの基本
・メンタルヘルスとは何か、日常生活や仕事への影響
・自分との対話の重要性
②自分とのコミュニケーションを深める方法
・自分の気持ちに気づく習慣
・心の声に耳を傾ける
③自己受容と自己対話の重要性
・自己受容の基礎
・ポジティブな自己対話
④日常生活に取り入れられるセルフケア
・セルフケアのための簡単な習慣
⑤講演のまとめとメッセージ
⑥Q&A
■内容詳細
ご希望により、下記実践ワークを追加することも可能です。
②自分とのコミュニケーションを深める方法の後に実践ワーク①
「心の声を書き出すワーク」
【内容】参加者に、自分の中にある気持ちを紙に書き出してもらう。
例:「今一番気になっていること」「最近感じたモヤモヤ」など、日常の感情を振り返る簡単なエクササイズ。
目的:書き出すことで、自分が何を感じているのか客観的に把握し、感情に気づく力を養う。
③自己受容とポジティブな自己対話の重要性の後に実践ワーク②
「ポジティブな自己対話を体験するワーク」
【内容】参加者が、自分へのポジティブな言葉を考え、簡単なフレーズを書き出してもらう。
例:「今日はここまで頑張れた」「まず一歩進んだことを評価しよう」など、普段の自分への言葉を少し前向きに変える練習。
目的:自分に向ける言葉の持つ力を実感し、セルフケアの一環として役立てる。
それぞれのワークを組み合わせることで、より効果的な講演になります。
元海上保安庁潜水士が語る熱中症対策 〜命を守るコミュニケーション〜
想定する受講者:
経営者、管理職、職場リーダー、安全大会、建設現場や工事作業者、運行管理者など
提供する価値・受講者へ伝えたい事:
地球沸騰化をむかえ、1人でも多くの熱中症にかかる方を減らすべく現場の方々のお役に立てれば幸いです。自身も熱中症経験者のためその経験談を盛り込みお話しします。
また、潜水士時代に実際に使っていたバディシステムを導入することで、熱中症を防ぐ手立てになると信じております。
講演概要:
プロローグ:海上保安庁紹介 �
1.なぜコミュニケーションが熱中症予防に必要なのか
・私の熱中症体験
・事故事例とその教訓
2.熱中症の基礎知識
・熱中症のメカニズムと症状
・現場でよくある危険なサインと誤解や油断
3.現場で役立つコミュニケーション術
・簡単にできる「声かけ」の具体的なフレーズとタイミング
・ミーティングで共有すべき熱中症リスク
4.バディで守る現場の命
・熱中症予防に効果的なバディシステム
【コミュニケーションが熱中症予防に有効な理由】
①本人の自覚症状が遅れがち
熱中症の初期段階では、本人が「少し体調が悪いだけ」と感じ、症状を軽視してしまうことがあります。また、体調が悪化している本人ほど、正常な判断ができなくなるため、自分自身で休憩を取ったり、水分補給をしたりする判断が難しくなります。そのため、周囲が早めに声をかけることが重要です。
②早期発見と対応による重症化防止
作業現場ではお互いに忙しいため、つい他者の異変に気付くのが遅れてしまいます。こまめに声を掛け合うことで、小さな体調変化に気づくきっかけが生まれ、早期に休息や水分補給が促されます。特に建築業や建設業の現場では、周囲との声掛けが、重症化を防ぎ、命を守る行動へとつながります。
③職場環境の心理的安全性の確保
現場のコミュニケーションが円滑であるほど、体調不良を気軽に伝えたり、休憩を申告したりすることができます。心理的な壁が低い職場環境は、熱中症予防につながる重要なポイントとなります。逆に、コミュニケーション不足の職場では「体調不良を言い出しにくい」「無理をしてしまう」といった状況が生まれ、重篤な熱中症事故のリスクが高まります。
④職場の連携力とチームワーク強化
コミュニケーションを活性化させることで、チームとしての連携力が向上し、互いの異変にすばやく対応できる職場になります。結果として、熱中症に限らず他の事故防止にも効果が生まれ、安全性の高い職場づくりが可能になります。
※基本90分講演ですが、ご要望に応じて60分に短縮することも可能です。
出演実績
・実録!奇跡の救出劇(フジテレビ 2025年)
当社実績
安全大会 2025年夏・大阪府
講演タイトル:元海上保安庁潜水士が語る事故防止
~ミスを前提で考える安全対策~
人材育成 2025年夏・愛知県
講演タイトル:元海上保安庁潜水士が語る熱中症対策
〜命を守るコミュニケーション〜
他多数

| #安田伸也,#やすだしんや |








