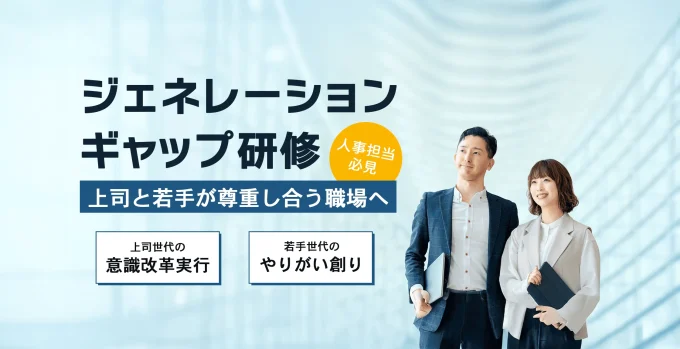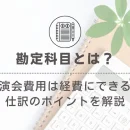源泉徴収税額の計算方法は?講演料の扱いや計算時の注意点3つ、役立つサイトを紹介
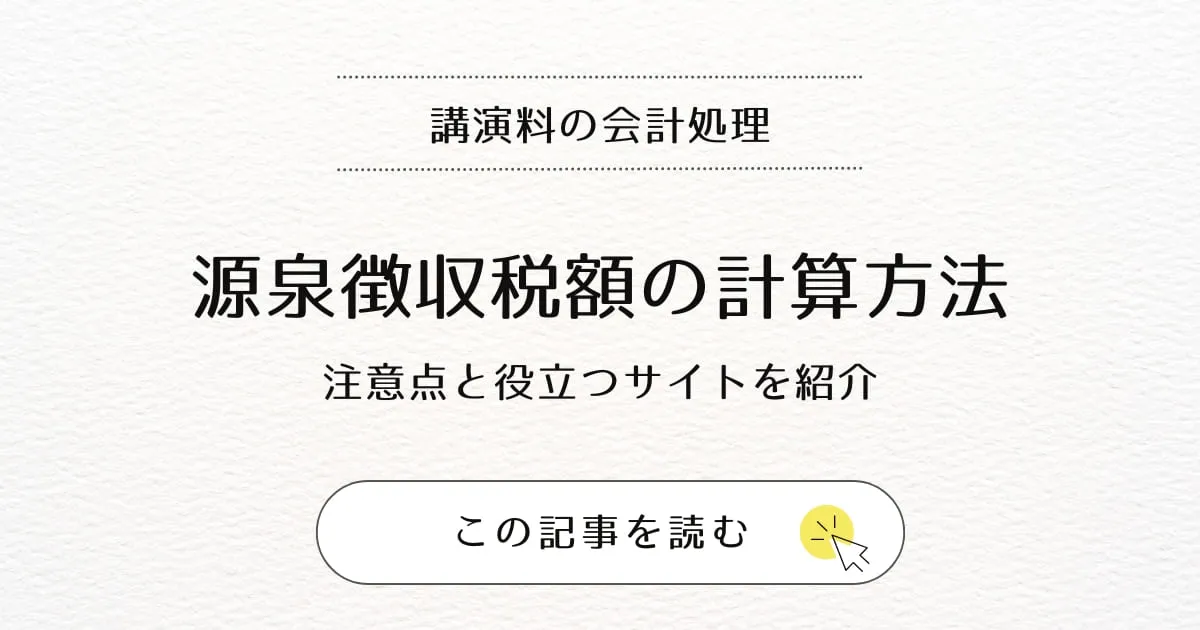
講演会やイベントに講師を招いた場合、講演料を支払います。このとき気になるのが「源泉徴収」の計算ではありませんか?
初めて講演を主催する場合、会計処理について迷うシーンは多いかもしれません。
この記事では、講演料における源泉徴収の計算方法をわかりやすく解説します。源泉徴収の計算に役立つ便利なツールの紹介や計算する際の注意点なども解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
講演サーチは講演会の講師や講演テーマ選びを丁寧にサポートいたします。面倒な講師とのやり取りや打ち合わせのサポートも行うため、社内の負担軽減につながります。講演会や研修会の開催をお考えの方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。

源泉徴収税額の計算方法は?講演料の扱いや計算時の注意点3つ、役立つサイトを紹介
目次
人気の講師

1位
佐藤 政樹
【劇団四季 元主役の感動創造トレーナー】

2位
村瀬 健
【放送作家・漫才作家】

3位
桂 三四郎
【落語家】

4位
安藤 美希子
【株式会社日動電設/ウエイトリフティング選手/オリンピアン/メダリスト】

5位
林家 鉄平
【落語家】
源泉徴収の基本!概要や徴収対象を詳しく解説
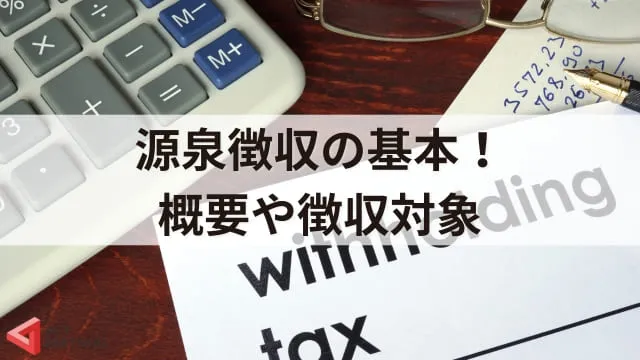
源泉徴収とはそもそもどのようなものなのでしょうか?
講演会を主催する際に知っておきたい、源泉徴収の基本を解説します。
そもそも源泉徴収とは
源泉徴収とは、イベントの主催者が講師や出演者に報酬を支払う際に、報酬額からあらかじめ税金を差し引いておく仕組みのことです。
差し引いた税金は、主催者が講師や出演者に代わって国へ納めます。
源泉徴収は、税金の回収を確実なものとし徴収漏れや未納を防ぐことが目的です。
所得税法によって、講演料などの報酬や謝礼が50,000円以上の支払いがあった際には源泉徴収を行う義務が発生します。もし源泉徴収を行わなかったり不足分があったりした場合には、追加税が課されたり行政指導が入るなどのペナルティが発生することもあるので注意しましょう。
参照:e-Gov 法令検索所得税法
源泉徴収の徴収範囲
源泉徴収は講師や出演者、その他関係者に支払う報酬に対して行います。
講演会をはじめとするイベントにおいて源泉徴収が必要となる項目は以下です。
・講演料や出演料
・原稿料
・デザイン料
旅費などの経費は含まれないため、計算を行う際には注意しましょう。
ただし場合によって、旅費などが対象になるケースもあります。例えば、講演料や出演料に旅費などの経費が含まれている場合や、経費を講師へと直接支払った場合などは報酬として扱われるため源泉徴収が必要です。
源泉徴収の概要はこちらでより詳しく解説しています。
講演料の税処理上の扱い方
講演料や出演料などの報酬が50,000円以上あった際には、源泉徴収を行う義務が発生しますが、支払い先が「法人」なのか「個人」なのかで扱い方が違います。
支払い先の違いで源泉徴収の扱い方にどのような影響を与えるのかみていきましょう。
支払い先が「法人」の場合
講師や出演者が仲介企業から派遣されたり組織に属していたりした場合は扱いが「法人」となります。
支払い先が「法人」である場合、主催者は源泉徴収を行う必要はありません。法人には自身で所得税を申告、納税を行う義務があるためです。法人は講演料を自社の所得として扱い、定期的に申告して税金を支払います。主催者が申告をせずとも、講師や出演者の所属している組織が代わりにしてくれるため源泉徴収を行う必要はありません。
法人に対して支払いを行う際、消費税が別途発生するため計算間違いに気をつけましょう。
支払い先が「個人」の場合
支払い先がフリーランスなどの個人事業主の場合には、源泉徴収が必要です。
講師や出演者に対して講演料を支払う際には源泉徴収を行い、徴収税を引いた残りの金額を報酬として支払います。
源泉徴収の詳しい計算方法はこの後詳しく解説しているのでご覧ください。
講演料における源泉徴収の計算方法
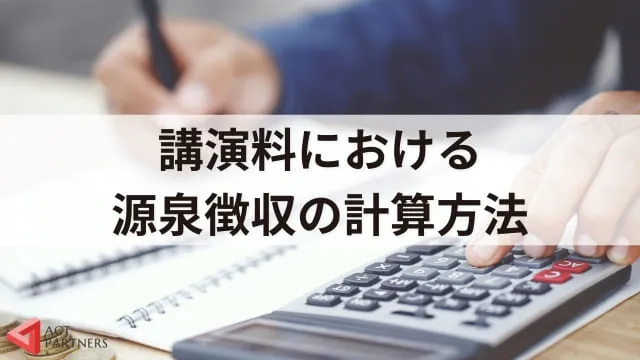
源泉徴収の計算は、支払い金額に税率を適用させて行います。税率は支払った金額によって変動するため、計算をする際には注意しましょう。
税率は講演料が
・100万円以下の場合
・100万円を超える場合
で変わります。
講演料が100万以下の場合
講演料が100万円以下である場合は、以下の計算式で求めます
支払い金額×10.21%
支払った金額に対して10.21%の税率を適用させることで源泉徴収額を算出できます。
例えば30万円の支払いをしたケースで考えてみましょう。
30万×10.21%=30,630
となり、30,630円が税金として納められます。
実際に講師や出演者に支払う場合には、報酬の30万円から源泉徴収額の30,630円を差し引いた金額が講師に支払う講演料となります。
計算方法はシンプルではありますが、計算ミスなどを起こさぬように注意しましょう。
講演料が100万円を超える場合
講演料が100万円を超える場合の計算は以下の方法で行います。
(支払い金額-100万)×20.42%+102,100
100万円以下までは10.21%、100万円を超えた金額に対しては20.42%の2段階で税率を適用させる必要があります。
仮に講演料が150万円だった場合で考えてみましょう。式に当てはめると以下の通りとなります。
(150万-100万)×20.42%+102,100=204,200
報酬が100万円を超える場合には、税率の適用を間違えないように注意しましょう。
「源泉徴収は難しくてよくわからない」という方は講演サーチをはじめとする講師派遣サービスの利用がおすすめです。講演会の開催サポートや講師派遣を委託できるため、さまざまな手間が軽減できますよ。

源泉徴収の計算を行う際に利用したいおすすめツール
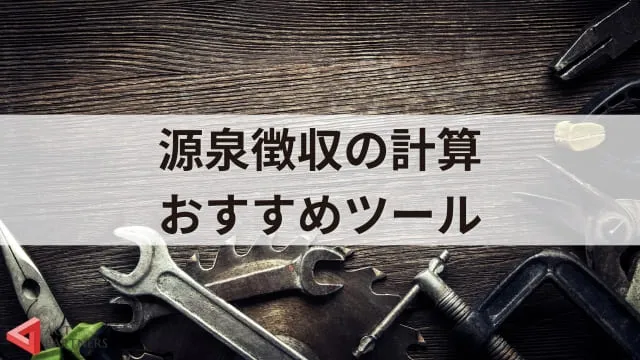
源泉徴収の計算方法を紹介しましたが、なかには複雑で面倒な計算をしたくない方も多くいるのではないでしょうか。
「もっと楽して正確に計算をしたい」という方へ源泉徴収の計算を簡単に行えるツールを紹介します。源泉徴収を行う際にこれから紹介するツールを取り入れて会計処理の効率化を図りましょう。
表計算ソフト
源泉徴収の計算を行う際にはExcelやGoogleスプレッドシートなどの表計算ソフトの利用がおすすめです。
表計算ソフトを活用すれば講演料を入力しただけで源泉徴収の計算ができるツールを自分でつくることができます。作成の手間はかかりますが、一度作成すれば何度も利用ができるツールとなるため、計算を行う際に電卓などの手動で行うよりも業務効率の向上を図ることができるでしょう。
源泉徴収の計算ができるサイト
Webブラウザ上で源泉徴収が行えるサイトがあります。ダウンロード無し、無料で利用できるため安全に使えるのは担当者にとっても嬉しいポイントではないでしょうか。
源泉徴収の計算が行えるサイトを今から3つ紹介していきます。それぞれ使い勝手の良いサイトを利用してみてくださいね。
Keisan「原稿料や講演料等の源泉徴収税額を計算」
Keisanは電卓で有名なカシオが運営するサイトで、原稿料や講演料などの報酬に対する源泉徴収の金額を自動で計算ができます。
請求額や消費税の有無を入力するだけで、それに対応した請求額や源泉徴収額が算出される仕組みです
同ページ内には源泉徴収に関するコラムや口コミ、よくある質問なども確認できるため、初心者でも使いやすいインターフェースとなっています。
講演量の源泉徴収はこちらから計算できます。
税理士法人経営サポートプラスアルファ「源泉徴収税額の計算シミュレーション」
税理士法人経営サポートプラスアルファが運用している「源泉徴収額の計算シミュレーション」もおすすめです。
税理士法人が監修している計算ツールであるため、正確さはもちろんのこと報酬や給与など税金に関するさまざまな計算も行えます。
ページ内には税理士が監修している源泉徴収のコラムも掲載されているため、不明な点があっても確認しながら計算を行えるのもメリットの1つです。
サイトはこちらから利用できます。
AccuntAgent「源泉徴収税額の計算シュミレーションツール」
会計や税務に関するサポートを提供するAccunt Agentが運営している「源泉徴収税額の計算シュミレーションツール」でも源泉徴収の計算を自動で行えます。
公認会計士と税理士の資格を持っている運営者が監修しているツールで、最新の税制に基づいているため法改正に対応した情報が反映された計算ができます。
また請求書の記入例も表示されるため算出結果を請求書に書き写す際の参考資料としても活用できる優れたツールです。
サイトはこちらから利用可能です。
源泉徴収の計算時に注意すべき3つのポイント
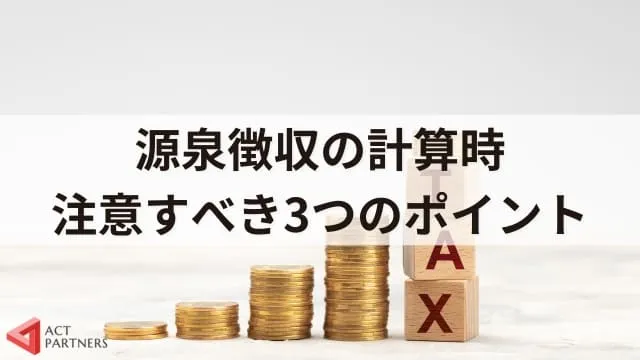
源泉徴収の計算をするときに、ミスが起きやすいポイントを3つまとめました。計算を誤ってしまうと税金の過不足が発生し、経済的な損失や税務トラブルが起る場合もあります。
源泉徴収の計算を正確に行うためにも、これから紹介する3つの注意ポイントを押さえて取り組んでみてください。
消費税込の金額で計算すること
源泉徴収の計算を行う際には、消費税込みで考えるのが一般的です。
講演料や出演料などに消費税が含まれているのかを確認してから、計算を行いましょう。
しかしなかには消費税込などの明記がなく、含まれているのか判別がつかないものもありますよね。調べてもわからない場合には、消費税込みで計上してもよいと法令によって定められています。
講師をはじめ多くの関係者が関わる講演などのイベントにおいて、請求書や領収書が統一されていないこともあります。源泉徴収を計上する際に、消費税込みと税抜きの金額が混在してしまわぬよう注意をしましょう。
端数は切り捨てる
源泉徴収の計算で小数点以下の端数がでてしまい、切り上げるべきなのか、切り捨てるべきなのか迷った経験はありませんか?
源泉徴収の計算をした際に小数点以下の端数がでた場合には、切り捨てて計上するようにしましょう。端数がでた場合に切り捨てる方法は、法令でも定められている共通のルールです。
切り上げや四捨五入をしてしまうと実際の徴収額より多く計上されてしまい、正確な徴収額が算出されません。正しい源泉徴収額を算出するためにも、端数の取り扱いには十分注意をしたうえで計算を実施しましょう。
税率の適用に注意する
源泉徴収の税率は、講師や出演者が日本の居住者か非居住者かによって変わります。
居住者の定義は税法によって明記されており
・1年以上日本に滞在していた実績があるか
・日本で1年以上滞在する意思や予定があるか(長期滞在ビザの有無など)
・生活の拠点が日本にあるか(日本に住所がある、職場が日本にあるなど)
などの条件を満たした個人が日本の居住者として認められます。
そのため単純に外国人の講師や出演者だからといって非居住者というわけではありません。上記の条件に当てはまっているのか確認することをおすすめします。
講師や出演者が非居住者であった場合には一律20.42%の税率で計算を行わなければいけません。計算式は「支払い金額×20.42%」です。
税率は一律であるため講演料が100万円以下であろうと100万円より高くとも変わりません。
講演料を支払う際に、講師や出演者が居住者かどうかを確認せずに源泉徴収を行なってしまうと正しく算出されず誤った徴収額になってしまいます。源泉徴収の計算は、講師や出演者がどこの居住者であるのかを確認してから行いましょう。
まとめ|源泉徴収の計算に不安を感じたら「講演サーチ」に依頼しよう
講演料を支払った際の源泉徴収の計算方法を解説してきました。源泉徴収は、特定の条件下において主催者は徴収する義務が発生するものです。源泉徴収を怠ったり徴収額を間違えたりしてしまうと、後から追加税の支払いや税務署から指導が入るなど負担や手間が発生してしまいます。
源泉徴収は税率の適用や消費税や経費との関係など考えることが多く、会計や経理に携わったことがないと難しく感じてしまう場合もあるかもしれません。そのようなときには、講演サーチをはじめとする講演依頼のプロに相談してみましょう。
講演依頼のプロに相談することで、講師への支払いややり取りを委託できます。経験豊富なスタッフと講師が多数在籍している講演サーチでは、いつでも無料相談を承っています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

人気の講師

1位
佐藤 政樹
【劇団四季 元主役の感動創造トレーナー】

2位
村瀬 健
【放送作家・漫才作家】

3位
桂 三四郎
【落語家】

4位
安藤 美希子
【株式会社日動電設/ウエイトリフティング選手/オリンピアン/メダリスト】

5位
林家 鉄平
【落語家】
ジャンルから講師を探す
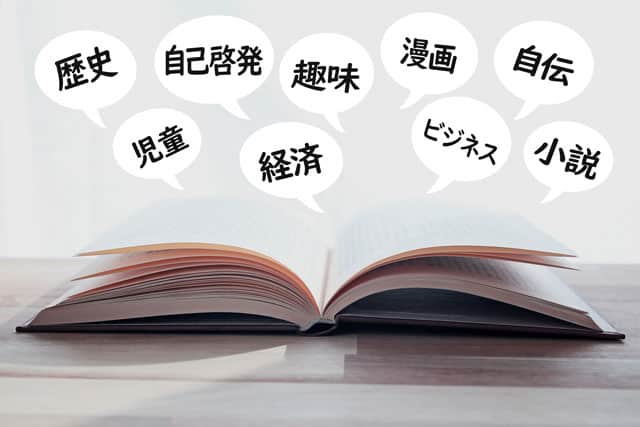 講演ジャンル |
|---|
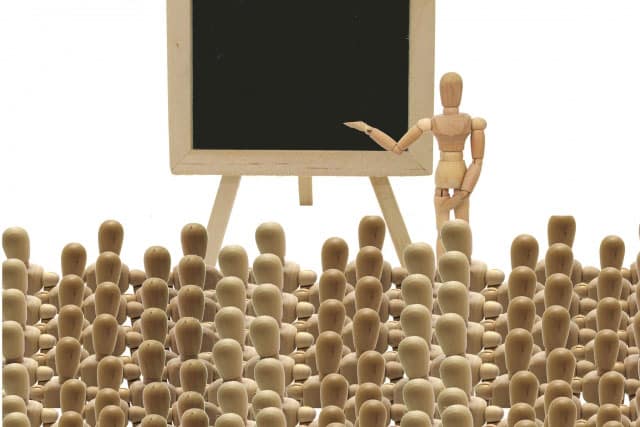 受講者 |
|---|