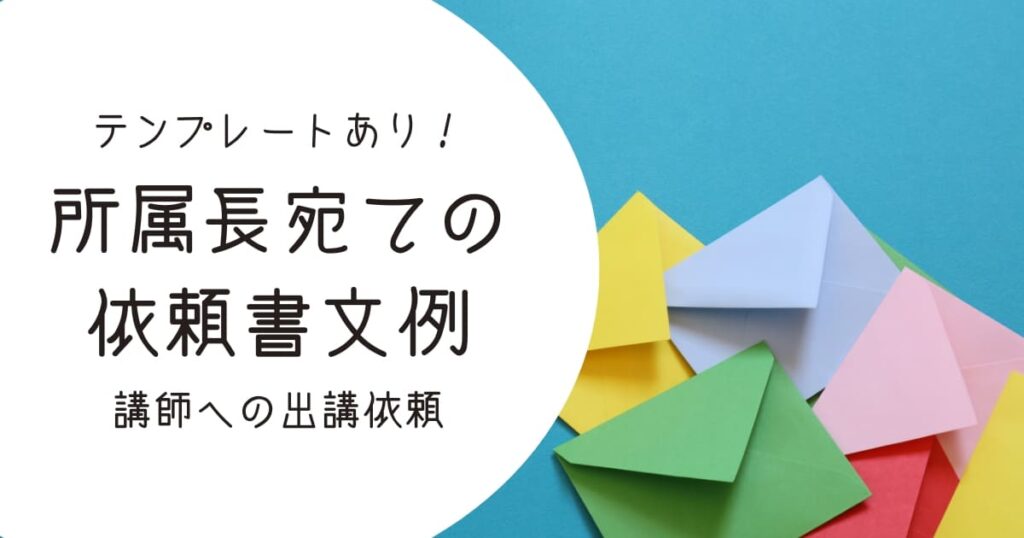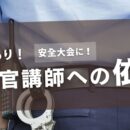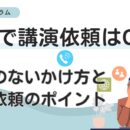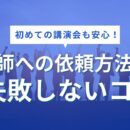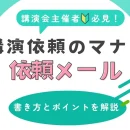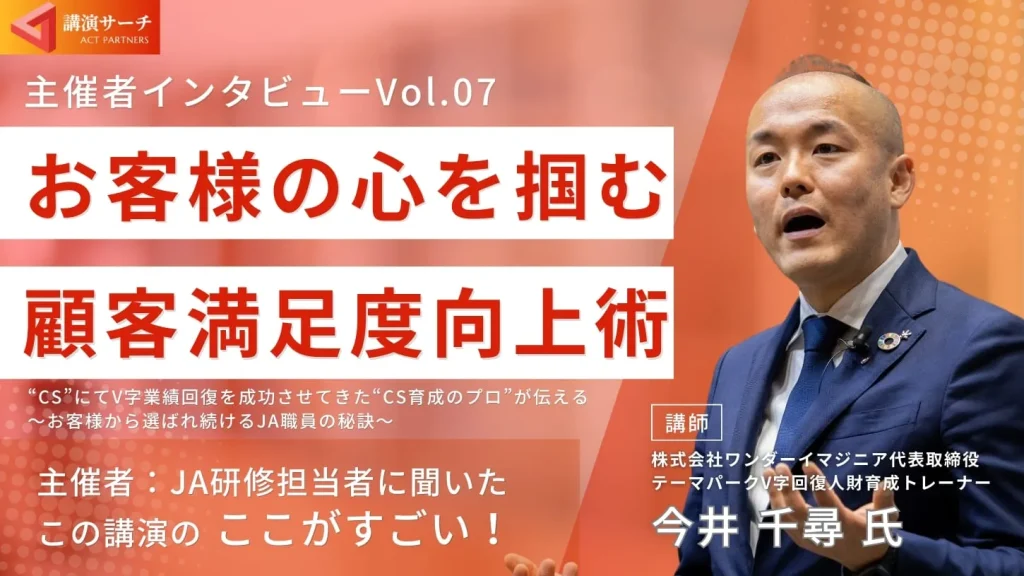講師本人宛の講演依頼文の書き方!依頼時のマナーやよりよい依頼方法を解説

講演会や研修で外部講師を招く際、最初の難関となるのが講師への依頼文作成です。
「どのような内容を書けば良いのか」「失礼にならない依頼方法は?」と悩む主催者の方も多いのではないでしょうか。
講師派遣の依頼は、単に「講演をお願いします」と伝えるだけでは不十分です。講師が快く引き受けてくれるよう、必要な情報を適切に伝え、相手への敬意を示すことが重要です。
本記事では、講師本人への依頼文の書き方から送付方法、押さえておきたいマナーまで、講師派遣依頼の全てを初心者向けに詳しく解説します。実際の依頼で役立つ具体的なポイントもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
講師本人に突然連絡をとるのは避けたい・人的コストを削減したい場合は、講師派遣会社のエージェントにご依頼ください。
講演サーチは、ご予算やご希望に合わせた講師・講演テーマをご提案いたします。失敗しない講演・研修を実現したい方は、お気軽にご相談ください。
講師本人宛の講演依頼文の書き方!依頼時のマナーやよりよい依頼方法を解説
目次
講師派遣の依頼書は誰に送る?
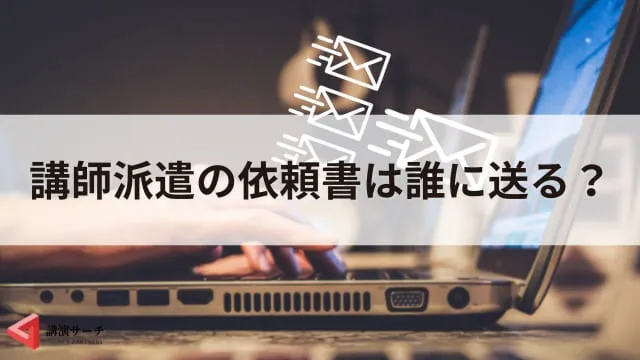
講師派遣の依頼書は、フリーの講師であれば講師本人に送り、組織などに所属している場合は講師本人と所属長の二人に送るのが一般的です。
「講師への依頼であれば本人だけでよいのでは?」と思うかもしれませんが、組織などはチームで動いています。急にチームに穴が開いてしまうと、組織に迷惑がかかってしまいますね。
迷惑をかけないためにも、本人だけでなく所属長にも依頼を送り、把握してもらわなければなりません。
また、その場合の依頼書は必ず本人と所属長の二人に別々で送ります。同じ組織だからといって1通だけで済ませるのは失礼にあたるため注意が必要です。
講師派遣の依頼書の送付方法
依頼書の送付方法は、郵送かメールとするケースが多いでしょう。電話依頼の場合もありますが、メジャーとは言えません。
郵送の場合、本人や所属先の休みなどを理由に、確認まで時間がかかる可能性があります。特に夏季や冬季の長期休暇期間が近い場合は、余裕をもって送るとよいですね。
メールの場合も同様で、長期休暇中はメールチェックがされない可能性があるため注意しましょう。
メールは他のメールに埋もれてしまって見てもらえない可能性もあります。埋もれないためにも、目を通しやすい件名にすると効果的です。
本人宛の講師派遣依頼書に記載する内容

依頼書には記載すべき内容があります。
記載内容の例は以下のとおりです。
・主催者名
・日時や場所
・講演会を開催する目的
・講話いただくテーマ
・参加者の人数や属性
・謝礼
これらの内容は講師を受けるかどうかの判断材料となるため、忘れないよう心がけたいですね。
講師を選んだ理由もプラスして記載すると、ポジティブな印象や希望が伝わりやすくなります。どういった点に魅力を感じ、どういった期待を込めて依頼をしたのか伝えられると承諾の後押しになりますよ。
講師に依頼する前に明確にしたいポイント
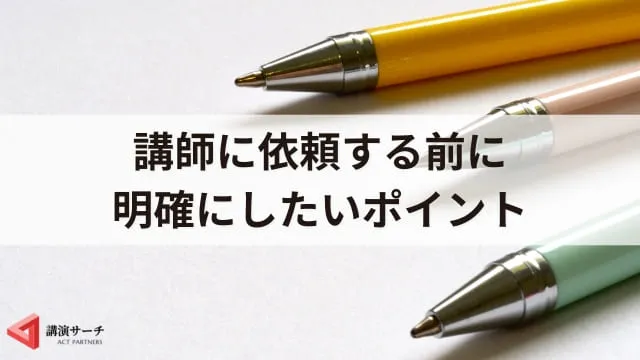
講師に依頼するには依頼書が必要ですが、依頼書を書く前に明確にしておくポイントがいくつかあります。
ポイントを明確にしておくと、講師が依頼を引き受けてくれる可能性が高まります。
日時や場所などの必要事項
依頼書は、講演会を開催する日時や場所などの最低限の内容が決まってから作成します。
例えば、日時が曖昧なままだと、講師側もスケジュール調整ができずに検討が難しくなります。
講演依頼を受けても具体的な日時や場所がわからないと、スムーズな返答ができないため、回答しやすい配慮が大切です。
講演会の目的やゴール
講演会の目的やゴールも明確にしておきたいポイントであり、講師にも必要な情報です。
講師はただ依頼されたテーマで講話をするだけではありません。主催者側の求める目的やゴールが達成できるよう、話す内容を考えて話をしてくれています。
そのため、目的やゴールを明確にして講師にも伝えておくと満足度が高まります。
講演会に参加してもらいたいターゲットのおおよその予定人数や属性も伝えておくと、より効果的です。
講師に期待すること
講師に期待することも明確にしておきたいポイントです。目的やゴールと異なり、主催者側がその方を講師に選んだ理由を明確にできるとよいでしょう。
講師選定の際は、プロフィールなどを見て、どの講師に依頼するか決めるのが一般的です。その際に「経歴がテーマに合っている」や「実体験を元にした話が聞けそうだ」など、講師に対する期待があって選定することが多くあります。
例えば、“実体験を元にした話が聞けそう”と思って指名したのであれば、その講師の「経験談や失敗から得た学びを話してほしい」と明確に伝えることが大切です。
本人宛に講師依頼する際のマナー

本人宛に講師依頼をする際、失礼がないようにしたいものです。講師に失礼な印象を与えないためにも、依頼時のマナーを意識すると安心です。
なるべく早く依頼する
講師への依頼は、なるべく早く行いましょう。講師は忙しい方も多く、スケジュールもすぐに埋まってしまう方も少なくありません。
講演会まであまり時間がないと講師も準備ができず、満足のいく講演会ができません。講師に引き受けてもらうため、満足度の高い講演会にするためには早めのアクションが大切です。
そのためには、必要事項が決まる前から講師探しを始めておき、希望講師の優先順位をつけておくとよいですね。
断られる可能性も考慮する
講師に講演依頼を送っても、断られる可能性がある点に注意が必要です。
特に、人気の高い講師はスケジュールがすぐに埋まりやすいです。断られる可能性も考慮して、講師は何人か選定しておくと安心ですね。
もし講師に出講を断られた場合は、相手に配慮した言葉をかけ、次回の開催時につながるように心がけましょう。
同時に複数の講師へ依頼しない
同時に複数の講師へ依頼しないのも大事なマナーです。確実に講師を確保するために、「一度に複数の講師へ講演依頼をすると効率的だ」と考えがちではないでしょうか。
しかし、複数の講師へ依頼して、もし全員が引き受けてくれたらどうなるでしょうか?
こちらから依頼したにもかかわらず、一人ひとりに断りの連絡を入れなくてはなりませんね。そうなると失礼にあたるうえに、主催者側の信頼がなくなってしまいます。
もし、また同じような講演会を開催するときに引き受けてもらえなくなるかもしれません。今後を考えて講師と良好な関係を保っておくために、複数の講師へ同時に依頼するのは避けましょう。
依頼後に依頼内容を変更しない
依頼後に依頼内容を変更しないのも大事なマナーです。
例えば、日時や会場などの基本的な内容や講演のテーマなどが変更になると、講師に迷惑をかけてしまいます。
「懇親会へ参加してほしい」など、講演会と直接関係がなくとも、希望があれば事前に相談すると親切です。
講師の予定を直前に崩さないよう、配慮を欠かさないように心がけたいですね。
講師への講演依頼は講演サーチへ
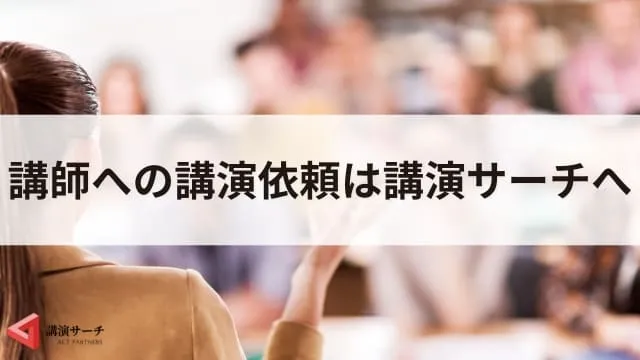
講師本人に依頼する場合、さまざまな点に注意して依頼書を作成する必要があります。講師への依頼に慣れていないと、依頼書の作成に時間がかかります。マナー違反で講師に不快な思いをさせてしまうかもしれません。
依頼書の作成にお困りの方や不安な方、講師とのやり取りの手間を削減したい方は、講師派遣や講演依頼をサポートする講演サーチにご相談ください。
講演サーチには、豊かな経歴をもったさまざまな講師が多数登録しています。講師との関係性も構築されているため、面倒な講師とのやり取りを任せて主催者の負担軽減も可能です。
まとめ
本人宛に講師派遣依頼をする際のマナーや方法を紹介しました。講師派遣の依頼は、依頼書の作成が必要です。講師に「引き受けたい」と思ってもらうためにはさまざまな点に気を配る必要があります。
講師本人とのやり取りにおいては、価格交渉やスケジュール調整、講演テーマ内容の打ち合わせなど、さまざまな工程が必要です。そのため、通常業務と並行しながら講演会準備を進めるのは容易ではありません。
講師とのやり取りや自社の課題や目的に適した講師や講演会テーマをお探しの方は、ぜひ講演サーチにご相談ください。
講演サーチでは、無料相談よりご希望やご予算を伺ったうえで業界経験豊富なエージェントがおすすめの講師や講演テーマを複数ご提案しています。お気軽にご相談ください。
人気の講師

1位
多湖 弘明
【株式会社Office Hit 代表取締役】

2位
植木 奈緒子
【気象予報士/気象キャスター/元客室乗務員】

3位
舟津 昌平
【経営学者/東京大学大学院経済学研究科講師】

4位
笑福亭 笑助
【落語家】

5位
伊庭 正康
【株式会社らしさラボ 代表取締役】
ジャンルから講師を探す
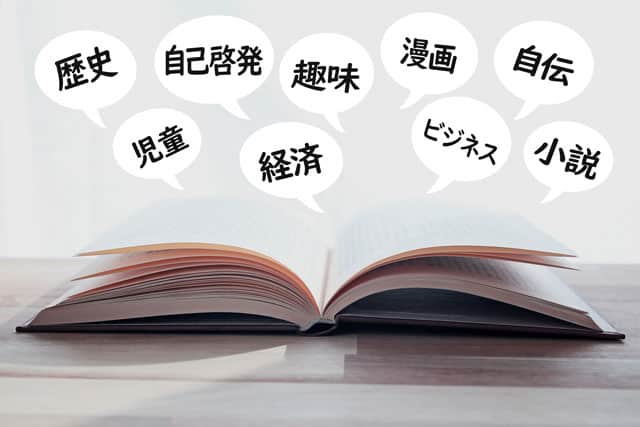 講演ジャンル |
|---|
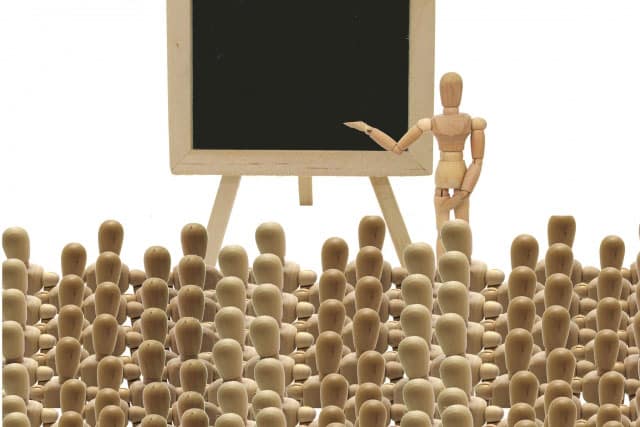 受講者 |
|---|