鎌田 敏 かまた びん プロフィール

鎌田敏(かまたびん)氏プロフィール
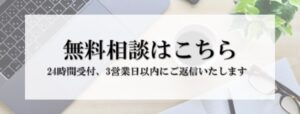
略歴
昭和43年生まれ。大阪育ち。岐阜市在住。株式会社エンパワーコミュニケーション代表取締役。こころ元気配達人・元気習慣アドバイザーとして、笑顔と元気をお届けすべく、全国各地で講演・研修活動を行う。
神戸大学卒業後、入社と同時にバブル経済の崩壊、いきなりリストラを経験。様々なアルバイト経験ののち、神戸大学大学院に進むが、卒業時に阪神大震災が襲う。神戸の地で「人生二度なし」の想いが心に刻まれる。その後、企業にて技術職、営業職、管理職に携わる。その間、パニック障害が発症し、格闘しながらの日々が続いた。様々な想定外の出来事を通して「人生は心のあり方ひとつでガラリと変わる」「自分から変わろうと行動することで扉は開く」ことに気づき、「こころ元気に積極的に生きる」ことの大切さをあらためて深く心に抱く。
平成17年3月「こころ元気研究所」を設立。すべての世代の笑顔と元気を応援すべく、こころ元気配達人として講演活動を始める。出会いに感謝の日々。現在、毎年2万人以上の方々へ元気講演を配達している。
「元気を分かち合う」べく、「楽しく、わかりやすく、ためになる!」をモットーに、90分も“アッ”という間の元気講演をお届けしています。産業カウンセラー、心理相談員、認定コーチなどの資格をもつ。日本産業カウンセラー協会正会員。
講演スタイルはみんなが笑顔になる参加型講演。また講演だけでなく研修講師・組織活性化ファシリテーターとして明るく元気な職場づくりを応援するために、ポジティブ組織開発、レジリエンス、メンタルヘルス、チームビルディング、リーダー研修などにも力を入れている。
講演テーマ
安全大会向け
楽しく学ぼう!安全・安心で活力ある元気職場づくり! ~ゼロ災の出発点は、心身の健康と職場の絆~
想定する受講者
安全大会参加者の皆さん
講演内容
仕事において、心身の健康は資本。そしてイキイキとした元気な職場は、仲間の「絆」を深め、「モチベーション」が高まりますので、「ゼロ災」「人材定着」にもつながります。「安全・安心、ゼロ災」に向けては、まずはひとりひとりの「心の安全」「体の健康」、そして「職場の元気」が出発点となります。コミュニケーションエラー防止、パワハラ防止なども交えながら楽しく学習していただきます。
講演内容
■仕事は人間関係に始まって人間関係に終わる
・安全意識について/意識していなければ気づかない、見えていない
・コミュニケーションエラー防止
■人と職場の元気力を高める ~安全は心の健康から~
・やる気のない人はいない/気がきく力を高める(共感力・協働力)
・安全意識やビジョンの共有/職場の絆について
・心の安全(健康)について/脳を休める/プラス思考/心身一如の方程式
・「元気を出す」と「元気は出てくるもの」/心の安全と人間関係
・ほめる/叱る/怒りのコントロール(アンガーマネジメント)
・あれダメ、これダメばかりだと萎縮する!萎縮は危険/コンプライアンスやパワハラ防止のポジティブアプローチ
■当事者意識と行動
・すべては小さなことの積みかさね
・他人事から自分事へ/ゼロ災への空気づくり
アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)に気づき、 コミュニケーションエラー・ヒューマンエラーを防止しよう!
想定する受講者
安全管理者、現場第一線の方々
受講者へ伝えたいこと
ヒューマンエラーの大きな要因である「うっかり」「不注意」「コミュニケーションエラー」。これらはなぜ起こるのか?
「私なら大丈夫」「私には無関係」「前も大丈夫だったから今回も大丈夫」「彼らがやるだろう」「言わなくても分かるだろう」
「これくらい出来るだろう」などの無意識の思い込み(アンコンシャスバイアス)が原因です。
アンコンシャスバイアスは誰にもあることです。「最近の若者たちは根性が足りない」「血液型がA型の人って几帳面だよね」「シニアはパソコンが苦手だよね」などなど。こんなふうに思ったことは無いでしょうか。
これらは実は、すべて無意識の思い込みです。しかし、立ち止まって考えれば、この思い込みと逆のケースがたくさんあることに気づきますよね。
無意識の思い込みは、だれにもあることでそれ自体が悪いわけではありませんが、場合によっては、トラブルにつながることも多いのです(本人はそんなつもりではなかったとしても)。
「これくらい言わなくても分かるだろう」という無意識の思い込み・・・でも実は、相手はその課題には具体的に指示しても らわないと出来ないケースだってあるのです。
「いつも大丈夫だから今回も大丈夫」「私は慣れてるから、大丈夫」という無意識の思い込み・・・意識が対象に向いてい ないいい加減な指差喚呼につながったりします。今回も大丈夫という保証はどこにもありません。
立ち止まって、アンコンシャスバイアスに気づき、上手く付き合うことが「うっかり」「不注意」「コミュニケーションエラー」を改善し、ヒューマンエラー防止につながります。
アンコンシャスバイアスを体感していただくことで気づきにつながります。そして上手く付き合う方法を学ぶことで、ヒュー マンエラー防止に役立てていただきます。
講演内容
(60分~90分の例)
■ウォーミングアップ「無関心は最大のNGと“気を付ける”の意味について」
■人は意識したものしか見えていないヒューマンエラー防止①「意識する」
■アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)に気づく
■コミュニケーションエラーを改善する(伝えるから伝わるコミュニケーションへ) ヒューマンエラー防止②「苦手ではなく、練習不足」
ヒューマンエラー防止③「あいまいな指示でなく、具体的な指示」ヒューマンエラー防止④「分かったつもりでなく、確認する」
■思い込みや未知を減らし、理解を増やす(共有する) ヒューマンエラー防止⑤「話し合う、聴き合う」
■確認動作はアンコンシャスバイアスの影響から離れる基本の型 ヒューマンエラー防止⑥「安全意識のスイッチ」
ヒューマンエラー防止⑦「集中力を迎えに行く」
■積小為大
ヒューマンエラー防止⑧「日々の小さなことの積みかさね」
■ゼロ災へ向けて
ヒューマンエラー防止⑨「当事者意識と行動」
今日から出来る!心理的安全性を高める仕事術 ~アップデートしていく人や組織~
想定する受講者
従業員全般
労働組合の組合員
受講者へ伝えたいこと
✔風通しの良い職場づくりに向けて自分たちが取り組むべきことがわかる
✔協力し合える職場は生産性の向上につながることを再認識できる
✔心理的安全性について学ぶことは、エンゲイジメント(仕事や組織に対する愛着心)を高めるだけでなく、メンタル不調、早期離職、ハラスメント、コンプライアンス違反の防止にもつながる
✔安心して働ける職場づくりに役立てることができ、今日から活かせる考え方や実践的スキルを習得することができる
講演内容
1.今の自分は何で出来上がっているか
・信用と信頼の違い
・積小為大(目的は「大」、大切なのは「小」)
・自分や組織の未来像を描こう
・犯人捜し(問題思考)ではなく未来へ向けての解決志向アプローチ
2.心理的安全性とは
・所属していることと心の居場所があることとは違う
・組織の成功循環モデル
・心理的安全性について
・コミュニケーションの報酬を意識しよう
3仕事は人間関係に始まって人間関係に終わる!
・コミュニケーションエラー防止
・声かけと声のかけられやすさ
・より良い人間関係づくりにおいて大切なポイント
・自分の指先はどこを向いているか
4.心理的安全性の中でアップデートしていく人や組織
・欠点凝視と美点凝視
・人はみな学び続ける
・人はみなダイヤモンドの原石
・仲良しクラブではなく、健全に磨き合う
・人や組織の元気力と生産性向上のために
5.大切なことを大切にする
・感謝の心
・(まとめ)心理的安全性を高めるKSCの法則
メンタルヘルス関連
レジリエンスを高める仕事術~折れない心を育むために~
レジリエンスとは、ストレスに対応する力のことで、回復力や柔軟性、適応力などが含まれます。竹のようなしなやかな強さのことです。
すべてのビジネスパーソンにとって大切なレジリエンスについて、レクチャーだけでなく、楽しいワークなどを通じて学んでいただき、明日への行動に活かしていただきます。
レジリエンスを高める仕事術 ~早期離職予防と人材定着のために~
想定する受講者
・ビジネスパーソン(特に人材育成担当者の皆さん)
・労働組合 執行部役員の方々(中央執行委員長以下、中執の皆さん)
受講者へ伝えたいこと
・「折れない心の育て方」をご存じですか?今、逆境から立ち直る力、「レジリエンス」に大きな注目が集まっています。レジリエンスとは、ストレスに対応する力のことで、回復力や柔軟性、適応力などが含まれます。竹のようなしなやかな強さのことです。
・様々な業界の共通課題でもある「早期離職防止」と「人材定着」。職場づくりや人財育成においては「悩みごとの解決」
「望みごとの実現」の2つの目的で取り組みことが大切と考えております。
・個々のレジリエンスとともに人材定着に欠かせない、『組織に所属」しているだけでなくそこに「心の居場所」があることが大切』(関係性からのレジリエンスになります)というアプローチやそのためのあり方にも触れさせていただきます。
講演内容
●STEP-1 コミュニケーションとメンタルヘルス
・職場の空気づくり/空気も仕事をしている/働く人にとって良い空気は、お客様にとっても良い空気
・コミュニケーションエラー防止のために/「声かけ」と「声のかけられやすさ」(相談されやすさ)
●STEP-2 元気力を高める(1)月曜の朝から皆が元気に出勤してくる職場づくり
・「やる気のない人はいない」は本当です/理由を探り対処するために
・傾聴「まず正そうとするな、分かろうとしよう」/共感力/安心感、信頼感/心の扉をひらく
・職場の絆とは/「心のサポーター」の存在/「元気を出す」(自律性)と「元気は出てくるもの」(関係性)
・心のエネルギーが下がる人間関係の原因が相手ではなく自分にもあるとしたらそれは何かを自ら問う ことが本当の改善につながる/心の居場所がないと感じる新人や若手の心理と行動パターン
・所属しているだけでなく、そこに「心の居場所」があることが早期離職やメンタル不調予防につながる
・月曜の朝からみんなが元気に出勤してくる職場づくりにおいて大切なこと
●STEP-3 元気力を高める(2)心と対話する・身体から心にアプローチする
・欠点凝視と美点凝視/苦手や失敗をどう受け止めるか(苦手⇒練習不足、失敗⇒未成功)
・心と身体、身体と心の関係/心のエネルギーを回復するためのレジリエンス2段階アプローチ
●STEP-4 当事者意識と行動
・レッツのコミュニケーション(Weメッセージ)で巻き込もう!
・他人事ではなく自分事/未来志向で望ましい姿へ向けて行動しよう!
レジリエンスを高める仕事術 ~ストレスに対応する力を磨こう~
想定する受講者
・ビジネスパーソン全般
・労働組合 組合役員の方々(職場委員、分会長、職場代表・・・など代議員の皆さん)
・労働組合 若手~中堅組合員
受講者へ伝えたいこと
レジリエンスとは、ストレスに対応する力のことで、回復力や柔軟性、適応力などが含まれます。竹のようなしなやかな強さのことです。すべてのビジネスパーソンにとって大切なレジリエンスについて、レクチャーだけでなく、楽しいワークなどを通じて学んでいただき、明日への行動に活かしていただく。
講演内容
■仕事は人間関係に始まって人間関係に終わる
・心は空気感染する/職場の空気は創るもの
・コミュニケーションギャップ体感/「攻め」の報連相/「あいさつ」の教え
■レジリエンスを高める仕事術(1)
~コミュニケーションの本質とストレスをパワーに変えるアプローチ~
・コミュニケーションの本質/理解と共感、ビジョンの共有、絆、一致団結、組織一丸
・未来を先取りしてempower(他燃力)
・壁の向こう側、仕事や組合活動の向こう側/「何のために、誰のために」(自燃力)
・ポジティブシンキング/壁は成長の糧/「未見の我」と出会う/失敗と未成功
・解決志向の「How」/Can I do it?/How can I do it?
・目標設定理論とモチベーション/その落とし穴と対処法
■レジリエンスを高める仕事術(1)
・傾聴(1):聴くは相手の話を引出す能動的なコミュニケーション
※やる気のない人はいない???
・傾聴(2):心得「まず正そうとするな、分かろうとせよ」
※共感のコミュニケーション
・メンタルヘルス:心身一如の方程式/脳のトラブルを予防/話す=放す
・モチベーション:「元気を出す」と「元気は出てくるもの」
・心のエネルギーと豊かな人間関係/みんながみんなの応援団/心のサポーター
職場を元気にするメンタルヘルス
講演内容
※気づきを深めていただく参加型ワーク満載です
※主催者様の要望により「セルフケア」に重きを置いた講演、または「ラインケア」に重きを置いた講演など柔軟に対応しております。
(例えば…)
■コミュニケーション体感ゲーム
■心の体力
・プラスのストローク、元気は人からいただいている
■まずは、相手を知ろう!脳とストレスの仕組み
・脳が“NO!”と悲鳴を上げる前に!
・身体はメンタル・メッセージを発している
■「絆」「元気」コミュニケーション!
・豊かな人間関係は心の健康の土台ですね
・信頼関係・気持ちに寄り添う、会話の力、職場の空気
■身体からコントロール~心身一如の方程式~
・いつでも出来る!簡単、心の健康法!
■元気な人の共通点とは?
・モノの見方・考え方
・ストレスをパワーに変える!ポジティブシンキング
■メンタルタフネス~ぶれない自分軸~ などなど...
知って得、やって納得!メンタルヘルス
想定する受講者
ビジネスパーソン
受講者へ伝えたいこと
ストレス社会において、心の健康を保つ(メンタルヘルス)ためには、ストレスをマネジメントしていくことが大切です。なかでも最も大切なのが、メンタル・セルフケア・・・自分自身がいかにストレスに対処していくか・・・です。
風邪の予防・対処を行なうのと同じようにストレスの予防・対処について、知っておくこと、そして実践していくことが大切なのです。
講演内容
心も空気感染する、職場の空気づくり
・ストレス解消法は複数のバリエーションがあるほうがいい
・心の病って?
・脳のトラブル、脳を休めるための提案
・心の健康にとって、人間関係こそ肝心要
・ストレスマネジメント(1)ポジティブ思考
・ストレスマネジメント(2)心身一如の方程式:身体、行動から心をコントロール
・明日への行動のために
※レクチャーだけでなく、楽しいワークを通して、より気づきを深めていただくスタイルいつでもどこでも出来る心の健康法などの実技も!
職場を元気にするメンタルヘルス&コミュニケーション ~よりよい職場づくりのために~
講演内容
■仕事は人間関係に始まって、人間関係に終わる♪
・コミュニケーションギャップ体感
・「あいさつ」に学ぶこと
■絆こそ宝&職場元気コミュニケーション
・理解と共感のコミュニケーション体感
・メンタルヘルス(ラインケア)
・人から元気をいただいている、元気は分かち合うもの(コミュニケーション報酬)
・豊かな人間関係が心の健康にとって一番大切ですね
■ストレスマネジメント法則1「モノの見方・考え方」
・エレベータークイズ
・ポジティブシンキング
■ストレスマネジメント法則2「心身一如の方程式」
・身体、行動から心をコントロール
・筋弛緩法(リラックス)、立腰(心のスイッチ)
■JUMP☆WORK ~当事者意識と行動~
・メンタルも空気感染します
・元気な職場の空気づくり!
■仕事の向こう側 ~メンタルタフネスとモチベーション~
・何のために、誰のために!
動画URL:http://
■テーマページhttp://www.sbrain.co.jp
ストレスコントロールで心のパワーを高めよう!
想定する受講者
ビジネスパーソン
ストレス社会において、心の健康を保つ(メンタルヘルス)ためには、ストレスをコントロールしていくことが大切となっている。
なかでも最も大切なのが、セルフメンタルサポート。自分自身がいかにストレスに対処していくかである。
受講者へ伝えたいこと
見方を変えればストレスとは自身の「成長の糧」とも言えるのです。 どうせなら、ストレスをモチベーションに変えてやりましょう!
問題思考ではなく解決思考でストレスに対処していくことは、ビジネスのトレーニングにもつながります。 自身の経験も交えた、メンタルヘルスの知恵をお話します。
講演内容
○まずは、相手を知ろう!脳とストレスの仕組み 脳が“NO!”と悲鳴を上げる前に!
○身体はメッセージを発している警告を無視してはいけません
○ストレスコントロール(1)「身体からコントロール」心身一如の大原則!リラクセーション
○ストレスコントロール(2)「元気な人の共通点とは?」木ばかり見てないで、森を見よう!
○ストレスコントロール(3)「ストレスをモチベーションに変える技」質問が変われば答えが変わる!問題思考から解決思考へ
○こころ元気に生きる知恵 「一隅を照らす」生き方
元気な心で元気な毎日 ~心のリフレッシュ術~
想定する受講者
一般市民
受講者へ伝えたいこと
■脳トレ・リフレッシュ&笑顔のコミュニケーション☆体感ゲーム
■「ありがとう」は魔法の言葉!
・生きがいと絆(人と人とのつながり)
■元気な人の共通点とは
・欠点だけでなく、美点をみつめよう!
・元気は伝染します
■今日から出来る、簡単!心の健康術
・リラクセーション
・元気が出る方法
・呼吸/息
■自分の番 いのちのバトン
~人と人との「つながり」の中で、支えあう生き方・分かち合う生き方~
「絆こそ宝」 ~組織活性化は、人と人とのつながりが出発点!~
想定する受講者
・労働組合 若手組合員
・ビジネスパーソン 若手従業員の方々
企業の資本・財産といえば、ヒト、カネ、モノと言われてきましたが、最近ではそこに知識・情報(知的資本)が加わっております。
そして現在、これらに対して社会関係資本という存在がクローズアップされています(時代が求めている!)。社会関係資本とは、人間関係(人と人とのつながり)...つまり、「絆(きずな)」です。
受講者へ伝えたいこと
絆あってこそ、すべてがイキイキ躍動します。
絆という人と人との温かいつながりは、人が誰しも持っている基本的欲求(愛と所属の欲求、認められたいという欲求、楽しみたいという欲求等々)を満たしてくれる土台だからです。
職場の絆は、個々のモチベーション、メンタルヘルスなどの向上につながり、さらには集団のイキイキとした感情(職場の空気)、協働、ダイナミズム(1+1が3にも4にもなる)につながっていく。
まさに、絆なくして、成長なし!なのです。
そして、絆のキモこそ、一人ひとりの心のあり方であり、コミュニケーションなのです。
講演内容
≪講義と参加型たっぷりの講演スタイル≫ 例えば…
・笑顔あふれるワクワク系☆コミュニケーション体感ゲーム
・時代は求めている~ヒト、カネ、モノだけでいいの?~
・絆が育む「5つの力」
・職場の元気~ストロークは、個人だけでなく職場の感情も変える~
※ストローク体感
・心のあり方~美点凝視と共感~
※ペアワーク(プラス発信と傾聴)
・JUMP☆ワーク~絆と自発的行動への気づき~
・絆こそ宝~支え合う・分かち合う生き方~
・ありがとうは魔法の言葉~一隅(いちぐう)を照らす仕事と人生~
※ワークについては、スキルの習得というよりも、絆、一体感、自己肯定感などを味わうなかで「気づき」を深めていただくことを狙いとしています。
コミュニケーション関連
アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)に気づき、 コミュニケーションエラーを防止しよう!
想定する受講者
組合役員の皆様
職場委員、職場リーダーの皆様リーダー層の皆様
受講者へ伝えたいこと
アンコンシャスバイアスは誰にもあることです。「最近の若者たちは根性が足りない」「血液型がA型の人って几帳面だよね」「シニアはパソコンが苦手だよね」などなど。こんなふうに思ったことは無いでしょうか。
これらは実は、すべて無意識の思い込みです。しかし、立ち止まって考えれば、この思い込みと逆のケースがたくさんあることに気づきますよね。
無意識の思い込みは、だれにもあることでそれ自体が悪いわけではありませんが、場合によっては、トラブルにつながることも多いのです(本人はそんなつもりではなかったとしても)。
「これくらい言わなくても分かるだろう」という無意識の思い込み・・・でも実は、相手はその課題には具体的に指示してもらわないと出来ないケースだってあるのです。
講演を通して、アンコンシャスバイアスを体感していただくことで気づきにつながります。そして上手く付き合う方法を学ぶことで、組織改善に役立てていただきます。
講演内容
(60分~90分の例)
■ウォーミングアップ「無関心は最大のNGと“気を付ける”の意味について」
■人は意識したものしか見えていない
■アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)に気づく
■コミュニケーションエラーを改善する(伝えるから伝わるコミュニケーションへ)
■思い込みや未知を減らし、理解を増やす(共有する)
■アンコンシャスバイアスの影響から離れる基本
■積小為大
■総括
職場を元気にするコミュニケーション
講演内容
例えば...
■笑顔あふれるワクワク系☆コミュニケーション体感ワーク
■コミュニケーションギャップ体感
■仕事は人間関係に始まり、人間関係に終わる
■「挨拶」の本当の教え
■「絆」「元気」コミュニケーションワーク、元気は分かち合うもの
■コミュニケーションの本質
■積小為大、職場の空気づくり
■ジャンプ☆ワーク~当事者意識と行動~
■仕事の向こう側とモチベーション
※楽しい参加型ワークを交えながら、気づき満載の笑顔の時間です!
今日から出来る! 心理的安全性を高めるためのリーダーのコミュニケーション ~人と組織の元気力と生産性向上のために~
想定する受講者
管理職
労働組合役員
リーダーの方々
受講者へ伝えたいこと
✔風通しの良い職場づくりに向けてのリーダーの役割と行動がわかる
✔生産性の向上において大切な協力し合える職場づくりにおける自身の役割と行動がわかる
✔心理的安全性について学ぶことは、メンバーのエンゲイジメント(仕事や組織に対する愛着心)を高めるための考え方の習得につながり、メンタル不調、早期離職、ハラスメント、コンプライアンス違反の防止にもつながる
✔組織には2種類のコミュニケーションがあることを理解し、上手く使い分けることができるようになる
✔安心して働ける職場づくりに役立てることができ、今日から活かせる考え方や実践的スキルを習得することができる
講演内容
1. リーダーにとってなくてはならない大切なものとは
・大切なことを大切にする
・リーダーは組織のコミュニケーション回路の要
・組織における2種のコミュニケーションを理解していますか?
2. 心理的安全性とは
・所属していることと心の居場所があることとは違う
・組織の成功循環モデル
・心理的安全性について
・コミュニケーションの報酬を意識しよう
3 仕事は人間関係に始まって人間関係に終わる!
・コミュニケーションエラー防止
・「攻めの報連相」と「YES-AND法」
・声かけと声のかけられやすさ
・より良い人間関係づくりにおいて大切なポイント
・信用と信頼について/信頼の階段から落ちるとき
4. 心理的安全性の中でアップデートしていく人や組織
・欠点凝視と美点凝視
・人はみな学び続ける
・人はみなダイヤモンドの原石
・仲良しクラブではなく、健全に磨き合う
・人や組織の元気力と生産性向上のために
・自分や組織の未来像を描き、考動する!
5. まとめ
・心理的安全性を高めるKSCの法則
~医療・福祉現場で働く人の笑顔のために~ 職場元気コミュニケーション&メンタルヘルス
想定する受講者
医療・福祉関係者
受講者へ伝えたいこと
対人援助の現場では、医療関係者の心の状態、つまり、心の健康、元気や笑顔が大切になってきますね。そしてその源は、個々の仕事に対する目的意識と職場における豊かな人間関係にあります。これは同時にコミュニケーション、メンタルヘルス、モチベーション、組織活性化と深く関わっているのです。お互いの心のエネルギーが高まる人間関係を中心にお伝えしていきます。
講演内容
レクチャーだけでなく楽しいワークを通して気づきを深めていただきます。笑顔いっぱい咲きますよ。
・心も空気感染する、職場の空気は創るもの
・仕事は人間関係に始まり、人間関係に終わる
・コミュニケーションギャップ体感
・あいさつの教え
・職場を元気にするコミュニケーション
・豊かな人間関係とモチベーションについて
・ストレスマネジメントについて
・当事者意識と行動
※コミュニケーション、モチベーション、メンタルヘルスの複合技の内容ですが、例えばコミュニケーションに特化した内容等、ご要望に合わせカスタマイズさせていただきます。
※講演だけでなく、1日研修なども担当させていただく機会も多いです。
【組合役員向け】 組織と人の元気力を高めるメンタルコミュニケーション ~サポート・ケア~
想定する受講者
・職場の管理監督者、リーダー
・労働組合 組合役員の方々(職場委員、分会長、職場代表・・・など代議員の皆さん)
受講者へ伝えたいこと
リーダーには職場におけるコミュニケーション回路の要としての役割があります。メンタルヘルスにおいてもその役割は重要ですね。
人は自分のことを理解してくれたり、共感してくれたり、話をしっかり聞いてもらえることで、信頼関係の構築とともに、心のエネルギーが高まります。ラインケアの本質はここにあると僕は考えます。
したがって、ラインケアを今まで以上に建設的に位置づけるならば、メンタルヘルス不全への予防や対処だけが目的ではなく、個々のモチベーションやメンタルケア、職場の活性化にもつながる普段からの心に栄養を与えてくれるコミュニケーションということになります。
講演内容
仕事は人間関係に始まり、人間関係に終わる
・コミュニケーションギャップ体感
・コミュニケーションの本質について(ペアワーク)
・傾聴力「まず正そうとするな、分かろうとしよう」
・共感力「empathy(共感)は、empower(相手の心のエネルギーが高まる)につながる」
・サインに気づくために
・対人援助のコミュニケーションをロールプレイで体感学習(グループワーク)
・ふりかえりで傾聴力と共感力を高めよう
・ふりかえりで様々な価値観とふれあい、視野を広げよう
・心のエネルギーが高まる職場の空気づくり
※楽しいワークを交えながら、ラインケアの大切なポイントへの気づきを深めていただく参加型講演です。
リーダーの役割、リーダーのコミュニケーション ~よりよい職場づくりのために~
想定する受講者
企業の管理職、リーダー層
受講者へ伝えたいこと
仕事は人間関係に始まって人間関係に終わると言います。つまり「絆」です。
職場の絆は、個々のモチベーション、メンタルヘルスの向上につながり、さらには集団のイキイキとした感情(職場の空気)、協働、ダイナミズム(1+1が3にも4にもなる)につながっていく。本研修では、職場のコミュニケーション回路の要であるリーダーのあり方、リーダーのコミュニケーションについて、上機嫌な職場づくりについて気づき、学んでいただきます。
講演内容
STEP-1 リーダーのあり方とコミュニケーションの本質について
・ウォーミングアップコミュニケーション/気づきを深める
・リーダーのあり方について
・コミュニケーションの本質について
STEP-2 リーダーのコミュニケーションとモチベーションについて
・言語コミュニケーションのポイント/信頼のコミュニケーションについて
・絆を深め、モチベーションを高めるコミュニケーション
・やる気のない人は本当にいるのか?
STEP-3 メンタルヘルス・マネジメントと上機嫌な職場づくりについて
・健康な職場づくりと人間関係について
・脳がNOと悲鳴をあげないために/ストレスマネジメント
・上機嫌な職場づくりのアイデア
・積小為大/行動する主体・当事者意識
・ふりかえり
リスペクト・コミュニケーション
想定する受講者
従業員全般
労働組合の組合員
受講者へ伝えたいこと
・ハラスメント、メンタル不調などの防止につながる
・心理的安全性が高い職場につながる、ダイバーシティへの対応につながる
・エンゲージメント(仕事や組織への愛着心)が高まる
・安心して働ける職場づくりだけでなく、他者と共に生きる私たちにとって大切な心のあり方への気づきにつながる
人は自分を大切にしてくれる環境では、仲間や組織に貢献しようとがんばるものです。一方で、自分を大切にしてくれない、軽んじられていると感じる環境では貢献意欲はわかないどころか、心が疲れていきます。
Netflixは作品を制作する前に、関係者全員がリスペクト・トレーニングに参加していると話題になっています。リスペクト、つまり「相手に敬意を払えているか」という観点をふりかえるのです。ハラスメント防止だけにとどまらず、お互いが気持ちよく仕事をしていくことにつながりますので、より良いパフォーマンス、より良いチームにつながることが期待できます。
「respect」の語源は、「re」(後ろ)「specio」(見る)というラテン語です。つまり、リスペクトの語源には「ふりかえる」という意味があります。
「相手を大切に出来ているだろうか?」「そこにリスペクトはあるんか~?」と、「ふりかえる」時間を持つことで、自分のコミュニケーションの改善点、お互いを大切にするために自分たちが出来ることへの気づきにつながります。そして、自分を大切にするという視点も忘れてはいけません。
リスペクトを邪魔してしまうことがあるアンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)という自身のフィルターに気づき、修正していくことが大切です。より良い職場づくりに向けて、楽しく学習する時間をお届けします。
講演内容
内容例(90分~120分)
1. まずは、心を整える
・バタバタ、イライラしていると適切なコミュニケーションが出来ないことを再確認
・感情のコントロール
2. アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み)とは
・無意識の思い込みが前面に出過ぎるとコミュニケーションエラー、相手の不快につながることがあることを知ろう
・リスペクト・コミュニケーション【1】少し立ち止まって、自分に指を向けて確認(指先は相手だけでなく自分にも向けるもの)
3 そもそもリスペクトとは
・人はみな人生の主人公
・事例で考える(リスペクト・コミュニケーション【2】対話を通していろんな価値観と触れることが視野を広げ、気づきにつながる)
4. コミュニケーションエラー体感
・どう受け止めるかは相手次第というコミュニケーションの大原則を再確認
・リスペクト・コミュニケーション【3】他者からのフィードバックで気づく
5.リスペクトを支える思いやり、心配りを高める習慣
・思いやりや心配りは日々の習慣の中で身につくもの
6. 大切なことを大切にする
・人権感覚「周りにいる人たちが少しでも笑顔になるために自分ができること」
・感謝の心(人を大切に、自分を大切に)
・心は空気感染します/職場の空気はつくるもの
モチベーションを見える化! 自分や仲間のやる気を高める方法
想定する受講者
・経営者・管理職、職場のリーダー
・労働組合 組合役員の方々(職場委員、分会長、職場代表・・・など代議員の皆さん)
受講者へ伝えたいこと
「やる気を出す」ことに重点が置かれているモチベーション理論はうまく機能しないことも多い。なぜなら関係性の中で「やる気は出てくる」ものでもあるからです。
自己、ペア、グループという様々なフェーズでのダイアローグ(対話)の手法を通して「やる気は出てくる」体験していただき、自分や仲間の「やる気」のポイントを知り、「やる気」を高める方法を学習していただきます。
「モチベーションを見える化」することは、自身のレジリエンス(折れない心)を高めることにもつながります。
さらに、他者を尊重しながら、自己主張するダイアローグ(対話)を体験することで、若手の方々の共感コミュニケーション力、関係性構築力の向上に、組合役員の方々のフォロワ―シップ力、後輩指導力の向上にもつながります。
講演内容
①やる気を高める4つのアプローチ
・「心」と「身体・行動」について
・「やる気を出す」と「やる気は出てくるもの」について
②「成長実感」ダイアローグ(ペア)
・ヒーローインタビュー
・対話を通して、刺激、共感、学びを得る
・心のエネルギー
③「他者を通して自分を知る」ダイアローグ(グループ)
・他己紹介
・Goodのフィードバック効果
④「モチベーションを見える化」ダイアローグ(自己&グループ)
・やる気グラフ
・自分や仲間のやる気の源を知る
・組織のモチベーションの源(ポジティブコア)
・対話を通して、自分軸の再確認、再構築につながる
⑤当事者意識と行動する主体 ~他人事ではなく自分事へ~
・やる気は空気感染する、明るく元気な職場づくりへ
・他者や環境への変化を求める前に、まずは自分自身が変化する
こころほぐし からだほぐし~自らを癒すコツ~
講演内容
楽しく学ぶ参加型講演!
■さぁ、楽しくいきましょう
・元気は分かち合うもの(挨拶、笑顔、ありがとう、ねぎらいの言葉etc.)
・自尊感情↑↑⇒こころのエネルギー↑↑
■「絆」「元気」コミュニケーション~豊かな人間関係と心のエネルギーアップ~
・お題「趣味、ストレス解消法」
・気持ちに寄り添ってくれる人の存在
・豊かな人間関係は、心の健康にとってとても大切ですね♪
■心の健康法あれこれ
・モノの見方を変えてみる
・アンガーコントロール
・「心身一如」の方程式、身体・行動から心をコントロール
・いつでもどこでも出来る簡単、心身健康法
・息、呼吸(リラックス呼吸で副交感神経優位、息抜き)
・笑い(笑う門には福来る)
■「一怒一老」ではなく「一笑一若」でいこう!
・笑顔は空間だけでなく、人の心も明るくする
・笑顔の輪を咲かせましょう♪
組織開発・チームビルディング関連
チームビルディング・ポジティブ組織開発 一致団結と未来志向の組織づくり
想定する受講者
・労働組合 組合役員の方々(職場委員、分会長、職場代表・・・など代議員の皆さん)
・チーム力を高めたい管理職、リーダー層
受講者へ伝えたいこと
仕事は人間関係に始まって人間関係に終わると言います。つまり「絆」です。「職場の絆」は、個々のモチベーション、メ ンタルヘルスの向上につながり、さらには集団のイキイキとした感情(職場の空気)、協働、ダイナミズム(1+1が3にも4にもなる)につながっていく。
さらには、ハラスメント防止へのポジティブなアプローチにつながります。防止対策として、あれはダメ・これはダメという アプローチも大切ですが、より一歩進んで、この組織で、あの人たちと一緒に働けてハッピーだというアプローチ、つまりそうした組織づくり、人間関係づくりが大切となります。
本研修では、課題解決に向け情報共有と協力し合うことで一致団結を体感し、それぞれの役割を全うすることの大切さ を学ぶ。また、組織をネガティブな視点で捉えるのではなく、未来志向のポジティブな視点で捉え、未来へ向けての組織 や個人の具体的なアクションにつながる組織づくりをめざす。
講演内容
STEP-1 チーム力を高めるコミュニケーション
・協力ゲームでチーム力を高めるコミュニケーションへの気づきを深める
・情報共有のポイント ~伝えると伝わる~
STEP-2 チームビルディング
・風通しの良い職場づくり
・協力すれば、衆知を集めれば、突破力が高まる
・先端実験ワークショップによるチームビルディングへのアプローチ
STEP-3 ポジティブ組織開発
・自己理解ワークシート
・理想の未来を共有しよう(Dream)
・ビジョン・行動計画の策定(Design)研修バージョン
・ふりかえり
働き方改革の出発点は、健康職場づくり! ~人と組織の健康が思考・行動・生産性の向上へのグッドサイクルの 流れを作る~
想定する受講者
企業内全階層、ビジネスパーソン
受講者へ伝えたいこと
労働人口が劇的に減少している日本社会において、「早期の離職防止」「人材の定着」は様々な業界の大きな課題と なっています。そして、「働き方改革」とは、労働人口が減少していく中でいかに生産性を高めていくかが本丸です。両課 題にとって「健康職場づくり」、つまり人と組織がイキイキしていることが大切になります。
仕事は人間関係に始まって人間関係に終わると言います。つまり「絆」です。健康職場における「職場の絆」は、個々のモチベーション、メンタルヘルスの向上につながり、さらには集団のイキイキとした感情(職場の空気)、協働、ダイナミズム(1+1が3にも4にもなる)につながっていく。さらには、ハラスメント防止へのポジティブなアプローチにつながります。防止対策として、あれはダメ・これはダメというアプローチも大切ですが、より一歩進んで、この組織で、あの人たちと一緒に働けてハッピーだというアプローチ、つまりそうした組織づくり、人間関係づくりが大切となります。これも健康職場の特徴です。
一方で、不健康職場とは人間関係の質が低いため協働姿勢がなく他人事、萎縮してしまう空気、モチベーションの低下、メンタルヘルス不全につながる可能性が高まります。これでは働き方改革における最先端技術の導入や多様な働き方の仕組み等を取り入れても上手く機能せず、生産性の向上につながりません。
「働き方改革」の出発点であり土台は、人と組織がイキイキしている「健康職場」なのです。
講演内容
■仕事は人間関係に始まって人間関係に終わる
・職場の空気はつくるもの
・働き方改革について
・負のサイクルは危険!成功循環モデル「グッドサイクル」について
・コミュニケーションエラー防止
■健康職場づくり ~人と職場の元気力を高める~
・バランスよりもワークとライフのハーモニー
・やる気のない人はいない!
・共感のコミュニケーション
・コミュニケーションの本質と職場の絆、ビジョンの共有
・モチベーションとメンタルヘルス/苦手と練習不足/心身一如の方程式
・「元気を出す」と「元気は出てくるもの」/健康職場と人間関係について
■グッドサイクルの流れをつくる
・不健康職場(他人事やパワハラ等)防止のためのポジティブアプローチ
・すべては小さなことの積みかさね/当事者意識と行動で空気が変わる
パワハラと無縁な職場づくりへのポジティブアプローチ ~“健康職場”が人権感覚を高め、人と組織の元気力を高める~
想定する受講者
経営者、管理職、管理監督者などリーダー層
受講者へ伝えたいこと
優秀な野球コーチは低めに手を出すなとは言いません、高めを狙えと指導します。つまり「望ましい姿」にコミットメントする姿勢です。パワハラ学習、メンタルヘルスのラインケア学習などでは、あれダメ、これダメ、こうしたことをするとあなたに責任が及びますよ、というNG学習が多い。このアプローチも大切ですが、そればかりだと人間は萎縮してしまいます。その結果として、適切な指導などに支障がでるのは危険ですね。ですので、望ましい姿である「この組織で、あの人たちと一緒に働けてハッピーだ」というポジティブアプローチが大切になってきます。これが健康職場づくりです。
「健康職場」とは人間関係の質が高い職場です。つまり、協働姿勢、共感力、承認力、支援力が高いため、相手の立場に立てる人たち、言い換えれば「人権感覚」の高い人たちの集団です。ダイバーシティ戦略においても大切な出発点です。一方で不健康職場とは、人間関係の質が低いため協働姿勢がなく他人事、パワハラなどにより萎縮してしまう空気、モチベーションの低下、メンタルヘルス不全につながる可能性が高まります。
また、労働人口が劇的に減少している日本社会において、「早期の離職防止」「人材の定着」は様々な業界の大きな課題となっています。そして、「働き方改革」とは、労働人口が減少していく中でいかに生産性を高めていくかが本丸です。両課題にとって「健康職場づくり」、つまり人と組織がイキイキしていることが大切になります。
健康職場づくりにおいて大切な考え方やコミュニケーションのポイントなどをお伝えします。
講演内容
■仕事は人間関係に始まって人間関係に終わる
・心も空気感染する/職場の空気はつくるもの
・パワハラ防止のためのポジティブアプローチ
・萎縮型の負のサイクルは危険!成功循環モデル「グッドサイクル」について
・コミュニケーションエラー防止
■健康職場づくり ~人と組織の元気力を高めるコミュニケーション~
・やる気のない人はいない!なぜならば・・・
・共感のコミュニケーションと人権感覚
・共感力の磨き方
・コミュニケーションの本質と職場の絆
・「元気を出す」と「元気は出てくるもの」/健康職場と人間関係について
・ミスを指摘するのは何のためか?
・効果的なほめ方、叱り方/言いにくいことの伝え方/アンガーマネジメント
■グッドサイクルの流れをつくる
・Let`sのコミュニケーション/Weメッセージ
・当事者意識と行動で空気が変わる
サポーターシップがチームワーク・団結力を高める! ~職場を変えるサポート力(共感力・協働力)の高め方~
想定する受講者
・若手ビジネスパーソンの方々
・労働組合 若手組合員~中堅組合員の方々
受講者へ伝えたいこと
〇サポーターシップとは「みんながみんなの応援団」であるということ。
〇共感力・協働力の高い人とコミュニケーションすると、「自分のことを理解してほしい」「気持ちを分かってほしい」という共感欲求や「自分の話を聴いてほしい」「一緒に考えてほしい」「自分は独りではない」という愛と所属の欲求を満たしてくれます。つまり、人間関係の質が高いので、個々の思考の質(モチベーション、当事者意識等)も高くなり、その結果、行動の質(協働姿勢、自発性等)が高まり、「チームワーク」「団結力」が向上します。
〇共感力・協働力の高い人とは、相手に無関心(他人事)ではなく関心を持ち(自分事)、相手を分かろうとする人、相手を応援する人です。つまり、仲間やお客様を大切にする人、「サポート力」が高い人です。
講演内容
※気づき満載の楽しいワークをまじえた笑顔咲く参加型講演です!
①仕事や組合活動は人間関係に始まって、人間関係に終わる
・愛は何色?職場は何色?
・萎縮型の負のサイクルは危険!
・チームワーク、団結力を高めるグッドサイクル
・コミュニケーションエラーを防ぐために
・他人事ではなく自分事(サポーター)
・苦手意識と練習不足、失敗と未成功(プレイヤー)
②チームワーク・団結力を高めるサポーターシップ・コミュニケーション
・やる気のない人はいない!なぜならば・・・
・共感のコミュニケーションと心の扉
・サポーターシップという船は乗客(仲間)を元気にする
・未来志向のコミュニケーション/人を元気にするほんの小さなコツ
・心のサポーターの存在/みんながみんなの応援団/ホームとアウェイ
・ホーム(チームワーク、団結力)はパフォーマンスを向上させる
③グッドサイクルの流れをつくる
・サポート力(共感力・協働力)を高める3つのポイント
・当事者意識と行動
やる気が持続する!主体的にイキイキと仕事をするために! ~ワーク・エンゲージメントを高める秘訣~
想定する受講者
・仕事にもっと意欲的に取り組みたいと前向きな方/仕事に対する前向きさが感じられない方
・仕事に主体性を持って取り組みたいと前向きな方/仕事にやらされ感を持っている方
・仕事のやりがいをもっと高めたいと前向きな方/仕事のやりがいを見いだしにくい方
・自信をもっと高めたいと前向きな方/自信を見失っている方
受講者へ伝えたいこと
“世論調査や人材コンサルティングを手掛ける米ギャラップが世界各国の企業を対象に実施した従業員のエンゲージメント(仕事への熱意度)調査によると、日本は「熱意あふれる社員」の割合が6%しかないことが分かった。”(日本経済新聞2017.5.26)
ワーク・エンゲージメントとは「主体的にイキイキと仕事に取り組んでいる心の状態/快」を意味します。
これはバーンアウト(燃え尽き)の対概念であり、ワーカホリック(無理をして頑張って仕事をしている心の状態/不快)とも異なるものです。主体的にイキイキと充実感を持って仕事をしていることが望ましいのですが、日経新聞が取り上げたように日本は国際的には低いレベルにあるようです。
ワーク・エンゲージメントは「活力」「熱意」「没頭」という3つのキーワードから成り立っているのですが、これは少しわかりにくいので「モチベーション・職場の人間関係」「使命感・未来志向」「貢献・自信」の視点から講演させていただきます。
このアプローチは組織における「攻めのメンタルヘルス対策」でもあります。そして、誰もが主体的にイキイキと充実感を持って仕事に取り組む人生であることを望んでいます。そのために大切なポイントをお伝えします。
楽しく、分かりやすく、元気が出る時間です!楽しく学ぶことで学習効率はぐんと飛躍します!
講演内容
・「やる気を迎えに行く」(心と身体)
心身一如の方程式でモチベーションマネジメント
・「心の安全を高める場」(心と環境) 心のKY活動
・「失敗と未成功」(出来事の受けとめ方)
自分OSをバージョンアップ/すべては学びであり、成長の糧である
・「仕事の向こう側」(意義)
壁の向こう側をイメージ/仕事と志事
・「未来を先取りする」(人は誰しも自分の未来に関心がある) 脳内ナビゲーションシステムのスイッチをONにする
・「サポーターシップ」(アウェイではモチベーションやパフォーマンスが低下する)
傷語を減らし、愛語を増やす/職場の人間関係
・「あなたがいないと困る人になろう」(人生の意味は貢献である/アドラー) 自己効力感を高めて生きる
・「自信とやる気」(日々の積みかさね) いいところ探しで加点していく
「自分らしく輝いて生きる」 ~未来へ向けて!意欲を高めてキャリアアップ~
想定する受講者
これから管理職となっていく社員、職員の皆様
講演内容
1.ウォーミングアップ
2.モチベーションの見える化「やる気グラフ」
3.良好な人間関係はキャリアアップのエネルギー「元気は出てくるもの」
4.キャリアアップへの意欲向上「仕事の向こう側」
5.セルフコーチング「未来地図」
6.ダイヤモンドの原石(可能性の開花)と切磋琢磨「誰もがキラキラ輝くヒーローになれる存在である」
7.未来への脳内ナビゲーションスイッチ「未来のヒーローインタビュー」
8.まとめ「人生の意味は貢献である(心理学者アドラー)」
※楽しく学習する、笑顔と元気がいっぱい開花する研修時間になります
「やり抜く力」を高める5つの法則
想定する受講者
若手~中堅社員
受講者へ伝えたいこと
「GRIT/グリット(やり抜く力)研究の第一人者」として知られる米ペンシルベニア大学心理学部のアンジェラ・ダックワース教授は、成果を上げてきた方々を研究した結果、人がそれぞれの分野で成果を上げていくには、才能やIQよりも「やり抜く力」が重要であると指摘されています。
「継続は力なり」と言いますが、あきらめずに続けることでゴールにたどり着けることは頭では理解していても、いざ自分がスタートし始めるとそのようにうまくいかないことが多いことに気づきます。その結果、「どうせ思考」などのように自己 否定などにつながるとますます「やり抜く力」は弱くなっていきます。
「やり抜く力」を維持し、高めるためにどうすれば良いのか?
5つのポイントに整理し、お伝えします。
講演内容
(90分講演プログラム例)
■「積小為大」という原理原則
■「グリット」(やり抜く力)について
■「美点凝視」(法則1)でエンゲージメント(仕事への愛着)を高める
■「脱・失敗意識と脱・苦手意識」(法則2)が、やれば出来る(脱・やらなければ出来ない)につながる
■「レジリエンス」(法則3)を高めて、折れない心を育む
■「感謝と切磋琢磨」(法則4)が人生や仕事を好転させる
■「貢献」(法則5)は、succession(継続)をsuccess(成功)へとつなげてくれる
~あなたがいないと困る人になろう~
チーム・レジリエンスを高めて逆境に強い組織をつくる!
想定する受講者
組織、チームのリーダー向け
チーム全体の士気を高めたい!
困難にも一丸となって乗り越えていける組織を作りたい!
そのためのポイントを知りたいというリーダー(次期リーダー層も)の方々
受講者へ伝えたいこと
レジリエンスとは、ストレスに対応する力のことで、回復力や柔軟性、適応力などが含まれます。竹のようなしなやかな強さのことです。これはひとりひとりのビジネスパーソンに必須のスキルでもあります。
同時に組織にふりかかる様々な困難に対処し、意気消沈した組織の空気で停滞するのではなく、逆境をはね返そうと前 を向く組織の空気をつくりだし、協働姿勢、良好なコミュニケーションによって1+1が3にも4にもなって(ダイナミズム)、未来をつくっていく組織づくりも大切ですね!こうした逆境に強い組織とは、チーム全体のレジリエンスが高いという事です。チーム・レジリエンスを高めるポイントをお伝えします。
講演内容
■チーム・レジリエンスを高めるポイント(1)リーダーのコミュニケーション
・チームのコミュニケーション回路の要であるリーダーは、チームレジリエンスを左右する要です
・リーダーシップとサポーターシップ
■チーム・レジリエンスを高めるポイント(2)良好なコミュニケーション、共感力の高いチーム
・コミュニケーションの本質/理解と共感、職場の絆、組織一丸
・「元気を出す」(自律性)と「元気は出てくるもの」(関係性)
■チーム・レジリエンスを高めるポイント(3)衆知を集めて解決力を高める
・解決志向の「How」/Can we do it?(不安)/How can we do it?(解決志向)
■チーム・レジリエンスを高めるポイント(4)逆境体験を教訓化する
・(私たちは)やれば出来る!を実感する(チーム効力感を高める)
■チーム・レジリエンスを高めるポイント(5)空気は読むものでなく、つくるもの
・心は空気感染する
・積小為大/職場の空気づくり
■チーム・レジリエンスを高めるポイント(6)未来は予想するのではなく、つくるもの
・未来志向な組織づくり
・幸せな職場とは?
■チーム・レジリエンスを高めるポイント(7)感謝の心
・今日もやるべき仕事があることをある視点から眺めてみる
JA向け
【JA向けセミナー】 こころ元気に仕事をするには ~感謝の気持ちが人生・仕事を変える~
想定する受講者
JAの皆さま
受講者へ伝えたいこと
感謝の心と同時に組合員の皆さまからの「ありがとう」や「笑顔」をたくさん集める、つまり目の前の方々に喜んでいただくために自分たちが出来ることへの気づきを深めていただき、明日への実践につなげていただくためのモチベーションアップ!
講演内容
■仕事は人間関係に始まり、人間関係に終わる
・「ありがとう」を言うことと、「ありがとう」と言われること
・笑顔や元気は分かち合うもの
■感謝のコミュニケーションと仕事の態度
・「お客さまや仲間に“感謝”したいこと」
・顧客満足を高めるには、まず働く満足度を高める
・今よりも目の前の方々が笑顔になるために出来ること
■何のために、誰のために
・笑顔の輪を咲かせよう
■当事者意識と行動
・Let’sの精神とWe canの行動
JAの人と組織の元気力を高めるリーダーの役割 ~リーダーのコミュニケーション!~
想定する受講者
JAグループの管理職、リーダー層
受講者へ伝えたいこと
仕事は人間関係に始まって人間関係に終わると言います。つまり「絆」です。
職場の絆は、個々のモチベーション、メンタルヘルスの向上につながり、さらには集団のイキイキとした感情(職場の空気)、協働、ダイナミズム(1+1が3にも4にもなる)につながっていく。
本研修では、職場のコミュニケーション回路の要であるリーダーのあり方、リーダーのコミュニケーションについて、上機嫌な職場づくりだけでなく、言いにくいことの伝え方、効果的なほめ方や叱り方、ストレスマネジメントやアンガーマネジメントなど部下育成に必要なスキルについても学んでいただきます。
また、パワハラ防止においてはあれダメ、これダメというNG学習が多くなるため、リーダーが委縮してしまうケースがあり ます。これは危険なことです。
パワハラ防止のためのポジティブアプローチもご紹介します。
講演内容
STEP-1 リーダーのあり方とコミュニケーションの本質について
・ウォーミングアップコミュニケーション/気づきを深める
・リーダーにとってなくてはならない大切なものとは?
・コミュニケーションの本質について
・コミュニケーションエラー防止
STEP-2 リーダーのコミュニケーションとモチベーションについて
・やる気のない人は本当にいるのか?
・メンバーの4つのモチベーションの状態に対する対処法
・「元気を出す」と「元気は出てくるもの」について/心のサポーター
・言いにくいことの伝え方/効果的なほめ方、叱り方
STEP-3 メンタルヘルスと上機嫌な職場づくりについて
・アンガーマネジメントとストレスマネジメント
・健康職場づくりと人間関係について
・パワハラ防止のためのポジティブアプローチ
・すべては小さなことの積みかさね/当事者意識と行動で空気が変わる
JAのためのポジティブ組織開発 ~チームビルディングとリーダーシップ~
想定する受講者
JAグループのチーム力を高めたい管理職、リーダー層の皆様
受講者へ伝えたいこと
仕事は人間関係に始まって人間関係に終わると言います。つまり「絆」です。
「職場の絆」は、個々のモチベーション、メンタルヘルスの向上につながり、さらには集団のイキイキとした感情(職場の空気)、協働、ダイナミズム(1+1が3にも4にもなる)につながっていく。
さらには、ハラスメント防止へのポジティブなアプローチにつながります。
防止対策として、あれはダメ・これはダメというアプローチも大切ですが、より一歩進んで、この組織で、あの人たちと一緒に働けてハッピーだというアプローチ、つまりそうした組織づくり、人間関係づくりが大切となります。
本研修では、課題解決に向け情報共有と協力し合うことで一致団結を体感し、それぞれの役割を全うすることの大切さを学ぶ。
また、組織をネガティブな視点で捉えるのではなく、未来志向のポジティブな視点で捉え、未来へ向けての組織や個人の具体的なアクションにつながる組織づくりをめざす。
講演内容
STEP-1 チーム力を高めるコミュニケーション
・協力ゲームでチーム力を高めるコミュニケーションへの気づきを深める
・情報共有のポイント ~伝えると伝わる~
STEP-2 チームビルディング
・協力すれば、衆知を集めれば、突破力が高まる
・楽しく盛り上がるワークショップによるチームビルディングへ気づき
STEP-3 ポジティブ組織開発
・組織の魅力を引出そう(Discovery)
・理想の未来を共有しよう(Dream)
・ビジョン・行動計画の策定(Design、Do)研修バージョン
・ふりかえり
※研修時間により内容が変更する場合があります
地域活性・生徒向け
こころ元気に生きる
受講者へ伝えたいこと
どんよりした空模様のニッポン…。
気になることが多すぎるからでしょうか?
「念ずれば花ひらく」という言葉。あれは、怖いぐらいに真理です。
「わしゃ、ダメじゃ」とマイナス言葉をつぶやいている(念じている)人は、本当に人生がダメになります。
「富士は天晴れ、日本晴れ!」と明るく、笑顔で、力強く、人生を歩むためにはどうすればいいのか! 何よりも「こころ元気」であることが大切です。そこから全てが始まります。
講演内容
何かを「集めるだけの人生」では、気になることが多くなるのは仕方がないのです。
相手に喜んでいただき、お役に立つことを通して「ありがとう」と言われる生き方が大切です。これは「集める人生」ではなく「与えていく人生」です。
「人生は二度ない」ことも真理です。
何かをどれだけ集めたとしても墓場までは残念ながら持って行けません。これも真理です。
だからこそ、「二度ない人生」を豊かに充実させていくためには「与えていく人生」が求められているように想います。
ここで大切な人生の態度が「一隅を照らす」です。
自分の与えられた片隅を照らし出していく積極的な、明るい人生の態度なのです。それは「こころ元気」から始まるのです!
様々な「よもやま話」を交えながら、「楽しく・わかりやすく・ためになる」講演です。
ニコニコ顔で人生を歩むには、こころ元気が一番です!
受講者へ伝えたいこと
健康診断を毎年受けて、どこも悪いところはない。でも、心が不健康…。
一方で、身体にハンディがある、病気がちであったとしても、心が健康であれば…。 どちらが、力強い充実した人生を歩んでいくと思われますか?
講演内容
「心が健康(こころ元気)」であることが重要なのです。
心の健康を保つための人生の態度や身近な習慣などをご紹介します。
(1)相手に喜んでいただき、お役に立つことを通して「ありがとう」と言われる生き方、つまり、与え合う生き方が求められています。それは、充実感や生き甲斐へとつながるのです。
集めるだけの生き方では、ストレスが溜まるのは無理ありません。ここで大切な人生の態度が「一隅を照らす」です。
自分の与えられた片隅を照らし出していく積極的な、明るい人生の態度なのです。
「人に喜びを与える生き方」が最高の人生なのです!それは「こころ元気」から始まるのです!
(2)例えば、身近な習慣としては、呼吸が大切です。「息」は「自らの心」と書きます。呼吸が心の健康と深く関わっていることを現代の私たちに教えてくれています。
簡単な呼吸法、ご一緒にやりましょう。
すぐ出来るんです。何故って、皆さんは何十年と呼吸をしてきた「呼吸の達人」だからです。しかも無料! 森信三先生(昭和の偉大な教育者)が全国で提唱されてこられた「立腰」もやってみましょう。
シャン、凛、効果抜群ですよ。簡単です。呼吸と一緒で、いつでも出来ます。これまた無料! 様々な「よもやま話」を交えながら、「楽しく・わかりやすく・ためになる」講演です。
こころ元気な大人が、子どもの未来を築く!
受講者へ伝えたいこと
・明るい社会、明るい地域とはなにか?それは、「子供たちが大人の世界に夢を描ける社会」です。だからこそ、親、先生、地域の身近な大人たちの明るい人生の態度、元気な背中が大切なのです。
講演内容
《元気父ちゃん、元気母ちゃん、5つの法則》
その壱「父ちゃん、母ちゃんは、美点凝視すべし」~元気な人の共通点~
・短所の改善も大切だけど、長所の伸展はもっと大切ですね!
その弐「父ちゃん、母ちゃんは、日常の明るい出来事を子どもに語るべし」
・大人が夢を語るから、子どもたちも夢を語る!
その参「父ちゃん、母ちゃんは、理解と共感で絆を深めるべし」
・親子のコミュニケーションにとって大切なこと。心のシャッターを降ろさないために
その四「明るい話題は、元気の源!」
・ポジティブな話題は人を元気にする!
その五「何事も(-)で終えず、(+)で終えると心得るべし」
・怒ると叱るの違い、明日へつながるプラス言葉
※5つの法則の後には、「元気な大人の背中」や「命の尊さ」についてお話させていただきます。
※コミュニケーションで大切なことを体感するワクワクゲームをはじめ、会場が一体感、笑顔いっぱいになる楽しい全員参加型ワークや最近ではこれまた盛り上がるコミュニケーション☆ペアワーク(理解と共感...家族の絆への気づき、元気の源など)なども盛り込んだ元気講演です。
※親子だけでなく、夫婦のコミュニケーションやさらには大人同士(職場など)でのコミュニケーションにもつながる内容です。
元気父ちゃん、元気母ちゃんが子どもの未来を築く! ~こころ元気に今日から、ここから~
受講者へ伝えたいこと
「富士は天晴れ、日本晴れ!」と明るく力強く人生を歩むには「こころ元気」からすべては始まります。子どもたちは次世代を担う日本の宝です。だからこそ、父ちゃん、母ちゃんの「こころ元気」な人生の態度が大切なのです!
明るい社会、明るい地域とはなにか?それは、「子どもたちが大人の世界に夢を描ける社会」です。だからこそ、親、先生、地域の身近な大人たちの明るい人生の態度、元気な背中が大切なのです。(これらを七か条を交えながらお話します)
講演内容
《元気父ちゃん、元気母ちゃんになるための七か条》
■その壱「父ちゃん、母ちゃんは、自らの歩むべき人生を自覚すべし」
・私は()のために生きている
⇒ここでは、()を埋めるのが目的ではなく、自分自身と向き合う時間の大切さ、心のゆとり、そうした中で自分自身の「子育てにおける、ぶれない軸」あるいは、人生のぶれない軸等と出逢うことの大切さを語ります。自分自身とコミュニケーションするゆとりの時間が現代の大人には大切です。
■その弐「父ちゃん、母ちゃんは、日常の明るい出来事を子どもに語るべし」
⇒「僕も大きくなったらお父さんみたいになりたい!」「私も大きくなったらお母さんみたいになりたい!」「大きくなったら、僕もJCに入りたいなぁ!」などなど…大人の世界に夢を描ける明るい会話が大切です。日常のどんな小さな出来事でも いい…そして、明るい会話が明るい会話を引き出します。これは、親子だけでなく大人同士でも職場でも同じことです。
■その参「父ちゃん、母ちゃんは、あいさつを毎日し、はきものをきちんとそろえ、出した椅子はきちんと机にもどすべし」
⇒生活習慣は言葉で伝えることと同時に、親が先生が、そして地域大人たち(挨拶・タバコのポイ捨てをしないなどな ど…)が、背中で伝えていくことが大切です。
■その四「ことば、声、態度がコミュニケーションの基本であり、聞くではなく聴くことからはじまると心得るべし」
■その五「ガッツポーズが元気の源と心得るべし」
■その六「何事も(-)で終えず、(+)で終えると心得るべし」
⇒その四~六は、親子のコミュニケーションについて。子どもたちの自立・自律へとつながるコミュニケーションについて もふれます。(親子だけでなく、大人同士の…例えば、職場でのコミュニケーションにおいても、大いに関係する内容です)
■その七「元気父ちゃん、元気母ちゃんは、家庭だけでなく、地域を、そして日本を元気にする存在なんだと自覚すべし」
⇒ここでは、「明るい社会とは何か?」そして「元気な大人の背中の大切さ」について語ります。
※90分講演の場合は、七か条の後に、「命の尊さ・大切さ」についてお話させていただきます。
こころ元気に仕事をするには
受講者へ伝えたいこと
人生において、仕事において、全てにおいて・・・何よりも「こころ元気」であることが大切です。そこから全てが始まります。
生きていることの素晴らしさ、心の豊かさ、生き甲斐、仕事のやり甲斐・充実感とは何か・・・。
講演内容
相手に喜んでいただき、お役に立つことを通して「ありがとう」と言われる生き方・・・。
仕事を通じての充実感は、ここにあります。ここから人生を貫く棒(生き甲斐、やり甲斐)がより明確に築かれていく。
「二度ない人生」を豊かに充実させていくためにはこのような生き方、仕事への態度が求められているように想います。ここで大切な人生の態度が「一隅を照らす」です。自分の与えられた片隅を照らし出していく積極的な、明るい人生の態度です。
また、「健康」は人間の最大の関心事でもあります。身体が健康であっても、心が不健康では力強く人生を歩むことが出来ません。「心が健康である」ことが重要なのです。仕事をしていると、日々様々なストレスシャワーを浴びています。心が枝葉末節に囚われてばかりいると、不健康に心が蝕まれていく。
心の健康を保つための人生の態度や身近な習慣などもご紹介します。
様々な「よもやま話」を交えながら、「楽しく・わかりやすく・ためになる」講演です。
命は宝~こころ元気に生きる出発点~
受講者へ伝えたいこと
■「命は宝」「この世に生を授かった私たち一人ひとりの命は尊いものである」を深く心に感じることこそ、「こころ元気に生きる」出発点であり、思いやりの心...そして、笑顔、挨拶、共に喜ぶ...そして元気を「分かち合う」生き方へつながります。
■大切なことは、「ありがとう」と感謝する心とともに、「ありがとう」と言われる生き方…そして、「笑顔を分かち合い」「元気を分かち合う」生き方、そして自分自身へも「ありがとう」と向き合える心のゆとり。
講演内容
■お話だけでなく、心と心の距離が近づくことを体感していただく、笑顔の全員参加☆ワークをやってみたり...行動への気づきにつながる、これまた笑顔の全員参加☆ワークをやってみたり...楽しい講演時間を一緒に過ごしていただきます。
■「明るい社会」とは何か?
それは、子供たちが大人の世界に夢を描くことの出来る社会だと僕は考えています。だからこそ、私たちは「命は宝」を深く心に養い、それぞれがそれぞれの「一隅(いちぐう)を照らす」という明るい人生の態度(大人の背中)がもとめられているのです。一人ひとりがそれぞれの片隅を照らし出していくことで、明るい社会は築かれると信じています。
【生徒向け講演】 こころ元気に生きる~命は宝~
想定する受講者
学生
受講者へ伝えたいこと
「“ありがとう”と言われる人生の態度」「こころの充実感(感動)の大切さ」「一隅を照らす生き方」そして「命は宝」などについてお話します。
これまでPTA講演会・家庭教育講演会などでお話させていただく機会がたくさんあり、共感いただいたお母さん、お父さんからの感想が多数よせられています。
講演内容
・人と人との出会いの大切さ、さらに「良い言葉と出会うことの大切さ」を通じて、「一所懸命・本気」、「努力は裏切らないこと」「コツコツ継続することの大切さ」「夢や目標は追いかけるから、追いつける!」などについてお話します。そして…
「命は宝物」について。
・壁を乗り越えていく、チャレンジする心、あきらめない心について。壁は成長の糧。ポジティブキングについて。
・お互いが支え合い、励まし合うことの大切さ。出逢いと感謝について。笑顔や元気は分かち合うもの。
・「ありがとう」と言うことは大切なことですが、それと同じぐらい、あるはそれ以上に大切なこととして、相手に喜びを与えていく、お役に立つ、そのことを通して、笑顔がこちらに返ってくる、「ありがとう」と言われる、そういう生き方が大切であります。「集めるだけの生き方」ではなく「与える生き方、与え合う生き方」です。これは、「思いやり」が育まれる生き方であり、「こころの充実感」やその先にある「夢」や「生き甲斐」と出逢える生き方なのです。
・こころを豊かに充実させていくためにはこのような生き方が求められているように想います。ここで大切な人生の態度が「一隅を照らす」です。自分の択んだ、与えられたその片隅を照らし出していく積極的な、明るい人生の態度です。
・そして、私たち一人ひとりが、「こころ元気に生きる」出発点、それは「命の尊さ」、「この世に生を授かった私たち一人ひとりの命は尊いものである」を深く心に感じ、養うことにあると思います。
・命の尊さを「感じる心」が大切なのです。
※ちょっとしたワークも交え、皆さんにインタビューしたりします!
地域の絆、みんなの笑顔!
想定する受講者
市民、民生委員・児童委員、福祉関係者、まちづくり関係者
講演内容
90分もアッという間の参加型講演
(起)■さぁ、楽しくいきましょう~人となかよく~
・脳トレ☆リフレッシュ!
・気分も空気感染しますね、明るくて元気な空気づくり、まちづくり
・元気は分かち合うもの(笑顔、ありがとう、がんばってるねetc.)
・ともに喜ぶ心の豊かさ、人の温もり
・「あいさつ」から学ぶこと
(承)■「絆」「元気」コミュニケーション~人と人とのつながり中で~
・愛の反対は??無縁社会って??
・人は人から元気をいただいている、支え合っている
・豊かな人間関係こそ、心の健康、元気にとって一番大切ですね
・「積小為大」、すべては小さなことの積み重ね
(転)■ちょっと一息、こころとカラダの元気リフレッシュ~自分となかよく~
・歩く
・いつでも出来る簡単、長寿&心身健康法
(結)■「一怒一老」ではなく「一笑一若」でいこう~みんな笑顔配達人~
・笑顔は相手の心まで明るくしますね
・地域に笑顔の輪を咲かせよう!
オンライン版
【オンライン版】 レジリエンスを高める仕事術 ~折れない心の育て方~
想定する受講者
・労働組合 若手・中堅組合員
・労働組合 組合役員の方々(職場委員、分会長、職場代表・・・など代議員の皆さん)
・ビジネスパーソン全般
受講者へ伝えたいこと
レジリエンスとは、ストレスに対応する力のことで、回復力や柔軟性、適応力などが含まれます。竹のようなしなやかな強さのことです。すべてのビジネスパーソンにとって大切なレジリエンスについて、『ストレスからの回復にとどまらず、より元気に仕事や組合活動に取り組むというポジティブなアプローチ』で学習していただき、明日への行動に活かしていただく。
講演内容
1.良い習慣のために
・習慣の力を体感(オンラインワーク:講師と画面上でちょっと変わった楽しいジャンケン)
・心の掃除のポイント
・バタバタはイライラ/少し立ち止まって適切な対処
・コミュニケーションギャップはトラブルのもと(オンラインワーク:講師の問いで簡単なお絵かき)
・レジリエンスとは
2.レジリエンスを高める仕事術(1)人間関係・コミュニケーション
・挨拶の教えとコミュニケーションの本質/理解と共感、ビジョンの共有
・一致団結、組織一丸、絆のために大切なこと
・心の病は脳のトラブル?/脳を休めるために大切なこと
・心のサポーターの存在/ほめ言葉、感謝言葉、ねぎらい言葉
・「元気を出す」(自律性)と「元気は出てくるもの」(関係性)
・「所属」しているだけでなく、そこに「心の居場所」があることが大切
・お互いを支えあうサポーターシップを高めよう/無関心やアウェイは最大のNG
3.レジリエンスを高める仕事術(2)自身のレジリエンス特性を確認
・モチベーションを見える化(オンラインワーク:モチベーション曲線)
・自身の心のエネルギーの回復ポイントを知ろう
4.レジリエンスを高める仕事術(3)ポジティブ思考
・壁は成長の糧
・困りごとの解決と望みごとの実現
5.レジリエンスを高める仕事術(4)心身一如の方程式
・職場などで簡単にできるレジリエンス術(オンラインワーク:講師の実演に合わせてその場でやってみよう)
・心はコントロールしにくいが、身体や行動はコントロールしやすい
6.レジリエンスを高める仕事術(5)まとめ
・心理的安全性が高い職場づくり/空気はつくるもの!
◎オンライン講演におけるポイント
同じ場で皆さんと一緒に作る楽しい学習の空気感の体感はリアル講演に対して劣りますが、学習内容、気づきという行動変容につながる部分はリアル講演と大きな差はないと思います。自分と向き合うワークやその場で座ったままできるレジリエンス視点の心の健康法、講師からの投げかけをその場で簡単に描いてみるなどオンラインでも簡単にできるワークを盛り込んで、講演のテンポ感が間延びしないように配慮します。
【オンライン版】 チームビルディング・ポジティブ組織開発 ~一致団結と未来志向の組織づくり~
想定する受講者
労働組合組合役員の方々(職場委員、分会長、職場代表・・・など代議員の皆さん)
受講者へ伝えたいこと
仕事は人間関係に始まって人間関係に終わると言います。つまり「絆」です。「職場の絆」は、個々のモチベーション、メンタルヘルスの向上につながり、さらには集団のイキイキとした感情(職場の空気)、協働、ダイナミズム(1+1が3にも4にもなる)につながります。
コミュニケーションの本質を学びながら一致団結を体感し、それぞれの役割を全うすることの大切さを学んでいただきます。また、組織をネガティブな視点で捉えるのではなく、未来志向のポジティブな視点で捉え、未来へ向けての組織や個人の具体的なアクションにつながる組織づくりをめざしていただきます。
コロナ危機は大きなストレスですが、この想定外の出来事をリーダーとしての自分や組織の「あり方」「未来」について再確認・再構築するための学習の機会にしてみませんか!これも未来をポジティブな視点で捉えるアプローチです。
講演内容
■チームビルディング
・チーム力を高めるコミュニケーション
・一致団結とは〇〇し合うこと
■ポジティブ組織開発
・困りごとの解決と望みごとの実現(1)シェア
・困りごとの解決と望みごとの実現(2)行動をデザインする
・未来はつくるもの
【オンライン版】テレワークライフのメンタルケア術セルフケア ~パフォーマンスを下げない工夫~
想定する受講者
・全階層の方々
・テレワーク中のすべてのビジネスパーソン
受講者へ伝えたいこと
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、在宅勤務されている方々の中には、これまでの仕事環境の変化からストレスが溜まっている方が多くなっています。また、通勤などで歩くことが減り、PC画面の前での座りっぱなしな状態が続くと身体の健康に悪影響であることをWHOは発表(身体不活動は死亡の危険要因としては肥満や高コレステロールよりも上位)しています。心身の健康はパフォーマンスに大きな影響を与えます。テレワーク・ライフにおける心身の健康のために大切なことをお伝えします。
講演内容
テレワーク・ライフにおける
1.メンタルケア術
2.パフォーマンスを下げない工夫
3.仕事中における家族とのコミュニケーションの取り方
4.同僚との雑談力を高める
(概要)
・テレワーク中の家族とのコミュニケーションのコツ
・心の掃除3原則を知ろう
・タイムマネジメントでストレスマネジメント
・コミュニケーションエラーはストレスのもと
・テレワークにおけるストレス解消法
・快適生活は気分で決まる/軽運動と脳内ホルモンの関係を知ろう
・集中力が途切れたとき/テレワークは窓際族がいい/自然を感じる
・オンラインで雑談力を高めるコツ
・心理的安全性を高めてパフォーマンスを高めよう
実績
行政、PTA、福祉団体、企業、商工団体、労働組合、青年会議所、医療機関など多方面から講演・研修依頼をいただいている。
これまで延べ2,000回を超え、30万人以上の方々が受講。
書籍
こころ元気に生きる – 元気スイッチをONにする41の知恵(デザインエッグ社 2017年)
幸せな働き方: 人と組織が輝くために「続けたい習慣」(デザインエッグ社 2019年)
ストレスの9割はコントロールできる(明日香出版社 2020年)
当社実績
安全大会 2023年秋・滋賀県
講演タイトル:心理的安全性を高めるためのリーダーのコミュニケーション
~人と組織の元気力を支えるラインケア~
他多数

| #鎌田敏,#かまたびん |








