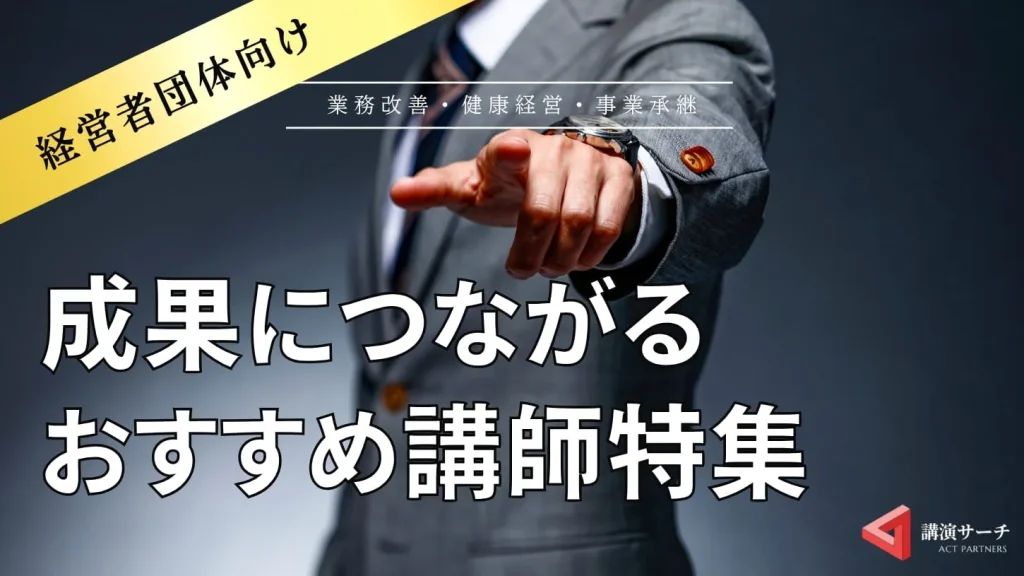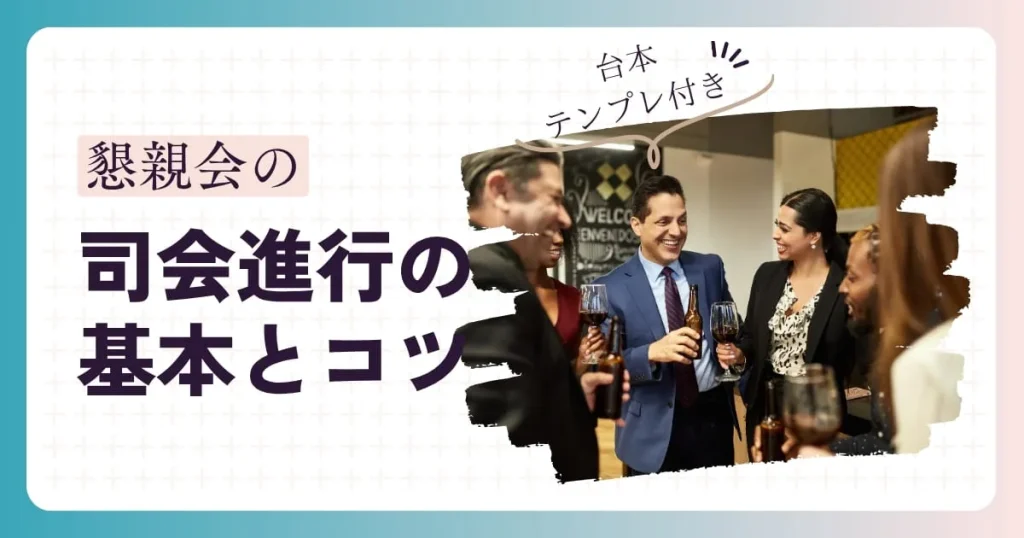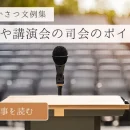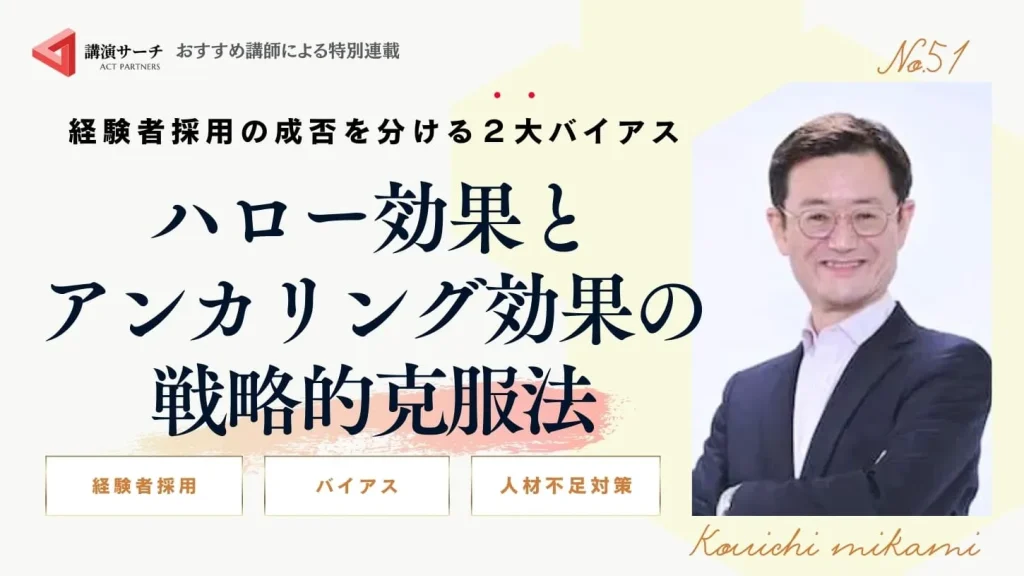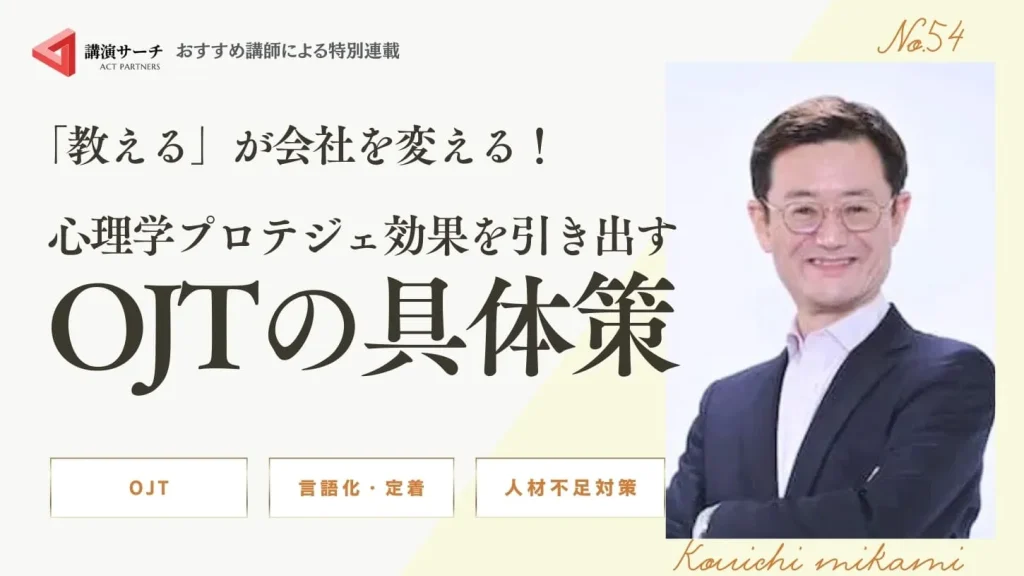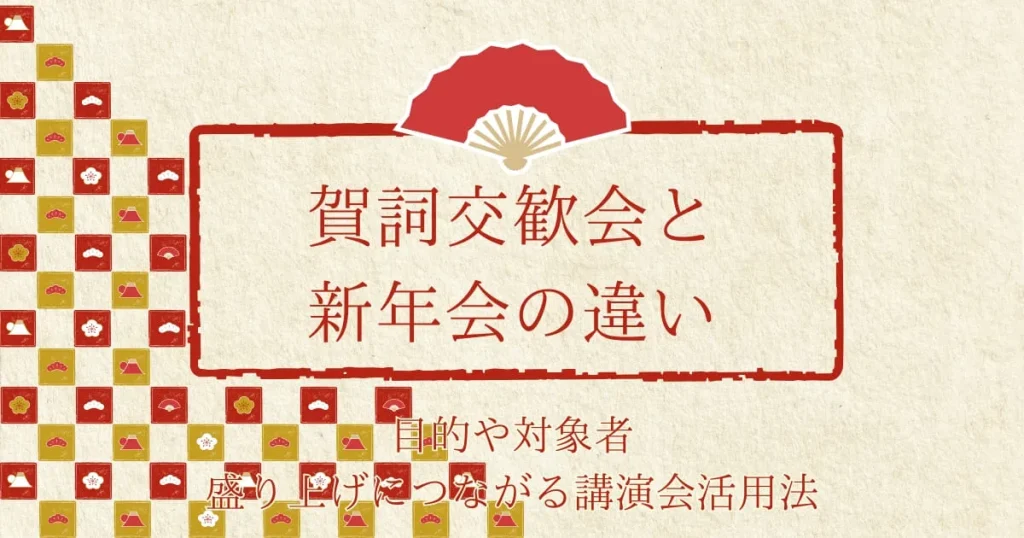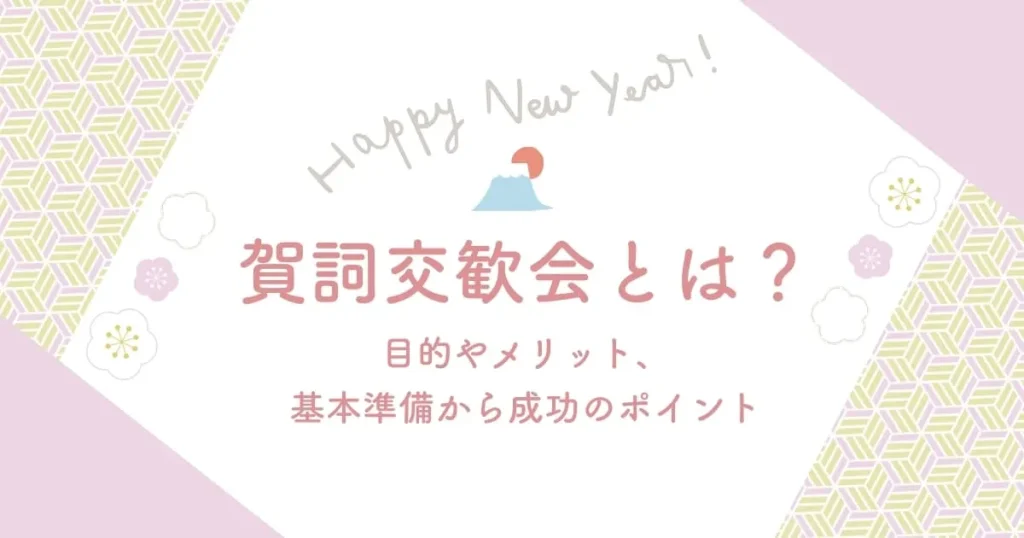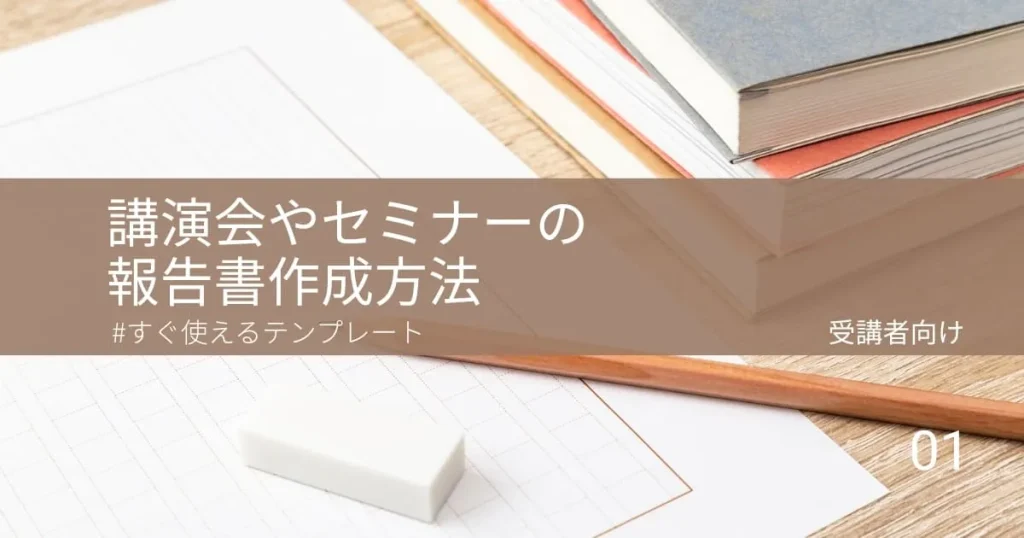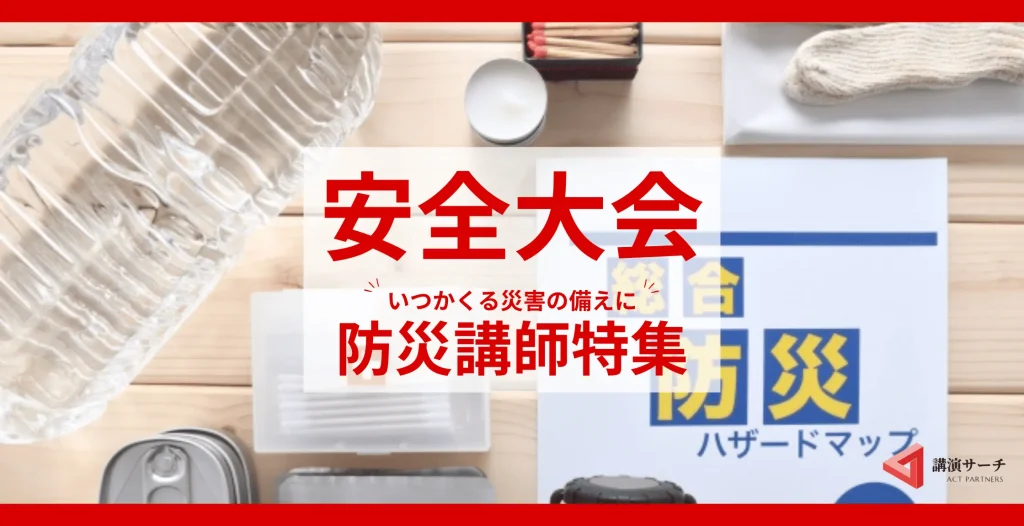【司会台本の作り方】講演会やセミナー進行台本作成のコツ!3ステップで解説
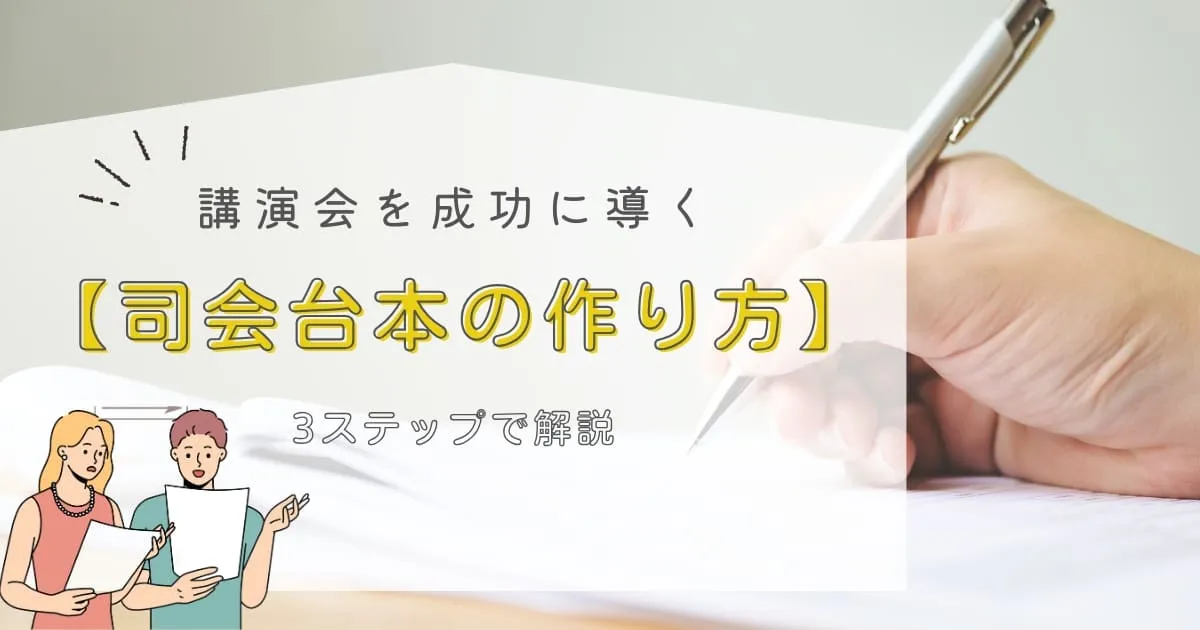
講演会やセミナーの司会者に選ばれた際、台本作成に悩む方は多いです。しかし、進行台本はたった2ステップで作成できます。
本記事では、司会台本の作成手順とポイントを紹介します。司会進行を成功させるコツも紹介しているため、自信をもって司会者を務められます。
本記事では、熱中症の症状やや予防方法、企業がとるべき対応を具体的にご紹介します。熱中症対策の重要性を知るとともに、大切な家族や従業員の命を守るためにお役立てください。
講演サーチは、組織の課題やご予算など、ご希望に合わせた講師・講演テーマをご提案いたします。従業員や地域の方の命を守る「熱中症対策」に取り組みたいとお考えの企業担当者や安全衛生管理者さまからの、ご相談をお待ちしております。
【司会台本の作り方】講演会やセミナー進行台本作成のコツ!3ステップで解説
目次
講演会やセミナーで進行台本は必要?
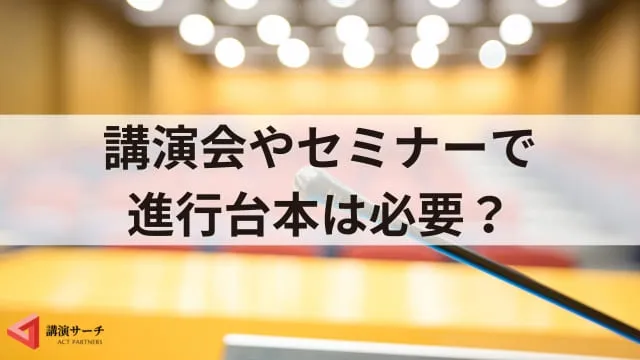
講演会やセミナーでは、司会者の存在が欠かせません。司会者は当日の進行役ですが、台本がないとスムーズに進行できなくなるため台本は必要です。
“台本”と一言でいっても、セリフだけが書かれているものでは意味がありません。全体の流れや担当者、やることまで台本に書き、講演会やセミナーの全容が見えるようにします。
講演会やセミナー参加者は、聴講や学習を目的に参加しますが、全体の進行がグダグダだと不信感や不安感を抱き、集中力を失います。これでは、講師がどれだけ素晴らしい講話をしても満足度が低くなりかねません。
講演会やセミナーを成功させるためにも、進行台本は用意するとよいでしょう。
講演会やセミナーの台本作成の手順
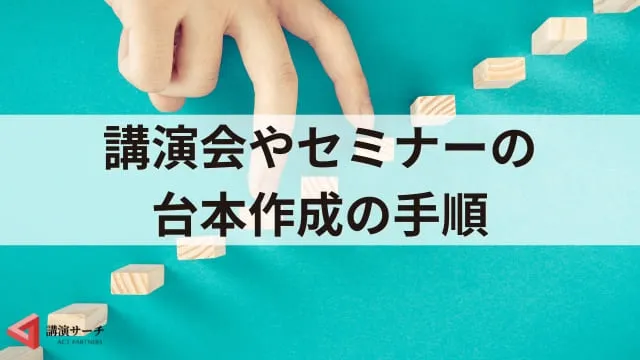
講演会やセミナーの台本作成の手順を解説します。いきなりセリフから書き始めず、手順に沿ってつくるのが大切です。
1.プログラムと流れを書き出す
まずは、講演会やセミナーで実施される「プログラム」と「全体の流れ」を書き出します。
どのようなプログラムを実施するかによって流れも変わるためです。講演会などによってプログラムは若干違いがあるため、必要なプログラムを事前に確認しましょう。
流れをつくる際には、次のプログラムへスムーズにつながる順番を意識するとよいですね。
2.各担当者の選定と書き出し
講演会やセミナーは、一人で行うわけではありません。受付や機材操作、参加者の案内など、多くのスタッフが必要です。当日に「誰が」「何を担当する」かを事前に決めて書き出しておきましょう。
書き出した情報は進行台本にも記載します。各担当者がどのプログラムでどのような動きをするか把握できると、トラブル時の対応もしやすい使いやすい台本となります。
また、参加者に何かをしてもらう場合も台本に記載しておくとよいですね。
3.司会が話す台本を考える
すべての書き出しができたら、いよいよ司会が話すセリフを考えます。
一般的な講演会などのプログラムは以下のとおりです。
・開会のあいさつ
・注意事項の説明
・講師の紹介
・講師の講話(呼び込み)
・質疑応答
・閉会のあいさつ
開会のあいさつや閉会のあいさつは主催の代表などが行うケースもあります。また、注意事項の説明は対面かオンラインかによって内容が異なるため、実施方法に合わせて内容を決め、台本を決めましょう。
講演会やセミナー台本作成のポイント3選

台本は手順に従ってつくると使いやすくなりますが、よりよい台本とするための3つのポイントがあります。ポイントをおさえた台本を作成し、スムーズな進行を実現しましょう。
簡潔に伝えるのを心がける
人は、だらだらと長く話されると集中力を失い、聞く気がなくなってしまいます。大切なポイントも伝わりにくくなるため、台本のセリフは簡潔さを意識してください。
特に注意事項では、一つの注意事項を一つの文で伝えるようにすると伝わりやすくなります。
例えば以下のような案内です。
「携帯電話の電源はお切りいただくか、マナーモードに設定してください」
「お手洗いは会場を出て左にございます」
また、講師紹介も同様です。素晴らしい経歴をお持ちの講師の場合、すべて伝えようとしてうっかり長くなってしまうケースがあります。
しかし、参加者が混乱してしまうため、経歴のなかでも「本講演会に合っている経歴」や「特に重要だと思われる経歴」をピックアップして伝えます。簡潔すぎるのもよくありませんが、台本をつくる際には「伝える」を意識してセリフを考えていきましょう。
余裕のあるタイムスケジュールにする
講演会やセミナーは、時間に制限があるのが一般的です。時間管理も司会者の役割ではありますが、余裕のあるタイムスケジュールで台本をつくりましょう。
講演会などではトラブルが起きる可能性もあります。余裕のないタイムスケジュールが組まれていると、トラブルに対処しきれず、時間がオーバーしてしまうかもしれません。講師の話が長くなって時間が押してしまう可能性もあるため、余裕の確保が重要です。
時間が余っても、質疑応答や休憩の時間を長めにとって対処できます。最初から余裕のあるタイムスケジュールで台本をつくっておけば、心にも余裕が生まれますよ。
聞く側の気持ちになる
講演会やセミナーには、対面でもオンラインでも聞いてくれる参加者が必ずいます。
聞く側の気持ちになって台本をつくる意識がとても大切です。簡潔な言葉でわかりやすく伝えるため、表現方法も考慮しましょう。
例えば、講演会などのテーマが専門的な場合は少し堅い話し方や言葉を選ぶとよいですね。対して、カジュアルなテーマであれば、柔らかい話し方や言葉が適しています。
強調したい言葉やポイントは台本にも記載しておくと進行中も忘れません。参加者により伝わりやすくなるため、太字にしたりマーカーでラインを引いたりしておくことをおすすめします。
司会進行を成功させるコツ
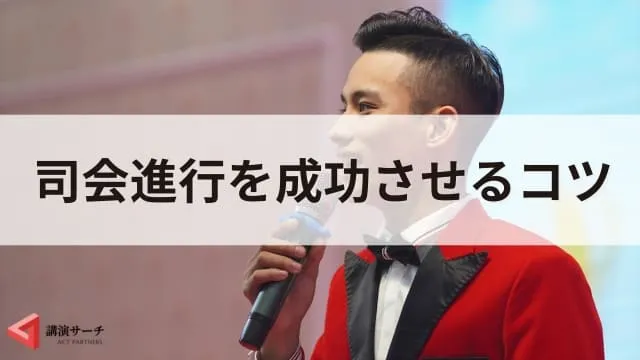
司会進行は、台本があれば必ずしも成功するわけではありません。これから紹介するコツをおさえ、成功に少しでも近づけるように準備しておきましょう。
台本は一言一句もらさず書く
台本のセリフは、一言一句もらさず書くのが大切です。
セリフがすべて書かれていない場合、言葉を探して進行が止まってしまう可能性があります。司会進行中は「あのー」や「えー」などのフィラーを使うのはよくありません。
フィラーを多用すると、参加者は集中力を失ううえに、進行に対して不安になり満足度が下がります。言葉を探し、話をつなぐためにフィラーは出てしまいがちなため、そうならないよう一言一句もらさず書いておきます。
台本は、本番中も手元におき、見ながら読んでも問題ありません。しかし、ずっと台本だけに目をやっていると下を向いたままになり、印象が悪くなります。台本を読んでいても、セリフの終わりなどには会場に目をやるように意識しましょう。
実際に声に出して練習する
台本ができあがったら、実際に声に出して練習してみましょう。実際に声に出してみるとおかしな点に気づきやすくなります。
例えば、伝わりにくい文章や予想以上に時間がかかる文章などに気づけるため、より伝わる台本に仕上げられます。漢字の読みや、かみやすいポイントにも気づけるため、スムーズな進行のためにも声に出すのが大切です。
また、実際に声に出して練習すれば、声の抑揚のつけ方の練習にもなります。
台本を熟読するだけでは抑揚のつけ方は身につきません。抑揚のついた話し方をするとメリハリがつき伝わりやすいうえに参加者を惹きつけられるため、満足度が高くなりますよ。
リハーサルを実施する
当日までにリハーサルを実施するのも大切です。本番と同じ流れで行うと、問題点や不明点に気づけます。事前に気づければ修正可能なため、本番ではスムーズに進行ができるようになりますよ。
リハーサルは、できれば複数回実施できると理想的です。複数回は難しい場合でも、一度は実施しましょう。リハーサルは全体の流れをチェックする意味もありますが、司会者の練習の成果を他の方にチェックしてもらう意味もあります。
自分だけで練習しているよりも他の方にチェックしてもらったほうが、読むスピードや声の大きさの善し悪しに気づけます。読み間違いをしている点もあれば指摘してもらえるため、リハーサルはとても重要です。
会場の下見や設備のチェック
本番までに、会場の下見や設備のチェックをしなければなりません。例えば、会場のレイアウトをチェックし忘れると、参加者に間違った情報を伝えてしまう危険性があります。会場のレイアウトは実際に見てチェックするか会場のホームページなどで確認しておいてください。
各担当者の立ち位置のチェックや音響設備や照明器具のチェックも大切です。オンラインで実施する場合は、配信ツールの操作方法や設備チェックをしておきましょう。
事前にチェックしておけば、対面でもオンラインでも環境に慣れた状態で本番を迎えられます。それが参加者の安心感や信頼感にもつながるため、満足度も高くなりますよ。
姿勢や声に気をつける
司会者は話す機会も多く、講演会やセミナーで最初に登場するため、参加者に注目される存在です。そのため、姿勢や声に気をつけて進行を行わなければなりません。
猫背になり声が暗くなると、参加者は不信感を抱き、印象が悪くなります。背筋を伸ばして胸を張り、あごを少し引いた姿勢を意識すると、自信に満ち溢れた印象を与えられます。さらに、姿勢をよくすると十分に呼吸できるため、声も出しやすいですよ。
声のトーンも大切です。声のトーンはいわゆる「音の高低」ですが、音が低いと暗い印象になり、音が高いと明るい印象になります。進行中は、普段よりも高いトーンを意識するとよいですね。
ただし、ずっと高いトーンで話すのではなく、高低差をつけながら話すと聞き手を惹きつける話し方になり、参加者の意識を集中させられます。参加者が集中できれば満足度も高くなるため、当日まで練習を重ねましょう。
まとめ
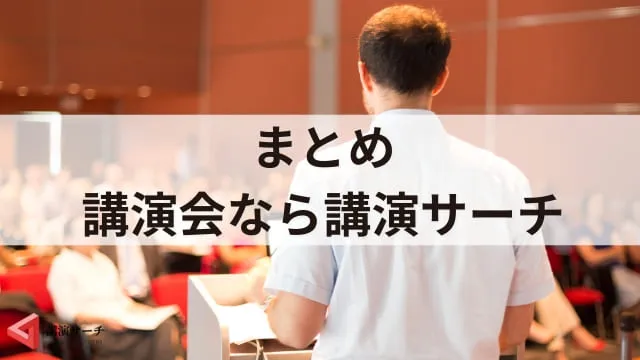
進行台本をつくる手順やコツを紹介してきました。進行台本は司会進行をするうえでとても大切でです。司会のセリフだけを書いた台本では、講演会やセミナーの全容を把握できず、うまく舵取りができません。
すべてのプログラムから流れをつくり、各担当者とやることも台本に書いておくとスムーズに進行できますよ。
また、台本があれば成功するわけではなく、司会者の事前準備がとても大切です。参加者の満足度が高い講演会やセミナーを実施するためにも、コツやポイントをおさえて準備を怠らないようにしましょう。
講演サーチは、司会が必要な規模の講演会や研修会の開催を丁寧にサポートいたします。組織の課題や希望に合わせた講師をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
経験者採用の成否を分ける2大バイアス:ハロー効果とアンカリング効果の戦略的克服法【三上康一講師コラム】
保護中: 「教える」が会社を変える!心理学プロテジェ効果を引き出すOJTの具体策【三上康一講師コラム】
採用危機を打ち破る!中小企業が今すぐ変えるべき「数字の見せ方」革命【三上康一講師コラム】
賀詞交歓会と新年会の違いは?目的や対象者・盛り上げにつながる講演会活用法
賀詞交歓会とは?目的やメリット、基本準備から成功のポイント
【例文あり】講演会やセミナーの報告書作成方法を解説!
【著名人・芸能】体験談で伝える安全大会講師特集
安全大会におすすめ!【人材・業務効率化】に特化したテーマ・講師特集
【社員の健康意識向上】におすすめ!健康に特化した講師特集
【気象・天気】関係の講演におすすめ!気象キャスター講師特集
【災害対策】におすすめ!防災に特化した講師特集
【交通・物流関係】におすすめ!交通安全に特化した安全大会講師特集
人気の講師

1位
今蔵 ゆかり
【Y’s room 代表/人材育成・上機嫌コーチなど】

2位
久杉 香菜
【航空自衛隊出身のミス・ユニバース秋田代表/モデル/タレント】

3位
稲村 悠
【日本カウンターインテリジェンス協会/外交・安全保障オンラインアカデミーOASISフェロー】

4位
土井 邦裕
【気象予報士/防災士/利き酒師】

5位
大隅 智子
【気象予報士/気象キャスター/防災士/健康気象アドバイザー/野菜ソムリエ】
ジャンルから講師を探す
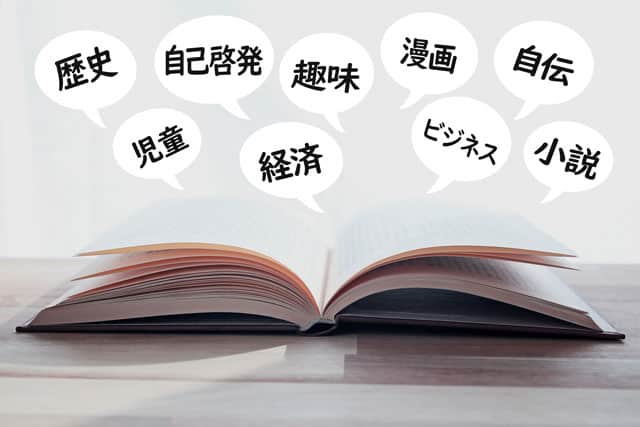 講演ジャンル |
|---|
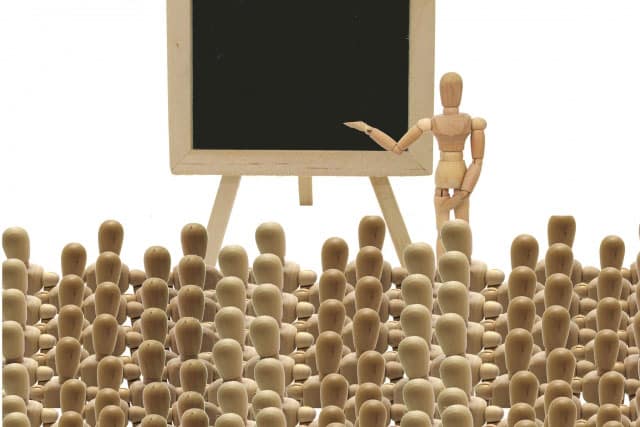 受講者 |
|---|