「春闘」とは? 目的や背景、交渉内容や流れをわかりやすく解説
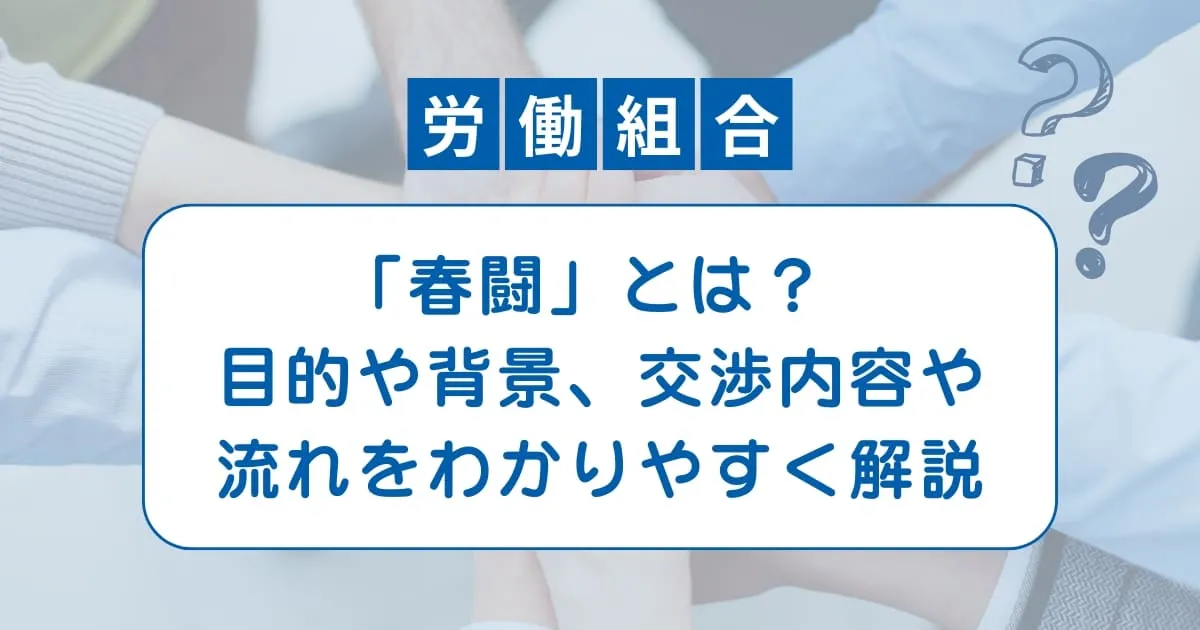
春には「春闘勉強会」を開催する組織も多いのではないでしょうか?
春闘は、ベースアップや労働環境改善などを目的とした労働組合による企業との交渉です。この交渉は春ごろにピークを迎え、企業にも労働者にも重要な役割があります。
本記事では、春闘勉強会の開催にあたって知っておきたい、春闘の目的や交渉内容、流れなどを、最新情報とともに解説します。2025年の動向予想も解説するため、ぜひ最後までご覧ください。
講演サーチは、春闘をはじめ、講演会や研修会の開催を丁寧にサポートいたします。春闘勉強会を開催する際は、専門家の講演会で理解を深めてみてはいかがでしょうか。
講演テーマや講師選びからご提案いたしますので、詳細が決まっていなくてもお気軽にご相談ください。
「春闘」とは? 目的や背景、交渉内容や流れをわかりやすく解説
人気の講師

1位
大久保 雅士
【メンタリスト/ビジネス心理コンサルタント】

2位
丹羽てる美
【笑顔クリエイター®/フリーアナウンサー/上級睡眠健康指導士/心理カウンセラー】

3位
多湖 弘明
【株式会社Office Hit 代表取締役】

4位
安藤 美希子
【株式会社日動電設/ウエイトリフティング選手/メダリスト】

5位
三遊亭 楽生
【落語家/上智大学非常勤講師】
春闘とは

春闘とは「毎年春に労働組合が企業などに賃上げ要求や交渉を行うこと」を指し、正式名称は「春季闘争」です。
労働組合は、以下の4つに分けられます。
・企業別組合(単位組合)
・産業別労働組合
・ナショナルセンター
・国際労働組合総連合(ITUC):
これらの組合が共闘して企業にベア(ベースアップ)などの要求や環境改善の要求を提出し、企業側の回答をもって締結するのが春闘です。
毎年2月ごろに要求が提出され、毎年3月の春ごろには回答が集まり、交渉のピークを迎えるため、“春”という文字が使われています。実際は夏ごろから組合でさまざまな検討を重ね、方針や要求を決定するなどをして半年以上かけて行われます。
参照:日本労働組合総連合会「「春闘」ってなに?」
ベア(ベースアップ)とは
ベアとはベースアップの略であり、春闘では基本給の水準を上げることを指します。
労働者が個人で基本給を上げようとしても、企業では労働者の立場のほうが下になりやすいため、交渉が難しいケースが多いですね。場合によっては交渉した労働者の印象が悪くなり、出世などに影響が出るかもしれません。
個人では難しいベアの交渉を労働組合が行うため、労働者の立場は悪化せずに、働きやすい職場づくりが期待できます。
春闘が始まったころのメインテーマはベアでしたが、働き方改革法案の議決からはベア以外に「働き方の協議」も要求内容に挙がりやすくなりました。
春闘のはじまり・背景
春闘のはじまりは、高度経済成長の1950年中頃からとされています。
現在の春闘になったのは、当時の労働組合の交渉力不足や戦後復興期ゆえの問題が背景にあります。
当時の労働組合は企業別になっており、企業と対等ではなかったため、労働条件を決める企業側が交渉では有利で、労働組合は交渉力不足でした。春闘がはじまったころは戦後復興期でもあったため、経済成長が優先され、労働者の賃金は低く改善が難しい時代でもありました。
そのような状況を変えるべく産業別労働組合も加わり、交渉力を上げて共闘したのが春闘のはじまりだとされています。
春闘に適用される労働組合法
春闘では、労働組合法が適用されており、団体交渉の拒否や不当労働行為などが禁止されています。
例えば、正当な理由がないにもかかわらず団体交渉を拒否したり、誠実な対応をしなかったりする行為です。労働組合への未加入もしくは脱退を条件に雇用契約を結ぶのも当てはまり、罰せられる可能性があるため注意しなければなりません。
労働者や労働組合に対して誠実に対応していれば、法に触れる可能性は低いでしょう。
春闘の目的
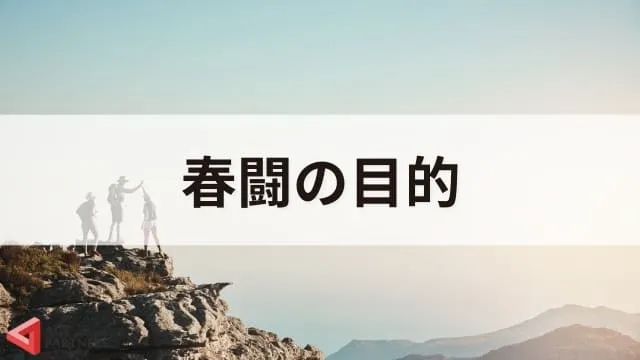
春闘の目的はベアと労働環境改善です。メインはベアですが、近年は労働環境改善にも力が注がれています。
労働者本人や交渉力のない労働組合がベアや労働環境改善を申し入れても、企業側のほうが力が強くて聞き入れてもらえないケースもあります。しかし、聞き入れてもらえないと、労働者はいつまでも安い給与や働きにくい環境で働かなければなりません。
そうならないようにするために春闘があるのです。
交渉力不足解消のために、それぞれの労働組合組織がまとまって交渉を行うため、企業側と対等に交渉できます。
春闘の流れ

春闘はいきなり交渉からはじまるわけではありません。夏ごろから検討がはじまり、春ごろに企業と交渉をスタートします。
具体的な年間の動きを解説します。
前年8月ごろ|連合が要求内容を検討する
全国組織の日本労働組合総連合会(連合)など、各労働組合は8月ごろから要求内容を検討しはじめます。
春闘は主に基本給の水準を上げるために行われますが、大企業と中小企業では利益に差があります。そのため、ベースアップの要求額を大企業に合わせるのではなく、それぞれの産業に適した水準になるように要求内容を検討しなければなりません。水準を達成するために「どのように要求をしていくか」も検討されます。
前年12月ごろ|連合が方針を発表する
毎年12月ごろになると、全国組織の連合が全体の方針を発表します。
なお、2025年の方針などは、日本労働組合総連合会の「2025年春闘」で確認できます。
方針を基に、それぞれの産業別労働組合が要求や交渉内容を決めます。
春闘は連合の目指す未来として、スローガンを定めています。
2024年から2025年のスローガンは、「社会を新たなステージへ、ともに歩もう、ともに変えよう〜仲間の輪を広げ 安心社会をめざす〜」です。
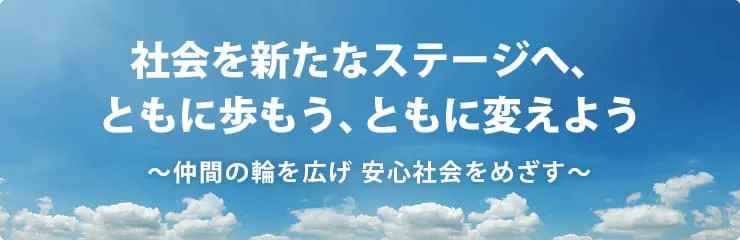
画像引用:日本労働組合総連合会「2024〜2025年運動方針」
参照:日本労働組合総連合会「連合のめざす社会 2024〜2025年運動方針」
前年12月ごろ|政府が経団連へ働きかける
同時期に政府から経団連へ賃上げの働きかけをする場合があります。春闘に政府が関わることから「官製春闘」と呼ばれる場合があります。
記憶に新しい動きといえば、2024年春闘に向けて岸田元総理が「インフレ率を上回る賃上げ」を新年会見で働きかけました。しかし、政府の働きかけに強制力があるわけではありません。
1月ごろ|労働組合が交渉内容を決める
1月ごろ、連合の全体方針を基に産業別労働組合と企業別労働組合が、交渉の内容を決めていきます。「要求の事項はどうするか」や「どのように交渉していくか」が、ここで決定していくのです。
産業別で水準が決定され、企業別で企業の業績やこれまでの賃上げ状況などを踏まえて、具体的な交渉内容が決定されます。
2月ごろ|春闘が始まる
2月ごろからいよいよ春闘がはじまりますが、組合と企業が面と向かって交渉するわけではありません。
労働組合が要求を企業に提出し、それに対する回答を企業が提出する流れで交渉が進んでいきます。遅くても2月末までには要求の提出が完了し、企業からの回答を待ちます。
3月ごろ|企業の回答集中および妥結する
3月ごろには春闘はピークをむかえ、要求に対する回答が多く集まります。企業側が要求を全て受け入れるケースもあり、その場合は書面にまとめて締結します。
中小企業などは全て受け入れられない事情もあるため、賃上げ率や労働条件の改善点などに対してさらに交渉して妥結するケースもあります。
その場合は、双方交渉を続けていき、合意に至ったら書面にまとめて締結します。

春闘の要求内容の具体例
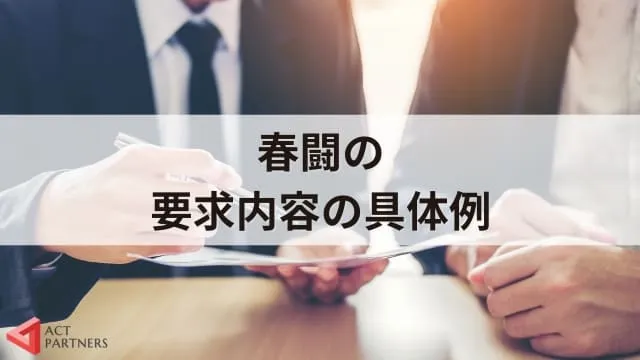
近年は、男性の育児参加やプライベートを大切にするワークライフバランスが重視されています。
これまでの労働環境とは違った環境や条件が必要になり、春闘での要求内容も変化がみられます。具体的な例を紹介します。
賃上げ(ベアなど)
春闘の主な要求内容は、賃上げです。
内容はベースアップをメインとしていますが、基本給だけでなく賞与などで上げるケースも少なくありません。年齢や勤続年数で昇給する定期昇給なども含まれます。
ベアと一言で言っても、どのような形で上がるかは企業の業績や状況に応じて異なります。
平均賃上げ率は、2000年ごろから毎年2%程度でしたが、2023年には3.6%、でした。2024春闘における賃上げ率は5.33%と、1991年以来33年ぶりに5%を超えています。
参照:厚生労働省「令和6年 民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況を公表します」
労働時間の適正化
2019年に働き方改革関連法が施行され、時間外労働の規制や有給取得の義務化などが実施されています。
それまでは、時間外労働が長時間にわたり、心身を病む方がいたり残業代が未払いになったりするケースが問題視されていました。しかし、働き方改革の影響で、不適切な雇用環境の是正が進んでいます。
そのため、春闘で労働時間の適正化を要求するケースも少なくありません。
現在は、残業ゼロや週休3日制などを導入している企業もあり、労働者も心身のリフレッシュができて働きやすい環境が整いつつあります。しかし、全ての企業で労働時間が適正なわけではありません。
未だサービス残業や有給取得が適正に行われていない企業もあるため、今後も春闘での労働時間の検討は続いていくでしょう。
非正規従業員の待遇改善
近年は正社員ではなく、非正規で働く方も多くいます。
非正規で働く理由はさまざまですが、正規でも非正規でも待遇格差があってはなりません。雇用形態による格差は「同一労働・同一賃金」によって禁止されています。
同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
引用:厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
しかし、2023年の調査では正規と非正規では100万円以上の賃金格差があります。
同じ労働をしているにもかかわらず、非正規という違いだけで、正規雇用より低い賃金で働かされている方がいるのです。非正規従業員の待遇改善は、これからも春闘で検討が必要な問題だといえるでしょう。
企業規模間の格差の是正
日本では多くの企業が存在しますが、大企業よりも中小企業が多く、2021年は全企業の99.7%を占めています。これだけの中小企業があるため、中小企業で働く労働者は全労働者の6割以上です。
大企業と中小企業では企業規模間の格差があります。格差が生まれる要因は、企業の業績や資金などの差、労働組合が存在せずに団体交渉できないケースなどが挙げられます。そのため、労働者は交渉ができず、中小企業側も労働者のためにベアや環境改善をしたいと思っても難しいのが現状です。
中小企業を守るためにも、春闘での企業規模間の格差の是正が重要視されています。
ワーク・ライフ・バランスの実現
近年では、求人票などにワークライフバランスの良さをアピールする企業も増えました。
仕事とプライベートの調和は、よりよく仕事をするためにもとても大切です。そのため、有給取得の推進や労働時間の削減などを実施している企業が多く、働きやすい環境が整いつつあります。
プライベート時間を増やす以外にも、テレワークの推進やメンタルヘルスケアなどに力を入れている企業もあります。
もちろん、業種によっては難しい面もありますが、労働者が働きやすく活き活きと生活をするためにはワークライフバランスの実現は外せませんね。
育児や介護制度の導入と改善
従来、男性が外で働き、女性が家を守るのが一般的とされていた価値観でした。そのため、育児や介護は女性が担うものというイメージが強く残る方も多いのではないでしょうか。
近年は共働きの世帯も増え、男性が育休や介護休暇を取得するケースも珍しくありません。
実際に、労働者の事情に合わせて柔軟な働き方を提供する企業もあります。とてもよい取り組みですが、制度があっても利用できるかどうかは企業の風土や慣習によって異なります。
共働きが当たり前となった時代に制度を心置きなく利用できなくては意味がありません。
春闘でも家庭の事情を考慮した制度の導入やすでにある制度の改善要求などが増えています。
ダイバーシティ(多様性)の推進
ダイバーシティとは“多様性”を意味しています。多様性の言葉はニュースやSNSなどで多く見られるようになり、広く認知されてきています。
認知されているからといって共存できているわけではありません。未だ年齢や性別、国籍や障害の有無による差別はあります。
多様性を認め、さまざまな方が一緒に働ける環境を整えている企業を増やすため、ダイバーシティの推進も春闘では重要視されています。

2025年春闘はどうなる?
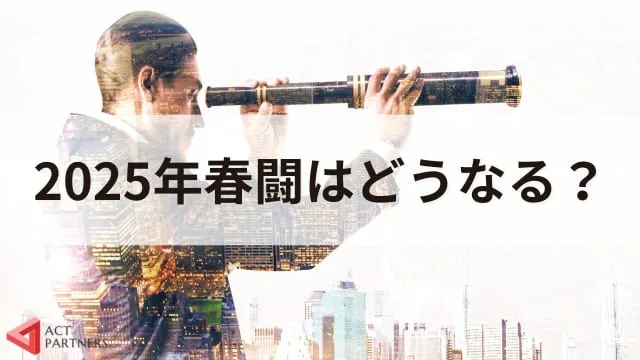
春闘が私たち労働者にとってどれだけ大切かがわかっていただけたと思います。
同時に「2025年はどうなるの?」と気になった方も多いかもしれません。
2025年は以下のようになると予想されます。
・賃上げの動きが続く
・賃上げの格差是正
・手取りアップのために第3の賃上げ
今ある問題改善はもちろんですが、持続的な生活向上を目指して動くと予想されます。
賃上げの動きが続く見込み
2024年の春闘では、ベアが5.3%と33年ぶりの5%台となりました。
2023年、2024年と上げてきた賃金を一時的な賃上げで終わらせず、今後も定着させていくのが目標のため、2025年も賃上げへの動きが続くと予想されます。
賃上げは人材確保には必要不可欠であり、実際に給与の高い企業には多くの就業希望者が集まります。中小企業では資金などの理由により、賃上げが難しいケースも少なくありません。企業規模間の格差を「どれだけ少なくできるか」も大きな課題となりそうです。
格差是正を目指す方針が定まっている
賃金は、企業規模や性別、雇用形態などによって格差があるのが現状です。
賃上げ率は、企業規模に比例して大きくなるため、中小企業で働く方は賃上げの効果を実感しにくいかもしれません。企業規模による賃上げ格差をなくすため、全体的に5%の賃上げを目安とし、中小企業には6%アップの交渉を求める考えです。
非正規雇用の場合は正規雇用よりも低い賃金となっているケースも少なくありません。雇用形態による格差是正に向けて、全体の時給を1,250円以上とする方針があります。さらに、勤続5年以上の場合は1,400円以上を目指すとされています。
手取り額アップに第3の賃上げも検討
手取りアップのための対策として、第3の賃上げが検討されています。
第1が定期昇給、第2がベアと考え、第3は福利厚生などを利用した賃上げです。ベアや昇給による賃上げは、課税対象となり引かれる金額も増えるため、あまり効果を実感できません。しかし、福利厚生は要件を満たせば非課税となるものもあります。
例えば、借り上げ社宅を利用すれば、家賃の一部を現物支給し、現物支給した金額を給与から差し引けば社会保険料などを減額できます。そうすると従業員の手取りが増え、課税対象のベアよりも賃上げの効果を実感しやすくなりますね。
非正規雇用は出勤数や勤務時間が給与に反映しますが、第3の賃上げは出勤数などに左右されないため待遇改善も期待できます。
第3の賃上げは労働者のみならず、中小企業などの資金に余裕がない場合でもコストを抑えて賃上げができるため、導入しやすい方法ですね。
まとめ
春闘を詳しく解説しました。企業に勤める方は、知っている方も多いと思いますが、改めて春闘を知ると、私たち労働者にもとても重要な役割があるのが分かります。
日本では中小企業が多くを占め、大企業と比べると資金などを理由にベアや環境改善が難しいケースも少なくありません。ベアや環境改善は労働者確保に必要不可欠なため、自社でできる範囲でよい方法を検討してみましょう。
初春には、春闘勉強会を開催する組織は多いのではないでしょうか?組合員や従業員一人ひとりが安心して活躍できる社会をつくるためにも、春闘で要望を伝える姿勢が重要です。
春闘勉強会を開催する際は、専門的知識と最新情報をもつ外部講師の講演会を実施するとよいでしょう。最新の動向から今必要な情報をキャッチできるため、多くの学びを得られるでしょう。
講演会や研修会の講演テーマや講師選びは、講師派遣の講演サーチにお任せください。活用シーンや課題に合わせた講師を複数ご提案いたします。
いつでも無料で受け付けているので、まずは無料相談フォームよりお気軽にお問い合わせください。

人気の講師

1位
大久保 雅士
【メンタリスト/ビジネス心理コンサルタント】

2位
丹羽てる美
【笑顔クリエイター®/フリーアナウンサー/上級睡眠健康指導士/心理カウンセラー】

3位
多湖 弘明
【株式会社Office Hit 代表取締役】

4位
安藤 美希子
【株式会社日動電設/ウエイトリフティング選手/オリンピアン/メダリスト/アスリート/コーチ】

5位
三遊亭 楽生
【落語家/上智大学非常勤講師】
ジャンルから講師を探す
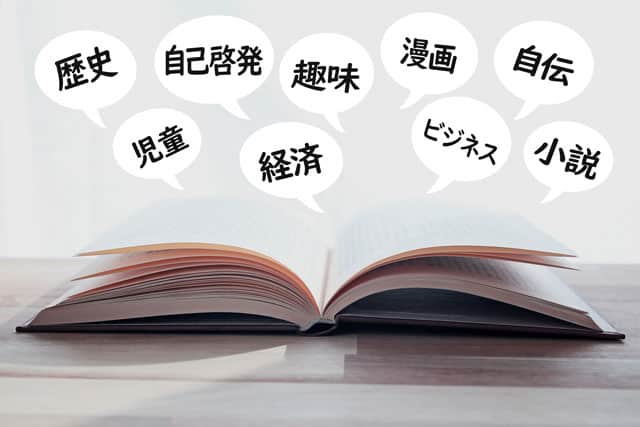 講演ジャンル |
|---|
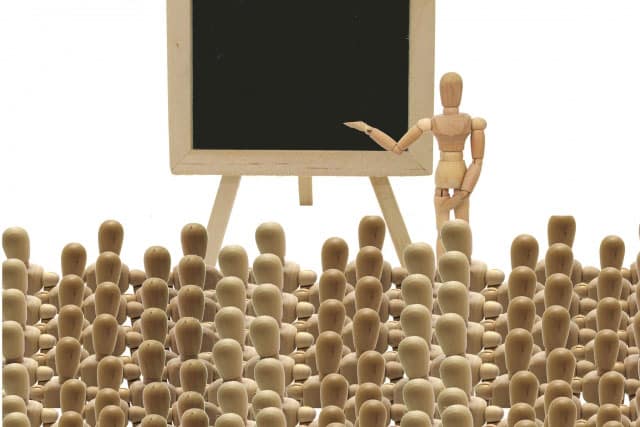 受講者 |
|---|









