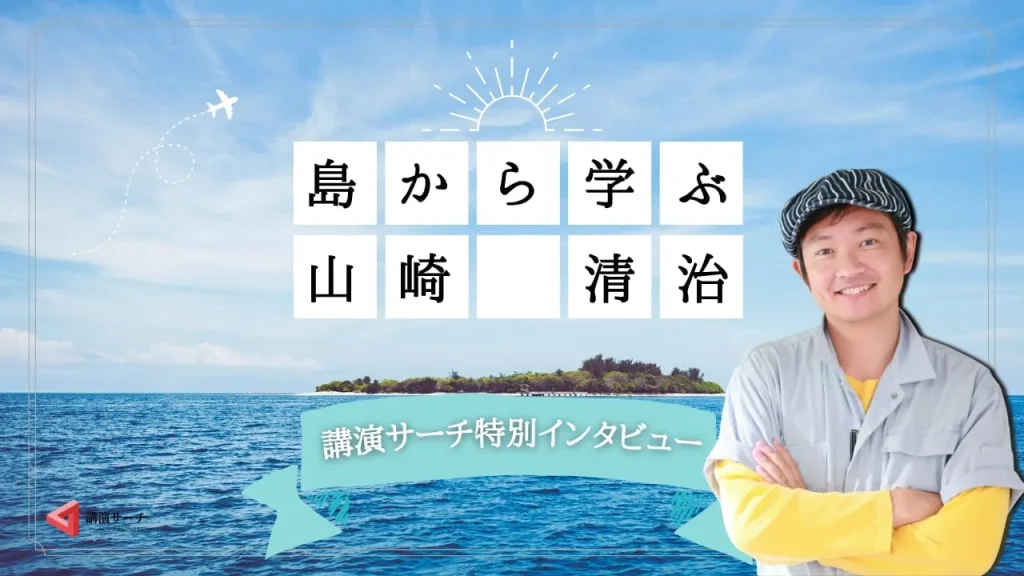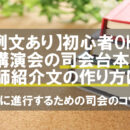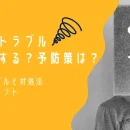【台本・例文付き】質疑応答での講演会司会進行のコツ!
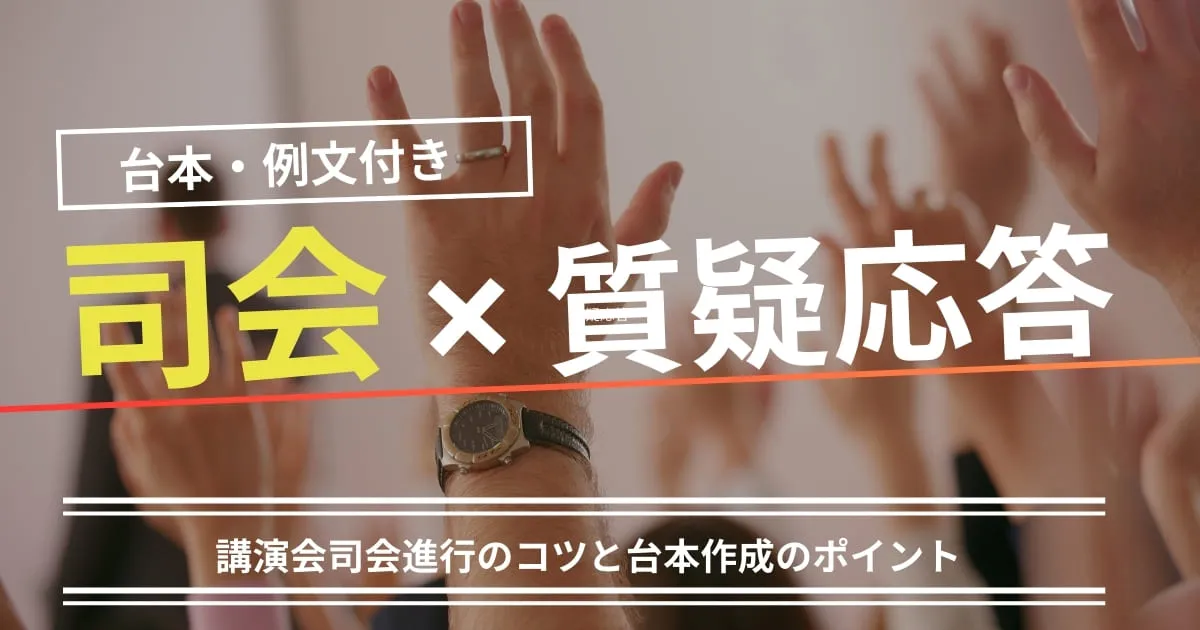
講演会では質疑応答を行うケースが多いですが、質疑応答で質問が出ずに「シーン」とした空気を味わった経験がある方もいるかもしれません。
そうならないためには、司会者が質疑応答を盛り上げていく工夫が必要です。
本記事では、質疑応答での講演会司会進行のコツを、台本・テンプレート付きで具体的に解説します。
講演サーチは、組織の課題やご希望に合わせた講師・講演テーマをご提案いたします。講演会や研修会の開催をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。「失敗しない講演・研修」を講演サーチと実現しませんか?
【台本・例文付き】質疑応答での講演会司会進行のコツ!
目次
講演会の司会者の役割
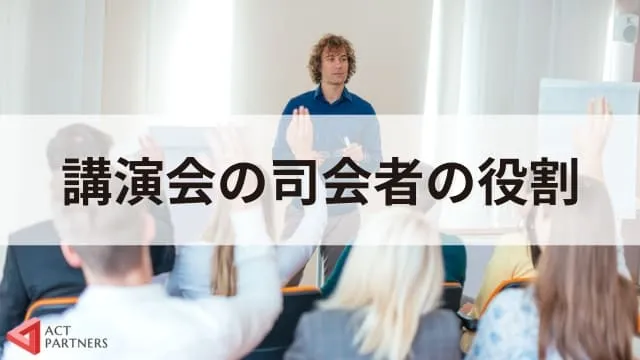
講演会では、その場を仕切る司会者の存在が欠かせません。
司会者の役割は、講演会を円滑に進めることです。講演会は時間に限りがあるため、時間内に終えられるようにするのも司会者の役割です。
さらに、会場の雰囲気をつくりあげ、和やかな空気で講演会が進められるかどうかも司会者にかかっています。
特に質疑応答では、講師と参加者の橋渡しをするため、両方に配慮して盛り上げていかなければなりません。
司会者はただ台本を読み進めるだけでなく、満足度や成功を左右する重要な役割を担っています。
講演会の司会進行の基本的な流れ
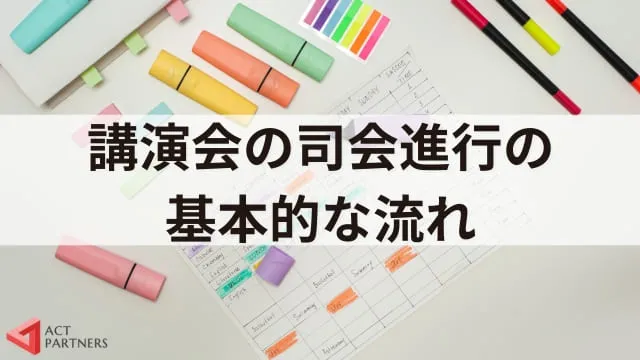
講演会の司会進行の基本的な流れは以下のとおりです。
1.開会前のアナウンス
2.開会の挨拶
3.講師の紹介
4.演題の紹介と呼び込み
5.質疑応答
6.閉会の挨拶
上記は講演会の基本的な流れであり、司会者は講演会の内容に合わせて、流れがスムーズになるよう進行します。
例えば、講演会が長時間にわたる場合、会の途中で休憩を挟むケースなどです。そのような場合は、休憩に入る前と終わるときに司会者はアナウンスをしなければなりませんね。
司会者は全体をコントロールするスキルが求められます。
司会進行の台本は必要?
司会進行に台本は必要です。
台本がないと、言葉がうまく出てこなかったり、時間管理ができなかったりする可能性があります。そうすると、参加者は進行に不安を感じ、講演会に集中できません。
せっかく講演してくださる講師にも不信感を与えてしまいますね。
講演会は必ず想定通りに進むとは限りません。講師の到着遅れや機材の不具合など、さまざまなトラブル発生が考えられます。
台本がないと、どう対処するべきか分からずに慌ててしまい、会場の雰囲気が不安に包まれてしまいます。台本に「トラブルが起きた場合の進行パターン」を盛り込んでおけば、万が一のときも安心です。
質疑応答の司会台本をつくるポイント
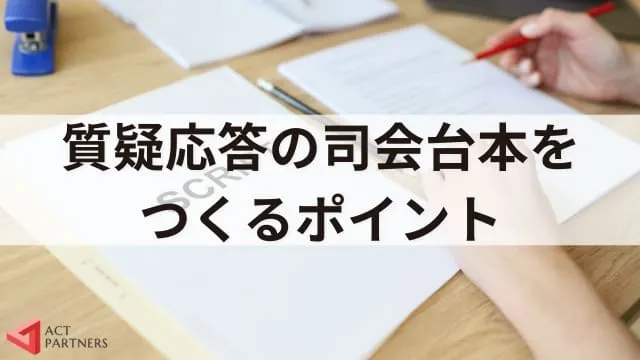
講演会の司会進行に台本は欠かせません。特に質疑応答では司会者は講師と参加者の橋渡役を担います。
質疑応答での質問の有無や雰囲気は、講演会の充実度や満足度にもつながるため、司会者はより気配りをしなければなりません。
質疑応答時の司会台本をつくるポイントを紹介します。
質問しやすい声掛けを意識する
講演会では、会場に多くの参加者が集まります。そのような場所で質問をするのは、注目を集めて緊張感や羞恥心を抱く方も多いです。
参加者のなかには「こんなレベルの低い質問をしてもよいのだろうか」と思う方もいます。その結果、参加者は質問したくてもできずに微妙な雰囲気のまま講演会を終えるケースも少なくありません。
そうならないためにも、参加者が質問しやすくなるような声掛けを台本に盛り込んでおくとよいですね。
いくつ質問を受けて、どのように質問をすればよいかを事前に案内しておくのも大切です。そこが曖昧なままだと参加者は余計に質問しづらくなってしまいます。
また、どのような質問でも構わないと伝えてあげるのもよいですね。参加者の緊張を解き、質問しやすくする声掛けを意識して台本をつくりましょう。
質問が出ないことを想定しておく
質疑応答があるからといって、必ずしも質問が出るわけではありません。質問が出ない場合は、司会者自ら質問をしてみてください。質問がまったくないと、会場の雰囲気も緊張感が漂い、せっかく来てくれた講師も残念に感じてしまいます。
司会者が質問をする場合は、講演内容の基礎にあたる質問がおすすめです。参加者のなかにある“質問へのハードル”を下げられるため、参加者も質問しやすくなりますよ。
質疑応答が活気づけば、会場の雰囲気もよくなり、講演会の満足度も高まります。
時間配分に気をつける
質疑応答が活発になると、時間がオーバーするケースがあるため、時間配分に注意しましょう。長時間では参加者の集中力は途切れ、満足度が低下してしまいます。
講演会での質疑応答にかける時間は、10~15分程度が一般的です。司会者はある程度質疑応答がされたら、時間を理由に締め切るのも大切です。また、質問を受ける数を事前に決めておき、参加者に案内しておくのも一つの手です。
質疑応答の司会台本の例文
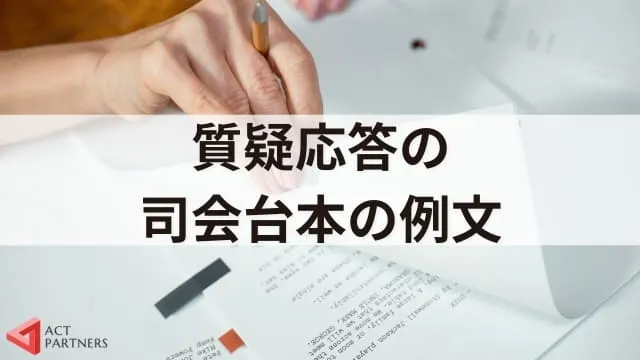
質疑応答の司会台本には「質問しやすい声掛け」や「質問が出ないことを想定した言葉」を盛り込むのが大切です。
では、具体的にはどのような言葉で台本をつくればよいでしょうか?ここからは、質疑応答の司会台本の例文を紹介します。いくつかのパターンの例文を用意したため、ぜひ参考にしてください。
なお、講演会全体における司会台本のテンプレートはこちらでご紹介しています。
質問方法の案内(質疑応答開始時)
質問方法が曖昧だと参加者はどう質問してよいか分かりません。
そのため、質疑応答が始まる際に質問方法を案内してあげると親切です。
質問方法を案内するには以下のような例文がおすすめですよ。
これより質疑応答の時間にうつります。
質問のある方は挙手をしていただき、係の者がマイクをお持ちいたしますので、お名前をお知らせいただいたあとに質問をお願いいたします。
時間の都合により、すべての質問にお答えできない場合がございます。あらかじめご了承ください。
それでは、質問のある方は挙手をどうぞ。
質問者がいる場合
質問者がいる場合、司会者は質問者(参加者)と回答者(講師)がスムーズに質疑応答できるように橋渡しをしていきます。
質問があった場合、その質問を受け取って講師に回答を促しましょう。
(挙手してくれた質問者を指名する場合)
前から2列目、右から3番目の方にマイクをお願いいたします。お名前と質問をどうぞ。
(質問を言い終わってから必要に応じて講師に回答を依頼)
〇〇というご質問をいただきました。
それでは、質問の回答をお願いいたします。
(回答後)
ありがとうございました。
それでは、つづいて質問のある方は挙手をお願いいたします。
質問者がいた場合、質問を言い終えたあとに司会者が「おー」などの感嘆詞や「確かに疑問ですね」などの共感の言葉でリアクションをとるのもよいでしょう。会場の雰囲気が和やかになるうえに、質問者は「質問してよかった」と思ってくれるはずです。
ただ、“参加者のための質疑応答の時間”であることを忘れず、リアクションは長すぎないよう注意が必要です。
質問者がまったくいない場合
質問者がまったくいないケースも少なくありません。
そのような場合は、司会者自ら質問をして参加者が抱える質問へのハードルを下げていきます。
質問のある方は挙手をお願いいたします。
(数秒待って手が上がらなければ)
では、私から質問してもよろしいでしょうか?
基本的な内容の質問になってしまいますが、~についてはいかがでしょうか?
講師の〇〇様、お願いいたします。
(回答後)
たいへん勉強になりました。〇〇様、ありがとうございました。
では、他に質問のある方は挙手をお願いいたします。
質問者がまったくいないケースを考え、司会者が率先して質問をする他に「身内の参加者に事前に質問するように依頼しておく」のも一つの手です。
その場合も一発目の質問ということを考慮し、あまり難しい質問にならないようお願いしておくのが大切ですね。
時間が迫っている場合
講演会ですべての質問に回答できれば理想的ですが、時間の都合でそうもいきません。
時間の都合で締め切る場合はいきなり締め切るのではなく、最後の質問の前に伝えてあげると親切です。
(前の質問の回答後)
ありがとうございました。
それでは、そろそろお時間も迫ってまいりましたので、最後の質問とさせていただきます。
質問のある方は挙手をお願いいたします。
質疑応答の締め方
質疑応答で最後の質問が出たら、質疑応答を締めて閉会の挨拶へとうつります。
その場合、以下のような例文をつかうと自然に閉会への挨拶にうつれますよ。
(最後の質疑応答後)
ありがとうございました。
まだまだ質問があるかとは存じますが、残念ながらそろそろ閉会の時間が近づいてまいりました。
それではここで最後に主催者であります〇〇企業の(氏名)から閉会のご挨拶を申し上げます。
よろしくお願いいたします。
このような流れで閉会の挨拶へとうつりますが、質問が少なかった場合に「まだまだ質問がある」と言うのはおかしいですね。
そのようなときは、質問してくれた参加者と回答してくれた講師にお礼の言葉を述べ、閉会の挨拶へとうつりましょう。
まとめ
司会台本のなかでも質疑応答に焦点をあてて解説しました。
司会者は講演会の進行が役割ですが、それだけではありません。時間管理や会場の雰囲気づくりも重要な役割です。
特に、参加者と講師の橋渡しをする質疑応答では、司会者が盛り上げていかないと雰囲気が悪くなり、満足度が低下します。参加者が質問しやすい声掛けや雰囲気をつくるのも司会者の務めであり、さまざまな想定で台本をつくるのが大切です。
司会台本のポイントをおさえ、紹介した例文をもとに安心できる司会台本をつくっていきましょう。司会者台本が作り込まれていると、研修や講演会の成功率や満足度が高くなります。
司会台本のテンプレートをお探しの場合は、講演サーチにご相談ください。失敗しない講演をお約束いたします。
人気の講師

1位
大久保 雅士 【メンタリスト/ビジネス心理コンサルタント】

2位
丹羽てる美 【笑顔クリエイター®/心理カウンセラー】

3位
多湖 弘明 【株式会社Office Hit 代表取締役】

4位
安藤 美希子 【株式会社日動電設/ウエイトリフティング/メダリスト】

5位
三遊亭 楽生 【落語家/上智大学非常勤講師】
ジャンルから講師を探す
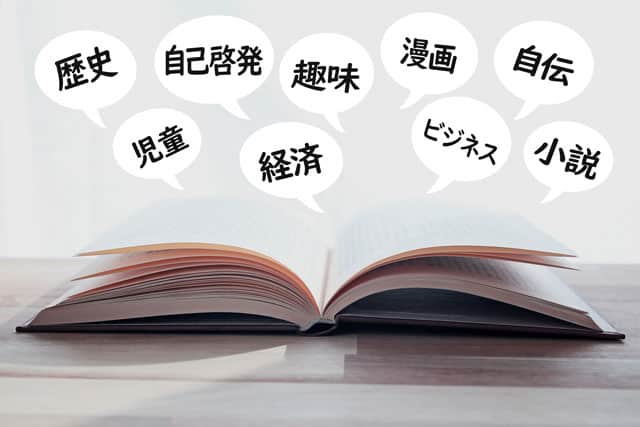 講演ジャンル |
|---|
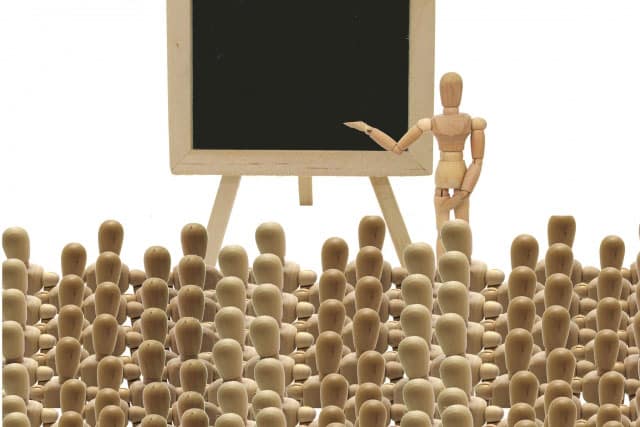 受講者 |
|---|