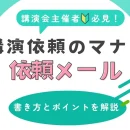【徹底解説】労働組合が開催する定期大会とは?関連する法律からわかりやすく紹介
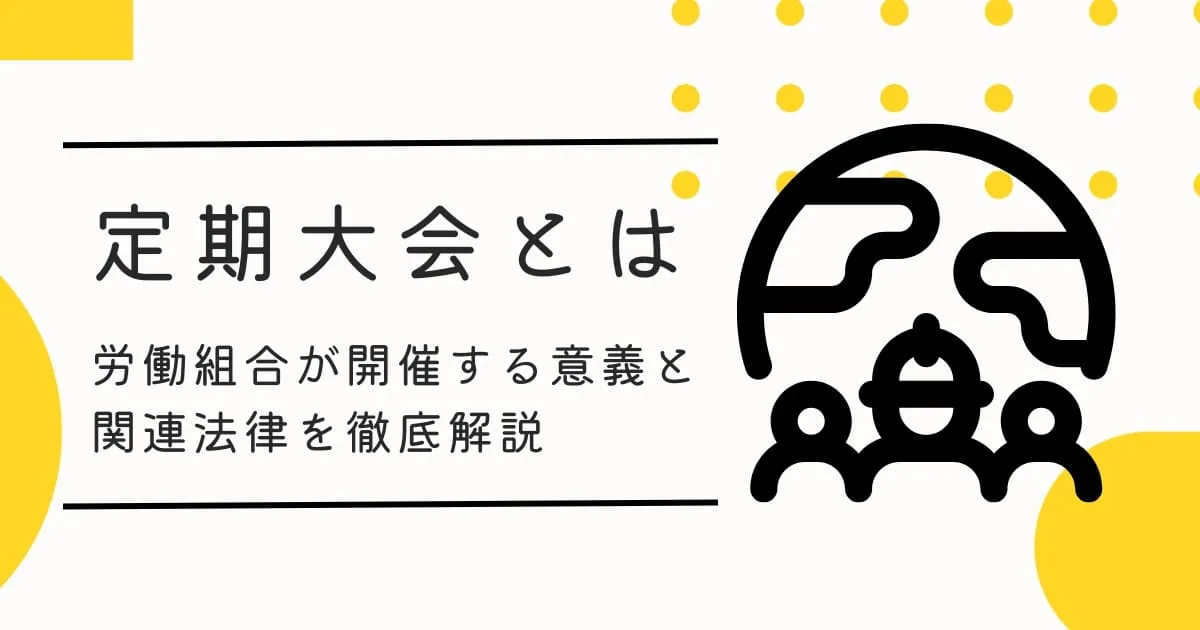
「労働組合に入っているけど、定期大会って何するの?」
「そもそも労働組合についてよくわからない」
「定期大会に参加することになったけど、事前に理解するべきポイントを知りたい」
定期大会について、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。定期大会は、労働組合の最高決議機関であり、通常年に一度開催されます。
しかし、定期大会について理解するには、そもそも労働組合とは何かを理解する必要があります。労働組合はよく聞く言葉ですが、実際に何をしているのかよくわからない方もいるかもしれません。
そこで本記事では、以下の内容を解説します。
・労働組合について知っておきたい基礎知識
・定期大会の概要と意義
・定期大会で実施する主な活動3つ
・よくある質問
この記事を最後まで読むことで、定期大会の理解を深められるだけでなく、参加する際に気をつけるべき点もわかります。
また、関連する法律や憲法についてもあわせて解説するため、労働組合自体の理解も深まるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
労働組合向けの講演会や講師をお探しの方は、ぜひ講演サーチにご相談ください。経験豊富なスタッフが組織の課題に沿った講師を複数ご提案させていただきます。

【徹底解説】労働組合が開催する定期大会とは?関連する法律からわかりやすく紹介
目次
人気の講師

1位
大久保 雅士
【メンタリスト/ビジネス心理コンサルタント】

2位
丹羽てる美
【笑顔クリエイター®/フリーアナウンサー/上級睡眠健康指導士/心理カウンセラー】

3位
多湖 弘明
【株式会社Office Hit 代表取締役】

4位
安藤 美希子
【株式会社日動電設/ウエイトリフティング選手/オリンピアン/メダリスト/アスリート/コーチ】

5位
三遊亭 楽生
【落語家/上智大学非常勤講師】
【前提知識】労働組合とは?定義や関係する法律を解説
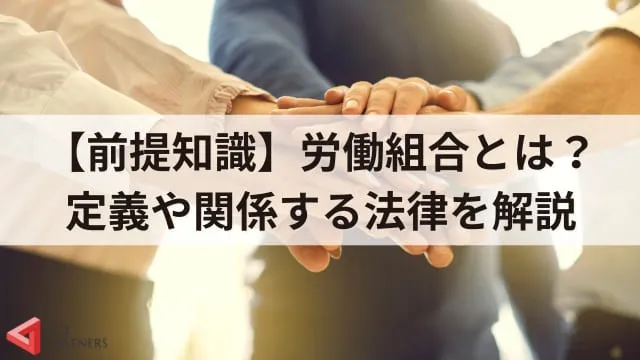
定期大会を理解する前提となる労働組合に関して、以下の内容を解説します。
労働組合の定義
労働三権
労働組合法
それぞれ詳しく解説します。
労働組合の定義
労働組合とは、労働者が自分たちの働く環境や待遇を良くするために、協力して活動する団体のことを指します。わかりやすく言い換えると、労働者の使用者(雇用主)に対して、労働者で力を合わせて交渉し、改善を目指す仕組みのことです。
労働組合を結成するメリットは、個人では言いにくいことを経営者に伝えやすい点です。賃上げ交渉などは労働組合があることで、経営者と対等の立場で交渉できます。
労働組合は、労働者にとって雇用者と対等に交渉するうえで大きな力となっています。
労働三権
労働組合を理解するには、関連する憲法や法律を知っておきましょう。
特に、労働組合の基盤となるものとして、憲法第28条があります。この条文では、労働者の権利として次の3つ(労働三権)を認めています。
| 労働者の権利 | 説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| 団結権 | 労働組合の結成や労働組合への加入ができる権利 | ・労働組合を結成する ・既存の労働組合に加入する ・全国規模の労働組合を結成する |
| 団体交渉権 | 労働組合を通じて経営者や企業と交渉する権利 | ・昇給制度の明確化を求める ・新たな安全対策導入を交渉する ・残業時間の削減を求める |
| 団体行動権 | 労働状況改善に向けて、ストライキなどの行動を起こす権利 | ・企業が話し合いに応じない場合に部分ストライキを行う ・企業との賃金交渉が決裂した場合に全面ストライキを行う |
労働三権は、労働者が企業から不利な条件を押し付けられるのを防ぐ役割を果たすため重要です。
労働組合法
労働三権を具体的に保証するための法律が労働組合法です。労働組合法により、労働組合は使用者と労働協約を締結する権利を有します。
労働協約とは、労働組合と企業が交渉を行い、働く条件やルールについて書面で取り決めた約束ごとです。労働協約は、働く人たちの権利を具体的に守るものとして、法律に匹敵する強い効力を持ちます。
労働協約は、労働者にとって法律よりよい条件を作れる点もメリットです。例えば、労働基準法では年間休日は最低105日ですが、労働協約で「120日以上」と設定できます。
さらに、労働組合法は、労働組合の活動が正当な場合は刑事責任や民事責任が免除される権利も保証しています。例えば、使用者に対して労働組合が正当なストライキを行った結果、企業に損害が発生しても損害賠償は発生しません。
参考:e-Gov 法令検索「労働組合法」

労働組合の定期大会とは?概要と意義について解説
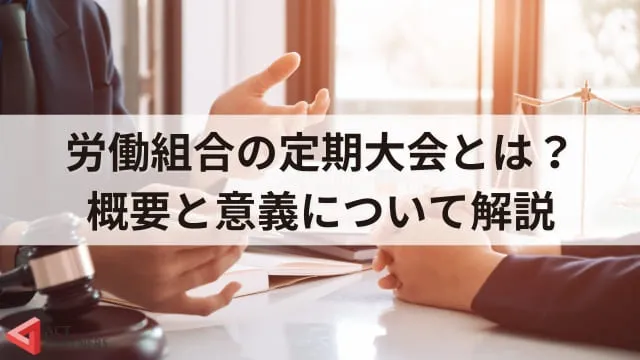
労働組合の定期大会について、以下を紹介します。
・定期大会の概要
・定期大会の意義
それぞれ見ていきましょう。
定期大会の概要
定期大会は、労働組合が開く大きな会議です。定期大会は、労働組合の国会のようなもので、最高決議機関です。
労働組合は、定期大会を開催して組合の活動方針や予算を決定します。
定期大会は、労働組合法により、年に一度以上の開催が義務付けられています。開催時期は、毎年初夏から秋ごろが多いです。
ただし、年度途中で急を要する重要な議題が発生した場合は、臨時大会が開催されます。
会社の突然のリストラ発表や賃金カットなど、労働条件や職場環境に関する緊急の問題が発生した場合がその一例です。これらの問題が発生した場合は臨時大会により迅速な意思決定が必要です。
参考:e-Gov 法令検索「労働組合法」
定期大会の意義
定期大会は、労働組合が民主的で透明性の高い組織として機能するために欠かせません。労働組合は、労働者自らが働く環境を改善するための組織であり、組合員の自主的な意思に基づき運営される必要があるからです。
民主的な運営には、全員の意思によって物事を決める必要があります。組織の労働者全員のために存在している労働組合にもかかわらず、一部の人物により運営されていては民主的ではありません。
定期大会は組合員全員が意見を出し合い、共通の目標を共有する場であるため、開催することで組合員同士のつながりが強まります。結果として連帯感が生まれ、組織運営が民主的に進められることにつながります。
労働組合が定期大会で行う主な実施事項3つ
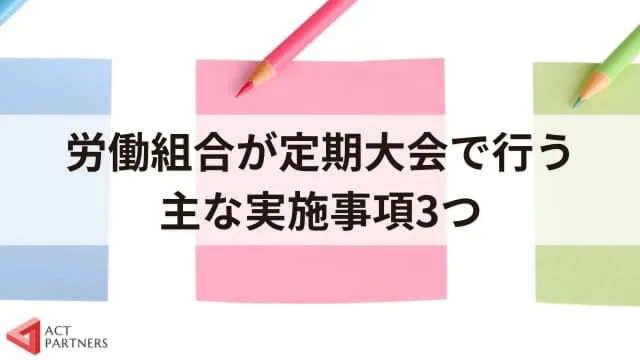
定期大会での実施事項は多くありますが、主に理解しておきたい実施事項は次の3つです。
過去1年間の活動と決算の報告
次年度の運動計画と予算案の決定
組合役員の選挙
それぞれ詳しく解説します。
過去1年間の活動と決算の報告
主な実施内容の一つが、前回の定期大会で決定した方針を元に活動した結果、実際にどういった成果や課題があったかの報告です。
例えば、賃上げ交渉での成果や、職場の安全対策への取り組み結果を報告します。
組合員が払った会費の使い道についても報告します。具体的な内容は、交渉費用やイベント費用、運営費などです。組合費の使い道を公開することで、不正や無駄遣いがないことを説明し、透明性を確保する効果があります。
直近1年間の報告により、組合員は、自分たちが払った組合費の使われ方と成果を認識できます。
次年度の運営計画と予算案の決定
過去1年間の活動報告の後は、次の1年間で労働組合がどういった活動を行うのか、方針を決定します。活動の具体的な方向性や優先順位の明確化により、組合の運営をスムーズにし、組合員のニーズに応える計画を作れます。
方針は各労働組合によって異なりますが、例えば次のような方針が考えられるでしょう。
・残業時間削減の交渉を優先する
・新しい組合員を増やす活動を強化する
運営計画は、組合員全員が納得するように話し合います。労働組合が適切に運営されるためには、活動方針だけでなく、活動費の議論も重要です。
限られた組合費などの収入を元に、活動方針を実行するためにも、活動に必要な支出を適切に管理する必要があります。そのため、次年度の予算についても、何の活動にどのくらいのお金を使うかを計画し、定期大会で承認を得ます。
組合役員の選挙
労働組合は、民主的な運営が基本です。そのため、国会議員が選挙により国民から選出されるのと同様に、労働組合のリーダーや役員を選ぶ際にも選挙を行います。
選挙は定期大会で行われます。選挙で選ばれるのは、委員長や副院長、書記長など、労働組合の運営で中心的な役割を担う役職者です。
民主的な選挙を行うことで、特定の人物だけが権力を握る状態を防ぎ、民主的な運営が実現できます。
選挙を通じて新しいリーダーが選ばれることは、時代や環境の変化に対応した労働組合の運営につながります。役職者が変わると方針の見直しや時代に適した組織文化の刷新などが期待できるからです。
選ばれる役職者によって組合の運営は左右されるため、組合役員の選挙は定期大会のなかでも重要な要素です。

定期大会に関するよくある質問3選
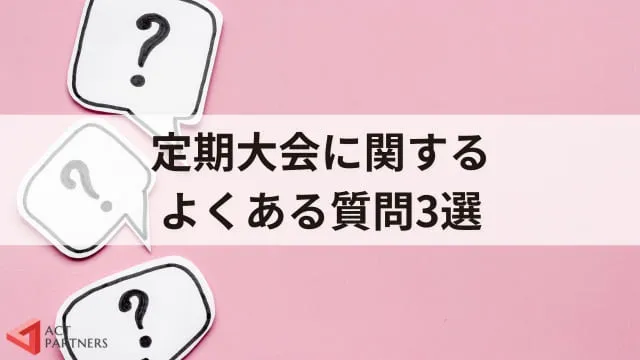
本項では、定期大会についてよくある質問に回答します。
Q1.定期大会の挨拶はどうすれば良い?
A.組合の役職者になっている場合、定期大会で挨拶をする場面があるでしょう。
挨拶の内容に悩んでいる方は、基本の型として以下の4ステップで行うとよいでしょう。
STEP1:組合員への感謝の意を伝える
STEP2:大まかな活動の成果や課題を共有する
STEP3:今後の組合の方向性を示す
STEP4:労働組合の活動への思いを語り士気を高める
4ステップの実施にあたり、日本経済や社会情勢、自社を取り巻くビジネス環境などに触れて話の幅を広げるのもポイントです。他にも、他の組合の役職者の挨拶を調べて参考にするのもよいでしょう。
Q2.定期大会は欠席できる?
A.定期大会は出席が原則ですが、病気や家庭の事情など、やむを得ない正当な事情がある場合は欠席も可能です。ただし、欠席することが分かった時点で、事前に所属する支部や執行部に連絡しましょう。
また、定期大会では重要な議案を決議するため、欠席の場合は委任状の提出が求められることがあります。
委任状を記載すると、自身の大会での権限を代理人に委任できます。やむを得ず欠席した場合は、大会の議事録や報告資料を後日確認し、決まった内容を把握するようにしましょう。
Q3.定期大会に参加するときの服装は?
A.定期大会の服装は、組合の雰囲気や業界、職場文化によって異なります。ただし、一般的に、定期大会はフォーマルな場なため、カジュアルすぎない格好がよいでしょう。
そのため、服装に迷う場合はスーツでの出席が無難です。

労働組合の活性化には講演会の開催がおすすめ
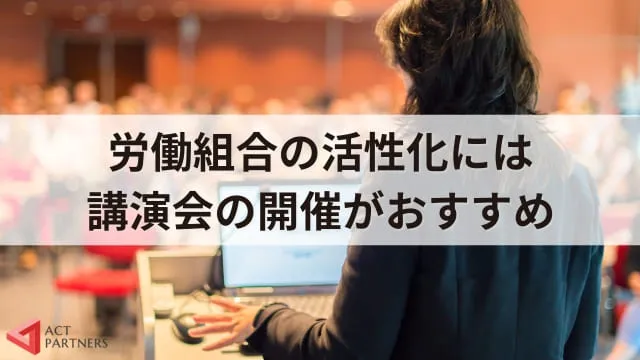
定期大会は、労働組合を健全に運営し、活動の方針を決める重要なイベントです。しかし、定期大会の参加率が低く、議論が形式的になっている労働組合もあるでしょう。
また、定期大会は基本的に年に一度の開催のため、情報共有の頻度が少ない点がデメリットです。現代の労働環境は絶えず変化しているため、このままでは長期間時代遅れの方針を続けてしまうリスクがあります。
変化する時代に乗り遅れないためにも、新しい知識と視点を取り入れ、より強固な組合活動を実施していく必要があります。
そこでおすすめなのが、講演・研修会の実施です。
組合員が積極的に参加したいと思えるような講演会を実施することで、組合組織の活性化が期待できます。
例えば、参加型の研修や、生成AIなどの最新テーマを取り上げた講演会は、組合員が関心を持ちやすいでしょう。
講演会を通じて労働環境の正しい知識が身につけられます。
講演会で学んだ内容をもとに、組合活動の問題点を洗い出し、課題解決に最適な方法を考えることもできるでしょう。
働き方の多様化やグローバル化など、変化が激しい現代で労働環境を改善するには、労働組合の活性化が必要です。そのための手段として、プロの講師による講演会を開催してはいかがでしょうか。
意味ある定期大会のために講演会を開催しよう
本記事では、労働組合が開催する定期大会について解説しました。定期大会は、年に一度開催される労働組合の最高決議機関です。定期大会では、組合員全員が意見を出し合い、共通の目標を共有します。定期大会は労働組合の民主的な組織運営を促す役割があるため重要です。
しかし、定期大会だけでは組合内の情報共有頻度が少ないため、活動が時代の変化に対応できないリスクがあります。こうしたリスクの回避には、講演会の開催がおすすめです。
講演会を開催することで、変化が激しい現代における労働環境改善に必要な知見が得られます。講師依頼・講演派遣のプロであるアクト・パートナーズでは、労働組合の活性化に役立つ講演会の開催を一気通貫でサポートしています。講演会実施を検討する際は、ぜひ一度ご相談ください。

人気の講師

1位
大久保 雅士
【メンタリスト/ビジネス心理コンサルタント】

2位
丹羽てる美
【笑顔クリエイター®/フリーアナウンサー/上級睡眠健康指導士/心理カウンセラー】

3位
多湖 弘明
【株式会社Office Hit 代表取締役】

4位
安藤 美希子
【株式会社日動電設/ウエイトリフティング選手/オリンピアン/メダリスト/アスリート/コーチ】

5位
三遊亭 楽生
【落語家/上智大学非常勤講師】
ジャンルから講師を探す
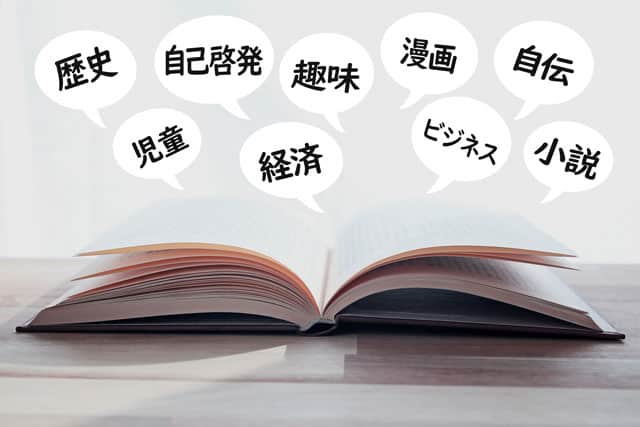 講演ジャンル |
|---|
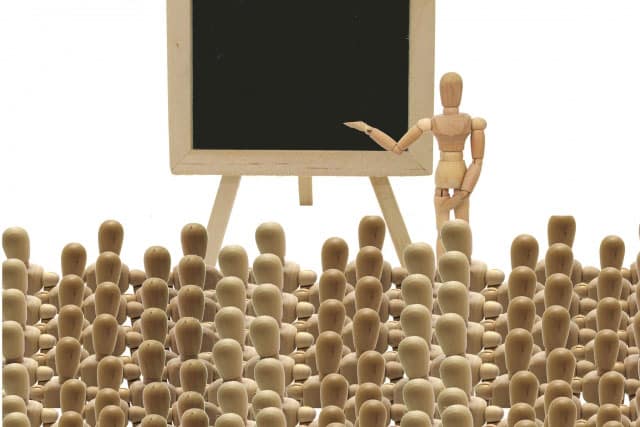 受講者 |
|---|